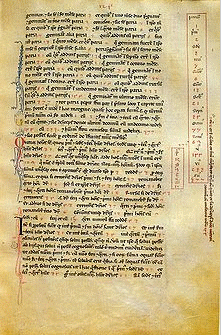
|
|
フィレンツェ国立中央図書館にあるリベル・アバチの一頁
右側のリストは 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377 (フィボナッチ数列) 2,8 と 9 は東アラビア数字やインド数字よりもアラビア数字に似ている。 |
以下の文書は次の翻訳です。
Liber Abaci - Wikipedia
リベル・アバチ (Liber Abaci) はアバカス (abacus) の本という意味で、アバカスは基本的には「そろばん」を意味しますが、 より正確には、あらゆる形式の計算も意味します。
リベル・アバチ (Liber Abaci あるいは Liber Abacci, 「計算の本」 のラテン語) は 1202 年にピサのレオナルド (Leonardo of Pisa) ―― 死後にフィボナッチ (Fibonacci) と呼ばれた ―― による算術に関してのラテン語の本である。 これは基本的に、 10 を基数とする位取り記数法 (base 10 positional notation) と記号を導入したことで有名で、 ヨーロッパでアラビア数字と呼ばれる。
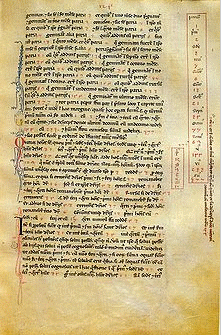
|
|
フィレンツェ国立中央図書館にあるリベル・アバチの一頁
右側のリストは 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377 (フィボナッチ数列) 2,8 と 9 は東アラビア数字やインド数字よりもアラビア数字に似ている。 |
リベル・アバチはインド・アラビア数字のシステムを記述し、 現代の「アラビア数字」に類似する記号を使用した最初のヨーロッパの本の 1 つである。 商人と数学者のどちらの応用にも対処することにより、 この本はシステムの優秀性と記号の使用を奨励した。
この本の表題はしばしば「そろばんの本」 (The Book of the Abacus) と翻訳されるが。 シグラー (Sigler, 2002年) が注意するように、 計算装置としてそろばんを言及するものとしてこれを読むことは間違いであるとしている。 むしろ 「そろばん」(abacus) の用語は当時、あらゆる形の計算を言及するものとして使用された; b が 2 つ付いた 「abbacus」 の綴りはかってもそうであったし、現在でも インド・アラビア数字を使用する計算を言及することに使用され、これで混乱を避けることができる。 この本はそろばんの助けなしで、計算をする方法を記述し、 オーア (Ore, 1948 年) が確証するように、その刊行以来何世紀もの間、 アルゴリズム主義者 (リベル・アバチに実証された計算スタイルの信奉者)は そろばん主義者 (ローマ数字と共にそろばんを使用し続ける伝統主義者) と 衝突し続けている。 数学の歴史家であるカール・ボイヤー (Carl Boyer) が「数学の歴史」 (History of Mathematics) で強調していることは、本質的に 「リベル・アバチはそろばんに関しているわけではないが、...」、それにもかかわらず 「...これはインド・アラビア数字の使用が強く唱導された代数的方法に関する完全な論説である。」
第一節はインド・アラビア数字システムの導入と、 これに含まれる算術と異なる表示システムの間の変換方法である。 この節に含まれることは、ある数が合成数であるか否かをテストするための、 最初の既知の 試し割り法 (trial devision) の記述と、もし合成数であれば、これを因数に分解することである。
第二節は商業からの実例が提示され、例えば通貨と測量の変換、そして利益と利子の計算である。
第三節は幾つかの数学の問題を議論する。 例えば、これに含まれることは、 中国の剰余の定理、 完全数、 メルセンヌ素数、 更には 等差級数、 四角錐数 (square pyramidal numbers) の公式である。 この節の他の実例に含まれるものに、うさぎの個体数の増加があり、ここで解法に数列の生成が要求される。 もっとも、その結果じる フィボナッチ数列はレオナルドよりずっと前にさかのぼるが、 彼がこれをこの本に含めたため、今日この数列が彼にちなんで命名されている。
第四節は平方根のような無理数の数値的・幾何学的な近似を導いている。
この本はユークリッド幾何学の証明も含んでいる。 代数方程式を解くフィボナッチの方法は 10 世紀初期のエジプト数学者の アブー・カーミル (Abū Kāmil Shujāʿ ibn Aslam) の影響を示している。
リベル・アバチを読む上で、有理数に対するフィボナッチの記号を理解することは有益である。 この記号はその時までに普通に使用された エジプト分数と今日なお使用されている常分数 (vulgar fraction) の間の中間的形態である。
フィボナッチの記号は現代の分数記号と 3 つの重要な点で違っている。
| 2 |
| 2 |
| = | + |
| = | + | + |
| + | + |
| 5 ヤード |
| 2 |
| 2 | と書くか、仮分数 |
この表記方法の複雑さにより、数を多くの異なる方法で書くことを可能にし、 フィボナッチは 1 つの表示スタイルから別のスタイルに変換する幾つかの方法を記述した。 特に II.7 章は仮分数をエジプト分数に変換する方法の一覧を含み、 これにはエジプト分数のグリーディ・アルゴリズム (greedy algorithm) を含み、 フィボナッチ・シルベスター展開 (Fibonacci-Sylvester expansion) とも呼ばれる。
リベル・アバチでフィボナッチは次を述べ、肯定的なインドの方式 (Modus Indorum) を導入し、 今日、インド・アラビア数字システム、あるいは 10 を基数とする位取り記数法 (base-10 positional notation) と呼ばれる。また数字も導入し、これは現代のアラビア数字に随分似ている。
言い換えると、彼は本の中で 0-9 の数字と桁の値 (place value) の使用を奨励した。 この時までに、ヨーロッパ人はローマ数字を使用し、現代的な数学はほとんど不可能であった。 従って、この本は 10 進数の拡散に重要な貢献をした。 オーア (Ore) が記述するように、 インド・アラビア数字のシステムの拡散は延々と続き、 広く広まるために何世紀もかかり、16 世紀後半に至るまで完全ではなく、 印刷の到来と共に 1500 年代になって始めて劇的に加速した。
最初の写本の登場は 1202 年である。このバージョンの写しは知られていない。 リベル・アバチの改訂版は マイケル・スコット (Michael Scot) に献呈され、1227 年に登場した。 このテキストの一部分を含む現存する少なくとも 19 の写本がある。 13 世紀と 14 世紀のこの写本の 3 つの完全なバージョンがある。 13 世紀と 14 世紀の間と思われるさらに 9 部の不完全なコピーがあり、 鑑定されていないものも、もっとあるかもしれない。
1857 年のボンコンパーニ (Boncompagni) のイタリア語訳に至るまでは、リベル・アバチの印刷版で既知のものはない。 最初の完全な英訳は 2002 年のシグラー (Sigler) のテキストである。