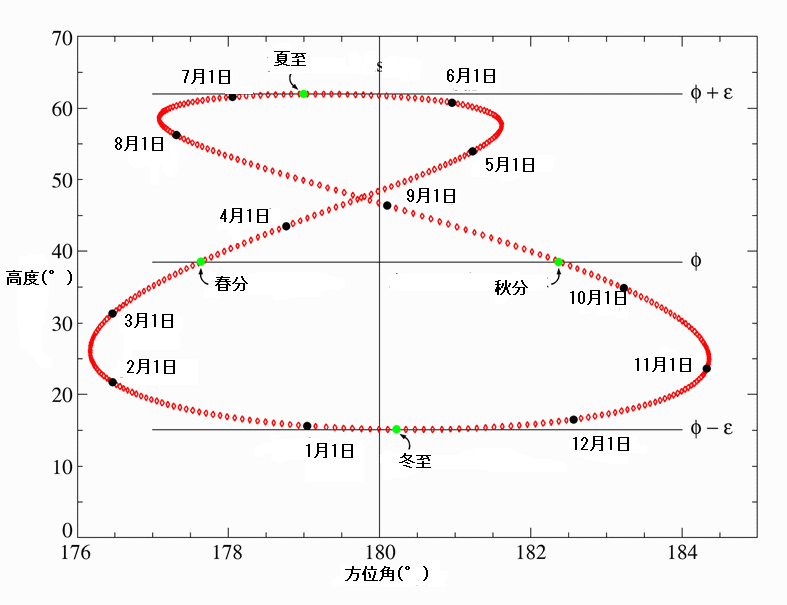
|
|
米国ニュージャージー、マーリー・ヒル (Murray Hill)、午後の
アナレンマの写真、1998 年 - 1999 年。 ジャック・フィッシュバーン (Jack Fishburn)、 撮影手前に ベル研究所の建物 |
以下の文書は次の翻訳です。
Analemma - Wikipedia
天文学では、アナレンマ (/ˌænəˈlɛmə/; 古代ギリシャ語の ἀνάλημμα (analēmma) 'support'(支え) に由来) は 一年を通して同一の平均太陽時で、 地球上の固定点から見た 天空の太陽の位置を示す図式である。 位置の変化は太陽の、星に対する通り道 (黄道) の、天空での角度変化の結果である。 この図式は 8 の字に似ている。 地球儀はしばしば、 (太陽が速い) 均時差×太陽の赤緯 の 2 次元図式 としてアナレンマを表示する。
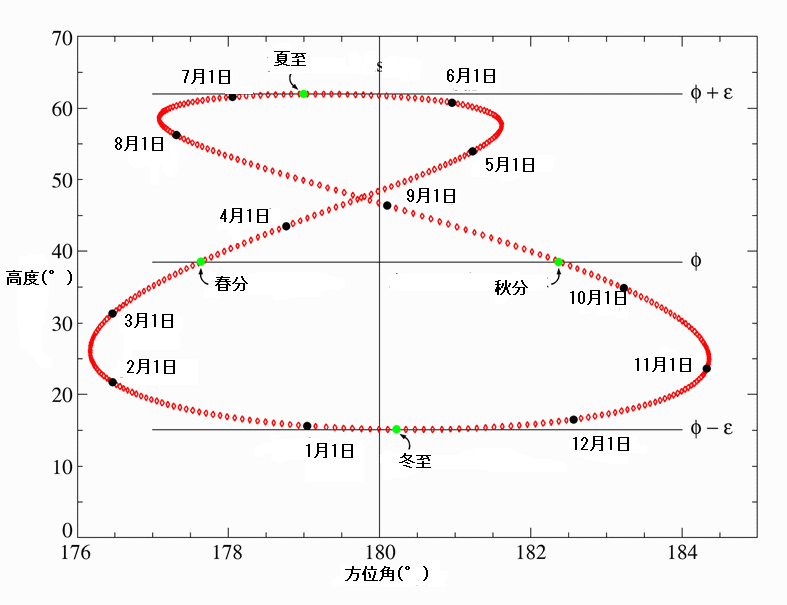
|
|
米国ニュージャージー、マーリー・ヒル (Murray Hill)、午後の
アナレンマの写真、1998 年 - 1999 年。 ジャック・フィッシュバーン (Jack Fishburn)、 撮影手前に ベル研究所の建物 |
アナレンマの南北成分は、地球が太陽をまわる時に、 地球の回転軸の傾きによって太陽の赤緯が変動する結果である。 東西の成分は太陽の不均一な赤経の変化率の結果であり、 これは地軸の傾きと軌道離心率の複合効果で支配されている。
アナレンマの写真を撮影するには、 カメラの位置と向きを固定して、一年を通して 1 日の同じ時刻 (夏時間を無視) に、 多重露光をすればよい。
アナレンマの用語は普通、地球の太陽アナレンマを言及するが、 他の天体にも同様に適用できる。
アナレンマは、太陽の位置を地球上の固定位置から、同じ時刻に 1 年を通してプロットして、 あるいは、太陽の赤緯と均時差のグラフを書き込むことで描くことができる。 得られる曲線は長く、ほっそりした 8 の字形で、一方のループ (lobe) が他方よりもずっと大きなものである。 この曲線は普通地球儀の、通常は東太平洋に印刷され、ここは陸がほとんどない唯一の大きな 熱帯地域である。 アナレンマを写真撮影することは、困難ではあるが可能であり、 カメラを完全に一年間固定して、24 時間間隔で写真を撮ればよい (あるいは多重露出のような ことをすればよい)、以下の節を参照。
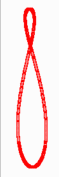
|
|
地球上のアナレンマ。赤い線は太陽が真上にある地球上
の位置を示す。一年を通して 24 時間間隔で取り込む。 |
この形の長軸 ―― アナレンマの最北端と最南端を結ぶ線分 ―― は、ほぼこれに垂直な天球の赤道で 2 等分され、 黄道の離心率の 2 倍の「長さ」 ("length") ―― およそ 47° ―― がある。 太陽の見かけの動きの、この軸に沿った成分は、一年を通しての 太陽の赤緯の馴染みの季節変動の結果である。 この形の幅は、均時差に起因し、 時刻の違いが 1 時間に 15° の比率 (すなわち 24 時間で 360°) で角度に関係する時、 その角度の範囲 (angular extent) は、地方太陽時の地方平均時からの最大の正と負の逸脱の差である。 アナレンマの幅はおよそ 7.7° で、従ってこの形の長さは幅の 6 倍以上である。 8 の字の形のループの大きさの違いは近日点と遠日点が秋分・春分から遠くで起きる事実から主に生じている。 その代わり、これらは夏至・冬至の数週間あとに起き、今度は 8 の字のわずかな傾きと ささいな横方向の非対称の原因となっている。
アナレンマのサイズと形に影響する 3 つのパラメーターがある ―― 赤道傾斜角 (obliquity)、 軌道離心率 (eccentricity)、そして北方の春分・秋分と近点の間の角度である。 完全な円軌道と軸の傾きがない天体から見ると、 太陽は 1 年を通して、1 日の同じ時刻に常に天空の同じ場所に登場し、アナレンマは点になる。 円軌道を持つが、随分と軸が傾いている天体に関しては、アナレンマは 8 の字形で北と南のループ (lobe) は サイズが同じである。 偏心軌道 (eccentric orbit) であるが、軸の傾きがない天体に関してはアナレンマは天空の赤道に沿った、真っすぐな 東西の直線である。
アナレンマの南北成分は太陽の赤緯 (Sun's declination) ―― 天球 (cerestial sphere) における緯度、 あるいは太陽が真上となる地球の緯度 ―― を示している。 東西成分が示すのは均時差、あるいは太陽時と地方平均時の違いである。 これは太陽 (あるいはアナレンマ日時計) が時計時間と比較して、 進んでいる時間量、あるいは遅れている時間量と解釈できる。 これは平均位置と比較して、太陽がどの程度、西よりか東よりかを示している。 アナレンマは太陽の赤緯と均時差を互いにプロットしたグラフと考えることができる。 多くのアナレンマの図式で第 3 の次元 ―― 時間 ―― も含まれ、 色々と随分密接な間隔の 1 年中の日付で、太陽の位置を表示する印が含まれている。
図式ではアナレンマは観測者が空を見上げた時に見えるように描かれる。 もしも北が上であれば西は右であり、均時差の符号 ―― 西方向が正 ―― と対応する。 平均の位置と比較して、太陽が更に西にあれば、日時計は時計と比較してもっと速い。 アナレンマが正の赤緯 (北) を上方に描いた図式であれば、 正の均時差 (西) は右にプロットされる。 これはグラフの伝統的方法である。 アナレンマが地球儀でマークされる時はアナレンマの西は右で、地球儀の地理的造作は 西が左に表示される。 混乱を避けるために、地球儀のアナレンマは左が西になるように印字することが提案されたが あったが、これはされなかった、少なくとも、頻繁には。 実際にはアナレンマは対称に非常に近く、ミラーイメージは簡単に区別できないが、日付の印があれば逆方向に行く。 太陽は夏至・冬至の近くでアナレンマの上で東に動く。 これにより、アナレンマがどの方向に印刷されているかの伝達に使用できる。 下の画像を 高解像度で見よ。
日食の画像を含むアナレンマは tutulemma と呼ばれる。 これは写真家の Cenk E. Tezel と Tunç Tezel によって作られた用語で、 トルコ語の日食の言葉に基づいている。
プトレマイオスによる本「アナレンマ」 (ギリシャ語 Περὶ ἀναλήμματος) は与えられた時間に 地理的緯度に対する太陽や他の任意の天体の天球座標をプロットする方法を扱っている。 日時計の建造はそのような考察に依存している。
アナレンマ (analemma) は 直投影 (orthographic projection) の日常的名称であったが、 1613 年に アントワープ (Antwerp) のフランソワ・ダギヨン (François d'Aguilon) が現代の名称に奨励した。
1644 年に数学者のジャン・ルイ・ヴァレザール (Jean-Louis Vaulezard) は アナレンマ日時計 (analemmatic sundial) がフランス (恐らくは世界) で始めて設置されたことを 記述している。 この日時計はブルー教会 (church of Brou) に設置され、8 の字のアナレンマを描いている。
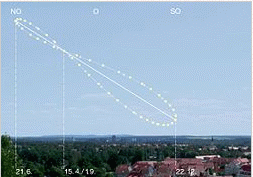
|
|
日付の入ったアナレンマが地球儀に印刷
オーストリア, ウィーン, 地球儀博物館 |
アナレンマは (用語の現代の意味で) 18 世紀以来、日時計と結合して 使用され、視太陽時と平均太陽時の間の変換をした。 これ以前には、この用語はもっと一般的な意味があり、 3 次元オブジェクトを 2 次元に表示する描画手順 (graphical procedure) ―― 現在は 直投影と呼ばれる ―― を言及した。
アナレンマは初期の地球儀にしばしば表示された。 このような実例の 1 つに 1846 年製造のジョージ・ウッドワード (George Woodward) による地球儀がある。 1812 年にジョン・レイスロップ (John Lathrop) は次のように書いている。
地軸の傾き (23.439°) と地球軌道の離心率 (eccentricity) により、 地平線上の太陽の相対位置は毎日同じ時計時刻で観測すると毎日一定ではない。 観測時刻が地方平均時の正午 12:00 でなければ、地理的緯度に依存して、このループは異なる 角度に傾く。
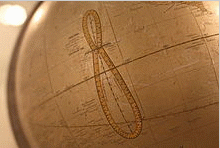
|

|
|
|
グリニッジ王立天文台の GMT 正午のアナレンマ
のプロット (北緯 51.48°, 西経 0.0015°) |
この日時計のアナレンマの出力が
影の端を真の時刻に落とす。 |
この節の図は北半球の地球から見たアナレンマの実例である。 これは 2006 年のイングランド、グリニッジ王立天文台 (緯度 51.48°N, 経度 0.0015°W) の 正午 12:00 における太陽の位置のプロットである。 水平軸は方位角の角度表示である (180° は南を向く)。 垂直軸は地平線上高度の角度表示である。 各月の最初の日は黒で記され、夏至・冬至と春分・秋分は緑で表示されている。 見て取れることは、春分・秋分はおよそ高度 φ = 90° - 51.5° = 38.5° ([訳注: 51.5° の余緯度]) で起き、 夏至・冬至がおよそ高度 φ ± ε (但し ε は地軸の傾き 23.4°) で 起きることである。 アナレンマは幅が随分と誇張されてプロットされ、 わずかな非対称を見せている (これは地球の 近点・遠点 (apsides) と夏至・冬至の間の 2 週間の不整合によっている)。
アナレンマは小さなループが大きなループの北に登場するように向きづけられている。 北極圏では、アナレンマは完全に上向き (頂上に小さなループがある 8 の字) で、 この上半分のみ見える。 南に向かい、一旦、北極圏の南に出れば、アナレンマ全体が見える。 もしも正午に見れば、上向きのまゝで、観察者が南に移動すれば、 地平線から高く持ち上がる。 赤道では、まっすぐ上である。 更に南では、北の地平線に向かって移動し、次に大きなループが上に見える。 アナレンマを朝方あるいは夕方の速い時刻に見れば、 観察者が北極から南に動くにつれ、一方に傾き始める。 赤道ではアナレンマは完全に水平になることになる。 観察者が南に向かい続ければ、これは回転して、天空で小さなループが大きなループの下になることになる。 南極圏に入れば、アナレンマは今や完全に逆向きになって消え始め、 終に 50% のみ ―― 大きなループの一部 ―― が南極から見えることになる。
アナレンマの東西の性質のもっと詳細な説明は均時差を参照せよ。
かって作成された最初の成功裏のアナレンマ写真は 1978 年 - 1979 年に 写真家のデニス・ディ・シコ (Dennis di Cicco) によりマサチューセッツ州 ウォータータウン (Watertown) で作られた。 カメラを動かさずに、彼はフィルムの 1 コマに、44 回露出し、 少なくとも 1 週間離して、すべて 1 日の同じ時刻に撮影した。 前景の画像と、3 回の長い露出も同じフレームに含まれ、全体の露出回数を 48 回にした。
アナレンマの写真撮影は技術的・現実的挑戦を提示するかもしれないが、 アナレンマは、地表の任意の与えられた場所に対して、 3D プロットで都合よく計算・提示できる。
アイデアは、地表の選択された点に原点を固定し、 方向が常に太陽の中心を指す単位ベクトルに基づく。 もしも我々が太陽の位置 ―― すなわち、太陽の高度と方位の角度を 例えば 1 時間ステップで、完全に 1 年間計算すれば、 単位ベクトルの頭部は、選択された点を中心とする単位球面上の 24 個のアナレンマをたどり、この単位球面は天球と同等である。 下左の図は合衆国本土 (contiguous United States) の地理的中心において計算された 「アナレンマの花輪」(wreath of analemmas) である。
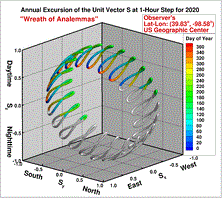
|
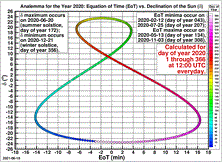
|
|
| 「アナレンマの花輪」 合衆国本土の地理的中心で 1 時間間隔の計算アナレンマ, 灰色は夜間 | アナレンマ : 均時差×太陽の赤緯, 2020年用の計算。 Astronomical Almanac for the year 2019 の公式 を使用。 |
地球儀でよく見られるように、アナレンマは「均時差 × 太陽の赤緯」の二次元図 としても、しばしばプロットされる。 上右の図 (「アナレンマ : 均時差 ...」) は 参考文献で提示されたアルゴリズムを使用して計算されており、参考文献は 「2019 年の天文暦」 (The Astronomical Almanac for the Year 2019) で与えられた 公式を使用している。
もしも、随分規則正しく太陽の位置がマークされていれば (例えば、各月の 1 日、11 日、21 日)、 アナレンマは、 太陽の平均位置に相対的な見かけ上の動きの、1 年を通した要約である。 日付でマークされたアナレンマの図式は、 南北と東西方向に同じスケールであれば、 太陽の位置に依存する日の出・日の入り時刻のような量を評価する道具として使用できる。 一般に、これらの評価は、アナレンマを天空の剛構造とする視覚化に依存し、 剛構造が地球の周りを一定速度で移動し、一日に一度、昇って沈み、太陽がここをゆっくり移動して 一年で一周する。
その過程で少々の近似が関連し、 主に天球における、位置表示のための平面図式の使用と、 数値計算のかわりに絵と計測の使用が関連する。 この理由から、評価は完全に正確ではない。 しかし実際の用途には十分である。 又、これは教える価値があり、日の出と日の入りの変化の仕方が、 単純な視覚的方法で示される。
アナレンマは一年の、最も早い、そして最も遅い、日の出と日の入りの日付の発見に 使用できる。これらは夏至・冬至には使用できない。
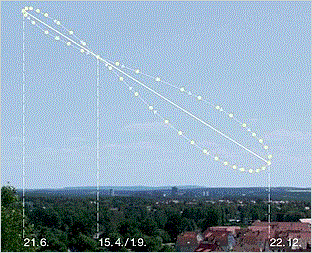
|
| アナレンマの図式、北半球で東を見る。 太陽の日付の位置が表示。このアナレンマは gam のために計算、写真撮影ではない。 |
東の空のアナレンマ・シミュレーションの画像に関して、 アナレンマ最低点は水平線の上に丁度昇った所にある。 太陽がその点にあれば、日の出は丁度起きたことであろう。 これは一年の最も遅い日の出である。 というのは、アナレンマの他の全ての点は、より早く 昇るからである。 従って、最も遅い日の出の日付は、太陽がこの最も低い点にいる時である。 (12 月 29 日、図式に示されているようにアナレンマが北緯 50° から見たように傾く時) しかしながら、夏時間を使用している場所では 最も遅い日の出は夏時間が終わりになるよりも以前の日に起きる。 同様に、太陽がアナレンマの最高点 ―― 上端の左 ―― にある時 (6 月 15 日) に、1 年で最も早い日の出が起きる。 同様に日の入りに関して、 最も早い日の入りが起きるのは、 太陽がアナレンマの最低点にある時である。 そして、最も遅い日の入りが起きるのは最高点にある時である。
これらのどの点も、正確にはアナレンマの末端 ―― 冬至・夏至 ―― の 1 つではない。 北方の中緯度から見ると、図式が示すように、最も早い日の入りは 12 月の 冬至以前のある時 ―― 典型的には 1, 2 週間前 ―― に起き、 そして最も遅い日の入りは夏至の 1,2 週間あとに起きる。 従って、最も暗い夕方は 12 月始めから中ごろに起きるが、朝は新年ごろまでどんどん暗くなる。
正確な日付は、地平線がアナレンマに接する点に太陽がいる時のものであり、 これは、今度は、 アナレンマ、あるいはこれを通る南北の子午線が、どれほど垂線 (vertical) から傾いているかに依存する。 この傾きの角度は本質的に、観測者の余緯度 (co-latitude, 90° - 緯度) である。 この日付を数値的に計算することは複雑であるが、随分正確に評価でき、 これには直定規 (straight-edge) を適当な角度で傾けて、 アナレンマの図式に接して置き、太陽が接触の位置にある時に、 日付 (必要であれば補間する) を読む。
中緯度では、緯度の絶対値が減少するにつれ、日付は夏至・冬至から更に進む。 赤道に近い緯度では、事情はもっと複雑である。 アナレンマはほとんど水平で、地平線はアナレンマに 2 点で接することができる (アナレンマの各ループに 1 点づつ)。 従って、1 年には 2 つの随分離れた日付で、隣接する日付よりも太陽が早く上るときがある、..... 等々。
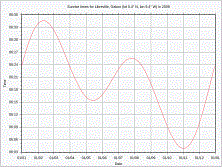
|
| ガボン (Gabon), リーブルヴィル (Libreville) の日の出時刻のグラフ, ここは赤道にとても近い、2 つの極大値と 2 つの極小値に注意 |
アナレンマに基づく類似の幾何学的方法は、 地球上の任意の場所 (北極圏と南極圏の内部とその周辺は除く) と任意の日付で。 日の出と日の入りの時刻を見つけるのに使用できる。
アナレンマの原点では、太陽の赤緯 (solar declination) と均時差が共に 0 となり、 観測者の緯度にかかわらず、毎日、地方平均時の 6 a.m. と 6 p.m. に 昇って・沈む。(この評価は大気の屈折を考慮に入れない)。 もしもアナレンマを図式に描き、 (上で述べたように) 観測者の緯度にとり適切な角度で傾ければ、 そしてもしも、水平線を任意の与えられた日に (必要であれば日付の印を補間して) アナレンマの太陽の位置を通るように描けば、 日の出にこの線は地平線を表示する。
原点は時速 15° (地球の回転速度) で天球の赤道に沿って動くように見える。 地平線に交差する点から日の出におけるアナレンマの原点までの天球の赤道に沿った距離は、 与えられた日に原点が 6 a.m. から日の出まで動く距離である。 この赤道の弧の長さを計測すれば 6 a.m. と日の出時刻の間の違いを与える。
計測は無論図式ですべきであるが、 これは地上の観測者に対して (天空のアナレンマでの対応距離を) 角度の形で表示すべきである。 これを 47° に対応するアナレンマの長さと比較することが有益となり得る。 従って、例えば図式の赤道の弧 (equatorial segment) の長さが、 図式のアナレンマの長さの 0.4 倍であれば、天球アナレンマの弧 (segment) は 地上観測者の 0.4×47° = 18.8° に対応する。 角度表示の角度から、日の出と 6 a.m. の間の時刻差を時間表示するには 15 で割る。 差の符号は図式から明らかである。もしも日の出における地平線の直線がアナレンマ原点の上を 通過すれば、太陽は 6 a.m. より前に昇り、逆も正しい。
同じテクニックはmutandis mutandis (準用・類推適用, ムタンディス・ムタンディス) により、日の入り時間を評価するのに使用できる。 評価された時間は地方時間である。 標準時や夏時間に変換するには補正が必要である。 これらの補正は観測者の経度に関連する項を含み、 従って、緯度と経度のどちらも最後の結果に影響する。
太陽が昇り・沈む場所の、地平線上の点の方位角 (真のコンパス方位) は、 上で説明した日の出・日の入りの時刻を見つけるために使用したものと同じ図式を使用して、 簡単に評価できる。
地平線が天球の赤道と交差する点は真東あるいは真西を表す。 太陽が日の出あるいは日の入りをする場所は日の出、日の入りの方向を表す。 これらの点の間の地平線に沿った距離を単純に計測すれば、 角度では (上で説明したように、アナレンマの長さと比較すれば)、 真東あるいは真西との間、そして日の出あるいは日の入りとの間の角度がわかる。 日の出あるいは日の入りが真東あるいは真西の北あるいは南であるかは、 図式から明らかである。 アナレンマのより大きなループは南端にある。
地球上ではアナレンマは 8 の字の形に見えるが、他の太陽系の天体ではとても違っている。 その理由は以下の相互作用である : 天体の軸の傾き、軌道が円でない事 (軌道の離心率)、 そして北方の春分・秋分と近点 (northward equinox and the periapsis) の間の角度。 傾きは、アナレンマを 8 の字にする傾向がある、というのは、これは 太陽の実際の位置が 1 年に 2 回平均太陽時より進むからである。 (そして、従って 2 回太陽時より遅れて進む。) 軌道が円でないことにより、アナレンマが 0 の字のようになる傾向があり、 ケプラーの惑星の運動に関する第 2 法則により、 1 年に 1 回、太陽の位置が平均太陽時の前を進む傾向がある。 火星の場合には、2 つの効果の和が涙の雫 (teardrop) の形のアナレンマを与える。 木星は、たった 3° の傾きしかなく、近似的に楕円のアナレンマを与える。
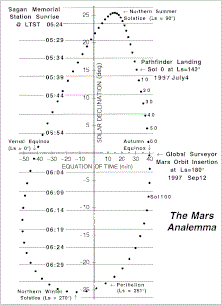
|
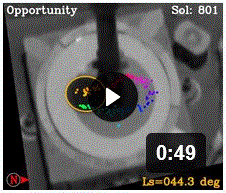
|
| 火星から見たアナレンマの 1 つ | 火星のアナレンマのコマ落とし撮影 オポチュニティ (Opportunity rover) の MarsDial の像を使用して作成 |
次の一覧で、1 日 (day) と 1 年 (year) は特定の天体の 1 日 (synodic day) と恒星年 (sidereal year) を言及する。
対地同期衛星 (geosynchronous satellites) は周期が 1 恒星日で地球の周りを回転する。 地球上の固定点から見ると、対地同期衛星は天空の通り道をたどり、 これを毎日繰り返す。従って、これは意味があるアナレンマである。 これは一般に大まかに、形が : 楕円、涙の雫 (teardrop)、あるいは 8 の字である。 その形と寸法は軌道のパラメーターに依存する。 対地同期衛星 (geosynchronous satellites) の部分集合に 静止衛星 (geostationary satellites) があり、 これは地球の赤道平面の中に、理想的に完全な円軌道を持つ。 静止衛星は従って、地表に相対的に静止し、赤道上の唯一の点に滞在する。 実際の衛星はどれも正確には静止衛星ではなく、従って天空の小さなアナレンマをたどる。 対地同期衛星の軌道の大きさは地球の大きさに大差なく、 地表の観測者の位置に依存して視差が随分あり、従って異なる場所の観測者は異なるアナレンマを見る。
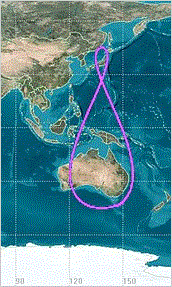
|
| 準天頂衛星システム (QZSS) 地上航跡、対地同期衛星軌道。 地上から見れば、このアナレンマは類似の形。 |
対地同期衛星により無線通信に使用されるパラボラアンテナ (paraboloidal dishes) は アナレンマの周りの衛星の動きを追跡するために、しばしば向きを変えなければならない。 従って、アンテナ駆動のメカニズムはアナレンマのパラメーターでプログラムしなければならない。 例外は (近似的に) 静止する衛星に使用されるパラボラアンテナ (dish) である。 このような衛星はほとんど動かないので、固定した衛星アンテナがいつでも適切に機能する。
準衛星 ―― 例えば図式で示されるもの ―― は太陽をまわる 順行軌道(prograde orbit) を動く。 この軌道はこれが同行する惑星と同じ軌道周期 (これは 1 年とも呼ばれる) を持つが、 異なる (通常はより大きな) 軌道離心率を持つ。 惑星から見ると、一年に一度、逆方向 (retrograde direction) に惑星の 周りを回転するように見えるが、異なる速度で、恐らくは黄道面に属さない。 平均位置に相対的に、黄道を一定速度で動き、準衛星は惑星の天空のアナレンマの跡をたどり、 1 年に 1 度、この周囲を動く。
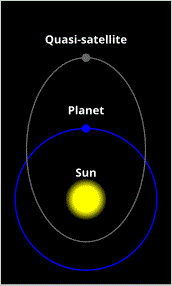
|
| 準衛星の軌道図式 |