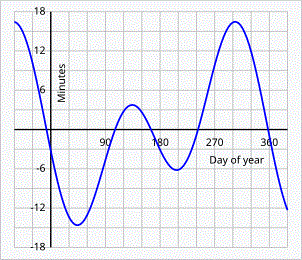
|
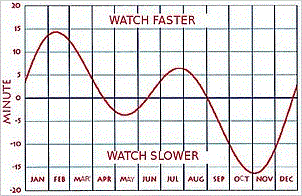
|
|
| 均時差: 軸より上では、日時計は地方平均時を示す時計に相対的に早く、 軸より下では、日時計より遅い。 | このグラフは時計が視太陽よりも、何分早いか (+)、遅いか (-) を示す。 以下の「記号」の章を参照。 |
以下の文書の翻訳です。
Equation of time - Wikipedia (均時差)
均時差とは、おおまかには日時計 (視太陽時)と機械式時計 (平均太陽時) の 食い違いのことで、主な原因は地球の太陽をまわる軌道が楕円であることと、 地軸の傾きによっている。軌道と地軸の傾きの長期的変動を無視すれば、 均時差の存在は機械式時計がなくても、恒星時との食い違い (太陽の黄道における位置を使用する) から 知ることができ、その理由から古代にも知られていたようである (古代ギリシャ)。 近世には振り子時計などの機械式時計で時刻を正確に合わせるのに 「日時計 + 均時差の表」が必要であった。(19 世紀以後, 鉄道などの日常生活)。 現代では、時計が非常に正確になったため、均時差の用語は日常生活から完全に消えている。
均時差は 2 種類の太陽時の食い違いを記述する。 異なっている 2 つの時間とは、 視太陽時 (aparent solar time, 太陽の日中の動きを直接たどる) と平均太陽時 (mean solar time, 天空の赤道に沿って一様な動きをする理論的な平均太陽をたどる) である。 視太陽時は太陽の現在位置 (時間の角度 (hour angle)) の計測により得ることができ、 日時計により (限定された精度で) 示される。 同時に平均太陽時は、安定した時計装置により示される時刻で、 1 年間では、視太陽時との違いは平均して 0 になる。
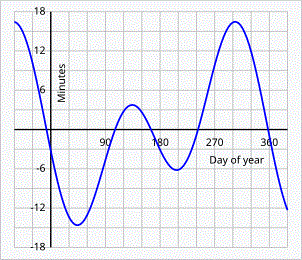
|
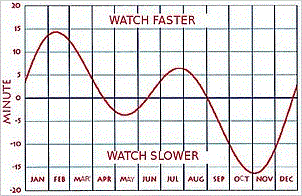
|
|
| 均時差: 軸より上では、日時計は地方平均時を示す時計に相対的に早く、 軸より下では、日時計より遅い。 | このグラフは時計が視太陽よりも、何分早いか (+)、遅いか (-) を示す。 以下の「記号」の章を参照。 |
均時差はアナレンマの東成分あるいは西成分で、 アナレンマとは太陽の天球における平均位置からのオフセット角を表す曲線である。 1 年の毎日の均時差の値は、天文台により蓄積されて、 天体暦 (almanacs and ephemerides) に広く一覧表にされている。
均時差は 2 つの正弦曲線の和によって近似できる。
Δtey = -7.659 sin(D) + 9.863 sin(2D + 3.5932) [分]
ここで:
D = 6.240 040 77 + 0.017 201 97 (365.25 (y - 2000) + d
但し、d は 現在の年 y の 1 月 1 日からの日数を表示する。
1 年の間に均時差はグラフで示されるように変化する; ある年から別の年への 変化はわずかである。 視太陽時と日時計は 16 分 33 秒ほども進み (11 月 3 日頃)、あるいは 14 分 6 秒ほども遅れる (2 月 11 日頃)。 均時差が 0 になるのは 4 月 15 日、6 月 13 日、9 月 1 日 そして 12 月 15 日の近くである。 地球の軌道と回転の随分ゆっくりした変化を無視すれば、 これらのイベントは 太陽年 (tropical year) 毎に同じ時に繰り返される。 しかしながら、1 年の日数が整数値でないことにより、これらの日は年ごとに 1 日程度は違い得る。 日々の不正確さの実例の 1 つは 米国海軍天文台 (US Naval Observatory) の 「対話式計算機年鑑」 (Interactive Computer Almanac) によれば、 均時差は 2011 年 4 月 16 日の 0:200 UT1 (世界時) で 0 であった。
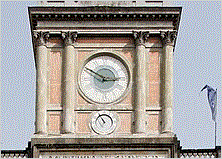
|
| 時計、補助の盤面が均時差を表示 ナポリ, ダンテ広場 (Piazza Dante) (1853) |
均時差のグラフは 2 つの正弦曲線の和によって密接に近似され、1 つの正弦曲線は 1 年の周期、 もう 1 つは 1/2 年の周期がある。 2 つの曲線は 2 つの天文的影響を反映し、各々は星に相対的な、太陽の見かけ上の毎日の動きに、 異なる非一様性を引き起こしている。
均時差がなくなるのは。軸の傾きが 0 で、軌道の離心率が 0 の惑星のみである。 大きな均時差を持つ惑星の 2 つの実例は火星と天王星 (uranus) である。 火星上では軌道の離心率が随分大きいため、日時計時間と時計時間の違いが 50 分にも及ぶ。 惑星の天王星は極端に大きな軸の傾きがあり、 均時差は、軌道上のどこにあるかに依存して、日々が数時間、前後して開始・終了する。
米国海軍天文台が述べることは、 「均時差は視太陽時から平均太陽時を引いた差」、即ち、 もしも太陽時が時計よりも進んでいれば正、もしも時計が太陽よりも進んでいれば負である。 均時差は 1 年よりわずかに長い期間に、上の左のグラフで示されている。 右のグラフ (これは丁度カレンダー 1 年間に及ぶ) は同じ絶対値を持つが、符号は逆である。 というのは時計がどれほど太陽より進んでいるかを示しているからである。 出版物はどちらの形式を使用してもよい。 英語圏では前者がより一般的であるが、常にこの通りではない。 印刷された表やグラフを使用するものは、最初に符号の使用法をチェックすべきである。 しばしば、これを説明する注意あるいは標題がある。 そうでなければ、毎年の最初の 3ヶ月に、時計は日時計より進んでいることで使用方法を決定できる。 省略用語 (二―モニック) の "NYSS" (ナイスと発音) は、 「新年」 (new year)、「日時計が遅い」 (sundial slow) の省略で、便利である。 印刷された表によっては、符号による曖昧さを避けるために、 「日時計が速い」あるいは「日時計が遅い」のような表現をする。
「均時差」(equation of time) の用語は中世ラテン語の (aequātiō diērum) に 由来し、これは「日々の差」 ("equation ofdays") あるいは 「日々の違い」 ("difference of days") を意味する。 単語の equation は中世の意味である "reconciliation of a difference" (「違いの和解」) で 使用された。 単語の aequātiō (そして 中英語の equation) が中世の天文学に使用され、 観測された値と予期された値の違いを表にするために使用された (例えば、 the equation of the center, the equation of the equinoxes, the equation of the epicicle がある)。 ジェラルド J. トゥーマー(Gerald J. Toomer) は、 プトレマイオスの平均太陽時と視太陽時の違いを示すために、 ラテン語の aequātiō (同等化 (equalization) あるいは 調節 (adjustment)) に由来する 中世の用語 "equation" を使用する。 equation の ヨハネス・ケプラー (Johannes Kepler) の定義は 「平均近点 (mean anomaly) の度・分と 修正された近点 (corrected anomaly) の度・分の間の違い」 である。
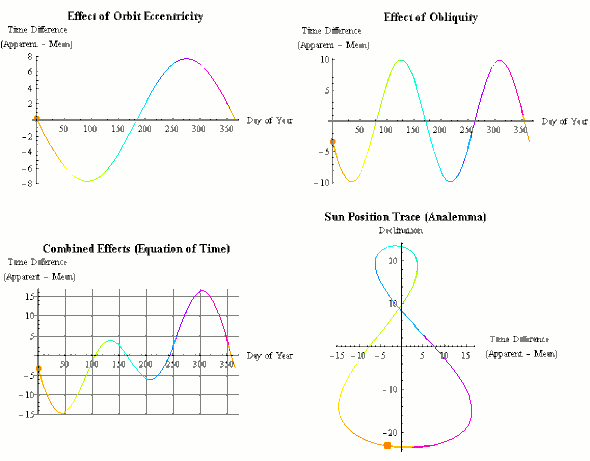
|
| 1 年間に及ぶ均時差とアナレンマを示す動画 |
視太陽時と平均時の間の違いは古代から天文学者に認められていたが、 17 世紀に正確な機械時計が発明されるまでは、 日時計は唯一の信頼できる計時装置であり、視太陽時は一般に認められた標準であった。 19 世紀始めまで、平均時は 国内天体暦 (national almanacs and ephemerides) で視太陽時にとってかわることがなかった。
太陽の不規則な動きはバビロニア人に知られていた。
プトレマイオスの アルマゲストの巻 III (Book III) (2 世紀) は 主に太陽の変則 (anomaly) に関連し、彼は Handy Tables (手近な表) で均時差を表にした。 プトレマイオスは、太陽の子午線通過 (meridian crossing of the Sun) を 平均太陽時 (mean solar time) に変換するのに必要な補正を議論し、 黄道に沿う太陽の一様でない動きと、黄経 (ecliptic longitude) の 子午線補正 (meridian correction) を考慮に入れている。 彼が述べることでは、最大補正は 8 1/3 時間-角度、あるいは 1 時間の 5/9 である (巻 III, 9 章)。 しかしながら、彼は大半の計算でこの効果が意味があるとは考えなかった。 というのはこれはゆっくり動く発光体 (luminary) には無視でき、早く動く発光体 ―― 月 ―― のみに適用された。
アルマゲストにおけるプトレマイオスの議論に基づいて、 均時差 (アラビア語 taʿdīl al-ayyām bi layālayhā) の値は、 中世イスラム天文学の本の表 (tables, Zij) の標準であった。
視太陽時と平均太陽時は ネヴィル・マスケリン (Nevil Maskerlyne) により、1676 年の 航海年鑑 (Nautical Almanac) で 与えられた : 『視太陽時は太陽から直ちにわかり、子午線通過の観測、 あるいは日の出と日の入りの観測から推測される。 この時刻は時計や懐中時計によって示される時刻とは違い、 こちらは陸上で良く制御され、平均時間と呼ばれる。』 彼は続けて次のように述べている: 海上では太陽観測からわかる視太陽時は、もしも観測者が平均太陽時を必要とすれば、 均時差で補正しなければならない。
正しい時刻は元々は日時計で表示されるものと考えられていた。 良好な機械式時計が導入された時、これらは毎年 4 日間の近くのみで日時計と一致した。 幾つかの時計は均時差時計 (equation clocks) と呼ばれ、この補正を実施する内部機構を 含んでいた。 後に時計が支配的に良好な計時装置になった時に、補正されていない時計時刻 (clock time)、即ち「平均時」 (mean time) が 認められた標準になった。 従って、日時計の読み取りは、使用されれば、当時、そして現在でもしばしば、 以前とは逆の方向で使用されて、均時差で補正されて時計時間が得られた。 従って、多くの日時計には均時差の表、あるいはグラフが刻印されて、 使用者がこの補正をすることを可能にしている。
均時差は歴史的には時計を合わせるために使用された。 1656 年の正確な時計の発明と 1900 年頃の商用の時刻配信サービスの到来の間に、 陸上に基礎を置いた時計合わせの幾つかの方法があった。 日時計が読み取られ、均時差の表やグラフで補正された。
もしも子午線装置 (transit instrument, 子午儀) が利用可能か、精度が重要であれば、太陽の 子午線通過 (太陽が、観測者の真南あるいは真北に現れる時のこと、南中と呼ばれる) が留意され、時計が正午に設定され、この日の均時差で与えられる時間で相殺された。 第 3 の方法は均時差を使用しなかった ; その代わりに星の観測をして 恒星時を決定し、恒星時と平均太陽時の間の関係を利用した。 もっと正確な方法は 本初子午線 (prime meridian) との関連で、観測者の経度を見つけるための先駆でもあり、 例えば陸上の 測地学 (geodesy) と海上の 天測航法のようなものであった。
本質的に正しい方法で、均時差を与えた最初の表は、 1665 年に クリスティアーン・ホイヘンス (Christiaan Huygens) により出版された。 ホイヘンス (Huygens) は一般にプトレマイオスと中世の天文学者の伝統に従って、均時差の値を一年を通して、正になるように設定した。 これが意味することは、ホイヘンス (Huygens) の表により平均時間に設定されたどの時計も、 今日の平均時間と比較すると、一貫しておよそ 15 分遅かった。
別の表一式が 1672 年 - 1673 年に ジョン・フラムスティード (John Flamsteed) により出版され、 彼は後に新しい 王室グリニッジ天文台 (Royal Greenwich Observatory) の最初の 王室天文官 (Atronomer Royal) になった。 これは、今日の平均時を与えた最初の本質的に正しい表であったようである。 (これ以前は、上で注意したように、平均時の符号は常に正であり、日の出の視太陽時が、 日の出の時計時間と関連して最も早い時が 0 に設定されていた。) フラムスティードは補正の集計・命名の慣例を、 平均時を得るために視太陽時に適用という意味で採用した。
太陽の動きの見かけ上の不規則性の 2 つの重要成分に、正しく基づいた均時差は、 1672 年 - 1673 年のフラムスティードの表までは一般に採用されなかった。 この表は エレミア・ホロックス (Jeremiah Horrochs) の本の死後出版と共に出版された。
ロバート・フック (Robert Hooke, 1635 年 - 1703 年) は、数学的に 自在継手 (universal joint) を解析し、 (非長期な) 均時差 ((non-secular) equation of time) と自在継手 (universal joint) の 幾何学・数学的記述が同一であることを注意した最初の人で、 機械式日時計 (non-mechanical sundial) の建造に自在継手 (universal joint) の使用を提案した。
1672 年 - 1673 年 及び 1680 年のフラムスティード (Flamsteed) の表の修正は平均時を本質的に計算し、 更なるオフセットの必要をなくした。 しかし、均時差の表の数値はそれ以来、少々変化し、それは 3 つの因子によっていた。
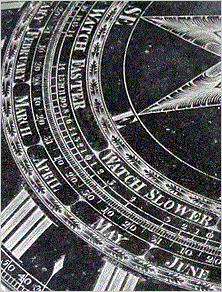
|
| 1812 年に「ホワイトハースト&サン社」 (Whitehurst & Son) が製造した日時計。 円形目盛りが均時差補正を示す。 これは現在 ダービー博物館・美術館に展示 |
1767 年から 1833 年に、英国の 航海年鑑 (Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris) は 以下の意味で、均時差を表にした : 視太陽時から平均太陽時を得るために、 (指示されたように) 分、秒を加えたり、引いたりした。 航海年鑑 (Almanac) の時間は、視太陽時であった。というのは船上の時間は、もっとも頻繁には太陽の観測に よって決定されたからである。 この操作は平均太陽時が必要とされる普通とは違った場合に実施された。 1834 年以来の版では、すべての時間は平均太陽時であった。というのは、この時までに 船上の時刻はますます頻々として、海洋クロノメータによって決定されたからである。 指示されたことは、その結果、視太陽時を得るために (指示されたように) 時間を 平均時に加える、あるいは引くことであった。 従って、今や加えることは正の均時差に対応し、引くことは負の均時差に対応した。
太陽の見かけ上の動きは 1 日に 1 回転、すなわち 24 時間で 360° であり、 太陽自身が空中で 0.5° の円板に見え、単純な日時計は最大精度がおよそ 1 分まで 読み取ることができる。 均時差はおよそ 33分の範囲があるので、日時計時間と時計時間の違いは無視できない。 均時差に付け加え、地方時間帯の子午線からの距離による補正、及び夏時間であれば、これによる補正も 適用しなければならない。
地球の回転の減速による平均太陽日のわずかな増加は、 1 世紀当たり 1 日におよそ 1 ミリ秒で、 現在は毎年 1 秒ほど累積しているが、これは 均時差の伝統的な定義に組み込まれない、というのは、これは 日時計精度のレベルでは感知不可能だからである。
地球は太陽のまわりをまわっている。 地球から見ると、太陽は 1 年で背景の星を通り抜けて、地球の周りを 1 度回転するように見える。 もしも地球が一定速度で、地球の軸に垂直な平面内を円形軌道で太陽をまわれば、 太陽は毎日正確に同じ時刻に南中し、完全な計時装置になる。 (但し、地球の減速する回転による非常に小さな影響を除く。) しかし地球の軌道は楕円で、太陽を中心にしておらず、 ケプラーの法則 (Kepler's laws of planetary motion) により、 その速度は 30.287 km/s と 29.291 km/s の間で変化し、 その角速度も変化する。 従って、太陽は 近日点 (現在は 1 月 3 日頃) で (背景の星に相対的に) より速く動き、 半年後の 遠日点で遅く動くように見える。
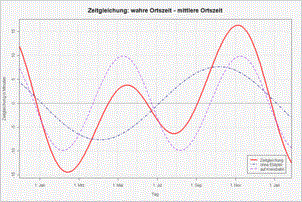
|
| 均時差 (赤の実線) とその 2 つの主要成分が別々にプロット、 黄道の傾斜による部分 (ふじ色の破線) と地球軌道の離心率による 黄道に沿った太陽の見かけの速度による部分 (黒青破線 & 点線) |
このような極端な点で、この影響は見かけ上の太陽日を平均から 7.9 秒/日 で変化する。 その結果、それ以外の日における速度のより小さな毎日の変化がこれらの点まで集積し、 惑星が平均と比較して、加速・減速する方法を反映している。
結果として、地球の軌道の離心率は周期的な変動に貢献し、 これは (一次近似 (first order approximation) で) 次の性質を持つ正弦曲線となる :
EofT (均時差) のこの成分は前述の因子 a で表示される :
a = -7.659 sin(6.240 040 77 + 0.017 201 97 (365 (y - 2000) + d))
地球の軌道が円であっても、天球の赤道に沿う太陽の理解された動きは、なお一様ではない。 これは地球の回転軸の軌道面に対する傾き、 あるいは同等なことであるが、天球の赤道に対する黄道 (= 太陽が天球で通過するように見える道) の傾きの 結果である。 天球の赤道 (これに沿って時計時間が測定) への、この動きの射影は、 夏至・冬至に最大で、 この時、太陽の毎年の動きが赤道に平行となり (認識される速度の拡大を誘導し)、主に赤経における変化を引き起こす。 これは春分・秋分の時に最小で、この時太陽の見かけの動きはもっと傾いて、 赤緯の変更がもっと起き、赤経成分の変更が少なくなる。 この赤経成分が太陽日の持続に影響する唯一の成分である。 軸が斜めであることの現実的描写は、 太陽が日時計に落とす影の毎日の変化 (shift) は、 赤道においてさえ、夏至・冬至の近くでより小さく、 春分・秋分の近くでより大きいことである。 この効果が単独で作用すれば、その時、 1 日は、夏至・冬至の近くでは 24 時間 + 20.3 秒までもの長さで (太陽の南中から南中までを計測)、 春分・秋分の近くでは 24 時間よりも 20.3 秒までも短い。
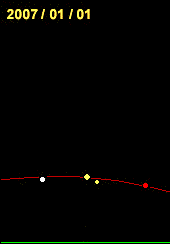
|
| 地方視太陽時の太陽と惑星 (黄道は赤, 太陽と水星は黄色, 金星は白, 火星は赤, 木星は赤い点がある黄色, 木星は輪がある白) |
上の図で、地球から見た太陽時間正午の黄道面の見かけ上の傾きの毎月の 変動を見ることができる。 この変動は、太陽時正午における太陽から見えるように、 1 年を通して回転する地球の見かけ上の 歳差 (precession) によっている。
均時差に関して、黄道の傾きにより、 正弦波変動への寄与において、次のような結果になる:
この EoT (均時差) の成分は前述の因子 "b" により表示される :
b = 9.863 sin(2(6.240 040 77 + 0.017 201 97 (365 (y - 2000) + d) + 3.5932)
上で言及した 2 つの因子は 異なる波長 (wavelength)、 振幅 (amplitude)、 相 (phase) があり、 結合した寄与は不規則な波である。 元期 2000 年に、これらは以下の値 (分、秒、 UT 日付) を持つ。
| 点 | 値 | 日付 |
|---|---|---|
| 極小 | -14分15秒 | 2月11日 |
| 0 | 0分0秒 | 4月15日 |
| 極大 | +3分41秒 | 5月14日 |
| 0 | 0分0秒 | 6月13日 |
| 極小 | -6分30秒 | 7月26日 |
| 0 | 0分0秒 | 9月 1日 |
| 極大 | +16分25秒 | 11月3日 |
| 0 | 0分0秒 | 12月25日 |
E.T. = 視太陽時 - 平均太陽時、正が意味すること : 太陽が進み, より早く南中, あるいは日時計が平均太陽時より進む。 年ごとのわずかな変動がうるう年の存在により起き、4 年毎に再設定される。 均時差曲線と付随するアナレンマの正確な形状は (軌道の) 離心率と (地軸の) 傾きの 両方の長期変動により、何世紀もの間に少しずつ変化する。 この時点では、どちらもゆっくりと減少するが、何千年の何百倍もの時間尺度では増大・減少する。
より短い時間尺度 (何千年間) では、春分・秋分と近日点の日付の変化 (shift) はもっと重要である。 前者は 歳差 (precession) が原因で、星と比較して春分・秋分を後方に変化させる。 これは現在の議論では無視できる、というのは我々のグレゴリー暦は、 春分を 3 月 20 に固定する方法で構成しているからである。 (少なくとも、ここにおける我々の目的には十分な精度である。) 近日点の変化 (shift) は前方に向かい、1 世紀毎におよそ 1.7 日である。 1246 年に、近日点は 12 月 22 日の冬至に起き、 従って、2 つの寄与する波は共通のゼロ点があり、均時差曲線は対称であった : 「天文アルゴリズム」(Astronomical Algorithms) でメーウス (Meeus) は 2 月と 11 月に極値の 15 分 39 秒、 5 月の 7 月に極値の 4 分 58 秒を与えている。 ここまでは、2 月の極小値は 11 月の極大値よりも大きく、 5 月の極大値は 7 月の極小値よりも大きかった。 事実、1901 年以前には、5 月の極大値は 11 月の極大値よりも大きかった。 2001 年以前には、5 月の極大値は 12 分と数秒進み、 11 月の極大値は 10 分よりわずかに少なかった。 長期間の変化は均時差の現在のグラフと 2000 年以上前のもの ―― プトレマイオスのデータから構築したもの ―― を比較すれば明らかである。
もしも (日時計の) ノーモン (gnomon, 影を落とすオブジェクト) が端(edge) ではなく点 (例えば板の穴) で あれば、影 (あるいは光の点) は一日の間に一つの曲線の跡をたどる。 もしも影が平面の表面に落とされれば、この曲線は円錐曲線 (普通は双曲線) である。 というのは太陽の動きである円とノーモンの点は円錐を定義するからである。 春分と秋分で、円錐は平面に退化し、双曲線は直線に退化する。 毎日、違う双曲線があり、時刻のマークを各双曲線に設置でき、 これが必要な補正を含む。 不幸にも各双曲線は 2 つの異なる日に対応し、1 つは 1 年の各半分にあり、この 2 つの日には異なる 補正が必要である。 便利な妥協は「平均時」のために線を引き、 一年間に正午の影の点の正確な位置を示す曲線を追加することである。 この曲線が 8 の字を形成し、アナレンマと呼ばれる。 アナレンマを平均正午の線に比較することにより、一般にその日に適用する補正量を決定できる。
均時差は、日時計及び類似の装置との関連で使用されるのみならず、 太陽エネルギーの多くの応用にも使用される。 太陽追跡装置 (solar trackers) と ヘリオスタット (heliostats) のような機械は均時差に影響を受ける方法で動く必要がある。
常用時 (civil time) はしばしば、タイム・ゾーンの中心近くを通過する子午線 のための地方平均時で、夏時間により更に変更されるかもしれない。 与えられた常用時に対応する視太陽時を見つけようとすれば、 関心領域とタイム・ゾーン子午線の間の経度の違い、 夏時間、 及び均時差をすべて考えなければならない。
均時差は出版された表やグラフから得られる。 過去の年代用には、そのような表は歴史的計測や計算により作られる; 無論、未来の年代用には、表は計算することができるのみである。 計算機制御のヘリオスタットのような装置で、計算機はしばしば、 均時差を計算するようにプログラムされている。 計算は数値的、あるいは解析的なものがある。 前者は運動の微分方程式の numerical integration に基づき、 すべての重要な重力効果、相対論的効果が含まれる。 結果は 1 秒より精度が高く、現在の年鑑の基礎である。 後者は太陽と地球の間の重力の相互作用 (gravitation interaction) のみを含む解法に基づき、 単純ではあるが、前者ほど正確ではない。 精度は小さな補正を含めることで改良できる。
以下の議論は適度に正確なアルゴリズム (長期間で年鑑データと 3 秒以内で一致) を記述しており、 これは天文学者に良く知られている。 また電卓で簡単に評価できる単純な近似公式 (長期間に 1 分以内) を獲得する方法も示し、 この記事で以前に使用した現象の単純な説明を提供する。
均時差 (EOT, equation of time) の正確な定義は :
EOT = GHA - GMHA
この等式に登場する量は
ここで、時間と角度は 2πラジアン = 360° = 1 日 = 24 時間 のような因子で関係する量である。 差 EOT は計測可能である、というのは GHA は計測可能な角度で、 ユニバーサル時間 UT は時間計測の尺度 (scale) だからである。 UT から π = 180° = 12 時間 のオフセットを取り除く必要があるのは、 平均時深夜で UT は 0、一方 平均時正午で GMHA = 0 だからである。 ユニバーサル時間は平均時深夜で不連続で、 従って、別の量である日数 (quantity day number) N ―― 整数 ―― が 連続量時間 t を形成するのに必要である : t = N + (UT/24 hr) 日。 GHA と GMHA のどちらも、すべての物理的角度のように、 それぞれの (視太陽時及び平均太陽時の) 正午に、 数学的な不連続性があるが、物理的な不連続性ではない。 成分の数学的不連続性にもかかわらず、EOT は GHA と GMHA の切れ目の間の小さな時間間隔で 24 時間を追加 (あるいは差し引く) すれば 連続関数として定義される。
天球の角度の定義によれば GHA = GAST - α (時角 (hour angle) を参照)、 但し
均時差に代入すると、
EOT = GAST - α - UT + offset
上の GHA の公式と同様に、GMHA = GAST - αM と書くことができる。但し最後の項は平均太陽の赤経である。 等式はしばしば、これらの項で次のように書ける。
EOT = αM - α
但し αM = GAST - UT + offset。この定式化で、ある時刻における EOT の計測あるいは計算は、 その時点における α の計測あるいは計算に依存する。 α と αM は共に、一年間に 0 時間から 24 時間まで変化する。 前者は UT の値に依存する時刻で不連続、一方後者はこれがわずかに後にある。 その結果、このように計算すると EOT は 2 つの人工的な不連続性がある。 これらは、α の不連続性の後、且つ αM の不連続性の前の 小さな時間間隔 (time interval) で EOT の値から 24 時間を取り除くことで、 両方とも取り除くことができる。 その結果の EOT は時間 (time) の連続関数である。
別の定義では、EOT と区別するために E と表示すれば、
E = GMST - α - UT + offset
ここで GMST = GAST - eqeq はグリニッジ平均恒星時 (mean sidereal time、 赤道面内の平均春分 (mean vernal equinox) と平均太陽 (mean Sun) の間の角度) である。 従って、GMST は GAST の近似 (そして E は EOT の近似) である。 eqeq は分点均差 (the equation of the equinoxes) と呼ばれ、 歳差運動 (precesional motion) に関する地球の回転軸の動揺 (wobbling) あるいは 章動 (nutation) によっている。 章動運動 (nutational motion) の大きさは 1.2 秒 (経度 (longitude) の 18'') でしかないので、 EOT と E の違いは 1 秒未満の精度に興味を持たない限り、無視できる。
第 3 の定義は EOT と E と区別するため Δt と表示され、 今や Equation of Ephemeris Time と呼ばれる。 (今では EOT, E そして Δt の間でされる区別以前は、後者が equation of time と呼ばれた。)
Δt = Λ - α
ここで Λ は平均太陽の黄道経度 (ecliptic longitude) (黄道面内における、平均春分から平均太陽までの角度) である。
差 Λ = (GMST - UT + offset) は 1960 年から 2040 年にかけて 1.3 である。 従って、この制限された年の範囲で、Δt は EOT の近似で、0.1 から 2.5 s の範囲にあり、 均時差の経度補正に依存する; 多くの目的のために、例えば日時計の補正のためには、この制度は十分すぎる。
赤経、そして均時差はニュートンの二天体理論 (Newton's two-body theory) から計算することができ、 ここで二天体 (地球と太陽) はその共通な重心の周りの楕円軌道を記述している。 この理論を使えば、均時差は次のようになる :
但し、登場する新しい角度は次のようになる :
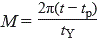 は
平均近点角 (mean anomaly)、
これは楕円軌道の近点 (periapsis) から平均太陽 (mean sun) への角度で、
t が tp から tp + tY に増加する時に
t の範囲は 0 から 2π である。
は
平均近点角 (mean anomaly)、
これは楕円軌道の近点 (periapsis) から平均太陽 (mean sun) への角度で、
t が tp から tp + tY に増加する時に
t の範囲は 0 から 2π である。
計算を完了するには、3 つの追加の角度が必要である。
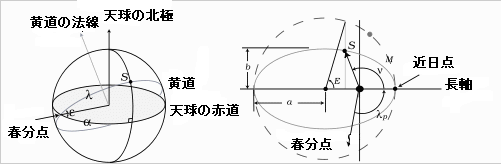
|
| 天球と太陽の黄道軌道、地球を中心とした観測者が黄道を垂直に見たもの, 均時差決定に必要となる 6 つの角度 (M, λp, α, ν, λ, E) が見える。 見やすくするために大きさをそろえていない。 |
以上の全ての角度は上の図に示され、ここに示されるのは、天球と地球から見た太陽の楕円軌道である。
(これは太陽から見た地球の軌道と同じである。)
この図で ε は黄道傾斜角 (obliquity)、一方 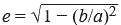 は楕円の離心率 (eccentricity) である。
は楕円の離心率 (eccentricity) である。
さて、0≦M≦2π の値が与えられた時に、次の良く知られた手順で α(M) を計算できる:
最初に M を与えて、 ケプラーの方程式 (Kepler's equation) から E を計算する :
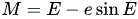
この方程式は正確には閉じた形では解くことができないが、E(M) の値は、 無限級数 (べき級数、あるいは三角級数) の方法、図による方法、あるいは数値的方法から得られる。 その代替には、e=0 に対しては E = M に注意。そして逐次近似により :
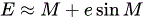
この近似は改良でき、小さな e に関しては、再び逐次近似により
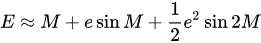
そして、継続した逐次近似により、e に関してのべき級数のより高次の項が順番に得られる。 (1 より随分小さい) 小さな e の値に対して、級数の 2 次あるいは 3 次の項は E の 良好な近似を与える; より小さな e には、近似はより良好である。
次に、E が既知の時に楕円軌道の関係式から、 真近点角 (true anomaly) ν を計算する。
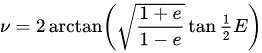
多価関数 arctan x の使用すべき正しい分岐 (branch) は νE=0 = 0 から開始して、 ν を E(M) の連続関数とするものである。 従って、0≦E<π に対しては arctan x = arctan x、 π<E≦2π に対しては arctan x = arctan x + π を使用し、 特別な値 E=π では、tan の argument は無限となるので、ν = E を使用する。 ここで arctan x は主値 (principal branch) で |arctan x|<π/2 である。 これは電卓と計算機のアプリケーションで返される関数である。 代わりに、この関数は e に関してのテーラー級数 (Taylor series) の形で表示でき、 この最初の 3 項は
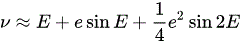
小さな e に対して、この近似は (あるいは単に最初のニ項でも) 良好なものである。 これとE(M) の近似を組み合わせると、次が得られる :
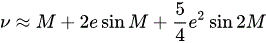
関係式 ν(M) は equation of the center と呼ばれる; ここに記述された表示は e に関する第二オーダー (second-order) の近似である。 地球軌道を特徴づける e の小さな値に関しては、これは ν(M) のとても良好な近似を与える。
次に ν が既知の時に定義から λ を計算する :

λ の値は M と非線形に変化する、というのは軌道は楕円であって円ではないからである。 ν の近似から
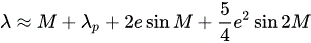
最後に、λ が既知の時に上で示された天球上の直角三角形 (right triangle) の関係式から
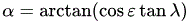
α の象限 (quadrant) は λ の象限と同じであることに注意し、 従って λ を α と 2π の範囲に帰着し、次のように書く

但し λ が第 1 象限であれば k = 0、 λ が第 2 or 第 3 象限であれば k = 1, λ が第 4 象限であれば k = 2 である。 tan が無限の時の値は α = λ。
α の近似値は tuncated Taylor series から ν のように得ることができるが、 次の式を使う方がもっと有効である。
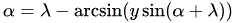
但し y = tan2 (ε/2)。ε=y=0 に対して α = λ に注意し、 2 度繰り返せば、
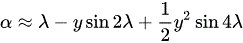
均時差は赤経の計算の結果を時間の公式の等式に代入して得られる。 ここで Δt(M) = M + λp - α[λ(M)] を使用した; これは、部分的には E の使用を正当付ける (1 秒のオーダーの) 小さな補正は含まれていないからであり、 そして、部分的には、目的は解析的な表現を得ることであるからである。 λ(M) と α(Λ) のニ項近似の使用により、Δt は 2 つの項の明示的な表現 (explicit expression) として 書くことが可能となり、これは e と y における一次近似の理由から Δtey として記す。
 分
分
この等式は最初にミルン (Milne) により得られ、彼はこれを λ = M + λp の形で書いた。 ここで記した数値は 2000 年 1 月 1 日の UT1 正午の epoch に対応する軌道変数値 e = 0.016 709, ε = 23.4393° = 0.409 093 そして λp = 282.9391° = 4.938 201 ラジアン を使用した結果である。 上で与えたように、Δtey の数値表現を評価することに、電卓は正しい値を得るためにラジアン・モードにしなければならない、 第二項の数値の 2λp - 2π はラジアンで書かれているからである。 高次近似も書くことができるが、必ずしもより多くの項があるわけではない。 例えば、e と y の両方の二次近似は 5 項から構成されている:
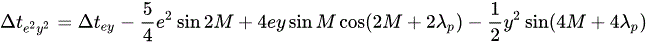
この近似は高い精度の可能性があるが、しかしながら、長い年月にこれを達成するには、 変数の e, ε と λp は時間と共に変化しなければならない。 これは追加の計算上の困難さを作る。 他の近似も提案され、例えば Δte は center の first order equation を 使用するが、α を決定する他の近似を使用しない。 また Δte2 は center の second order equation を使用する。
時刻の変数 M は、近日点以後の日数に関して、あるいは特別な日と時刻 (epoch) 以後の日数に関して 書くことができる :
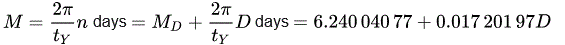
ここで、MD は選択した日と時刻における M の値である。 ここで与えた値に関しては、MD は 2000 年 1 月 1 日正午 UT1 の epoch における 実際の太陽に関して測定され、D はこの epoch を過ぎた日数である。 近日点においては M = 2π で、そこで解くことにより、D = Dp = 2.508 109 を与える。 これによると近日点は 2000 年 1 月 4 日の 00:11:41 になるが、 一方、実際の近日点は Multiyear Interactive Computer Almanac (MICA と省略) の結果によると、 2000 年 1 月 3 日の 05:17:30 である。 この大きな不一致が起きるのは、2 つの位置における軌道半径の間の違いが、わずか 100 万分の 1 だからである。 別の言葉では、半径は、近日点の近くでは、時間のとても弱い関数だからである。 実際の問題として、これが意味することは n を使用して、与えられた年の実際の近日点に加えることで、均時差の高度に正確な 結果を得ることができないことである。 しかしながら、高い精度は D に関しての定式化を使用することにより達成できる。
D>Dp の時、M は 2π より大きく、これを 0 と 2π の 範囲にするために 2π の倍数 (これは年に依存) を引かなければならない。 同様に 2000 年以前の年には 2π の倍数を加えなければならない。 例えば、2010 年に関しては D は 1 月 1 日正午の 3653 から、12 月 31 日正午の 4017 まで変化する; 対応する M の値は 69.078 9468 と 75.340 4748 であり、 2πをそれぞれ 10 回と 11 回を引くことにより、0 から 2πの範囲に帰着する。
常に次のように書くことができる。
但し
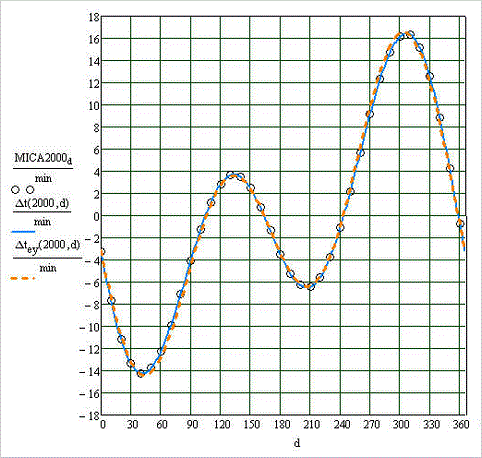
|
| Δt と Δey の曲線と正午における毎日の値を示すための印 (10 日毎)、 Multiyear interactive Computer Almanac vs d (day) for the year 2000 |
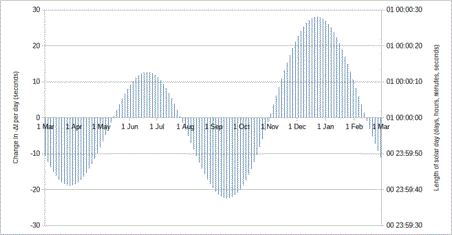
|
| -Δt のderivative。右の軸は太陽日 (solar day) の長さを示す。 |
2000 年以後の結果の等式は、 2 項の和 ((1),(4), (5) で与えられる) として書かれ、次で ある :
a = -7.659 sin(6.30 040 77 + 0.017 201 97 (365.25 (y - 2000) + d))
b = 9.863 sin(s(6.240 040 77 + 0.017 201 97 (365.25(y - 2000) + d)) + 3.5932)
6) Δtey = a + b [分]
平文のフォーマットでは
EoT = -7.659sin(6.24004077 + 0.01720197(365*(y-2000) + d)) + 9.863sin( 2 (6.24004077 + 0.01720197 (365*(y-2000) + d)) + 3.5932 ) [分]
項 a は離心率からの寄与を表し、項 b は黄道傾斜角からの寄与を表す。
計算の結果は通常、1 組の表として与えられるか、あるいは d の関数として均時差のグラフとして与えられる。 2000 年の全ての Δt, Δtey のプロット、MICA の結果は図で表示されている。 Δtey のプロットは MICA により作られた結果に近いことがわかり、 エラーの絶対値 Err = |Δtey - MICA 2000| は 1 年を通して、1 分以内である。 この最大の値は 43.2 秒で、276 日目 (10 月 3 日) に起きている。 Δt のプロットは MICA の結果と区別がつかない。 2 つの間のエラーの絶対値の最大は 2.46 秒で、324 日目 (11 月 20 日) である。
関数の連続性に関して、arctan の適切な枝 (branch) を選択するために、 arctan の修正バージョンが便利である。 これはパラメーターにより、予期された値に関して以前の知識を持ち込む。
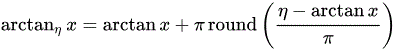
これはできる限り η に近い値を作る。関数の round は最も近い整数に丸める。
これを適用すると次が得られる:

パラメーター M + λp は Δt の最も近い 0 に配置され、これが望まれたものであった。
MICA と Δt の間の違いは 1960 年から 2040 年の範囲で 5 年毎にチェックされた。 どの瞬間にも、絶対値エラーの最大値は 3 秒より少なかった。 最大の違いは 1965 年 5 月 22 日 (141 日目) に起きた 2.91 秒であった。 しかしながら、この範囲の年月で、このレベルの精度を達成するためには、 時間と共に軌道パラメーターの長期変動を配慮する必要がある。 この変動を説明する等式は :
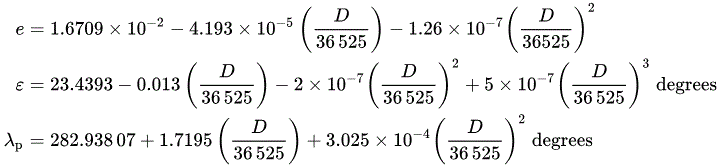
これらの関係式によれば、百年間 (D = 36 525) に、λp はおよそ 0.5% (1.7°) で増加し、 e はおよそ 0.25% で減少、ε はおよそ 0.05% で減少する。
その結果、均時差の任意の高次近似に必要とされる幾つかの計算は、 広範囲な時間で、本来の精度の達成を望めば、その完結に計算機を必要とする。 このイベントで、コンピューターを使用して Δt を評価することは、 その近似物を使用して評価するよりも、より難しいわけではない。
このすべてにおいて、上で記述された Δey は 電卓でさえ評価が容易で、 日時計の修正には十分に精密で (80 年間にわたり、精度が 1 分以上も良好)、 2 つの項の和とする素晴らしい物理的説明があり、 この記事の最初に使用したように、1 つは地軸の傾き、もう 1 つは離心率である。 これは Δt を M の関数と考えた時、あるいはその高次近似のいずれかと考えた時には事実でない。
均時差を計算するための別の手順は次のようになる。 角度の単位は角度 (degree) である ; 通常の計算順序が適用される。
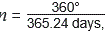
ここで n は一日当たりの軌道の平均角速度を角度 (degree) で与えたもの、すなわち「一日当たりの平均速度」(the mean daily motion) である。
但し D は日付で 1 月 1 日を 1 で開始して数える (即ち、1 年の普通の日の日付部分)。 9 は 12 月の冬至から 12 月 31 日までのおよその数。 A は地球が 12 月の冬至から、日付 D まで平均速度で動く角度である。
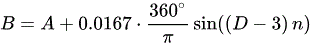
B は冬至から日付 D まで地球が動く角度で、地球の軌道離心率 (orbital eccentricity) が 0.0167 であることによる 一次補正を含む。 数値の 3 は、12 月 31 日」から地球の現在の近日点までの、およその日数である。 この B の表示は定数を以下のように加えることにより単純化できる。
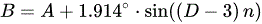
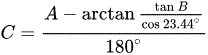
ここで C は平均速度で動いた角度と赤道面に射影された補正速度の角度差を 180° で割って差を半回転 (の数) に したもの。 23.44° の値は地軸の傾き (obliquity) である。 差は均時差に通常の符号を与える。 x の任意の与えられた値に対して、arctan x (時には tan-1x と記す) は複数の値を取り、 互いに半回転の整数倍だけ違っている。 電卓やコンピューターで生成された値はこの計算には適切でないかもしれない。 これにより C は半回転の整数倍で違う原因になる。 余剰の半回転が計算の次のステップで取り除かれて、均時差が与えられる :
nint(C) の表示は、C に最も近い整数 (nearest integer) の意味である。 計算機では、例えば INT(C + 0.5) のようにプログラムされる。 この値は 1 年の異なる時に 0, 1 あるいは 2 である。 これを引けば、小さな正もしくは負の半回転の分数が残り、これに 720 を掛ける。 720 は太陽に相対的に地球が半回転する分の数 (12 時間) に等しく、 これで均時差を得る。
印刷された値と比較すれば、この計算は 二乗平均平方根エラー (root mean square error) はたった 3 秒である。 最大のエラーは 6.0 秒である。 これは上で記述した近似よりもずっと正確であるが、入念な計算ほど正確でない。
上の計算の B の値は太陽の黄道経度 (90° でシフト) の正確な値で、 従って太陽の赤緯 δ は直ちに得られる :
この誤差は 1° 未満である。