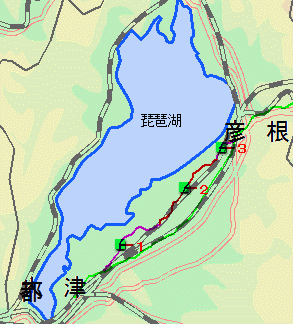
|
必ず、トップページの前書きを呼んでください。
旧街道
「朝鮮人街道」のことを始めて知ったのは以下の第一番目の文献によっています。 「朝鮮人街道」は「中山道」の脇道で、江戸時代に朝鮮の国史、通信使がソウルから 江戸に至るときにたどった道だそうです。 但し、この第一番目の文献は「朝鮮人街道」を全部歩いているのではなく、 彦根から近江八幡までの経路しか描いていなく、しかも経路が不鮮明でした。
そうこうするうちに、中山道を歩いている最中に、中山道との分岐点 (あるいはその近く) にあった案内板 に気が付きました。 少し興味に駆られて、ネットを色々検索しているうちに 2 番目のページを見つけました。 これでほぼ経路がはっきりしました。しかも頼りとなる文献が唯一つのようだということもはっきりしました。この 2 番目のページの地図ではほぼ経路がわかるのですが、市街地域では少し不明となります。 まず近江八幡の中のコースがわかりません。 幸いなことに、これは 3 番目のページの中に登場する朝鮮人街道の画像が拡大でき、 これから確定することができました。
しかし、安土と彦根が残っています。随分調べましたが検索でヒットしません。 しかし、どういうわけだか 4 番目のページに行きつきました。 どうもこれは往時の朝鮮人街道を表しているようです。従って実際に歩いてみないと 現在のコースが確定しないようです。以下、実際に歩いた記録です。
- 関西周辺 街道古道を歩く、歩く旅シリーズ、山と渓谷社、ISBN 4-635-60031-9
- 朝鮮人街道を訪ねて
- 近江八幡観光物産協会 いにしえの道 -- 中山道・朝鮮人街道
- 朝鮮人街道 - 地図 Z
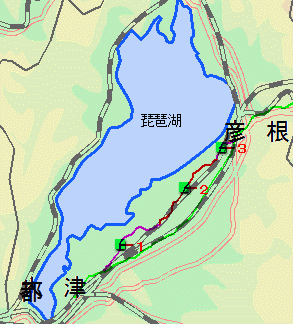
|
このクリッカブル・マップでは緑色の線が中山道です。 従って、中山道は現在の JR 東海道の沿線にあり、 朝鮮人街道は新幹線の沿線にあることがわかります。
歩き始めるまでに色々不明な点がありました。 まず、JR 野洲駅を降り、中山道の分岐まで戻り、 ここから朝鮮人街道を歩くのですが、すぐに JR とぶつかります。 ここで鉄道を横断できるかどうか不明でした。実際に歩いてみると、 これが不可能であることがわかり、少し戻って迂回することになりました。
朝鮮人街道を表す道標はきわめて少なく、これは  で表しています。
中山道から分岐する所にも小さな道標があり、一応これで出発点は確定しますが、
念のため少し中山道を 100 m 程東に歩き、そこにある「外和木の標 (しるべ)」を
再度、読むことにしました。ここに朝鮮人街道の説明が書いてあったことを
記憶していたためです。
で表しています。
中山道から分岐する所にも小さな道標があり、一応これで出発点は確定しますが、
念のため少し中山道を 100 m 程東に歩き、そこにある「外和木の標 (しるべ)」を
再度、読むことにしました。ここに朝鮮人街道の説明が書いてあったことを
記憶していたためです。
近江八幡の市街地域では一応地図上では経路が確定していたのですが、 朝鮮人街道を表す道標あるいは案内板が数か所あり、それを結べば確かに 地図の経路と合致することがわかりました。
あと問題となりそうなのが、安土市街への西からの入り口です。 国土地理院の地図では碁盤目があり、曲がる個所を間違える可能性が ありそうだと思ったのですが、西から進入する場合には、少し広い道はユニークだと わかりました。それ以外は車が通れない狭い路地です。だから安土駅に至るまでは ほとんど問題となる点がないことがはっきりしました。
2012 年 7 月にもう一度歩きました。朝鮮人街道の道標が増えていました。歩く人が増えているようです。
安土の市街地域には路地のように細い道が随分あります。 ひょっとすると、江戸時代には安土の道は朝鮮人街道以外は すべて路地のように細かったのかもしれません。 信長が作った安土の城下町はこんな具合だったのでしょうか ?
江戸時代に朝鮮からの通信使がわざわざ、曲がりくねった街道を通ったのか、 しばらく疑問で色々ネットを検索しているうちに「琵琶湖が見たかったせいだ」と思うようになりました。 今ではこの街道からは琵琶湖は全然見えませんが、当時は琵琶湖がすぐそばに迫っていたはずです。 途中には「望湖神社」の名前の神社もあり、確信を深めることになりました。
途中、あまり見物するような所もありません。 ずっと時間をかけるつもりであれば安土城あたりにも寄れますが、 今回はそこまで時間を使うつもりがありませんでした。まず「朝鮮人街道」を間違いなく歩くことが 目的だったためです。 犬神川の手前で大きく鍵型に曲がる場所がありますが、この場所がわからない可能性があると思い、 少し不安でした。しかし道路のつながり具合が非常に変になっているので、 その点から曲がる位置を特定できました。
街道沿いにあるものでは「十王村の水」の雰囲気がとってもよかったです。一見の価値があります。 祭りで有名な繖峰三神社(さんぽうさんじんじゃ) も街道沿いにありますが、 あまりに急な斜面にあるので境内に入る気にもなりませんでした。
近江鉄道の鳥居本駅は彦根駅と米原駅の中間にあり、 彦根駅は 1 つ目の駅で、米原駅は 2 つ目の駅です。 近江鉄道のホームページに路線図が載っています。
近江鉄道
今回のコースは 2 時間程度の非常に短いコースです。
佐和山越えは現在では歩道トンネルを通る以外に方法がありませんが、 昔はどうであったのであろうかと考え、インターネットでしつこく検索しました。 どうやら大正時代まで山越えをしていたようですから、 痕跡ぐらいはありそうだと思ったのですが、 いざ実際にトンネルの場所を見てみると、 トンネルを掘るために、山を深く掘り下げていることに気が付きました。 だから道は残っていないのだとようやく納得しました。
また、佐和山歩道トンネルの手前で佐和山の方に向かう道があることもはっきりしていましたが、 何の道か不明でした。この道の入り口に「佐和山城跡案内図」があり、 佐和山に向かう道は佐和山城跡のハイキングコースであることもわかり、 昔の佐和山城は佐和山全体に及ぶ規模であることがはっきりしました。 従って、街道は佐和山城のそばを通るようにできていた可能性があります。
江戸時代初期に佐和山城が廃城となり、その代わりに彦根城が井伊氏の城となるようです。
佐和山城 - Wikipedia