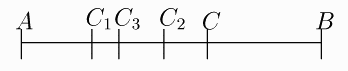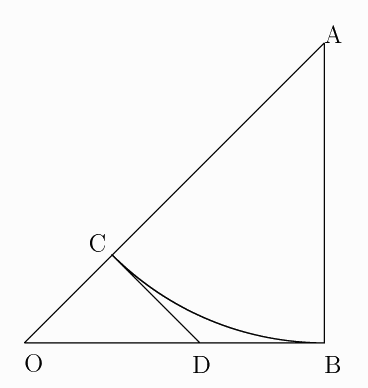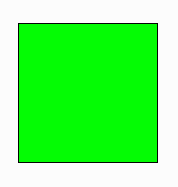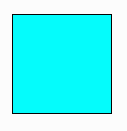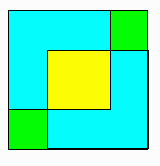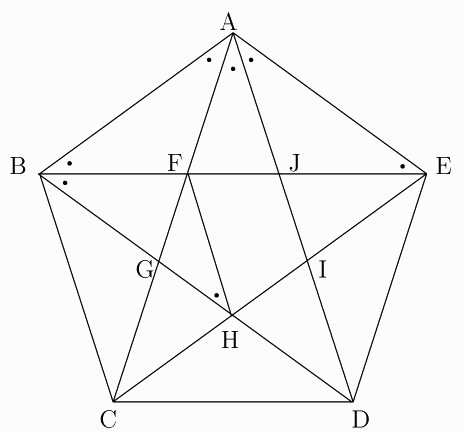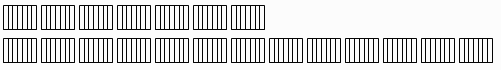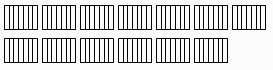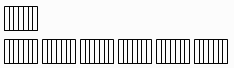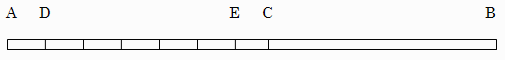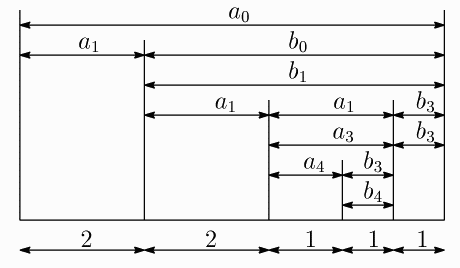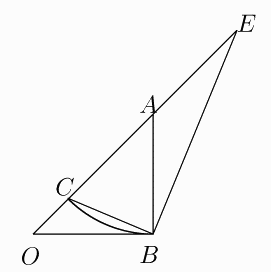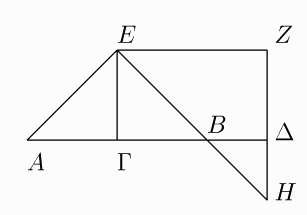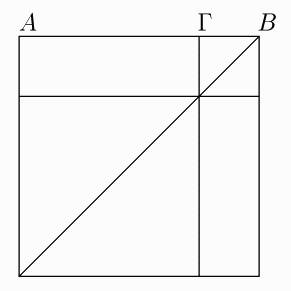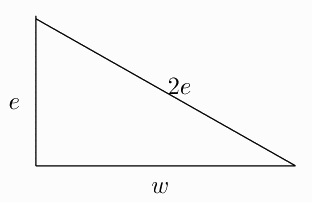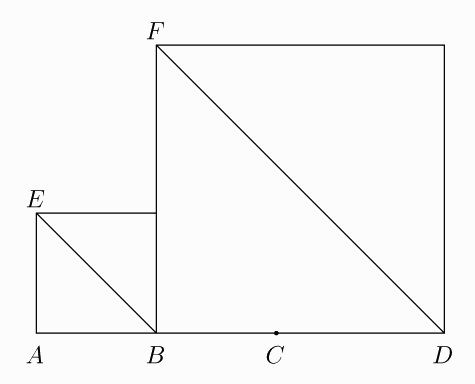�y�[�W�̍ŏI�Z���N���� :
�������̔����̗��j
-- �ڎ� --
1. �n�߂�
���������ǂ̂悤�ɔ������ꂽ���Ɋւ��āA
�ŏ��͂��܂�[���l���Ă͂��Ȃ������̂ł����A�����O�����̍u�`�^ (��ʎs�������̍u��, ��q)
�ɏ�����Ă��邱�Ƃ���A�l���������ƂɂȂ�܂����B
���p����Ă����̂́A�n�[�f�B�[�E���C�g�̗L���ȌÓT�i��q) �ł��B
���������Ă���̂ł����A���܂���j�Ƃ̊֘A�œǂ��Ƃ��Ȃ��A
�����O�����̎w�E���琏���Ⴄ���ƂɋC���t�����ƂɂȂ�܂����B
| �s�^�S���X | BC 569 �� - BC 475 �� | ���������ł��邱�Ƃ��s�^�S���X�w�h�ɂ���Ĕ��� |
| �e�I�h���X | BC 465 - BC398 | ���������ł��邱�Ƃ̏ؖ� (m��17 or m��17, m��������) |
| �f���N���g�X | BC 460 �� - BC 370 �� | �u���������Ɨ��́v |
| �e�A�C�e�g�X | BC 417 - BC 369 | m�������� �̂Ƃ��� ���������ł��邱�Ƃ̏ؖ�
���[�N���b�h���_�̑� 10 ���A�� 13 ���̌��X�̒��� ? |
| �G�E�h�N�\�X | BC 408 - BC 355 | ���[�N���b�h���_�̑� 5 ���̌��X�̒��� |
| �A���X�g�e���X | BC 384 - BC 322 | ���������ł��邱�Ƃ�
������Ɋ�Â��Ď�����邱�Ƃ����y |
| ���[�N���b�h | BC 325 �� - BC 265 �� | �f���q�����̈�Ӑ� |
�����悻�̗��j�������A��̕\�̗l�ɂȂ�܂��B�����܂�Ő���������ƁB
�s�^�S���X�w�h�ɂ���āu ���������ł��邱�Ɓv���ؖ����ꂽ�悤�ł����A
���̎��_�ł́u�f���q�����̈�Ӑ��v���m���Ă��Ȃ������悤�ŁA���̂���
m ���������łȂ��Ƃ��� �u ���������ł��邱�Ɓv�͏ؖ��ł��Ȃ������悤�ł��B
�u�f���q�����̈�Ӑ��v�̓��[�N���b�h���_�ŏؖ�����Ă���Ƃ���Ă��܂�����A
���̎��_�ŁA�����̖������̑��݂��悤�₭�m�肵�����ƂɂȂ�܂��B
�e�I�h���X�̎��_�ł͂����܂œ��B�ł����Am��17 ���邢�� m��17 �܂ł�
�����ɑ��Ă̂� ���������ł��邱�Ƃ��ؖ��ł����܂ł̂悤�ł��B
���̃e�I�h���X�̏ؖ��͎c���Ă��炸�A�����̉���������܂��B�{�����ł̓n�[�f�B�[�E���C�g��
�{�ɂ���ʂ�ɏЉ�����Ă���܂��B
�Ñ�M���V���ł͂ǂ̂悤�ɂ��Ė������_�����W�����̂��悭�킩��܂��A
���̏W�听�̓��[�N���b�h���_�� V �̂悤�ŁA����̓G�E�h�N�\�X�ɂ����̂�
����Ă��܂��B���[�N���b�h���_�� V �ł͎��������������ۂ����u�f�f�L���g�̐ؒf�v�ɂ���Ē�`���Ă��܂�����A
�킸�����S�N�̊Ԃɖڊo�������W�𐋂������Ƃ��킩��܂��B
�f���q�����̈�Ӑ��̏ؖ��ɂ͒ʏ펟���K�v�ƂȂ�܂��B
����̓s�^�S���X�w�h�̎���ɂ͒m���Ă��Ȃ��������ƂŁA
���[�N���b�h���_�ɂ� (������) �L�ڂ�����܂��B��ʂɂ�
�u��{�藝�v�Ƃ͌Ă�܂��A�f���q�����̈�Ӑ����m������Ƌ���
���ɑ����̖��������������ꂽ���R�ł�����悤�Ȃ̂ŁA
���̈Ӗ��ŁA���̃y�[�W�ł́u��{�藝�v�ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��B
��{�藝
p ��f���Ƃ���Bp �����R�� a, b (��1) �̐� ab �������Ap �� a, b �̂����ꂩ��
�����B
�������̔����Ɋւ���b�����邽�߂ɂ́A�u�f���q�����Ƃ��̈�Ӑ��v�̂��Ƃ���n�߂Ȃ��Ƃ����܂���B
�ŏ��ɂ����܂�Ő������܂��B���̎��́u�������̔����v�̓��e��
��{�I�ɂ̓n�[�f�B�[�E���C�g����̈��p�ł��B
�����܂ŏ����I������ŁA�C���^�[�l�b�g�̉p��̃y�[�W�Łu�������v�A�u�w�I�ؖ��v
����������Ɛ��������̃y�[�W���q�b�g���邱�Ƃ��킩��܂����B
�u�������ł��邱�Ƃ̊w�I�ؖ��v�͉p�ꌗ�ł͂ƂĂ��|�s�����[�Șb��Ȃ悤�ł��B
�ʔ������Ƃ������Ă���̂ŁA�F�X�������ꂽ�y�[�W���Q�l�ɂ���
�u ���������ł��邱�Ƃ̊w�I�ؖ��v��t�������邱�Ƃɂ��܂����B
�p�ꌗ�ł̓s�^�S���X�w�h�� �u ���������ł��邱�Ɓv���w�I��
�ؖ������ƍl���Ă���l�������A���ꂪ�|�s�����[�ł��闝�R�̂悤�ł��B
�lj��F
�ȏ��������������ŁA�����Ԃ�o���Ă���A�t�@���E�f���E���F���f���̖{�����C�Ȃ�
�ڂ�ʂ��Ă�����A�����Ƀs�^�S���X�w�h�ɂ��u ���������ł��邱�Ƃ̏ؖ��v���������Ă��邱�Ƃ�
�C�����܂����B���_�ł����A�ƂĂ������͂�����܂��B�u�n�I�ڂ�ʂ��Ă���̂ɂȂ��C�����Ȃ������̂� ?�v
�ƌ���ꂻ���ł����A�u�f�B�t�@���g�X�������v�Ƒ肵���͂̒��́u�y���������v�̉ӏ��ɏ�����Ă���A
����͂����ƌ㐢�̃f�B�I�t�@���g�X�̍��̉���ł��낤�ƌ��߂��Ă������߂ł��B
�s�^�S���X�w�h�ɂ��u ���������ł��邱�Ƃ̏ؖ��v��
����I�Ȍ������������
�̘A�����W�J���L���ŏI�����Ȃ��Ƃ������Ƃ���̌��_�ŁA���킹�ē��ʂȌ`�̃y���������������Ă��邱�Ƃ��m���ƂȂ�܂����B
�s�^�S���X�w�h�� ���������ł��邱�Ƃ��������Ƃ�ړI�Ƃ����̂ł͂Ȃ� ��L�����ŋߎ����悤�Ƃ��āA
���̌��ʋC���t�����͂��Ȃ̂ł��B
�Ȃ�����̈Ӗ��ɂ�����A�����W�J�́A�����ɂ͌Ñ�M���V���ɂ͂���܂��A
�����̂��Ƃ������ɑ��āA���[�N���b�h�ݏ��@��K�p���邱�Ƃœ����܂��B
���[�N���b�h���_�ɂ����̂悤�Ɉ����Ă��܂��B
�s�^�S���X�w�h�ɂ�� �̋ߎ��Ɋւ��Ă̓f�B�N�\���ɂ��L�q������A�t�@���E�f���E���F���f���Ɠ��l��
�v���N���X�ɂ�钍�߂������ɂ��Ă��܂��B
�f�B�N�\���ɂ� �̋ߎ������邽�߂̑Q�����̍����������Ă���܂���B
�t�@���E�f���E���F���f���́A���̑Q���������݂̌��t�ł� �̘A�����W�J���瓾������̂ł���
���Ƃ��w�E���A�܂����̌`����A�A�����W�J���z���邱�Ƃ��킩��A
����� ���������ł��邱�Ƃ����_�ł���͂����ƌ����Ă���̂ł��B
�F�X������������
�u�A�����W�J - ����I���_����v�Ɓu�y�������� - ����I���_����v
��t�������܂������A�����ǂނ͕̂s�v��������܂���B
�u���@ - �Ñ�M���V���̊ϓ_����v
�ړǂޕ������ϓI�ɂ�藝���ł��邩������܂���B
���̉ӏ��̋L�q�̓t�@���E�f���E���F���f���̋L�q���Q�l�ɂ��āA
���@ (�ݏ��@�̂���) ���ǂ̂悤�ɌÑ�M���V���ŗ�������Ă����̂��𐄑����ď��������̂ł��B
�V���ɒlj������̂͑�͈Ȍ�ł��B��͂Ɍf�����u ���������ł��邱�Ƃ̊w�I�ؖ��v
�́A�{�C���[�ɍڂ��Ă�����̂ł��B�F�X�ǂ݂������Ă��邤���ɋC�����܂����B
2. �f���q�����Ƃ��̈�Ӑ�
������{�I�Ȍ��t���瓱�����܂��B
���� a, b (�� 0) �ɑ���
�Ə�����Ƃ�
- a �� b �̔{��
- b �� a �̖�
- b �� a �������
�ƌ����܂��B���R�� a, b (�� 0) �ɑ���
- a, b �̗���������鎩�R���� a, b �������ƌĂсA
- a, b �̗����Ŋ����鎩�R���� a, b �����{���ƌĂԁB
-
2 �̎��R�� a, b �ɑ��āAa, b ���݂��ɑf�ł���Ƃ́A
a, b �̌��� 1 �݂̂ł��鎞�ł���B
-
���R�� p (��1) �̖� 1, p �݂̂̂Ƃ��ɁAp ���f���ƌĂсA�����łȂ����
�������ƌĂт܂��B
�f���Ɋւ��Ă͎��̒藝����b�ƂȂ�܂��B
�藝 (�f���q�����Ƃ��̈�Ӑ�)
�C�ӂ̎��R�� n �͑f���̐ςŏ����A���̕����̎d���͐ς̏����������Έ�ӓI�ł���B
�C�ӂ̎��R�� n ��f���̐ςŕ\�����邱�Ƃ͊ȒP�ł��B
n ���������ł���A2 �̐��̐� n = n1n2 ��
�Ȃ� ni ���������ł���A�X�ɂ��������悢����������ł��B
������A�����͑f���̐ςɂȂ�܂��B
�]���āA�{���I�Ȃ̂́u�f���q�����̈�Ӑ��v�̕��ł��B����������ɂ�
n = p1 ... pr = q1 ... qs�@�@(pi, qj �f��)
�̂悤�ȕ\�����������Ƃ���
p1 ... pr = q1 ... qs ...... (*)
�̗��ӂ��瓯���f���������āA���ԂɊ����Ă����A���_�ɓ��B���܂��B�Ⴆ�� p1 = q1
�ł��邱�Ƃ��킩���
�ƂȂ邽�߂ł��B�ς̏��Ԃ���בւ��āA��ɂ��̂悤�ɂ��邱�Ƃ��ł���A����ŏؖ����������܂��B
�ȏ�̓_����A�f���q�����̈�Ӑ��������ɂ́A���̒藝���������Ƃ��ł����
�悢���Ƃ��킩��܂��B���̒藝�����x���K�p���邱�Ƃɂ���āA(*) �̍��ӂ� pi ��
�E�ӂ� qj �̒��ɂȂ��Ƃ����Ȃ����߂ł��B
��{�藝
p ��f���Ƃ���Bp �����R�� a, b (��1) �̐� ab �������Ap �� a, b �̂����ꂩ��
�����B
�����A����̓��[�N���b�h���_�Œm���Ă������� (p 166) �ŁA���̂��߁u�f���q�����Ƃ��̈�Ӑ��v��
���[�N���b�h�ɒm���Ă����Ƃ���Ă��܂��B�A���A���[�N���b�h���_�ł͏����Ⴄ�`��
�q�ׂ��Ă��܂��B����I�Ȍ��t�ŏ����Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B
�܂����[�N���b�h���_�̏ؖ�������I�Ȍ`�ŏЉ�邱�Ƃɂ��܂��B
��{�藝 (���[�N���b�h���_�ɂ�����`)
a, b �� x �ƌ݂��ɑf�ł���Ƃ���B���̂Ƃ� c = ab �� x �ƌ݂��ɑf�ł���B
��{�藝�̌���I�ȏؖ����t���Ă������ɂ��܂��B(�ؖ��ɂ��F�X����܂����A
���_�Ȃǂɐ[���肹���ɂ����ꍇ�̏ؖ��ł�)
3. �������̔���
���������ł��邱�Ƃ� 2 �̏ؖ�
�n�[�f�B�[�E���C�g �̖{�� 4.3 (p 39) �̂����肩�甲��������K�v������܂��B
�܂��藝���f���Ă��܂��B
�n�[�f�B�[�E���C�g �� 2 �̏ؖ��������Ă��܂��B������Љ�Ȃ��Ƃ����܂���B
(�ǂ݂₷�����邽�߁A�����������ύX���ďЉ�܂��B)
�u���̏ؖ��v�ł͑f�� p �� a2 ��������Ă��邱�Ƃ��� p �� a ��������Ă��邱�Ƃ�
���_���Ă��܂��B�]���āA����́u�f���q�����Ƃ��̈�Ӑ��v�Ŏ������u��{�藝�v��
�K�p���Ă���̂ł��B
�n�[�f�B�[�E���C�g�� 2 �̏ؖ����r�������Ă��܂� (p 41)�B���e�������Љ�邱�Ƃɂ��܂��B
���̏ؖ��ł�
p �� a2 ������� ���� p �� a �������
�Ƃ����������g�p���Ă���A����ɂ́u�f���q�����Ƃ��̈�Ӑ��v�́u��{�藝�v
�Ə̂������̂��g���K�v������܂��B���̏ؖ��̗ǂ��_�� m ���������łȂ��ꍇ�ɂ�
���������ł��邱�Ƃ��������Ƃ��ł��邱�Ƃł��B
����A���̏ؖ��ł�
2 �� a2 ������� ���� 2 �� a �������
�Ƃ����������g�p���Ă��܂����A����������ɂ́u��{�藝�v��m��Ȃ��Ă��\�ł��B
�Ƃ����̂́Aa ��� 2s + 1 �ł����
a2 = (2s + 1)2 = 4s2 + 4s + 1
�ƂȂ�Aa2 �͋����Ƃ͂Ȃ�Ȃ����߂ł��B������ a2 �������ł����
a �͋����ł��B
���̏ؖ��Ɋւ��Ă� ���������ł��邱�Ƃ��������߂ɕ���邱�Ƃ��ł��܂��B
�������A
5 �� a2 ������� ���� 5 �� a �������
�Ƃ��������������ɂ́A5 �� a �������Ȃ���� a = 5s+1, 5s+2, 5s+3, 5s+4 ��
�\��������܂�����
a = 5s+1 ���� a2 = 25 s2 + 10 s + 1
a = 5s+2 ���� a2 = 25 s2 + 20 s + 4
a = 5s+3 ���� a2 = 25 s2 + 30 s + 9
a = 5s+4 ���� a2 = 25 s2 + 40 s + 16
�̂悤�ɁA�N������ꍇ�����ׂČv�Z���āA������� a2 �� 5 ��
�����Ȃ����Ƃ��m���߂�K�v������܂��B
�ȏ�̕��@�����Am ���������łȂ��ꍇ�� ���������ł��邱�Ƃ������ɂ�
m ���傫���Ȃ�Ȃ�قǁA�v�Z����ςƂȂ�A����ƂȂ�܂��B
�s�^�S���X�w�h�̏ؖ��� m ���傫���Ȃ�A����ł��������Ƃ����́u�e�I�h���X�̔����v
�Ŗ��炩�ƂȂ�܂��B�]���āA���̏ؖ����s�^�S���X�w�h�̏ؖ��ł������\����
�c�邱�ƂɂȂ�܂��B
�e�I�h���X�̔���
�n�[�f�B�[�E���C�g���I�ɖ|�邱�Ƃɂ��܂��傤�B
�u�s�^�S���X�̒藝�v�������A�N�ɂ���Ĕ������ꂽ���͕s���ł���B
Heath �̂��Ɓu�����͋��炭�A�s�^�S���X���g�ɂ����̂ł͂Ȃ��A������
�s�^�S���X�w�h�ɂ����̂ł��邱�Ƃ͊m���ł���v�B
�s�^�S���X�̐������Ԃ� BC 570-490 ���ŁA
BC 470 �N���ɐ��܂ꂽ�f���N���g�X (Democritus) �́u���������Ɨ��̂ɂ��āv(on irrational line
and solids) ���������B���̂��߁u ���������ł��邱�Ƃ��������ꂽ�̂�
�f���N���g�X�����ȑO�ł���ƌ��_������Ȃ��v
���@(1)�u�s�^�S���X�̒藝�v�Ƃ́u ���������ł��邱�Ɓv
(2) ���p����Ă��� Heath �̕����́@Sir Thomas Heath, A manual of Greek mathmatics, 54-55
�藝�� 50 �N�ȏ���g������Ȃ������悤�ł���B�v���g���̃e�A�C�e�g�X (Theaetetus) ��
�͗L���Ȃ����肪����A�����ł̓e�I�h���X(Theodorus, �v���g���̐搶) ��
, , ....
���������ł��邱�Ƃ��A�ʁX�Ɏ��グ�āA�ؖ��������Ƃ��L�q����Ă��܂��B
�Ƃ��낪 17 �̕������Ɏ����āA���炩�̗��R�œˑR�ɒ��~���Ă��܂��B
��X�̓e�I�h���X�ɂ�邱�̔����A���邢�͕ʂ̔����Ɋւ��āA���m�ȏ���
�������킹�Ă��܂���B������ �v���g���̐������Ԃ� BC 429-348 �ł�����A
���̔����͂��悻 BC 410-400 �N���ł��낤�Ƃ��Ă悢�Ǝv���܂��B
�e�I�h���X���ǂ̂悤�ɂ��Ē藝���ؖ��������Ɋւ��Ă̖��͑����̗��j�w��
�̍I���Ȕ��z�����N�����B
�n�[�f�B�[�E���C�g�͍X�ɋc�_�𑱂��A�e�I�h���X�������ؖ��Ɋւ��ẮA
McCabe �ɂ��ؖ����ł��\���̂�����̂ł���Ƃ��Ă��܂��B ����舵�������ۂ��̓M���V�����
�j���A���X����͕s���ŁAMcCabe �̕��@�� �ŏؖ�������ɂȂ�Ƃ������̂ł��B
�Ō�� Zeuthen �ɂ��u ���������ł��邱�Ƃ̊w�I�ؖ��v�ɂ��ł������Ă��܂��B
������e�I�h���X��������������Ȃ��ؖ��ł��B
���̂ǂ���̏ؖ����n�[�f�B�[�E���C�g�ɏ�����Ă���悤�ɏЉ�邱�Ƃɂ��܂��傤 (�|��ł�)�B
���������ł��邱�Ƃ̏ؖ� (McCabe)
�n�[�f�B�E���C�g����̖|��ł��B
���Ԃ� N �ɑ��� ���l�@����ۂɁA�e�I�h���X�� N = 4n �����邱�Ƃ��ł����B
�Ɋւ��Ă͂��łɈ����Ă������߂ł���B����ȊO�� N �������ł���ꍇ�ɂ� N ��
2( 2n + 1) �̌`�����A �̏ؖ������̂܂ܓK�p�ł���B�]���� N ����̏ꍇ��
�l����悢�B���̂悤�� N �Ɋւ��Ă�
= a/b,�@�@gcd(a, b) = 1
�Ƃ���� Nb2 = a2 �ƂȂ�Aa, b �͋��Ɋ�ƂȂ�B
a = 2A + 1, b = 2B + 1 �Ƃ����
N(2A + 1)2 = (2B + 1)2
N �͎��̌`�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
4n + 3, �@�@8n + 5, �@�@8n + 1
������ N = 4n + 3 �ł���A�ς�����āA2 �Ŋ���A����B
8nA(A + 1) + 6A(A + 1) + 2n + 1 = 2B(B + 1)
����͕s�\�ł���B���ӂ���ŁA�E�ӂ������ł���B
N = 8n + 5 �ł���A�ς�����āA4 �Ŋ���Ύ���B
8nA(A + 1) + 5A(A + 1) + 2n + 1 = B(B + 1)
������s�\�ł���B�Ƃ����̂� A(A + 1), B(B + 1) �͋��ɋ����ł��邩��ł���B
8n + 1 �̐����c�邱�ƂɂȂ����A����� 1, 9, 17,... ���Y������B
���_ 1, 9 �͎����ŁAN = 17 �ō���ƂȂ�B���̏ꍇ�Ɠ��l�ɋc�_����ƁA���̎���
���B����B
17(B2 + B) + 4 = A2 + A
���ӂƂ������ł���B�����ł��낢��ȉ\�����l���Ȃ�������Ȃ��Ȃ�A
���͂����ƕ��G�ƂȂ�B
�����A���ꂪ�e�I�h���X�̕��@�ł���A�������R�� �̎�O�ŃX�g�b�v���邱�ƂƂȂ�B
���������ł��邱�Ƃ̊w�I�ؖ� (Zeuthen)
�n�[�f�B�[�E���C�g����̖|��ł��B
Zeuthen �ɂ�莦�����ꂽ�ؖ��́A���ɂ���ĈقȂ�A
���̈Ⴂ�� ��\����������I�A�����W�J�̒�Ɉˑ����Ă���B
��X�͓T�^��Ƃ��čł��P���ȏꍇ (N = 5) �����グ��B
��X��
x = ( - 1)/2
�ŋc�_������B���̂Ƃ� x2 = 1 - x �ł���B
�w�I�ɂ́AAB = 1, AC = x �ł����
AC2 = AB�ECB
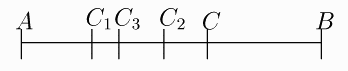
�ƂȂ�AAB �͓_ C �Łu������v�ɕ��������B
�����̊W���͉~�ɓ��ڂ��鐳 5 �p�`����}����̂Ɋ�{�I�Ȃ��Ƃł��� (���[�N���b�h���_ IV, 11)�B
������ 1 �� x �Ŋ����āA�ő�̐��̐������� (���Ȃ킿 1) �Ƃ���A�]��� 1 - x = x2
�ł���B
������ x �� x2 �Ŋ���A���͍Ă� 1 �ŗ]��� x - x2 = x3
�ł���B
���� x2 �� x3 �Ŋ���A���̑�����ɑ�����B�ǂ̒i�K�ł�
�����鐔�A���鐔�A�]��̔��͑S�ē������B
�w�I�ɂ́A������ CB �̔��Α��� CC1 �������A
AB �� C �ɂ������ (���Ȃ킿������) �Ɠ������ CA �� C1 �ŕ�������� (������)�B
�������AC1A �̔��Α��� C1C2 �������A
C1C �� C2 �ʼn�����ɕ�������� (������)�A�Ȃǂł���B
�ǂ̒i�K�ł���������ɕ������邱�Ƃ������Ă��邽�߁A���̑���͖����ɑ������ƂɂȂ�B
���@�u�����̕����v�Ɓu����v�͉p��ł͓����udivide�v�ł���B
����́A����Z���A���Ƃ��Ɛ����̕������痈�Ă��邽�߂ŁA���邱�Ƃ͕������Ӗ����Ă��܂��B
���ꂪ�Ax ���L�����ł��鉼��ɖ������邱�Ƃ��������Ƃ͂ƂĂ��ȒP�ł��B
������ x ���L�����ł���� AB, AC �͓��������̐����{�ƂȂ�܂��B
�����Ă���͐}�̒��̐���
C1C = CB = AB - AC,�@�@C1C2 = AC1 = AC - C1C, ....
�ւ��Ă��S�ē��Ă͂܂�܂��B�]���āA
�̐����{�̌��������ɑ������ƂɂȂ�܂��B����͒P�ɕs�\�ł��B
�����O�����́A���̃y�[�W�̍ŏ��ň��p���������ŁA�e�I�h���X�ɂ��ؖ���
�w�I�ؖ��ł������l����ق��������͂�����Ƃ����Ă��܂��B
4. ���������ł��邱�Ƃ̊w�I�ؖ�
�u�͂��߂Ɂv�ł��Љ���悤�ɉp���̃y�[�W�ł́u�������ł��邱�Ƃ̊w�I�ؖ��v��
�����|�s�����[�Șb��̂悤�ł��B���̂����A�ڂɂƂ܂܂������̂��Љ�����Ǝv���܂��B
���� 1
�����Ŏ��グ��u ���������ł��邱�Ƃ̊w�I�ؖ��v�͉p��̃y�[�W�ł�
���鏊�ŏЉ��Ă�����̂ł�
Tom M. Apostol, Irrationality of the Square Root of Two - A Geometric Proof,
American Mathematical Monthly, November 2000, pp. 841-842.
�ɂ��ؖ��ŁA�Ⴆ��
A new proof that the square root of 2 is irrational
�ɏЉ��Ă��܂��B�ؖ����g�͔��ɊȒP�ł��B���̂悤�Ȓ��p�ӎO�p�`���l���܂��B
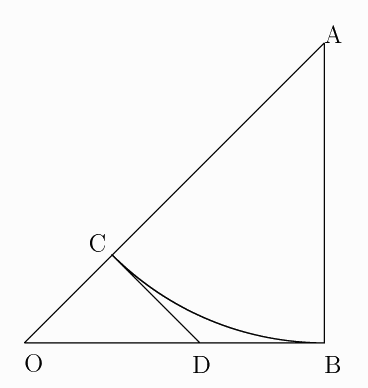
��ABO �����p�� AB = OB = 1, AO = �ł��B�� A �𒆐S�ɂ��āA���a AB ��
�~�ʂ�`���AAO �Ƃ̌�_�� C �Ƃ��܂��BC �Ő����𗧂āAOB �Ƃ̌�_�� D
�Ƃ��܂��B
��AOB �� 45 �x�ŁA��OCD �͒��p�ł�����A��OCD �͒��p�ӎO�p�`�ł��B
���� OC = CD �ł��B
�� CD, DB �͓_ C, B �ʼn~�ɐڂ��Ă��܂�����ACD = DB �ł��B�]����
DB = OC�B
���L�����Ƃ��܂��B���̂Ƃ� AO, AB �̒����͋��ɂ����ƂȂ��
�����{�ƂȂ�܂��B�]���� CO �̒������̐����{�ƂȂ�܂��B
OD �� OB ���� DB ���������ʂł�����A
OD �̒������̐����{�ƂȂ�܂��B
����Ŗ����ł��B���̂Ȃ�A���p�ӎO�p�`��OAB �͕ӂ̒�����
���ׂă̐����{�ŁA
���������菬���Ȓ��p�ӎO�p�`��OCD���\���ł��A���������̕ӂ�
���������ׂă̐����{�ł��B������ɑ�����ƁA
���� (��0) �̖��������\���ł��邱�ƂɂȂ�A�����ƂȂ�܂��B
���� 2
�ʐς� 1 �̐����` 2 �ƁA�ʐς� 2 �̐����` 1 ��p�ӂ��܂��B
�ʐς� 1 �� 2 �̐����`��ʐς� 2 �̐����`�ɉ��̐}�̂悤�ɏd�˂܂��B
�ʐ� 1 �̐����`���d�Ȃ��Ă��镔�������F�ŕ`���Ă���܂��B
���F�̕����̖ʐς́A�̕����̖ʐςɓ������Ȃ�܂��B
�]���āA�����`�̐����` 2 �̖ʐς� 1 �̖ʐςɓ������Ȃ�܂����B
����Ł@ ���������ł��邱�Ƃ��킩��܂��B
�������A�L�����Ƃ���ƁA�ŏ��̗Ɛ̐����` 1 �ӂ̒����͊�ƂȂ�̐����{�ƂȂ�܂��B
��̑���ɂ���āA��菬���Ȑ����`�ł���Ɠ��������ɂȂ���̂�����܂����B
(���炽�ɍ\�����ꂽ�����`�� 1 �ӂ��̐����{�ƂȂ�܂��B)
���́A����͖�����J��Ԃ����Ƃ��ł��A�]����
���� (��0) �̖��������ł��A�����ƂȂ�܂��B
������ǂ����̉p���̃y�[�W�Ō������̂ł����A
�ǂ��Ō����̂����ł͂킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�������ł��邱�Ƃ��w�I�Ɏ������@�͔��z�𗝉������
�ǂ���ȒP�Ȃ��̂���ł��B�����A�������ɂ����K�p�ł��Ȃ���
�v���܂����A�s�^�S���X�w�h�����̂悤�ȕ��@�ŁA ���������ł��邱�Ƃ�
�������Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
5. ���������ł��邱�Ƃ̊w�I�ؖ�
�ȉ��Љ�邱�Ƃ́A�u�{�C���[�A���w�̗��j 1, ���q���X�v�� p 103 �ɍڂ��Ă��邱�Ƃł��B
�ؖ��̃X�P�b�`��������Ă��邾���ŁA
�ŏ��͂킯���킩��܂���ł����B�������A�Ñ�M���V���ł́A
�����̒����ɑ��Ă����[�N���b�h�ݏ��@ (��萳�m�ɂ͌��@) ��K�p���Ă����Ƃ������Ƃ�
�t�@���E�f���E���F���f���Œm�邱�ƂɂȂ�A�悤�₭�Ӗ����킩�邱�ƂɂȂ�܂����B
�������Ƃ� (1 + )/2 ���������ł��邱�Ƃł��B�Ȃ����̏ؖ����p�ꌗ�ł͂悭�m��ꂽ���̂̂悤�ł��B
�ݏ��@ (���邢�͌��@) ��K�p����O�ɁA�}����킩�邱�Ƃ���܂��B
���܊p�` ABCDE ��`���A�Ίp���������Γ����ɍĂѐ��܊p�` FGHIJ ��
�ł��܂��B���܊p�` ABCDE �͉~�ɓ��ڂ��邽�߁A
���������̉~�ǂ̏�ɂ���~���p�͂��ׂē������Ȃ�A
��ABE, ��AEB, ��BAC, ��CAD, ��DAE �͂��ׂē����p�x�ɂȂ�܂��B
�������� ��ABE �� ��/5 �ɂȂ�܂��B�܂������Ȑ��܊p�` FGHIJ ��
�l����A�����悤�� ��GHF �� ��/5 �ƂȂ�܂��B�ȏ�̂��Ƃ���A
��ABJ, ��FBH �͓ӎO�p�`�ɂȂ�܂��B
���āA���܊p�`�̈�ӂƑΊp�� (�̒���) �ɑ��āA�ݏ��@ (���邢�͌��@) ��
�K�p���܂��B�P�ɑ傫��������A����������������������x�������܂��B
�ȉ��A�����̒����݂̂���Ƃ��ABE �Ƃ���ΐ��� BE �̒����̂��Ƃ�
�Ӗ����܂��B
| | (BE, BA) = (BE, BJ) |
| ���� | (BE - BJ, BJ) = (JE, BJ) = (BF, BJ) |
| ���� | (BF, BJ - BF) = (BF, FJ) = (FH, FG) |
�ȏ���A���܊p�`�̑Ίp���ƈ�ӂ̒����̔�͖������ƂȂ�܂��B
�Ȃ��Ȃ�A�������䂪�L�����ł���ABE, BA �͒P�ʂƂȂ钷�� �� �̎��R���{��
�Ȃ���Ȃ�܂���B���݂ɍ�����鑀�������ƁA
���A�����Ȑ��܊p�`�̑Ίp�� FH �ƈ�ӂ̒��� FG �ƂȂ�܂��B
�]���āAFH �� FG �� �� �̎��R���{�łȂ���Ȃ�܂���B
����ɂ��A�����Ɍ������鎩�R���̗\���ł������ƂƂȂ�A�����ƂȂ�܂��B
AB = 1 �Ƃ���ABE = (1 + )/2 �ł�����A����� ���������ł��邱�Ƃ�
�����ꂽ���ƂɂȂ�܂��B
6. �s�^�S���X�w�h�ɂ��u ���������ł��邱�Ƃ̏ؖ��v
�s�^�S���X�w�h���u ���������ł��邱�Ɓv���ؖ��ł����̂́A
�̗L�����ߎ������߂邽�߂ɘA�����W�J���������߂ł��낤�A
�ƃt�@���E�f���E���F���f�����������Ă��܂��B
�������A����͐����Ƃ������́A�܂��ԈႢ�Ȃ������ł��낤�Ǝv���܂��B
�������̌v�Z�ɂ́A�ߐ��ɂ̓e�C���[�W�J���g�p����܂����A
����ȑO�͂����ς�A�����W�J�ł��B
�u�A�����W�J - ����I���_����v�A�u�y�������� - ����I���_����v
��t���������̂́A�F�X������������ł��B
�A�����W�J��y���������̂��Ƃ�m��Ȃ���u���@ - �Ñ�M���V���̊ϓ_����v
��ǂ߂������āA�ȒP�ɗ����ł��邩������܂���B
�A�����W�J - ����I���_����
�A�����W�J�Ɋւ��Ă�
���ؒ��A���������_�u�`�A�����o��
�ɏڂ����L�ڂ���Ă��܂����A�����ł̓t�@���E�f���E���F���f���̋c�_�̗����ɕK�v�Ǝv���邱�Ƃ�
�����������Ǝv���܂��B
��`
�A�����Ƃ͎��̂悤�ȕ����̂��Ƃł��B
| a0 + | b0 |
| a1 + | b1 |
| a2 + | b2 |
| | a3 + | b3 |
| | | a4 + �E�E�E |
�ʏ�͎��̂悤�ȘA�����������̂����ʂł��B
| k0 + | 1 |
| k1 + | 1 |
| k2 + | 1 |
| | k3 + | 1 |
| | | k4 + �E�E�E |
��������̂悤�ɕ\���܂��B(�ʓ|�ȏꍇ�ɂ� [k0, k1. �E�E] �̂悤�ɏ������Ƃ�����܂��B)
| k0 + | 1 | | 1 | | 1 | |
| k1 | + | k2 | + �E�E�E + | kn | �E�E�E |
���� �ց�1 �ɑ��āA���̐������Ə��������A�������� 1/��1 �Ə����A
��1 �ɂ����l�ȑ�������A������J��Ԃ��܂��B
| �� = k0 + | 1 | , k0�@����, �@��1��1 |
| ��1 |
| ��1 = k1 + | 1 | , k1�@����, �@��2��1 |
| ��2 |
| ��2 = k2 + | 1 | , k2�@����, �@��3��1 |
| ��3 |
| �E�E�E |
��������ƁA���̂悤�ȕ����\���������܂��B����� �� �̘A�����W�J�Ƃ����܂��B
| �� | = | k0 + | 1 |
| ��1 |
| | = | k0 + | 1 |
| k1 + | 1 |
| | | | ��2 |
| | = | k0 + | 1 | |
| k1 + | 1 |
| | | | k2 + | 1 |
| | | | | ��3 |
| �E�E�E |
| |
| | = |
| k0 + | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| k1 | + | k2 | + �E�E�E + | kn-1 | + | ��n |
|
��n ��A�����W�J�̏I���ƌĂсA
| k0 + | 1 | | 1 | | 1 |
| k1 | + | k2 | + �E�E�E + | kn-1 |
���� �̋ߎ������ƌĂсA�ւ��������̎��An ���傫���Ȃ�Ƌߎ������̓ւɎ������邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�ؖ��͍��ؒ����Q�Ƃ��Ă��������B
�A�����W�J�͖�������L�����ŋߎ����邽�߂̕��@�Ƃ��Ēm���Ă�����̂ł��B��������A�����ŋߎ�����ƁA
���ꂪ�ł������������ƂȂ�A�������ǂ��Ȃ�܂��B
�ȏ�̓_�Ɋւ��āA�������������������������ǂ��悤�ł��B
���ԋߎ����������̂悤�ɒu���܂��B(pn, qn �͎��R��)
| pn | = k0 + | 1 | | 1 | | 1 |
| qn | k1 | + | k2 | + �E�E�E + | kn-1 |
��������ƁA�C�ӂ� xn �ɑ��āA�����������܂��B
| k0 + | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | = | pnxn + pn-1 |
| k1 | + | k2 | + �E�E�E + | kn-1 | + | xn | qnxn + qn-1 |
xn �� kn �Ɉ�v����A���̕����̒l�� pn+1/qn+1 �Ɉ�v���A
xn = 1, 2, .., kn - 1 �̂Ƃ��ɁA���̕��������ԋߎ������ƌĂ�܂��B
(���ӂ� 1/xn ���������ɁA�E�ӂ� pn/qn �Ɉ�v���Ȃ��Ƃ����܂��A
��������邽�߂ɂ͉E�ӂ̕��ꕪ�q�� xn �Ŋ���Axn ����ɂ���悢�ł��B)
�p�ꂪ�܂���킵���ꍇ�ɂ� pn/qn ���u��Ȃ�ߎ������v�ƌĂ�܂��B
�ȏ�͍��ؒ��̖{�ɏ����Ă��邱�Ƃł��B���̖{��ǂƂ��ɂ͉��́A�u��Ȃ�ߎ������ȊO�v�Ɂu���ԋߎ������v
�Ȃ���̂��l�@����K�R�����s���ł����B
�A�����W�J�͖{���I�ɂ̓��[�N���b�h�ݏ��@�Ɠ������̂ł��邱�Ƃ͈ȑO����悭���m���Ă������Ƃł����A
�t�@���E�f���E���F���f���̖{��ǂ�ŁA
���[�N���b�h�ݏ��@���A�Ñ�M���V���ł͌��@�ł������Ǝw�E����Ă������߁A���ؒ���ǂݒ����Ă݂āA
���̈�ʉ����ꂽ�u���ԋߎ������v���u���@�v��K�p�������ɏI�������ē����镪���ł��邱�Ƃ�
�C�����܂����B(1 �Â����Ă����� xn �� 1 �Â�����B) ���̒��ԋߎ��������A��������L�����ŋߎ�����Ƃ��ɍł������̂悢���� (���ꂪ�ł�����������)
�ł��邱�Ƃ����ؒ��̖{�ŏq�ׂ��Ă��邱�Ƃł��B
�A�����W�J�̓��[�N���b�h�ݏ��@�Ɠ���
�A�����W�J�̓��[�N���b�h�ݏ��@�Ɠ������̂ł��B
a, b �𐳂̎����Ƃ��Aa �� b �Ŋ��邱�Ƃ��Aa ����ł������ b ���������ƂƗ������܂��B
����Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B
| a | = | q0 b + r1 | q0�@����, 0��r1��b |
| b | = | q1 r1 + r2 | q1�@����, 0��r2��r1 |
| r1 | = | q2 r2 + r3 | q2�@����, 0��r3��r2 |
| �E�E�E |
��������Ǝ��̂悤�ɂȂ�Aa/b �̘A�����W�J�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
| a/b | = | q0 + | 1 |
| b/r1 |
| b/r1 | = | q1 + | 1 |
| r1/r2 |
| r1/r2 | = | q2 + | 1 |
| r3/r2 |
���[�N���b�h���_�ł́Aa, b �������̒����ł���Ƃ� a �� b �Ŋ��邱�Ƃ��A
a ����ł������ b ���������ƂƂ݂Ȃ��Ă���A�ݏ��@�̓K�p�� a, b �������̏ꍇ��
�����Ă���킯�ł͂���܂���B���[�N���b�h���_�ł͘A�����W�J�̓��[�N���b�h�ݏ��@�̌`��
��舵���Ă���̂ł��B
�������ł��邱�Ƃ̔������
���[�N���b�h���_�̑� 10 ���� 2 �Ɏ��̒藝���q�ׂ��Ă��܂��B
���[�N���b�h���_ X2
��̕s���ȗ� �`�a�A���� ������A���̂��� �`�a ���������A������
�����������傫�������������A�c���ꂽ�ʂ��������Ď����̑O�̗ʂ�����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ���B
�� �`�a�A���� �͒ʖ�ł��Ȃ��Ǝ咣����B
����I�Ȍ�����������A����͎��̂悤�ɂȂ�܂��B
���� a, b (��0) �ɑ��āA���[�N���b�h�ݏ��@��K�p���āA
�L���ŏI�����Ȃ���� a/b �͒ʖ�ł��Ȃ� (�܂�L�����ł͂Ȃ�)�B
�n�[�f�B�[�E���C�g�ɋL�ڂ���Ă���Zeuthen �ɂ��u ���������ł��邱�Ƃ̏ؖ��v
�͎��͂�����g�p���Ă����悤�ł��B�t�@���E�f���E���F���f���Ɏw�E������܂� (p 137)�B
�t�@���E�f���E���F���f���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂� (�|��)�B
�ʖ�s�\���̂��̔�������́A(���[�N���b�h���_��) ���̂��Ƃł͌����Ďg�p����Ă��Ȃ��B
�� 10 �̒��ŁA�ʖ�s�\���̂������̏ؖ����^�����Ă��邪�A�ǂ̏ؖ���������� X2 ��
���ƂÂ����̂ł͂Ȃ��B
���̔�������́A����ȑO�̒ʖ�s�\��̗��_�̎c�����Ǝv����B
�t�@���E�f���E���F���f���� p 138 �Ŏ��̂悤�ɂ��q�ׂĂ��܂� (�|��)�B
���ɁA�e�I�h���X�����̂悤�ɋc�_��i�߂��̂ł���A
���[�N���b�h�����j�I�ɏd�v�Ȓ藝 X2 �����_�Ɋ܂߂����R�𗝉����邱�Ƃ��ł���B
�Ȃ��A����ł͐F�X�L�����g�p���邱�Ƃ��ł��܂�����A���[�N���b�h���_�̔������ X2 �͂قƂ�Ǔ�����O�ł��B
�����̃��[�N���b�h�ݏ��@�͕K���L����ŏI�����܂�����A
�L����ŏI�����Ȃ��̂͐��̔䂪�L�����łȂ����Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B
, ���������ł��邱��
���[�N���b�h���_�̒藝 X2 ��O��ɂ���A, ���������ł��邱�Ƃ������ɂ�
, �̘A�����W�J������悢�����ł��B2 ���������̘A�����W�J�̂��Ƃɏڂ�����A����͓�����O�Ȃ̂ł����A
���ۂɂ��Ă݂��
| | = 1 + ( - 1) |
| 1 | = + 1 = 2 + ( - 1) |
| - 1 |
| �� | = 1 + | 1 | = 1 + | 1 |
| + 1 | 2 + | 1 |
| + 1 |
| | = [1, 2, + 1] |
| | = [1, 2, 2, 2, �E�E�E,2, + 1] |
| = 1 + ( - 1) | |
| 1 | = | + 1 | = 1 + | - 1 | |
| - 1 | 2 | 2 |
| 2 | = | + 1 = 2 + ( - 1) |
| - 1 |
| �� | = | [1, 1, 2, ( + 1)/2] |
| | = | [1, 1, 2, 1, 2, ( + 1)/2] |
| | = | [1, 1, 2, 1, 2, �E�E�E, 1, 2, ( + 1)] |
�ƂȂ�A�ǂ���̓W�J���z���邱�Ƃ��킩��A��ɏI�����܂���B
�]���āA�ǂ�����������ł��邱�Ƃ��킩��܂��B����ł͂���͋ɂ߂ĊȒP�ɂł���v�Z�ł����A
�F�X�ȋL���̂Ȃ��Ñ�M���V���ł͂ƂĂ���ςȂ��Ƃł������͂��ł��B
�y�������� - ����I���_����
�y�������� (Pell's equation) �Ƃ�
x2 = D y2 + 1
�̌`�̕������ŁA���ׂĂ̐����� (x, y) �����߂���̂ł��B(x, y) = (1, 0) �����̈�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��B
���̕��������y���������Ɩ��O��t�����̂̓I�C���[�ł����A
����̓I�C���[�������������߂̂悤�ŁA���ۂ� John Pell ��
�y���������ɉ����֘A���Ă��܂��� (Pell's equation - Wikipedia ���Q��)
�t�@���E�f���E���F���f���ł͓ǎ҂�����I�ȃy����������
��������m���Ă��邱�Ƃ��O��ƂȂ��Ă���悤�ł��B
�����ŁA����������܂�ŏЉ�邱�Ƃɂ��܂��B
�Ȃ�
���ؒ��A���������_�u�`�A�����o��
�ɂ��y���������͏ڂ����������Ă��܂����A�ϓ_���Ⴄ����
�����ǂ݊�����K�v������܂��B
�Ñ�̃y���������������ړI�� �̗L�����ߎ������߂邱�ƂŁA
�ȉ��̃y���������̎�舵���̓t�@���E�f���E���F���f���̉����
���킹�����̂ł��B�Ȃ��ȉ��̋c�_�ł� 2 ���̐����s��Ɋւ��Ă͊��m�̂��̂Ƃ��Ă��܂��B
���[�N���b�h�ݏ��@�ƈꎟ�ϊ�
���{��ł́u���[�N���b�h�ݏ��@�v�ƌĂт܂����A
�p��ł́u���[�N���b�h�E�A���S���Y���v(Euclidean Algorithm)�A
�M���V����ł� Antanairesis (���@) �ƌĂт܂�
2 �̐��� s, d ���^����ꂽ�Ƃ��A���@ (���[�N���b�h�ݏ��@) �� 1 ��̑���ł�
�傫���������珬�����������������Ƃ��������݂̂ł��B
| (s, d) | ���� | (s - d, d) | (s��d) |
| (s, d) | ���� | (s, d - s) | (d��s) |
�A�����W�J�̕\�L�ł�
���̂悤�ȕϊ����J��Ԃ���������ƁA�ǂ��Ȃ�ł��傤�� ?
���₷�����邽�߂ɂ́A�ꎟ�ϊ������Ȃ���Ȃ�܂���B
�����W���� 2 ���̐����s��ŁA�s�� 1 �̂���
�ƔC�ӂ̎��� �� �ɑ���
�ƒu���A�� ---> A(��) ���ꎟ�ϊ� �ƌĂт܂��BA' �����l�� 2 ���̐����s��Ƃ����
�A���AAA' �͍s��̐ρA���Ȃ킿
�ȏ�̋L�@��K�p����ƁA���@ (���[�N���b�h�ݏ��@) ���U����������̕ϊ���
| �� ���� | �� - 1 | = |
|
(��) |
| �� ���� |
|
= |
|
(��) |
�ƂȂ�A�����̕ϊ��̊���̍�����
�ƂȂ�B�A��
�ꎟ�ϊ��ƃy���������̐�����
���āA�y���������Ƃ̊֘A���q�ׂ悤�B
�藝
���R�� D ���������łȂ��Ƃ��A�� = �ƒu���B
�����W���� 2 ���̐����s�� A �� |A| = 1 �ƂȂ���̂ɑ��� �� = A(��) ��
�����
�ƂȂ�B�A�� x, y �̓y�������� x
2 - D y
2 = 1 �̔C�ӂ̐������B
�@
�@
���� x, y �ɑ���
�� = x + y �ɑ��� = x - y
�ƒu���A �� �� ������ �ƌĂԁB�ȏ�̂悤��
��߂�ƁA���̑Ή��� 1-1 �ƂȂ�B
| |
{ (x,y) | x,y ����, x2 - D y2 = 1 } |
�� | (x,y) |
| |
{ �� = x + y | x,y ����, �� = 1 } |
�� | x + y |
| |
{ |
A |
| 2 ���̐����W���s��, |
| |A| = 1, A() = |
|
} |
�� |
|
�������A�Ō�̑Ή��͏�@��ۑ�����B���̎����͍Ō�̑Ή��������\���ł��邱�Ƃɂ�邪
���̂悤�ɒ��ڊm���߂Ă��悢�B
|
( x + y )( x' + y' )
|
= |
( x x' + y y' D ) + (x y' + y x')
|
| |
|
|
= |
|
�ȏ�̎������炽�����ɂ킩�邱�Ƃ́A
�藝
A, A' ���y���������̐������ɑΉ������ AA', A-1 ���y���������̐������ɑΉ����A
���A��, ��' ���y���������̐������ɑΉ������ �ƃ�', ��-1 ���y���������̐������ɑΉ�����B
�y���������̉��̍\��
�t�@���E�f���E���F���f����ǂނɂ́A�y���������̐������Ɋւ��āA����ȏ�ڂ������Ƃ�
�K�v���Ȃ����A������_�t�������Ă����������ʂ����悢�B
�藝
�y�������� x
2 - D y
2 = 1 �̐��̐����� (x
0, y
0)
�Ŏ��̏����������̂�����B
�C�ӂ̐��̐����� (x, y) �ɑ���
x + y = ( x0 + y0 )n
�������R�� n ������B
�@
������y���������̑S�Ă̐����������߂�ɂ́A�������ɑΉ����� �Ɓ�1 �ōŏ��̂��̂����߂�悢�ł��B
���@ - �Ñ�M���V���̊ϓ_����
�L����ŏI������Ƃ�
���[�N���b�h�ݏ��@���Ӗ�����M���V����� Antanairesis �ł���A
����݂͌��Ɉ������Ƃ��Ӗ�����B���̑g (x, y) �������͐����̑g (u, v) ����o�����āA
�傫�������珬������������������B�����������Ȃ��Ď菇���I�����邩�A�������͉i�v�ɑ����B
�Ⴆ�� 49 �� 91 �Ƀ��[�N���b�h�ݏ��@ (���邢�͌��@) ��K�p����Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B
| 49 | 49 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 91 | 42 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 |
�}��������Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B�܂� 49 �� 91 ���Z�b�g�B
���ɁA91 ���� 49 �������� 42 ���c��B
49 ���� 42 �������ƁA7 ���c��B
42 ���� 7 �� 5 ������� 7 ���c��A����ŏI���B
�}����A���Ă킩��悤�ɁA���̑���ŁA49 �� 91 �ɋ��ʂȒP�ʗv�f�A���Ȃ킿�ő����
�����܂�܂��B���[�N���b�h���_�ł͌ݏ��@������̏ꍇ�ɂ��K�p���Ă���A
������̕����������₷���B�܂����� 91 �� 49 �̐�����p�ӂ���B
���� 91 �̐����� AB �Ƃ��A�������璷��49 �̐��� AC �������B
����ƁA�c�� (���邢�͗]��) �� CB �ƂȂ�A����� AC ��蒷�����������B
�����ō��x�� AC ���� CB �Ɠ��������� CD �������B
�c�� (���邢�͗]��) �� AD �ƂȂ�B
CD �̕��� AD ���傫���Ȃ�̂ŁACD ���� AD �� 5 ������ƁAEC ��
�c��A����� AD �Ɠ������Ȃ�B
���ꂪ AB �� AC �̋��ʂ̒����̒P�ʂł���B�قǂ������ϊ���
| | (a0, b0) = (49, 91) |
| ���� | (a1, b1) = (a0, b0 - a0) = (49, 42) |
| ���� | (a2, b2) = (a1 - b1, b1) = (7, 42) |
| ���� | (a3, b3) = ((a2, b2 - 5�~a2) = (7, 7) |
�Ō�̕ϊ�����Aa2 = a3, b2 = b3 + 5�~a2
��������B���̂悤�ɂ��ď�̕ϊ��͋t�����ǂ邱�Ƃ��ł���B
(a3, b3) = (1, 1) �ƒu���A
��̋t�ϊ������ǂ�ƁAa0�Fb0 ���킩��B
| | (a3, b3) =(1, 1) |
| ���� | (a2, b2) = (a3, b3 + 5�~a2) = (1, 6) |
| ���� | (a1, b1) = (a2 + b1, b2) = (7, 6) |
| ���� | (a0, b0) = (a1, b1 + a0) = (7, 13) |
�܂�A49�F91 = 7�F13 ���킩�����̂ł���B���_�A����̂ɂ킴�킴��������K�v�͂Ȃ��B
���ꕪ�q�̍ő���� 7 ���킩�������_�ŁA���ꕪ�q�� 7 �Ŋ���� 7�F13 ��B
�L����ŏI�����Ȃ��Ƃ�
�䗦 a0�Fb0 ��������łȂ���� (���邢�� a0/b0 ���L�����łȂ����)
��̎菇�͉i�v�ɑ����B�������A�傫�� n �� (an, bn) �� (1, 1) �Œu�������āA
�t�����ǂ�ǂ��Ȃ�̂ł��낤�� ?
�Ⴆ�A(a0, b0) = (, 1) �ɑ��āA���@��K�p����ƁA
| | (a0, b0) = (, 1) | |
| ���� | (a1, b1) = (a0 - b0, b0) = | ( - 1, 1) |
| | | ( - 1)�F1 = 1�F( + 1) |
| ���� | (a2, b2) = (a1, b1 - a1) = | ( - 1, 2 - ) |
| | | ( - 1)�F(2 - ) = 1�F |
| ���� | (a3, b3) = (a2, b2 - a2) = | ( - 1, 3 - 2) |
| | | ( - 1)�F(3 - 2) =�P�F( + 1) |
| ���� | (a4, b4) = (a3 - b3, b3) = | (3 - 4, 3 - 2) |
| | | (3-4)�F(3 - 2) = �F1 |
�����͎̏��̂悤�ɑJ�ڂ���B
a0 ���� b0 �������ƁAa1 ���c��A
b1 �� b0 �ƂȂ�Ab1 ����A
a1 �� 2 ������ƁAb3 �ƂȂ��āA
a3 �� a1 �ƂȂ�B
a3 ���� b3 �������ƁAa4
�ƂȂ�Ab4 �� b3 �ƂȂ�B
(a4, b4) = (1, 1) �Ƃ݂Ȃ��A
���̔䗦�͂��̂܂܂Ƃ���ƁA�e�����̒����͐}�� 1 �ԉ���
�\������Ă�����̂ƂȂ�A(a0, b0) = (7, 5) �ƂȂ�B
�J��Ԃ��𑽂̉�����A��̂悤�Ȑ}���炷���ɂ킩��킯�ł͂���܂��A�t�̕ϊ���ǂ����Ƃ��ł��A
���̂悤�Ȃ��Ƃ�����Aa0/b0 �̋ߎ�������
���߂��邱�Ƃ͂قږ��炩�ł��B
�t�@���E�f���E���F���f���̎咣���鏊�́A
�Ñ�M���V���l�͌ʂɂ��������I���Ɏ�舵�� (�Q���� !)�A
���̂悤�ȕs���������̂ł͂Ȃ����Ƃ������̂ł��B
���̕s�����̓A���L���f�X�ɂ����̂ł����A
�s�^�S���X�w�h�����l�ȕ��@��I��ŁA �ɓK�p�����Ǝv����\���ȍ���������̂ł��B
�t�@���E�f���E���F���f���̖{����̖|��
����I�ȃy���������̉�@�͂��̂܂܂ł́A�Ñ�M���V���ł͎��s�ł��܂���B
�����Ƃ�����_�́A�ꎟ�ϊ��̍s��̐����ɕ��̐����o�Ă���_�ł��B
�Ñ�M���V���ł͕��̐����Ȃ����߁A���̂܂܂̌`�ł̓y���������������ł��Ȃ��̂ł��B
����������Ńy���������̉����� �� �̋ߎ���^���Ă������Ƃ��z�肳��܂��B
�t�@���E�f���E���F���f���͌Ñ�M���V���l���ǂ̂悤�ɏ������Ă����̂���
�ւ��Ĕ[���ł��鐄����^���Ă��܂��B�ȉ��A�t�@���E�f���E���F���f���̖{��
�����I�Ȗ|����Љ�܂��B��Ɂu�y���������v����̖|��ł����A
�� 3 �͂ɂ��֘A�������Ƃ��L�q����Ă���̂ŁA�Y���ӏ������܂��B
�� 3 �͂���̔���
�t�@���E�f���E���F���f���̑� 3 �͂́u�M���V���̑㐔�v�������Ă���A���̒���
���[�N���b�h���_�̑� 2 ���̒藝 10 ��������Ă��܂��B
���[�N���b�h���_�AII 10
���� AB �� �� �ɂ����� 2 ��������A���� B�� �� AB �ƈ꒼�����Ȃ��ĉ�����ꂽ�Ƃ���B
A��, ��B ��̐����`�̘a�� A��, ���� ��̐����`�̘a�� 2 �{�ł���Ǝ咣����B
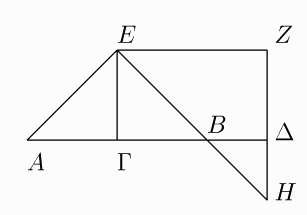
�藝�ŏq�ׂĂ��邱�Ƃ�����I�Ɍ����Ȃ����A
A�� �̒����� s, B�� �̒����� d �Ƃ����
(2s + d)2 + d2 = 2 { s2 + (s + d)2 }
�̓������������邱�Ƃł��B������ 2s + d = x, d = y �ƒu����
x2 + y2 = 2{ ((x-y)/2)2 + ((x+y)/2)2 }
�Ə����������Ƃ��ł��܂��B��������Γ���݂ȓ����ƂȂ�܂����A���[�N���b�h���_�ł͗�ɂ����
���ʊ��g�p���Ē藝���ؖ����Ă��܂��B
�藝�����̌`�ɂ��Ă����܂��B
(2s + d)2 + d2 = 2 s2 + 2 (s + d)2
�t�@���E�f���E���F���f���ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B
�� 3 �́Ap 86 ���� (�|��)
�v���N���X (Proklos) ��
�v���g���́u���Ɓv (Plato's "Republic") (Kroll �ŁA�� 2 ���A��23) �̒��߂ŁA
�s�^�S���X�w�h�́u�Ӑ��ƑΊp�����v�̗��_�����������ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�s�^�S���X�w�h�� (���[�N���b�h���_��) �藝 II, 10 ���g�p���āA���̂悤�ȃG���K���g�Ȓ藝��
�����Ă���B���Ȃ킿�ws �� d �����鐳���`�̕ӂƑΊp�� (�̒���) �ɓ�������A
s+d �� 2s+d �͕ʂ̐����`�̕ӂƑΊp�� (�̒���) �ɓ������x
�܂�Ad2 = 2 s2 �ł���A(2s+d)2 = 2(s+d)2
�ƂȂ邱�Ƃł��B����͊m���ɒ藝 II, 10 ���瓾���邱�Ƃł��B
�u�y���������v����̖|��
������ x2 = 2 y2 �}1
�u���Ɓv(Republic) �� 546C �Ńv���g���͐� 7 ���u�L���Ίp���v(rational diagonal) ��
�Ă�ł���A���߂���A���̐��́u�L���Ӂv(rational side) 5 �ɑΉ����Ă��邱�Ƃ�
�킩��B���� 7�F5 �̔䗦�͐����`�̑Ίp�� (�̒���) �ƕ� (�̒���) �̔�ɂ���߂Ă悢
�ߎ��ł���B
���̒i���ɂ����钍�߂Ńv���N���X (Proklos) �́u�Ӑ��v�Ɓu�Ίp�����v�����̂悤�ɒ�`���Ă���B
2 �̒P�ʂ���o�����āA�v���N���X�Ɏ�����Ă���K����K�p����A
���X�e�b�v�Łu�Ӑ��v
�������A�Ή�����u�Ίp�����v
��������B����
| s' = s + d | (2) |
| d' = 2s + d |
�ɓ��Ă͂߂āA���̕����𑱂���ƁAs' = 5, d' = 7 ��B
���ꂪ�v���g���Ō��y����Ă��邱�Ƃł���B
sn, dn �� n �Ԗڂ̕Ӑ��A�Ίp�����Ƃ����
�ł����āA
| sn+1 = sn + dn | (3) |
| dn+1 = 2sn + dn |
�����Q���� (inductive rule) ���u�X�~�����i�̃e�I���v��
�w�v���g����ǂނ̂ɕK�v�Ȑ��w�x(Expositio rerum mathematicorum) �� p 43 �ɂ�
���y����Ă���B�v���N���X�͕Ӑ��ƑΊp�����̍\���̓s�^�S���X�w�h�ɂ����̂Ƃ��Ă���B
dn�Fsn �̔�� (n ����������Ƌ���) �����`�̑Ίp�� (�̒���) ��
�� (�̒���) �̔� d�Fs �ɂ܂��܂��߂Â��čs���B����͓���
���瓾���邱�Ƃł���A������v���N���X�ɂ�茾�y����Ă���B(�F���Ƃŏؖ�����܂��B)
���ӂ� (sn)2 �Ŋ����
�ƂȂ�Adn/sn �̕����� 2 �ɂقړ������Ȃ�B
�v���N���X�̃e�L�X�g�ɂ��A
�s�^�S���X�w�h�̓��[�N���b�h�̒藝 II 10 �ɂ�� (4) ���ؖ����Ă���B
�� 3 �͂Ō����悤�ɁA���̒藝�͎��̓����ɏ����������Ƃ��ł���B
| (2s + d)2 + d2 = 2 s2 + 2 (s + d)2 | (5) |
�v���N���X�ɂ��s�^�S���X�w�h�� II 10 ���g�p���ăG���K���g�Ȓ藝���ؖ������F
�ws, d �������`�̕� (�̒���), �Ίp�� (�̒���) �ł���� s + d, 2 s + d �͕ʂ̐����`��
�� (�̒���), �Ίp�� (�̒���) �ƂȂ�x�B
�� 3 �͂ł͉�X�́A���̒藝�͓��� (5) ����A���ۂɂ���߂ėe�Ղɓ��邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��������B
�ꎟ�ϊ� (2) �̓��[�N���b�h�ݏ��@�Ɩ��ڂɌ��т��Ă���B
���� (2) �� s, d �Ɋւ��ĉ�����
����āAd', s' �������`�̑Ίp�� (�̒���), �� (�̒���) ��
���݂ɍ�����郆�[�N���b�h�̕��@ (�F���[�N���b�h�ݏ��@�̂���) ��
�K�p����Ύ��̂悤�ɂȂ�B
(d', s') --> (s, s') --> (s, d)
����̈Ӗ����鏊�́F
�ϊ� (2) �́A�� (�̒���) �ƑΊp�� (�̒���) �ɓK�p����邪�A
����͒P�ɁA���傫�Ȑ����`�̑Ίp�� (�̒���) d' �ƕ� (�̒���) s'
�ɓK�p����郆�[�N���b�h�ݏ��@�̋t�ł���B
���_�A���� (5) �͕ӂ̒����ɗL���݂̂Ȃ炸�A���ɂ��L���ł���B
������ s, d ��Ӑ� sn, �Ίp���� dn �Œu��������Ύ���������B
(2 sn + dn)2 + (dn)2 = 2 (sn)2 + 2 (sn + dn)2
���邢��
| (dn+1)2 + (dn)2 = 2 (sn)2 + 2 (sn+1)2 | (6) |
���̓������v���N���X�ɂ�茾�y����Ă�����̂ł���A
���̓_���猋�_���Ă��ԈႢ�Ȃ������Ȃ��Ƃ́A
�s�^�S���X�w�h�ɂ� (6) �����m�ŁAII 10 �ɂ��ؖ����Ă����̂ł��낤�B
������ (4) �̏ؖ������悤�B
���炩�� (4) �� s1 = d1 = 1 �Ő�������B
�������Ȃ���A������ (4) ������ n �Ő�������A���� (4) ��
���� (6) �ɂ�� n + 1 �ł���������B�A�� �} �̕����͋t�ƂȂ�B
����ɂ�� (4) �͔C�ӂ� n �Ő������邪�A���� �} �͌��݂ɕω�����B
���̏ؖ��̓v���N���X�̃e�L�X�g����e�Ղɍč\���������̂ł��邪�A
�u���w�I�A�[�@�v(complete induction) ���邢�́un ���� n + 1 �ւ̕ϑJ�v�ɂ��ł��ŏ���
�ؖ��̎���ł���B
�s�^�S���X�w�h�͑Q���� (3) ��K�p���� (4) �����������A
���炵�����w�ҒB�ł������ɑ���Ȃ��B
���[�N���b�h�ݏ��@�̎�����
���[�N���b�h�ݏ��@�����鐳���`�̑Ίp���ƕӂɓK�p����ƁA2 �X�e�b�v��ɁA
�ʂ̐����`�̕ӂƑΊp�������邱�Ƃ������B
�������A���̏������J��Ԃ��Ήi�v�ɑ����B
���[�N���b�h���_�̑� 10 ���̈�ԍŏ��Ƀ��[�N���b�h�ݏ��@�Ɋւ��Ă�
���ɒ��ڂ��ׂ��藝 X1, X2 ������B2 �Ԗڂ̒藝�Ō����Ă��邱�Ƃ�
��̕s���ȗ� �`�a�A���� ������A���̂��� �`�a ���������A������
�����������傫�������������A�c���ꂽ�ʂ��������Ď����̑O�̗ʂ�����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ���B
�� �`�a�A���� �͒ʖ�ł��Ȃ��Ǝ咣����B
�ʖ�s�\���̂��̔�������́A(���[�N���b�h���_��) ���̂��Ƃł͌����Ďg�p����Ă��Ȃ��B
�� 10 �̒��ŁA�ʖ�s�\���̂������̏ؖ����^�����Ă��邪�A�ǂ̏ؖ���������� X2 ��
���ƂÂ����̂ł͂Ȃ��B
���̔�������́A����ȑO�̒ʖ�s�\��̗��_�̎c�����Ǝv����B
���́u����ȑO�̗��_�v�Ɋւ��āA���������邱�Ƃ�����ł��낤�� ?
�v���g���̑Θb�ł���e�A�C�e�g�X (Theaitetos) ��
����ł���e�A�C�e�g�X�̓L�����l�̃e�I�h���X�ɂ��
�u�`�̐��������Ă���B
�����Ńe�I�h���X�͖ʐς� 3, 5, 6,... (����) �t�B�[�g��
�����`�̕� (�̒���) �������̒P�ʂƒʖ�ł��Ȃ����Ƃ��������B
�ނ͂����̐����`���X�Ɏ��グ�A17 �t�B�[�g�̐����`�ŁA
���邢�͂��̒��O�Œ�~�����B
�ނ̏ؖ����@��K�ɐ����ł���ł��낤�� ?
2, 3, .. �̖ʐς��������`�̈�ӂ̒����� w2, w3, ...
�ƕ\�����Ƃɂ���B���� w2 �͒P�ʐ����`�̑Ίp���̒����ł���B
�����̒P�� (�v���g���̃e�L�X�g�ł� 1 �t�B�[�g) �� e �ŕ\���B
�e�I�h���X�͉���� w3 �ŊJ�n���Ă���B
���炭�� w2 �� e ���ʖ�ł��Ȃ����Ƃ��s�^�S���X�w�h�ɂ���ďؖ�����Ă������߂ł��낤�B
�v���g���̃e�L�X�g����A�e�A�C�e�g�X�͈�ʓI�Ȓ藝 --- wn �� e �ƒʖ�ł��邽�߂ɂ� n ��
�������ł��� --- �Ă����Ƃ��Ă悢�B
�e�I�h���X�̓e�A�C�e�g�X�̈�ʓI�ȕ��@��m��Ȃ������Ǝv���A
���̑���� w2, w3, ... �̌X�̏ꍇ�ɓ��ʂȕ��@����g�����Ǝv����B
Zeuthen �ɂ����ɐ����͂̂��鉼���̓e�I�h���X�� X2 ���g�p�������Ƃł���B
����܂Ō������Ƃ��烆�[�N���b�h�ݏ��@�� w2 �� e �ɓK�p�����A
���邢�͐����`�̑Ίp�� d' �ƕ� s' �ɓK�p�����A2 �X�e�b�v�ŁA
��菬���Ȑ����`�̑Ίp�� d �ƕ� s �ɓ��B���邱�Ƃ��Ӗ����邱�Ƃ́A
���@ (�F�ݏ��@�̂���) �͌����ďI��邱�Ƃ��Ȃ��̂ł���B
����́A�e�I�h���X�͓����A���S���Y���� w3 �� e �ɓK�p���A
�� w3�Fe �����X�e�b�v�ŌJ��Ԃ����ۂ������悤�Ƃ������Ƃ��z�肳���B
���ۂɂ� 3 �X�e�b�v�ŌJ��Ԃ��B
����ɂ͎��̂悤�ɂ��Ď������Ƃ��ł��A����ɂ͏����̃M���V���̊w�҂̔\�͂�
�\���ɉ\�Ȃ��Ƃł���B
w3 = w �ƒu����
w ���� e �������F �c�� (���邢�͗]��) �� w - e.
���X�̐����ł��� w �� e �̑���ɁA��������� e �� w - e �ƂȂ����B
����𑱂��邽�߂ɁA e �� w - e ��������� 2 �̐����Œu��������B
��������������B
e�F(w - e) = (w + e)�F2 e
����͓����̐ςƊO���̐ς����������Ƃɂ��B
(w - e)(w + e) = w2 - e2 = 3 e2 - e2 = 2 e2
���ɓ������@����� w + e �� 2 e �ɓK�p����B w + e ���� 2 e �������Aw - e ��B
���� 2 e �� w - e �͍Ăѓ�������������ɒu�������邱�Ƃ��ł���B
2e�F(w - e) = (w + e)�F e
�ĂсA�����̐ςƊO���̐ς���v����Bw + e �� e ������ꂽ�̂ł���A
�O�҂����҂������Aw �������A�����J�n���������� w�Fe �ɓ��B����B
�� w�Fe �͌J��Ԃ���A����͎����I�ł���A�����ďI��邱�Ƃ��Ȃ��B
����� w3 �� e �͒ʖ�ł��Ȃ��B
�e�I�h���X�����[�N���b�h�ݏ��@���g�p�������ǂ����͒肩�ł͂Ȃ��B
���̉\���� W. R. Knorr �ɂ��{�u���[�N���b�h���_�̔��W�v
(The Evolution of the Euclidean Element, Dordrecht, 1975)
�Ŏw�E����Ă���B�������Ȃ��玄�� Zeuthen �̉����������͂�����Ɗ�����B
�� 1 �ɂ́A�s�^�S���X�w�h�����łɁuw2 �� e �Ƀ��[�N���b�h�ݏ��@��K�p����Ύ����I�ł���v
���Ƃ������Ă���A�e�I�h���X�͒P�ɓ������@�� w3, w5,.. �ɓK�p�����
�ǂ���������������ł���B
�� 2 �ɁA�e�I�h���X�����̂悤�ɏ��������̂ł���A
���[�N���b�h�����_�ɗ��j�I�ɏd�v�Ȓ藝 X2 ���܂߂����R�������ł��邩��ł���B
���@ (Reciprocal Subtraction)
���[�N���b�h�ݏ��@���Ӗ�����M���V����� Antanairesis �ł���A����݂͌��Ɉ������Ƃ��Ӗ�����B
���̑g (x, y) �������͐����̑g (u, v) ����o�����āA�傫�������珬������������������B
�����������Ȃ��Ď菇���I�����邩�A�������͉i�v�ɑ����B
�� 2 �͂Œ����́u��͎Z�p�v�̎���ɂ��A���̎菇���������B
�����̋��ȏ��ɂ��A�� x, y ���Z�Ղ̏�ɒu�����B
x �� y �����傫����A�ŏ��̎菇�� x ���� y ���������Ƃł���B����𑀍� S �Ƃ���F
| S�F | (x, y) ---> (x - y, y) |
y �� x �����傫����A�ŏ��̎菇�� y ���� x ���������Ƃł���F
| T�F | (x, y) ---> (x, y - x) |
������ 2 �̎菇�𐳕��`�̑Ίp�� d' �ƕ� s' �Ɏ����玟�ɓK�p����ƁA
���łɌ����悤�� 2 �X�e�b�v��ɁA�ʂ̐����`�̕� s �ƑΊp�� d ��B
�t�̕ϊ��͉����邱�Ƃł���B
| A�F | (x, y) ---> (x + y, y) |
| B�F | (x, y) ---> (x, x + y) |
������ 2 �̎菇�𐳕��`�̕� s �ƑΊp�� d �ɑ��ēK�p����� 2 �X�e�b�v��Ɏ��̂悤�ɂȂ�B
(s, d) ---> (s, s + d) ---> (2 s + d, s + d)
����̓s�^�S���X�w�h���ӂƑΊp���̐�������ł���B
���ē������@�������� w3 �� e �ɔ�Ⴗ������̑g u', v' ��
�K�p�ł��邩�ǂ������Ă݂悤�B�������A�菇 STS ��K�p����A
���łɌ����悤�� (u', v') �ɔ�Ⴗ������̑g (u, v) ��B
�t�̎菇�� ABA �ł���F
(u, v) ---> (u + v, v) ---> (u + v, u + 2 v) ---> (2 u + 3 v, u + 2 v)
�]���āA���̌��ʂ�F
u, v �������ŊW��
������
| u' = 2 u + 3 v | (10) |
| v' = u + 2 v |
���A�Ăѓ��� (9) ���������ƂȂ�B
���̒藝�́A���̊ȒP�Ȍv�Z����m���߂邱�Ƃ��ł���B
| (2 u + 3 v)2 - 3 (u + 2 v)2 = u2 - 3 v2 | (11) |
���ӂ� 2 �̕����̓��[�N���b�h���_ II 4 �ŕ]���ł���B
���_�A���̍�������āA(11) �����[�N���b�h���Ɏ��̂悤�ɏ������Ƃ��ł���B
(2 u + 3 v)2 + 3 v2 = 3 (u + 2 v)2 + u2
���Ĉꎟ�ϊ� (10) �Ɠ��� (11) �� D = 3 �̃y���������̉�@�ɓK�p���悤�B
���� x2 = 3 y2 + 1 �� x2 = 3 y2 - 2
D = 2 �̏ꍇ�ɂ̓s�^�S���X�w�h�� 1�F1 ����o�����āA
�Q���� (3) ��K�p���āA��� w2�Fe ���ߎ����鐔�����ɓ���Ă���B
D = 3 �̏ꍇ�ɂ� ( ��) �ߎ��ł��� 2�F1 ����o�����āA�ꎟ�ϊ� (10) ���J��Ԃ�
�K�p����A����������B
| xn+1 = 2 xn + 3 yn | (12) |
| yn+1 = xn + 2 yn |
�o���_�ƂȂ����g (2, 1) �͎��̓��������B
���āA���� n �Ɋւ��Ď��̓�������������Ƃ���B
���� (11) ��K�p����Ύ���������B
(2xn + 3 yn)2 - 3 (xn + 2 yn)2 = 1
����͎��̂悤�ɏ�����B
�]���āA���w�I�A�[�@����A���� (12) �����ׂĂ� n �ɑ��Đ�������B
(xn)2 �� 3(yn)2 �����傫�����߁A
xn�Fyn �̔䗦�� w3�Fe �̔䗦������ł���B
������������̋ߎ�����ɓ���邽�߂ɂ͑g (1, 1) ����n�߂āA
�����Q���� (12) ��K�p����悢�B����ɂ��A���̏����������̑g (sn, tn)
����ɓ���B
�g (xn, yn) �� (sn, tn) ���v�Z�����
| n = 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
xn = 2
yn = 1 |
7
4 |
26
15 |
97
56 |
362
209 |
1351
780 |
sn = 1
tn = 1 |
5
3 |
19
11 |
71
41 |
265
153 |
|
�g (1351, 780) �� (265, 153) �̓A���L���f�X�ɂ���Ēm���Ă������̂ł���A
����͂����ɂ����邱�ƂɂȂ�B
D = 2 �̃y���������̉��͓��� (5) �Ɋ�Â����̂ł���B
�S�����l�� D = 3 �̉��͓��� (11) �Ɋ�Â����̂ł���B
(5) �� (11) �̓����͂ǂ�����A���̂���ʓI�ȓ����̓��ʂȏꍇ�ł���B
| (a x + D c y)2 - D(c x + a y)2 = (a2 - D c2)(x2 - D y2) | (14) |
���̓����͗e�ՂɌ��ł��邪�A�u���[�}�O�v�^ (Brahmagupta) �ɂ��A
�X�ɂ̓I�C���[�ƃ��O�����W���ɂ��y���������̉�@�Ɏg�p���ꂽ�B
�u���[�}�O�v�^�̕��@�Ɋւ��Ă͂��̏͂̌�ŋc�_����B
�A���L���f�X�ɂ�� w3 �̏���A����
���ɋ�������_���u�~�̑���ɂ��āv(On measurement of the Circle)
�ŁA�A���L���f�X�͉~���̒��������a�� 3 + 1/7 �{��菬�����A
3 + 10/71 �{���傫�����Ƃ��ؖ����Ă���B
�ނ��J�n���铙�ӂłȂ����p�O�p�`�� 1 �̊p�x�͒��p�� 1/3 �ł���B
���������Α��̕ӂ�P�� e �Ƃ���A�Ίp���� 2e �ŁA�� 3 �̕ӂ� w = w3 �ł���B
�Ȃ��Ȃ�A���̕����� (2 e)2 - e2 = 3 e2
�ł��邩��ł���B
�����ŃA���L���f�X�͔䗦 w�Fe �͎��̊Ԃɂ���ƒf�����Ă���B
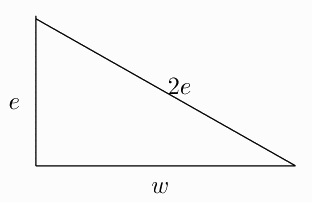
�A���L���f�X���J�n�����O�p�`
����̌��t�ł͎��̂悤�ɏ������Ƃ��ł���B
�����̕s���������������Ƃ��m�F���邱�Ƃ͊ȒP�ł���B
�Ȃ��Ȃ�� 265 �� 153 �͎��̓�������
������g�̐��͎���������ł���B
�A���L���f�X�͂ǂ̂悤�ɂ��Ĕ�� w�Fe �̌��E���̂ł��낤�� ?
���w�j�̐��Ƃ͂��̖��Ɋւ��Ă̊���̗\�z�������Ă���B
���̈ӌ��ł́A�ł���������_���͈ȉ��̂��̂ł���F
- P. Tannery�F Sur la mesure du cercle d'Archmède, Mémoires scientifique I, p. 246-253
- C. Müller�FWie fand Archimedes die von ihm gegebenen Näherungswerte von ?
Qullen und Studien zur Geschichte der Mathematik B 2, p. 281-285.
- O. Toeplitz�FBemerkungen zu der vorstehenden Arbeit von Conrad Müller, same journal, p. 286-290.
- K. Vorgel�FJahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 41, p. 5-8.
�Z���i�K�ɂ�����lj��B�ȉ����Q�Ƃ̂��� W. R. Knorr�FArchimedes and the Measurement of the Circle,
Archive for History of Exact Science 15, p 115-140 (1970)
�A���L���f�X�̌��E���������\���̈���O�߂Ő��������菇�ނ��Ƃł���F
(15), (16) �̓���� (1, 1) �� (2, 1) �ŊJ�n���A�Q���� (12) ��K�p���邱�Ƃł���B
���̐����� Tannery �̘_�� 1 �ŗ^����ꂽ���̂ł���B
�_�� 2 �� Müller �͕����� �̉����Ə���邽�߂̈�ʑ��������A
����ɂ��A�A���L���f�X�� �̌��E�� 3 �X�e�b�v�ŋ��߂��B
Müller �̕��@�̌����́F
�� �� �� ������ �̏�E�������͉��E�ł���A
�� = (���� + D)/(�� + ��)
�͏�E�ł���B�� �����E�� �� ����E�ł���A�� �͏�E�ł���B
�_�� 3 �ŁAToepliz �͂��̋K���̓u���[�}�O�v�^�̓��� (14) �̒��ڂ̌��ʂł��邱�Ƃ��������B
�]���āATannery �̐����������ɂ���AMüller �̐����������ɂ���A
��Ƀu���[�}�O�v�^�̓��� (14) �ɖ߂邱�ƂƂȂ�B
�Q���� (12) �ɂ��A�e�X (16), (15) �����g (xm, ym), (sm, tn)
�Ɏ��邱�Ƃ������B
�ŏ��̐���� An�A���Ƃ̐���� Bn �Ƃ��悤�B
Toeplitz �����������Ƃ͈ȉ��̂��Ƃł���B
�������u���[�}�O�v�^�̓����� 2 �̑g Am �� An �ɓK�p�����ƁA
�g Am+n �������A������ Am �� Bn �ɓK�p�����ƁA�g Bm+n
��������B
����̈Ӗ����邱�Ƃ�
xm xn + Dym yn = xm+n
xm yn + ym xn = ym+n
xm sn + Dym tn = sm+n
xm tn + sm yn = tm+n
�����̌����ɂ��A�A���L���f�X�̑g
A6 = (1351, 780) �� B5 = (265, 153)
�����̂悤�ɂ��Ă��₭�v�Z�ł���悤�ɂȂ�F
A1 �� A1 ���� A2 ���v�Z�ł��A
A2 �� A2 ���� A4 ���v�Z�ł��A
A4 �� A2 ���� A6 ���v�Z�ł��A
A4 �� B1 ���� B5 ���v�Z�ł���B
���Ԃ̑g�͌v�Z���Ȃ��Ă悢�B
���āA�܂Ƃ߂邱�Ƃɂ��悤�B
�������u�Ñ�M���V���̊w�҂������A
���[�N���b�h�ݏ��@���V�X�e�}�e�B�b�N�Ɏg�p���āA
������̗L�����ߎ������߁A���ʂ� D �ɑ��ăy�����������������v�Ƃ���̂ł���A
-
�s�^�S���X�w�h���Ӑ��A�Ίp�����ɍs�������������R�𗝉��ł��A
-
�L�����l�̃e�I�h���X���A�����`�̕ӂ��ʖ�ł��Ȃ����Ƃ������̂ɁA
�ʐς� 3, 5, .. �̌X�̐����`��ʁX�ɏؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������R�𗝉��ł��A
-
���[�N���b�h�́A���Ƃŗ��p���Ȃ��ɂ�������炸�A���_�ɒʖ�s�\���̔������ X2 ���܂߂����R�𗝉��ł��A
-
�A���L���f�X���ǂ̂悤�ɂ��Ĕ�� w3�Fe �̋ߎ������̕��@�𗝉��ł���B
���̉������ؖ�����Ă��Ȃ����Ƃ͎����ł���A�������A����͊���̎����̐�����^���A
�����Ēm���Ă��鎖���ɂ���ĊԈႢ�ł���Ƃ��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B
���ꂪ�A�ǂ����݂��瓾���邷�ׂĂ̂��̂ł��낤�B
(�Ñ�) �C���h�ɂ�����y���������̉�@�𖾗Ăɂ��邽�߂ɂ��������݂�K�p�ł��邱�Ƃ�
���邱�ƂɂȂ�B
�A����
�y�����������������߂̃I�C���[�ƃ��O�����W���̕��@�� ��A�����W�J���邱�Ƃ�
�������B
�ŊJ�n���āA�ł������ 1 �������A�]�� r �� 1 ��菬�����Ȃ�悤�ɂ���B
���� 1/r ���v�Z���āA�Ăтł������ 1 �������A�ȂǂȂǁB
D = 3 �̏ꍇ�ɂ́A����B
| | | |
| - 1 | | |
| 1/( - 1) | = | ( + 1)/2 |
| ( + 1)/2 - 1 | = | ( - 1)/2 |
| 2/( - 1) | = | + 1 |
| | , | �Ȃ� |
���̕��@�́A����܂łɋc�_���Ă��� w = w3 �� e �ɓK�p�������@ (antanairesis) �Ɗ�{�I�ɓ����ł���B
���@�ɂ����� 1 ��̈����Z�͘A�����W�J�ɂ����� 1 ��̈����Z�ƑΉ����Ă���B
�W�J�̂���i�K�ŁA�]�� r �� 0 �Œu����������A�ߎ���������B
���������� �̘A�����W�J�ɂ����āA�ŏ��̋ߎ� 1 �͏��������A
���ߎ� 1 + 1/2 = 3/2 �͑傫������A�ȂǂȂǁB
�A������ߎ��́A�Ίp�����ƕӐ��̏��ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�������@���A��蕡�G�ȕ������ߎ�����ȒP�ȕ�������ɓ���邽�߂Ɏg�p���邱�Ƃ��ł���B
�M���V���l�����̂悤�ɂ����ł��낤�Ǝv����g�p�Ⴊ�����Ԃ��̂ł���B
��̎���Ƃ��āA�A���L���f�X�ɂ��~���̌v�Z���l���悤�B
�A���L���f�X�͉~�� (�̒���) �͊O�ڂ��鑽�p�` (�̕ӂ̒���) ��菬�����A
���ڂ��鑽�p�` (�̕ӂ̒���) �����傫���A�ƍŏ��ɏq�ׂĂ���B
�A���L���f�X�͊O�ڂ��鐳 96 �p�`�̎��͂̒������v�Z���A���̎��͂̒����Ɖ~�̒��a�̔䂪
���̐��������������Ƃ������Ă���B
���ɃA���L���f�X�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���F
�O�̐��͍ŏ��̐��� 3 + 1/7 �ȉ��ł���A���̂��߁A
�O�ڂ��� 96 �p�`�̎��͂̒����A���ɉ~���̒����́A���a�� 3 + 1/7 �{�����ȉ��ł���B
���ʂ� 22/7 �� 14688/(4673 + 1/2) �̘A�����W�J�ߎ��ł���B
���[�N���b�h�ݏ��@�ɂ��ȉ��̂悤�ɂ��ėe�ՂɌ��o�����Ƃ��ł���B
667 + 1/2 �� 1 �� 1 �� 0 �Œu�������āA�t�Ɍv�Z�����
���̌��E�l 3 + 10/71 �����l�ɂ��ē�����B�v�Z�̍Ō�̕������Č������
�X�ɂ����ƗL�v�Ȃ��̂́A�G���g�X�e�l�X�ɂ��v�Z�ł���B
�ނ́A�A���L���f�X�Ɠ�������̐l�ŁA���N���ł������B
�v�g���}�C�I�X�ɂ��� (�A���}�Q�X�g I, 12),
�G���g�X�e�l�X�͑��z�̐Ԉ܂̌��E�Ԃ̌ʂ����S�~�� 11/83 �ł���ƕ]�������B
����͉����~�̌X���� 23��51' 20'' �ł��邱�Ƃ��Ӗ�����B
�������ϑ��̒��ڂ̌��ʂł���ƐM���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�ǂ�ȓV���w�҂ł���A���z�̓쒆���̍����𑪒肷�邽�߂ɉ~�� 83 �������邱�ƂȂǂ���͂����Ȃ��B
�������Ȃ���A11/83 ���A�����ߎ��̌��ʂł��邱�Ƃ͑傢�ɂ��蓾�邱�Ƃł���B
�Ⴆ�A�G���g�X�e�l�X�� 1/4 �̉~�� 100 �������A���߂ɂ����鑾�z�̍��x���ł��������ƁA
�ł��Ⴂ���̈Ⴂ���A 53 ���̈Ⴂ�ł������Ƃ��Ă݂悤�B
1/4 �̉~�� 90�x�ɕ����āA�ʂ� 47 + 7/10 �x�ł������Ƃ����Ƒz�肵�Ă��悢�F���ʂ͓����ł���B
���āA���S�~�� 400 �� 53 ���r����ۂɁA�G���g�X�e�l�X�͌��@�����s������������Ȃ��B
4 �� 1 �� 1 �� 0 �Œu�������āA�t�����Ɍv�Z�����
���� 11/83 ���A�����ߎ��̌��ʂƂ��Đ����ł��邱�Ƃ́A(�J���t�H���j�A�B�A�T���f�B�G�S�s��) �f�j�X�E���[�����Y (Dennis Rawlins) ��
�w�E�ɂ����̂ł���B
�e�I�h���X�̏ؖ��Ɋւ���
�t�@���E�f���E���F���f���̖{�̒��ł� �u, , ... ���������ł��邱�Ɓv�̃e�I�h���X�������ł��낤�ؖ���^���Ă��܂���B
���X���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B
�v�Z���鐔�� m �������� (��1) �Ŋ����Ȃ��ꍇ�� (, 1) �Ɍ��@��K�p����悢�̂ł����A
�ʓ|�Ȃ̂ŘA�����W�J���܂��B �̓t�@���E�f���E���F���f���̖{�ɂ���̂� ����X�^�[�g���܂��B
| | = | 2 + ( - 2) |
| 1/( - 2) | = | + 2 |
�������� 1 �� 2 �x������ �ɂȂ�̂� 1 �X�e�b�v��Ɍ��@���z���邱�Ƃ��킩��܂��B
| | = | 2 + ( - 2) |
| 1/( - 2) | = | ( + 2)/(7 - 4) = ( + 2)/3 |
| | = | 1 + ( - 1)/3 |
| 3/( - 1) | = | 3( + 1)/(7 - 1) = ( + 1)/2 |
| | = | 1 + ( - 1)/2 |
| 2/( - 1) | = | 2( + 1)/(7 - 1) = ( + 1)/3 |
| | = | 1 + ( - 2)/3 |
| 3/( - 2) | = | 3( + 2)/(7 - 4) = + 2 |
4 �X�e�b�v��� �̌��@���z���邱�Ƃ��킩��܂��B
| | = | 3 + ( - 3) |
| 1/( - 3) | = | ( + 3)/(10 - 3) = + 3 |
1 �X�e�b�v��� �̌��@���z���邱�Ƃ��킩��܂��B
| | = | 3 + ( - 3) |
| 1/( - 3) | = | ( + 3)/(11 - 9) = ( + 3)/2 |
| | = | 3 + ( - 3)/2 |
| 2/( - 3) | = | 2( + 3)/(11 - 9) = + 3 |
2 �X�e�b�v��� �̌��@���z���邱�Ƃ��킩��܂��B
| | = | 3 + ( - 3) |
| 1/( - 3) | = | ( + 3)/(13 - 9) = ( + 3)/4 |
| | = | 1 + ( - 1)/4 |
| 4/( - 1) | = | 4( + 1)/(13 - 1) = ( + 1)/3 |
| | = | 1 + ( - 2)/3 |
| 3/( - 2) | = | 3( + 2)/(13 - 4) = ( + 2)/3 |
| | = | 1 + ( - 1)/3 |
| 3/( - 1) | = | 3( + 1)/(13 - 1) = ( + 1)/4 |
| | = | 1 + ( - 3)/4 |
| 4/( - 3) | = | 4( + 3)/(13 - 9) = + 3 |
5 �X�e�b�v��� �̌��@���z���邱�Ƃ��킩��܂��B
| | = | 3 + ( - 3) |
| 1/( - 3) | = | ( + 3)/(14 - 9) = ( + 3)/5 |
| | = | 1 + ( - 2)/5 |
| 5/( - 2) | = | 5( + 2)/(14 - 4) = ( + 2)/2 |
| | = | 2 + ( - 2)/2 |
| 2/( - 2) | = | 1 + ( - 3)/5 |
| 5/( - 3) | = | 5( + 3)/(14 - 9) = + 3 |
4 �X�e�b�v��� �̌��@���z���邱�Ƃ��킩��܂��B
| | = | 3 + ( - 3) |
| 1/( - 3) | = | ( + 3)/(15 - 9) = ( + 3)/6 |
| | = | 1 + ( - 3)/6 |
| 6/( - 3) | = | 6( + 3)/(15 - 9) = + 3 |
2 �X�e�b�v��� �̌��@���z���邱�Ƃ��킩��܂��B
| | = | 4 + ( - 4) |
| 1/( - 4) | = | ( + 4)/(17 - 16) = + 4 |
1 �X�e�b�v��� �̌��@���z���邱�Ƃ��킩��܂��B
| | = | 4 + ( - 4) |
| 1/( - 4) | = | ( + 4)/(19 - 16) = ( + 4)/3 |
| | = | 2 + ( - 2)/3 |
| 3/( - 2) | = | 3( + 2)/(19 - 4) = ( + 2)/5 |
| | = | 1 + ( - 3)/5 |
| 5/( - 3) | = | 5/( + 3)/(19 - 9) = ( + 3)/2 |
| | = | 3 + ( - 3)/2 |
| 2/( - 3) | = | 2( + 3)/(19 - 9) = ( + 3)/5 |
| | = | 1 + ( - 2)/5 |
| 5/( + 3) | = | 5( + 2)/(19 - 4) = ( + 2)/3 |
| | = | 2 + ( - 4)/3 |
| 3/( - 4) | = | 3( + 4)/(19 - 16) = + 4 |
6 �X�e�b�v��� �̌��@���z���邱�Ƃ��킩��܂��B
���������Ƀe�I�h���X���ȏ�̕��@�������̂ł���A �� 6 �X�e�b�v���K�v�Ȃ̂ŁA
5 �X�e�b�v���v�Z������Ŗʓ|�ɂȂ�A��߂Ă��܂����̂�������܂���B
�����̌v�Z�͕������̋L�����Ȃ��̂Ő�����ςł������Ǝv���܂��B
�����āA�e�I�h���X�͍u�`�����Ă���̂ł�����A�v�Z����ɂȂ�A
�ƂĂ����Â炭�Ȃ�͂��ŁA�����đ����Ȃ��������R�ɂ��Ȃ肻���ł��B
�Ȃ���̌v�Z�ł͕���̗L���������x������K�v������A����ɂ͓��R�����g�p�����B
�f�B�N�\���̖{����̖|��
�t�@���E�f���E���F���f���̖{�̒��ň��p���Ă����� L.E. Dickson �́u�����_�̗��j�v(History of the Theory of Numbers II)
�̊Y���ӏ���������x�ǂݒ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B p 341 ���� p 342 �̓��e�ł��B
�ȉ��Ƀf�B�N�\���̖{����̖|���t�������܂��B�ǂ߂킩��܂����A
�f�B�N�\���̖{�ł� �̋ߎ��ƃy���������̉�@�̊ϓ_����L�q���Ă��邾���ł��B
�t�@���E�f���E���F���f���̖{�ł́A���̉�@�ɂ͘A�����W�J���z���Ă��邱�Ƃ�m���Ă���K�v�����邱�Ƃ��w�E����A
�X�ɂ́A�������� ���������ł��邱�Ƃ����R�Ɍ��_�ł��邱�Ƃ��w�E����Ă���̂ł��B
�t�@���E�f���E���F���f���̓f�B�N�\���̋c�_�̓��t�������邱�Ƃɂ���āA
�s�^�S���X�w�h�� ���������ł��邱�Ƃ��������@�ɋC���������ƂɂȂ�܂��B
�f�B�N�\���̖{�ɂ͌�A�������āA�ꕔ�Ӗ����s���ƂȂ��Ă��܂����A�S�̂Ƃ��Ă�
�u�Ӑ��v�A�u�Ίp�����v�̐����ƂȂ��Ă���A�Q�������t�@���E�f���E���F���f���ƈ�v���Ă��܂��B
�� 12 �͂���̖̂|��
�I�C���[�ɗR�����鍬�����璷���ԃy���̖��O�̕t�������ɏd�v�ȕ����� x2 - D y2 = 1
�́u�t�F���}�[�������v�ƌĂԂׂ��ł���B
�C���h��I���O 400 �N�̃M���V���ɓo�ꂵ�� �̋ߎ� a/b �� a2 - 2 b2 = 1 �������̂�A
���̕������́A���̏��A�y���������̉�@�ŏ��Ԃɋߎ����邱�Ƃœ���ꂽ���̂ł���B
�Ⴆ�C���h�ł����Ƃ��Â� Sulva-sutras �̒��҂ł��� Baudhayana �� �̋ߎ��Ƃ��� 17/12 �� 577/408 ��
�^���Ă���B���ɒ��ӂ���B
17
12 | + | -1
2�E17�E12 | = | 577
408 |
, |
172 - 2�E122 = 1 |
, |
5772 - 2 �E4082 = 1 |
�v���N���X (AD 410 - 485) �̓s�^�S���X�w�h�����̍�}���������Ƃ��w�E���Ă���B
�Ίp���� BE �ł��鐳���`�̕� AB ���������āABC = AB, CD = BE �ƂȂ�悤�ɂ���B�����
AC2 + CD2 = 2 AB2 + 2 BD2
�������ACD2 = BE2 = 2 AB2�D�@�����
AD2 = 2 BD2 = FD2,�@�@FD = AD = 2 AB = EB
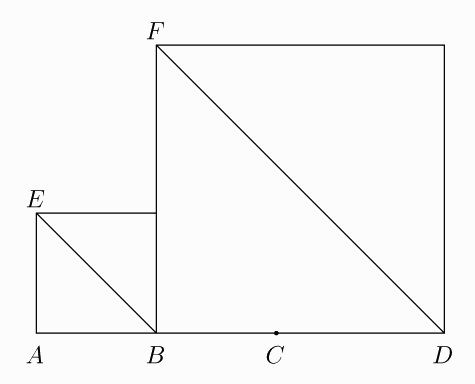
�܂� BD = AB + EB�D�� AB, BD,... �� s1, s2,... �Ίp�� BE, FD,... �� d1,
d2,... �Ə����B�����
sn+1 = sn + dn,�@�@�@dn+1 = 2 sn + dn
���āAs1 = 1 �ƒu���Ad1 = �𐮐��̋ߎ� ��1 �Œu�������A
�Q������ dn �� ��n �Œu�������āA�K�p�����
s2 = s1 + ��1 = 2,�@�@��2 = 2 s1 + ��1 = 3,
s3 = s2 + ��2 = 5,�@�@��3 = 2 s2 + ��2 = 7,..
����� ��n, sn �͕����� ��2 - 2 s2 = (-1)n �̉��ƂȂ�B
�X�~�����i�̃e�I�� (Theon of Smyrna) (���悻 AD 130) �� s, �� ��Ӑ��A�Ίp�����ƌĂсA
��L�̑Q�������w�I�ȉ��߂Ȃ��ɗ^���Ă���B
�A���L���f�X (���悻�A�I���O 3 ���I) �� �̋ߎ��Ƃ��� 265/153, 1351/780 ��^���Ă���A
����� x2 - 3 y2 = -2, x2 - 3 y2 = 1 �Ƃ̊֘A�Ő������邱�Ƃ��ł���B
�`�����邢�͒ʐ��Ɋւ���
�ʐ��ł� ���������ł��邱�Ƃ������̂̓��^�|���g���̃q�b�p�\�X�Ƃ���Ă��܂��B
��ɂ���ē��{��� Wikipedia �ɂ͂قƂ�NjL�ڂ��Ȃ��B�p��ł� Wikipedia �̈ꕔ�����p����B
�q�b�p�\�X�͎��X�A�������̑��݂������Ƃ���A
���̌��ʁA�_�̎�ɂ��C�ł��ڂꂽ�Ƃ����B
�s�^�S���X�w�h�͂��ׂĂ̐��������̔�ŕ\�킳���Ɛ����A
�������̔����͔ނ�ɃV���b�N��^�����ƌ����Ă���B
�������Ȃ���A�������q�b�p�\�X�Ɍ��т���؋��͍������Ă���B
�p�b�v�X (Pappus) �������Ă��邱�Ƃ́A�������̒m���̓s�^�S���X�w�h�ɋN��������A
�ŏ��ɔ閧��\�������k�����ڂ�Ď��Ƃ������Ƃ݂̂ł���B
�C�A���u���J�X (Iamblichus) �͈�A�̂��܂̍���Ȃ������Ă���B
��̘b�ł́A�s�^�S���X���k����������\�������ƂŒP�ɒǕ����ꂽ���Ƃ�
�������Ă��邪�A
���̒��ɐ��\��ʑ̂���}������@��\�������ƂŁA�C�ł��ڂꂽ�s�^�S���X���k
�̓`�������p���Ă���B
�ʂ̘b�ł͐��\��ʑ̂̍�}�@�𐢂ɒm�炵�߂āA
������������������̂悤�Ɍ����� (���̌���) �C�ł��ڂꂽ�̂̓q�b�p�\�X�ł���Ƃ��Ă���B
�������A�ʂ̘b�ł́A����������������\�I�����s�^�S���X���k�ɉ�����Ă���B
�C�A���u���J�X���͂�����q�ׂĂ��邱�Ƃ́A�C�ł��ڂꂽ�͕̂s�h�ȍs���ɂ���Ă���_�ł���B
�����̘b�͒ʏ�A�������傭���ɂ���āA�������̔������q�b�p�\�X�ɂ����̂�
����Ă���B�������A�ނ������������ǂ����s���ł���B
�����I�ɂ͘b�͌��т��邱�Ƃ��ł���B
�Ƃ����̂͐��\��ʑ̂̍�}������Ƃ��ɖ������̔��������邱�Ƃ��\�ł��邩��ł���B
���܊p�`�̉�����ɂ����Č��@�������ɑ������Ƃ���A
�������ł��邱�Ƃ��e�Ղɓǂݎ��邩��ł���B
�{�C���[�A�u���w�̗��j 1�v�Ap 101 �ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B
���^�|���g�� (�܂��̓N���g��) �̃q�b�p�\�X�́A�t�B�����I�X�Ƃقړ�����ŁA
���Ƃ��Ƃ̓s�^�S���X�w�h���������A�̂��ɋ��c����Ǖ����ꂽ�Ƃ�����B
����ł́A�s�^�S���X�w�h�̓q�b�p�\�X�������̂Ƃ��ĕ�����Ă���
�����Ă���B�ʂ̘b�ł́A����̔w�M�s�ׂ͑D�̓�j�ɂ�鎀�Ŕ�����ꂽ���Ƃ�
�Ȃ��Ă���B���̂悤�ȋ��c�Ƃ̌���̊m���ȗ��R�͂킩��Ȃ����A
��ɂ͋��c�̔閧��`�̂������������Ǝv����B�������A
���̎O�̉\����������Ă���B���̈�́A�q�b�p�\�X�͕ێ�I�ȃs�^�S���X�w�h
�̂�肩���ɔ��R���Ė���I�ȉ^���̐擪�ɗ��������߁A�����I�s���]�̂��ǂŒǕ����ꂽ�̂���
������B 2 �Ԗڂ́A���̒Ǖ����܊p�`���\��ʑ̂̊w -- ���̂ǂ��炩�̍�}�ł��낤 --
��\�I���������ł���Ƃ�����B 3 �Ԗڂ́A�s�^�S���X�w�h�̓N�w�ɂƂ��ĂƂ�ł��Ȃ��Ӗ���
�����w��̔��� -- �ʖ�s�\�ʂ̑��� -- ��\�I�������ߒǕ����ꂽ�̂��Ƃ�����ł���B
7. �Ñ�M���V���̐��w�͂ǂ̂悤�ɂ��Č���ɓ`������̂�
�Ñ�M���V���̐��w�̂��Ƃɂ͎��̃y�[�W���Q�l�ɂȂ�܂��B
- History Topics Index
- Index of Ancient Greek mathematics
- How do we know about Greek mathematics?
��ԍŏ����ڎ��ŁA�����u�Ñ�M���V���̐��w�v�Ɋւ��Ă̖ڎ��ŁA
�����u�Ñ�M���V���̐��w���ǂ̂悤�ɂ��Ēm�邱�Ƃ��ł���̂��v�Ƃ����\��̃y�[�W�ł��B
�����ł͎�ɂ��̃y�[�W����Љ�����Ǝv���܂��B
�A���A�ꕔ�M���ł��Ȃ�����������܂��B
����͌Ñ�M���V�����������ł����̂��Ƃ����_�ł��B���̃y�[�W�ł� BC 450 �N����܂ł�
�M���V���ɕ������Ȃ��u���`���̓`���v(oral tradition) �����Ȃ������Ƃ��Ă���܂��B������
�p��ł� Wikipedia
-
Greek alphabet - Wikipedia
-
�M���V�A���� - Wikipedia
�ɂ͋I���O 8 ���I���ɂ����ăM���V���������ł����Ƃ��Ă��܂��B
���{��� Wikipedia �ɂ��ގ��̋L�ڂ�����܂�����A�����M���ł������ł��B
�������A���̈Ⴂ�͖����ł��邩������܂���B���̗��R�͌Ñ�M���V���� 1 �̍��ł͂Ȃ��A
�s�s���Ƃ̘A���̂̂��߁A�s�s���Ƃ��ƂɎ������Ă����ƍl���邱�Ƃ��ł��邽�߂ł��B
�܂��������������ɂ���A�������L�q���邽�߂̔}�̂��L���g�p����Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��͂��ł��B
���āu�Ñ�M���V���̐��w���ǂ̂悤�ɂ��Ēm�邱�Ƃ��ł���̂��v��
�y�[�W�̓��e�ɖ߂�܂��B�Ñ�̃M���V���������L�ڂ��ꂽ���̂Ō��݂܂ŕۑ�
����Ă�����̂͂قƂ�ǂȂ��悤�ł��B�����I�ɓ���̔j�ЂɎc���ꂽ���̂Ȃǂ�
���邾���̂悤�ł��B
�����̓G�W�v�g�Ŏg�p���ꂽ�p�s���X�ɕ������L�ڂ��ꂽ�Ƃ��Ă���A
���[�N���b�h���_���A�p�s���X�̊����ɋL�q���ꂽ���Ƃ��z�肳���Ƃ��Ă��܂��B
���̏ꍇ 1 ���� 10 ���[�g�����x�̊����ƂȂ����悤�ł��B
�p�s���X�͂��낢���߉��x���ǂ߂����ɂ��������Ă��܂��܂��B
�܂��������Ȃ��Ă��A�p�s���X�̓G�W�v�g�̂悤�ɋɂ߂Ċ��������ꏊ�ȊO�ł���A
�ȒP�ɕ����Ă��܂��悤�ł��B
���̂��߁A����ł����珑���ʂ��K�v���o�Ă��܂��B
�㐢�ɂȂ�A�r�玆�ɏ����ʂ���Ďn�߂Ē����Ԃ̕ۑ��ɑς��邱�Ƃ�
�ł���悤�ɂȂ����悤�ł��B���̍��ɂ͊����ł͂Ȃ����݂̏��Ђ̌`�Ԃ��Ƃ��Ă��܂��B
�Ƃ��낪�r�玆�ɏ����ʂ���Ă��A
�Ñ�M���V���̐��w�ɂ͎��҂��Ă����̂ł�
�r�玆�͍����ł��������߁A�������L�ڂ���Ă���r�玆������āA
�ʂ̕������L�ڂ���邱�Ƃ��������悤�ł��B
������p�����v�Z�X�g (palimpsest) �ƌĂт܂��B
�p�����v�Z�X�g�ł́A�ŏ��ɏ����ꂽ�����͔��ǂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�A���L���f�X�̖{�ɂ̓p�����v�Z�X�g�Ƃ��Č��݂ɓ`����Ă�����̂����邻���ł��B
������ɂ���A�r�玆���o�ꂷ��܂ł͏��Ђ͎n�I�����ʂ��K�v������܂����B
���̂��߁A�]��ɑ����̖{��ۑ����邱�Ƃ�����ŁA�d�v�Ƃ��ꂽ�{�݂̂�
�㐢�ɓ`����ꂽ�̂ł��B
������s�^�S���X�w�h�����������͎̂c���Ă��Ȃ��̂ł��B
���������ł��邱�Ƃ̂��ȒP�ȏؖ����A
�f���q�����Ƃ��̈�Ӑ��Ŏ�����邩��ł���A����̓��[�N���b�h���_����
�ǂݎ��邩��ł��B
�܂��e��̌v�Z�@ (�Ƃ�킯�A�����W�J) �Ɋւ��Ă̋��ȏ����c���Ă��Ȃ��̂ł��B
�v�Z���@�Ȃǂ����Ђ̌`�Ŏc�����Ƃ͏d�v�ł͂Ȃ���������ł��B
�Œ���d�v�Ȃ��Ƃ�c��ȘJ�͂������ď����ʂ��������̂ł��B
�����Ƃ����ۂ̏����ʂ��͐g���̒Ⴂ�l���킸���Ȓ�����������Ă������Ƃ̂悤�ł��B