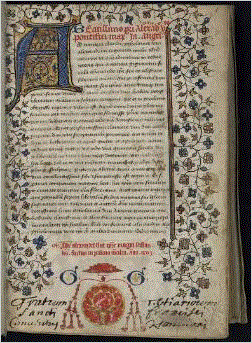
|
| 紀元 1411 年のプトレマイオスのゲオグラフィアの ヤコブス・アンジェルス (Jacobus Angelus) によるラテン語の翻訳。 Claus Swart による 27 枚の地図。 |
以下の文書は次の翻訳です。
Geography (Ptolemy) - Wikipedia
oikoumene (人が住んでいる場所) のカナ表記はオイコウメネとしました。(ecumene (エクメーネ) とも書いています。) インターネット上の発音はどういうわけだか、発音があまりはっきりしませんが、次が少しマシであったので これを参考にしました。 Oikoumene Meaning - Greek Lexicon | New Testament (NAS)
本文中で一部分グーグル翻訳を使用しています。(ラテン語などの文章をグーグルで英訳し、 これを手動で日本語に訳しています。直接、グーグル翻訳で日本語訳するよりははるかにましです。)
ゲオグラフィア (Georgraphy、古代ギリシャ語では εωγραφικὴ Ὑφήγησις, Geōgraphikḕ Hyphḗgēsis, 逐語訳 地理案内)) は、 ラテン語でゲオグラフィア (Geographia) 及びコスモグラフィア (Cosmographia) とも呼ばれ、 地名索引, 地図帳, 且つ 地図製作の論説で、 2 世紀ローマ帝国の地理知識を編集している。 元々、紀元 150 年頃の古代ギリシャ・アレクサンドリアの クラウディオス・プトレマイオス (Claudius Ptolemy) により書かれ、 この作品は現在は喪失した マリノス (Marinus of Tyre) による地図帳の改訂版で、 ローマとペルシャの地名索引を追加し、新しい原理を使用した。 9 世紀における アル=フワーリズミー (Al-Khwarism) による、 アラビア語への翻訳 (Kitab Surat al-Ard) は イスラム世界の地理的知識と地図作成の伝統にとても影響した。 イスラム世界の学者の作品 ―― 及び アルフラガヌス (Alfraganus) の改訂・もっと正確なデータを含む注釈 ―― と共に、 プトレマイオスの作品はその後、中世とルネッサンス・ヨーロッパに随分影響した。
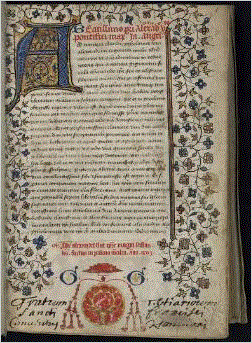
|
| 紀元 1411 年のプトレマイオスのゲオグラフィアの ヤコブス・アンジェルス (Jacobus Angelus) によるラテン語の翻訳。 Claus Swart による 27 枚の地図。 |
古代におけるプトレマイオスの作品のバージョンは、恐らく地図が付属した適切な地図帳であった。 もっとも学者によっては、テキストにおける地図参照は後の追加と信じている。
ゲオグラフィアのギリシャ語の写本で 13 世紀よりも前のものは、どれも現存していない。 しかしながら、後の多少、派生的著作物の断片的パピルス ―― 例えば 「著名な都市の表」 (Table of Noteworthy Cities) ―― は最も初期のもの (ライランズ図書館 ( Rylands Library) GP522, 3 世紀初期) と共に見つかっている。 東ローマ帝国の修道士のマクシモス・プラヌーデース ( Maximus Planudes) により書かれた手紙は、1295 年夏に、 コーラ修道院で 1 つを探したことを記録している; 最も初期の現存するテキストの 1 つは彼が当時収集したものの 1 つかもしれない。 ヨーロッパでは、プラヌーデースが強制的に仕向けられたように、 地図は時々テキストで提供される座標を使用して描き直された。 後の書記 (scribe) と出版社はこの新しい地図をコピーした。 これはアタナシオス (Anthanasius) が皇帝 アンドロニコス2世パレオロゴスのためにしたことと同様である。 地図がついた最も初期の 3 つの現存テキストは、プラヌーデースの 著作物に基づいた コンスタンティノープル ( イスタンブール) のものである。
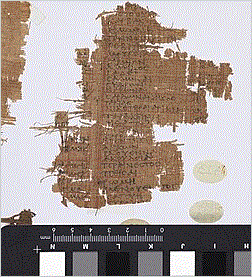
|
| プトレマイオスの「著名な都市の表」の 3 世紀のパピルスの断片 |
これらのテキストの最初のラテン語の翻訳は、イタリア, フィレンツェで、 Geograhia Claudii Ptolomaei の名の下にヤコブス・アンジェルス ( Jacobus Angelus) が 1406 年あるいは 1407 年に 実施した。 彼の版には地図がなかったと思われている。 もっともマヌエル・クリュソロラス ( Manuel Chrysoloras) は 1397 年にフィレンツェで、 パッラ・ストロッツィ ( Pala Strozzi) にプラヌーデースの地図のギリシャ語のコピーを与えた。
| 保存場所 収集番号 | 記号 (siglum) | 日付 | 地図 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| バチカン図書館, Vat.Gr.191 (f.128v-169v) | X | 12 - 13 世紀 | 現存せず | |
| コペンハーゲン大学図書館, Fragmentum Fabricianum Gracecum 23 | F | 13 世紀 | 断片, 元々世界と 26 地方 | |
| バチカン図書館, Urbinas Graecis 82 | U | 13 世紀 | 世界と 26 地方 |

|
| イスタンブール・サルタンの図書館, Seregliensis | K | 13 世紀 | 世界と 26 地方 (貧弱な保存) |
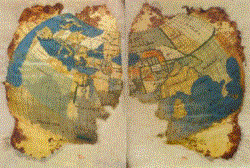
|
| バチカン図書館, Vat. Gr. 177 | V | 13 世紀 | 地図は現存せず | |
| ラウレンツィアーナ図書館 ( Laurentian Library), Plut 28.49 | O | 14 世紀 | 元々 世界,ヨーロッパ 1, アジア 2,アフリカ 1, 63 地方 (65 地図 現存) | |
| フランス国立図書館, Gr. Supp 119 | C | 14 世紀 | 地図は現存せず | |
| バチカン図書館, Vat. Gr. 178 | W | 14 世紀 | 地図は現存せず | |
| 大英図書館, Burney Gr. | T | 14 - 15 世紀 | フィレンツェ, Pluto 28.49 から得られた地図 | |
| ボドリアン図書館, 3376 (46) - Qu. Catal.i (ギリシャ), Cod. Seld. 41 | N | 15 世紀 | 地図は現存せず | |
| バチカン図書館, Gr. 388 | 15 世紀 | 世界と地方 63, 現存する地図無し | ||
| ラウレンツィアーナ図書館 (Laurentian Library), Pluto 28.9 (と関連する写本 28.38) | 15 世紀 | 現存する地図無し | ||
| 国立マルチャーナ図書館, Gr. 516 | R | 15 世紀 | 元々 世界地図と地方地図 26 (世界と 2 地図と 2 半地図が紛失) | |
| バチカン図書館, Pal. Gr. 314 | Z | 15 世紀 | 現存する地図無し、 クレタ島の Michael Apostoios により記述 | |
| 大英図書館, Harley MS 3686 | 15 世紀 |
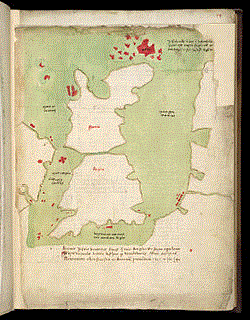
|
||
| ハンティントン図書館, Wilton Codex | 15 世紀 | 世界 1, ヨーロッパ 10, アフリカ 4, アジア 12, 上品に色付け, 光沢のある金で照明 |
バーグレン & ジョーンズ (Berggren & Jones, 2000 年) はこれらの写本を系統図に配置し、 これにより U, K, F と N は マクシモス・プラヌーデース ( Maximos Planudes, 1255 年 - 1305 年頃) の 活動に関連した。 UKFN の姉妹写本は R, V, W & C に伝達する。 しかし地図のコピーは欠陥があるか、まったくなかった。 これらが述べる「ゲオグラフィアのテキストにとり、最も重要なもの」は 写本 X (Vat. Gr. 191) である; 「というのは、これはビザンチン改訂 (Byzantine revision) によって影響を受けていない唯一のコピーだからである」。 ビザンチン改訂には例えばプラヌーデースの 13-14 世紀の修正があり、 恐らく地図の再構築に関連していた。
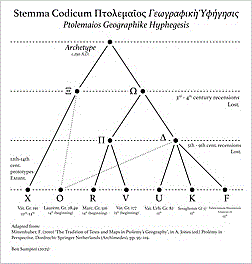
|
| ゲオグラフィアの写本系統図 (stemma codicum) |
地図に関して彼らが結論することは、 よしんば地図が古代に存在していたにせよ、 現存する地図が上の系統図の伝達で生き延びたことは、ありそうもない :
ミテンヒューバー (Mittenhuber, 2010 年) は更に系統図を、 失われた AD 150 年頃のオリジナルの 2 つの校訂本 (recension) に分割する : Ξ と Ω (3/4 世紀頃に喪失)。 校訂本 Ω は現存する写本の大半を含み、更に 2 つのグループに細分されれ : Δ と Π。 グループ Δ は 13 世紀末からの羊皮紙の写本を含み、これはゲオグラフィアの最も初期の 現存する写本を含み、 U, K & F である。 校訂本 Ξ は唯一の コデックス (codex, 冊子状の写本) X のみで代表される。 ミテンヒューバーはバーグレン & ジョーンズ (Berggren & Jones) に同意して、次のように述べている。 「いわゆるコデックス X はとりわけ重要である。というのは他の写本と違う多くの地方名と座標を含み、... これは単なる伝統エラーによっては説明できない」。 13 世紀末より前の写本は生き延びていないが、古代末の古代コデックスの存在の言及がある。 そのような実例の 1 つは カッシオドルスによる書簡にある (紀元 560 年頃)。
基本的に現存する写本の伝統と異なる古代の校訂本の存在は ステファヌス (Stephanus) による マルキアノス (Markianos) の要約に見ることができる。
シュトゥッケルベルガー & グラスホフ (Stückelberger & Grasshoff) による現存する写本 (13 世紀 - 14 世紀) の系統図 (stemma) 内に保有されている 伝統は、英国 (Βρεττανικήσ) の 「B」 のみで 「Π」 の校訂本ではない。
ゲオグラフィアは 3 節から構成され、8 巻に分割されている。 巻 1 は地図作成と地誌に関しての論説で、 プトレマイオスのデータの収集と配置に使用される方法を記述する。 巻 2 から巻 7 の最初まで、 地名索引が、古代ローマ人に既知の世界 (エクメーネ ( ecumene, 居住可能地域)) の 経度と緯度の値を提供する。 巻 7 の残りは世界地図の構成に使用される 3 つの射影に関しての詳細を提供する、 これは複雑さと忠実さに違いがある。 巻 8 は地方地図の地図帳を構成する。 地図には本の最初に与えられた値の少々の要約を含み、 これは地図の中身を明確にするための見出しとして使用し、 コピーの最中に精度を維持することが意図された。 巻 8 は「著名な都市の表」 (Table of Noteworthy Cities) の基礎をなしている。
科学的原理に基づいた地図は、ヨーロッパでは紀元前 3 世紀の エラトステネス (Eratosthenes) の時から作られていた。 プトレマイオスは 投影法の扱いを改良した。彼は、本の最初の節で彼の地図を作る方法を提供した。
プトレマイオスの本の地名索引の節は 本の中で、全ての場所と地理的造作に、緯度と経度を提供した。 緯度は赤道からの弧を度 (degree) で表示し、今日と同じシステムである。 但し、プトレマイオスは分 (minutes) ではなく、 1 度の端数 (fraction) を使用した。 彼の、経度 0 の 本初子午線は記録されている最西端の 至福者の島 (Fortunate Isles) を通り抜け、 カナリア諸島の エル・イエロ島の位置にあった。 地図は経度の 180° にわたり、大西洋の 至福者の島から中国に至った。
プトレマイオスはヨーロッパ人は地球のおよそ 1/4 しか知らないことに気が付いていた。
プトレマイオスの作品が含んでいたのは、単一の大きな、それほど詳しくない世界地図、及び 分離した、もっと詳細な地方地図である。 マクシモス・プラヌーデース ( Maximos Planudes) によるテキストの再発見以後、編集された最初のギリシャ語の写本は 64 個もの 地方地図を含んでいた。 西ヨーロッパの標準セットは 26 個あった ; 10 個のヨーロッパの地図、 4 個のアフリカの地図、 12 個のアジアの地図。 早くも 1420 年代に、これらの標準的地図は 追加のプトレマイオス地方地図 ―― 例えばスカンジナビアのもの ―― により補足された。
ゲオグラフィアは 8 巻にわたり、作品の主要部 (2 巻 - 7 巻) は 8000 ヵ所ほどの地名の一覧で、 紀元 2 世紀のオイコウメネ (Oikumene) を包含している。 巻 1 は散文で書かれ、プトレマイオスの説明で、 プロジェクト、彼の方法、そして情報源 (主に テュリオスのマリノス (Marinos of Tyre)) が解説されている。 巻 8 は巻 2-7 で作られた地図の各々に説明を提供し、 「著名な都市の表」の基礎になっている。 厳密な校訂版がシュトゥッケルベルガー (Stückelberger), ミテンヒューバー (Mittenhuber) と Klöti により出版された (2006 年)。
巻 1 はプトレマイオスによる理論的論説で、主題の問題とこれ以前の仕事を概説して、 彼の投影システムを使用した世界地図を描く読者への指示である。 節はプトレマイオスの表題を使用すれば :
西大西洋の外辺, ガウル (Gaul, 仏), 中央ヨーロッパ そしてイベリア半島。
| 章 | 地方 |
|---|---|
| 序 | |
| 1 | ブリタニア (Britannia): イベルニア (Hibernia) [アイルランド] |
| 2 | ブリタニア (Britannia): アルビオン (Albion) [グレート・ブリテン] |
| 3 | ヒスパニック・バイティカ (Hispanic Baetica) |
| 4 | ヒスパニック・タラコネンシス (Hispanic Tarraconensis) |
| 5 | ヒスパニック・ ルジターニア (Hispanic Lusitania) |
| 6 | アクィタニアン・ガウル (Aquitanian Gaul) |
| 7 | ルグドネンジャン・ガウル (Lugdunensian Gaul) |
| 8 | ベルジック・ガウル (Belgic Gaul) |
| 9 | ナルボネンジャン・ガウル (Narbonensian Gaul) |
| 10 | グレーター・ジャーメイニア (Greater Germania) |
| 11 | リーシア (Raetia) と ビンドレシー (Vindelica) |
| 12 | ノリカム (Noricum) |
| 13 | 上 パノニア (Upper Pannonia) |
| 14 | 下パノニア (Lower Pannonia) |
| 15 | イリリア (Illyria) あるいは リバニア (Liburnia) そして ダルメイシャ (Dalmatia) |
イタリア、ギリシャ、主な地中海の島。
| 章 | 地方 |
|---|---|
| 1 | イタリア (Italy) |
| 2 | コルシカ (Corsica) |
| 3 | サルデーニャ (Sardinia) |
| 4 | シチリア (Sicily) |
| 5 | Sarmatia [ Sarmatai の住んでいた場所, サルマート参照} |
| 6 | Tauric Peninsula [クリミア半島] |
| 7 | Iazyges Metanastae [ イアジゲス人 (Iazyges)参照] |
| 8 | ダキア (Dacia) |
| 9 | 上 モエシア (Upper Moesia) |
| 10 | 下モエシア (Lower Moesia) |
| 11 | トラキア (Thracia) と ペロポネソス半島 (Peloponnesian Peninsula) |
| 12 | マケドニア (Macedonia) |
| 13 | Epirus |
| 14 | アカエア (Achaia) |
| 15 | クレタ島 (Crete) |
モロッコからエジプトとエチオピアに至る北アフリカ
| 章 | 地方 |
|---|---|
| 1 | マウレタニア・ティンギタナ (Mauritania Tingitana) |
| 2 | マウレタニア・カエサリエンシス (Mauritania Caesariensis) |
| 3 | ヌミディア (Numidia) と本来のアフリカ (Africa proper) |
| 4 | Cyrenaica |
| 5 | 適切にリビアと呼べる Marmarica, エジプト全部 (上と下の両方) |
| 6 | リビア内部 (Libya Interior) |
| 7 | エジプトより下のエチオピア (Ethiopia below Egypt) |
| 8 | これより下のエチオピア内部 |
アナトリア (Anatoria), 小アジア (Asia Minor)、中東、近東、更にはキプロス島に及ぶ。
| 章 | 地方 |
|---|---|
| 1 | Bithynia and Pontus |
| 2 | Asia |
| 3 | リュキア (Lycia) |
| 4 | パンフィリア (Pamphylia) |
| 5 | Galatia |
| 6 | Cappadocia |
| 7 | キリキア (Cilicia) |
| 8 | Asiatic Sarmatia |
| 9 | コルキス (Colchis) |
| 10 | イベリア (Iberia) |
| 11 | アルバニア (Albania) |
| 12 | アルメニア (Greater Armenia) |
| 13 | キプロス (Cyprus) |
| 14 | シリア (Syria) |
| 15 | パレスチナ (Palestine) |
| 16 | アラビア・ペトラエア (Arabia Petraea) |
| 17 | メソポタミア (Mesopotamia) |
| 18 | Arabia Deserta |
| 19 | バビロニア (Babylonia) |
巻 6 では、プトレマイオスは近東、 コーカサスそして中央アジアをカバーする。
| 章 | 地方 |
|---|---|
| 1 | アッシリア (Assyria) |
| 2 | Media |
| 3 | スーサ (Susiane) |
| 4 | Persis |
| 5 | パルティア (Parthia) |
| 6 | Karmania |
| 7 | Eudaimon Arabia |
| 8 | Karmianien |
| 9 | Hyrkanien |
| 10 | Margiane |
| 11 | バクトリア (Bactriane) |
| 12 | ソグディアナ (Sogdianer) |
| 13 | パミール高原 (Saken) |
| 14 | スキシア (Skythia) |
| 15 | スキシア (Skythia) |
| 16 | 新疆ウイグル自治区 (Serike) |
| 17 | ヘラート (Areia) |
| 18 | ヒンドゥークシュ山脈 (Paropanisaden) |
| 19 | Drangiana |
| 20 | カンダハール (Archosien) |
| 21 | Gedrosien |
インド、中国、そしてスリランカ。
| 章 | 地方 |
|---|---|
| 1 | ガンジス川手前のインド (India before the Ganges) |
| 2 | ガンジス川以遠のインド (India beyond the Ganges) |
| 3 | インドシナ半島 (Land of Sinen) |
| 4 | タプロベイン (Taprobane, [スリランカのこと]) |
| 5 | オイコウメネの地図のまとめの表題 (Summary caption of the map of the oikoumene) |
| 6 | とりまく地球とオイコウメネの対応 (The mapping of a ringed globe with the oikoumene) |
| 7 | [オイコウメネを] 平らにしたものの表題 (Caption for the flattening [of the oikoumene]) |
これまでの節で作られた地図で、夏至・冬至の日の長さ等の詳細な説明。 地名辞典は「著名な都市の表」(Table of Noteworthy Cities) の基礎を形成したと思われている。
| 章 | 地方 |
|---|---|
| 1 | オイコウメネを地方地図に分割する基礎について (On the basis for dividing the oikoumene into the [regional] maps) |
| 2 | 各地図の表題に含めるのが適当なこと |
| 3 | ヨーロッパ地図 1 |
| 4 | ヨーロッパ地図 2 |
| 5 | ヨーロッパ地図 3 |
| 6 | ヨーロッパ地図 4 |
| 7 | ヨーロッパ地図 5 |
| 8 | ヨーロッパ地図 6 |
| 9 | ヨーロッパ地図 7 |
| 10 | ヨーロッパ地図 8 |
| 11 | ヨーロッパ地図 9 |
| 12 | ヨーロッパ地図 10 |
| 13 | アフリカ地図 1 |
| 14 | アフリカ地図 2 |
| 15 | アフリカ地図 3 |
| 16 | アフリカ地図 4 |
| 17 | アジア地図 1 |
| 18 | アジア地図 2 |
| 19 | アジア地図 3 |
| 20 | アジア地図 4 |
| 21 | アジア地図 5 |
| 22 | アジア地図 6 |
| 23 | アジア地図 7 |
| 24 | アジア地図 8 |
| 25 | アジア地図 9 |
| 26 | アジア地図 10 |
| 27 | アジア地図 11 |
| 28 | アジア地図 12 |
| 29 | オイコウメネの土地の住所録 (Directory of the lands of the oikoumene) |
| 30 | 個々の地図の縦横の一覧 |

|
|
プトレマイオスの世界地図、Serica, Sinae (Cattigara) が最右端に含まれ、 Taprobane (スリランカ) の島と Aurea Chersonesus (マレー半島) の向こうにある。 |

|

|

|
|
最初のヨーロッパ地図 Albion と Hibernia の島 |
2 番目のヨーロッパ地図 Hispania Terraconensis, Baetica と Lusitania |
3 番目のヨーロッパ地図 Gallia Lugdunensis, Narbonensis と Belgica |
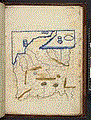
|
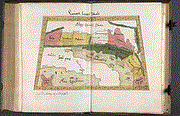
|

|
|
4 番目のヨーロッパ地図 Greater Germany と Cimbric Peninsula |
5 番目のヨーロッパ地図 Rhaetia, Vindelicia, Noricum, Pannonia, Illyria, Liburnia と Dalmatia |
6 番目のヨーロッパ地図 イタリアとコルシカ |
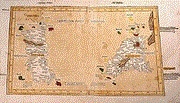
|

|
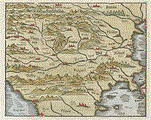
|
|
7 番目のヨーロッパ地図 サルジニア島, シチリア島 |
8 番目のヨーロッパ地図 ヨーロッパの Sarmatia |
9 番目のヨーロッパ地図 Darcia, Maesia と Thrace |
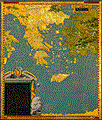
|
|
10 番目のヨーロッパ地図 Macedonia, Achaea, Peloponnesus, と Crete |
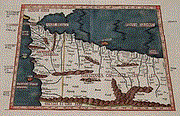
|

|
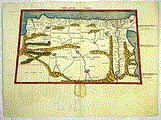
|
|
最初のアフリカ地図 Tangerine と Caesarian Mauritania |
2 番目のアフリカ地図 |
3 番目のアフリカ地図 Cyrenaica, Marmarica, Libya, Lower Egypt と Thebaid |
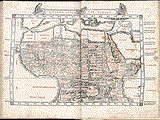
|
|
4 番目のアフリカ地図 北,西,東,及び中央アフリカ |
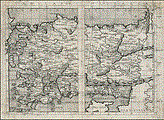
|
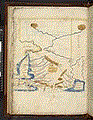
|

|
|
最初のアジア地図 Bithynia and Pontus、Asia、 Lucia, Pamphylia, Galatia, Cappadocia, Cilicia, Lesser Armenia |
2 番目のアジア地図 Asiatic Sarmatia |
3 番目のアジア地図 Colchis, Iberia, Albania, Greater Armenia |

|
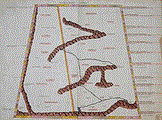
|
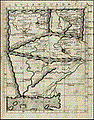
|
|
7 番目のアジア地図 Scythia within Imaus, Sogdiana, Bactriana, Margiana, and the Sacae |
8 番目のアジア地図 Imaus の向こうの Scythia と Serica |
9 番目のアジア地図 Ariana, Drangiana, Gedrosia, Arachosia, and Paropanisus |
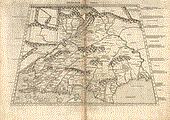
|
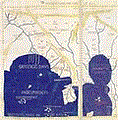
|
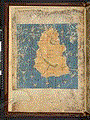
|
|
10 番目のアジア地図 Ganges 内のインド |
11 番目のアジア地図 ガンジス川以遠のインド、 Golden Chersonese, Magnus Sinus, and the Sinae |
12 番目のアジア地図 Taprobana |
プトレマイオスのゲオグラフィアの基礎をなした マリノス (Marinus of Tyre) による 元々の論説は完全に失われている。 プトレマイオスに基づく世界地図はローマ時代末にアウグストドゥヌム (Augustodunum) (フランスの オータン) に 展示されていた。 パップスは 4 世紀にアレクサンドリアで執筆し、プトレマイオスのゲオグラフィアの注釈を作り、 彼の (現在は失われた) 「エクメーネの地勢図」 ("Chorography of the Ecumene") の基礎として使用した。 しかしながら、後の帝国の執筆家と数学者はプトレマイオスのテキストの改良をせずに、 その論評に限定しているように思われる。 現存する記録は、実際には実位置への忠実性を減少させているように見えるのにも かかわらず、ビザンチンの学者は中世を通じて、この地理学的伝統を継続した。
一方、それ以前のギリシャ・ローマ (Greco-Roman) の地理学者、例えば ストラボンと 大プリニウスは、 インド洋の遠隔地に定期的に往復する船乗りと商人の当時の説明に 依存することに乗り気ではないことを示していた。 マリノスとプトレマイオスは彼らから受け取る情報を組み込むことに、より大きな受容力を示した。 例えば、グラント・パーカー (Grant Parker) が議論するように、船乗りたちの説明なしに、 ベンガル湾 (Bay of Bengal) を正確に作図することは可能性が極めて低い。 Golden Chersonese (ie. マレー半島) とマグナス・サイナス (Magnus Sinus (ie. タイ湾と南シナ海 (Gulf of Thailand と South China Sea)) の説明になると、 マリノスとプトレマイオスはアレクサンドロス (Alexandros) と呼ばれるギリシャの船乗りの証言に頼り、 彼は 「カッチガラ」("Cattigara") と呼ばれる最も東の場所を訪れたと主張した。 (カッチガラ (Cattigara) はベトナムのオケオ (Oc Eo) である可能性が高く、ここで アントニヌス時代 (Antonine-era) のローマの物資が 発掘された。また北ベトナムの 交趾郡 (Jiaoshi) の地域から遠くなく、ここは 古代中国の情報から、 幾つかのローマの大使館が 2 世紀と 3 世紀に始めて設置されていた。)
イスラム人の地図製作者は 9 世紀まで、プトレマイオスのアルマゲストと
ゲオグラフィアのコピーを使用していた。
9 世紀に、
カリフの
マアムーンの宮廷で、
アル=フワーリズミーは彼の 「地球描写の本」 (Book of the Depiction of the Earth (Kitab Surat al-Ard)) を
編集した。これはゲオグラフィアの真似をして、
ナイル川、Island of Jewel, Sea of Darkness そして
アゾフ海の
地方地図を提供した。
これらの 1037 年のコピーはイスラム世界の土地の最も初期の現存する地図である。
テキストが明確に述べることは
アル=フワーリズミーがより初期の
地図で取り組んだことであるが、プトレマイオスの正確なコピーではなかった :
彼の
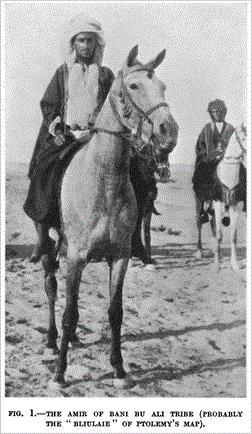
|
|
Amir of Bani Bu Ali tribe, プトレマイオスの地図の Bliulaie と思われる。 |
プトレマイオスによる数多くの場所と座標の地名索引から編集を始めたのにもかかわらず、 イスラム世界の学者は現存するプトレマイオスの地図におけるプトレマイオスの原理を ほとんど使用しなかった。 その代わりに、彼らはアル=フワーリズミーの修正と Suhrāb の 10 世紀始めの 「7 つの気象地方の驚異から居住地の果て」 (Marvels of the Seven Climes to the End of Habitation) の論説により主張された 直交射影に従った。 中世から生き延びた地図は数学的原理に基づいていない。 11 世界地図の 「好奇心の本」 (Book of Curiosities) の世界地図は、 地理座標を含むイスラム世界あるいはキリスト教世界も最も初期の現存する地図である。 しかし、コピーした人はその目的を全く理解しておらず、 意図されたスケールの 2 倍を使用して、左から始め、 次に (間違いに気が付いたらしく) 途中であきらめている。 この存在が強く示唆することは、 プトレマイオス、 アル=フワーリズミーや Suhrāb の方法を数学的に派生する今では失われた、 より初期の地図の存在である。 そのような地図が存在していたことの現存する報告がある。
プトレマイオスのゲオグラフィアは 12 世紀のシチリアの ルッジェーロ2世の 宮廷でアラビア語からラテン語に翻訳された。 しかしながら、この翻訳のコピーは生き延びていない。
ゲオグラフィアのギリシャ語のテキストが 1400 年頃に コンスタンティノープルからフィレンツェに到着し、 1406 年頃にスカルペリア (Scarperia) のヤコブス・アンジェルス ( Jacobus Angelus) によりラテン語に翻訳された。 ラテン語ヨーロッパでのゲオグラフィアの受け入れは多様であった。 15 世紀の前半には、フィレンツェの古典研究者 (humanist) はこれを文献学の資源として利用し、 古代テキストの地理を理解した。 ベニスの地図製作者はプトレマイオスの地図を ポルトラノ海図と中世の マッパエムンディ (mappaemundi) で調整しようとし、 占星術に興味を持ったフランスとドイツの学者はプトレマイオスの 宇宙誌的概念に焦点を合わせた。 15 世紀後半にゲオグラフィアの名声が拡大し、地理空間の熟考に必要な枠組みとなった。
地図の付いた最初の印刷版は、1477 年に ボローニャで出版され、彫刻印刷の挿絵のある最初の印刷本でもあった。 多くの版が続き (初期には木版を使用)、あるものは地図の伝統版に従い、別のものはこれを更新した。 1482 年に ウルムで出版された版はアルプスの北で印刷された最初のものであった。 これは商的に成功となり、1486 年に再版された。 1482 年にはまた、フランチェスコ・ベルリンギェリ ( Francesco Berlinghieri) は自国語のイタリア語版をはじめて印刷した。 1513 年に ストラスブールで出版された版は、ゲオグラフィアの現代化の重要な段階であった。 これはできる限りオリジナルに忠実なプトレマイオスのテキストと地図の集積を維持し、 一方で、別の 20 個のもっと精密で最新的現代地図を提供した。 ギリシャ語原典のもっと改良したラテン語訳は 1525 年のストラスブール版のために、 ヴィリバルト・ピルクハイマー ( Willibald Pirckheimer) により作られ、最初のギリシャ語そのままの印刷版は 1533 年に バーゼルの ロッテルダムのエラスムスにより著された。
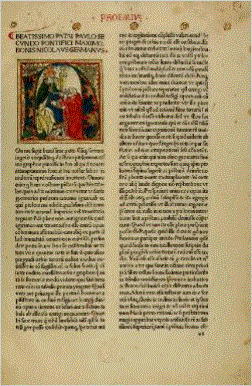
|
| 1482 年に ウルム (Ulm) で印刷された版 |
プトレマイオスは 至福者の島 ( Fortunatae Insulae、 カーボベルデあるいは カナリア諸島) から、 東方のマグナス・サイナス (Magnus Sinus) の東海岸に至る全世界の地図を作った。 世界のこの既知の部分は 180° 以内から成っていた。 プトレマイオスが最も東の端に設定したのは、 Serica (絹の土地)、Sinarum Situs (Sinae の港) とカッチガラの市場である。 ヘンリックス・マルテルス (Henricus Martellus) による 1489 年の世界地図では、アジアは岬 ―― カッチガラ岬 ―― の南東の点で終了していた。 プトレマイオスが理解していたことは、カッチガラは サイナス・マグナス (Sinus Magnus) あるいは Great Gulf (実際はタイ (Thailand) の湾) の港で、赤道の北 8.5°、カンボジアの海岸にあり、 ここが彼が 「有名都市の一覧」 (Canon of Famous Cities) の中で、カッチガラを設定した場所である。 ここは、ギリシャ・ローマ (Graeco-Roman) 世界から、極東の土地に船舶トレードで到達した最も 東端の港である。 プトレマイオスの、後年の良く知られたゲオグラフィアで、 書記の間違いからカッチガラは赤道の南 8.5° にあることになった。 プトレマイオスの複数の地図で、例えばマルテルスの地図で、 カッチガラは Mare Indicum (インド洋) の最も東端の岸にあって、 サン・ヴィセンテ岬の東 180° で、書記の間違いから赤道の南 8.5° にある。
カッチガラは マルティン・ヴァルトゼーミュラー (Martin Waldseemüller) の 1507 年の世界地図のこの場所にも 表示され、これはプトレマイオスの伝統に公然と従っている。 プトレマイオスの情報は従って、間違って理解され、 中国の海岸は東アジアの海岸の一部分として表示すべきであったのに、間違えてインド洋の東海岸を 表示することになった。 その結果、プトレマイオスは 180 番目の子午線の東にもっと多くの土地と、その向こうに外洋を暗示した。 マルコポーロの東アジアへの旅行の説明は、大地と東の外洋の港を記述し、 これは明らかにプトレマイオスに知られていなかった。 マルコポーロの物語は マルティン・ベハイムの 1492 年の地球儀の上に示されるプトレマイオスの地図に 広大な追加の根拠を与えた。 プトレマイオスがアジアの東海岸を描かなかった事実により、べハイムがこの大陸をずっと東に 拡張することを可能にした。 べハイムの地球儀はマルコポーロの Mangi と Cathay をプトレマイオスの 180 番目の子午線の東に置き、 クビライ (Great Khan) の首都のカンバルク (Cambaluc, 北京) を 41 番目の緯線上、およそ東経 233 度に置いた。 べハイムは、プトレマイオスの 180度 を越えて、アジア本土を 60度拡張し、 更に チパング (Cipangu, 日本) の東海岸までもう 30 度を拡張した。 チパング (Cipangu) とアジア本土は、従ってカナリア諸島の西に、それぞれ、たった 90 度と 120 度になった。
Codex Seragliensis は 2006 年に業績の新版の基礎として使用された。 この新版を使用して、多分野にまたがる ベルリン工科大学チームが、 プトレマイオスの巻 2 と 3 の座標を解読し、 2010 年と 2012 年に出版に供した。
クリストファー・コロンブスはこの地理を更に修正した : 1度の長さとして、プトレマイオスのより長い長さの代わりに、 53 2/3 イタリア海里を使用し、 マグナス・サイナス (Magnus Sinus) の東海岸に マリノス (Marinus of Tyre) の 225度の経度を使用した。 これにより、 マルティン・ベハイムとコロンブスの同時代の人達によって、 与えられた経度が東へ随分前進することになった。 何らかの過程で、コロンブスが判断したことは、東アジアと チパングの経度はそれぞれ、 東に 270度 と 300度、あるいはカナリア諸島の西 90度 と 60度であることであった。 彼は 1492 年にキューバを見つけた時に、カナリア諸島から 1100リーグを帆走したと言った。 これは彼が東アジアの海岸を見つけると思ったおよその場所であった。 計算の基礎で彼は イスパニョーラ島を チパングと同一視し、 カナリア諸島から外側に向かっておよそ 700 リーグの距離で見つけることを予期していた。 彼の後の航海で、キューバを更に探検し、南米と中米の発見になった。 最初は南米 ―― Mundus Navus (New World, 新世界) ―― は 大陸サイズの大きな島と考えられた; しかし 4 回目の航海の結果、これは明らかに 偉大な「上インド半島」 (「上インド」) (Upper India peninsula (India Superior)) ―― べハイムでは「カッチガラ岬」と表示 ―― と同一視された。 これがバーソロミュー・コロンブス (Barthoolomew Columbus, クリストファーの兄弟) の忠告で、 1506 年頃にアレッサンドロ・ゾルディ (Alessandro Zordi) により作られたスケッチ地図の最善の解釈と思われ、 ここに記入されていることは、 古代の地理学者 マリノスとクリストファー・コロンブスによれば、 ポルトガルの海岸の サン・ヴィセンテ岬から「上インド」 (India Superior) の半島のカッチガラまでの距離は 225度で、 一方、プトレマイオスによると、同じ距離は 180度であった。
16 世紀以前に、 オスマン帝国の地理学の知識は範囲が限られており、 プトレマイオスに取って代わった初期のイスラム世界の学者の業績に ほとんどアクセスできなかった。 プトレマイオスのゲオグラフィアは メフメト 2 世の下に、 アラビア語に再び、翻訳・更新された。 メフメト 2 世は 1465 年にはビザンチン (Byzantine) の学者である George Amiroutze に仕事を依頼し、 1481 年にはフィレンツェの古典研究者 (humanist) のフランシス・ベルリンギエーリ (Frances Berlinghieri) に依頼した。
2 つの関連するエラーがある。
これが示唆することは、プトレマイオスは地球の円周に 180,000 スタジオンの数値 ―― これを彼は一般的なコンセンサスと述べている ―― に適合するように、 経度データのスケールを変更したことである。 プトレマイオスは実験的に得られたデータのスケールを変更して、地理学、占星術、音楽、そして光学で 使用した。

|

|

|
|
Codex Seragliensis GI 57, fol. 33v |
Zamoyski Codex の スカンジナビア (1467 年頃) |
1535年の印刷版の表題頁 |

|
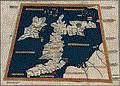
|
| 19 世紀のラテン語版 (3 巻) |
最初のヨーロッパ地図 (Prima Europe tabula) グレート・ブリテン島とアイルランド のプトレマイオスの 2 世紀の地図 の現存する最古のコピーの 1 つ。 第 2 版, 1482 年 |
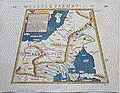
|
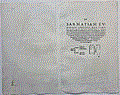
|
|
ゼバスティアン・ミュンスター
(Sebastian Munster),
Sarmatia 地図 (Tabula Sarmatiae), 1571 年 |
ゼバスティアン・ミュンスター
(Sebastian Munster),
Sarmatia 地図 (Tabula Sarmatiae), 1571 年 (裏側) |