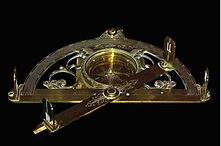
|

|
| バターフィールドのコンパス・グラフォメーター |
ドイツのグラフォメーター、ゲッチンゲン、
都市博物館 (Stadtmuseum)、 装置は横向き 後方にヤコブ・スタッフを付けるソケット |
以下の文書は次の翻訳です。(一部)
Graphometer - Wikipedia (グラフォメーター)
このページを翻訳しようとして困ったのは英和辞書には「graphometer」が載っていないことでした。 以下を読めばわかりますが「graphometer」はフランス語の「graphomètre」の英語表記です。 手許にある古い日仏辞典には「graphomètre 」の意味として「測角器」としていますが、 大半の測量の機械は角度を測定するものですから、この訳語は適切ではありません。 そこでカナ表記をすることにしました。
江戸時代にはグラフォメーターは「半円方位盤」の名称で知られていたようです。次のページに写真が載っています。
測量装置の比較に関しては円周儀の訳注をご覧ください。
グラフォメーター (graphmeter, semicircle or semicircumferentor) は測量機器で、角度の測定に使用される。これは 180° に分割された半円の縁から構成され、 時には (角度の) 分に細分されている。 両端に 2 つの照準がある直径が、半円に向かっている。 直径の中間には「箱と針」 (コンパス) が固定されている。 同じ中間に、他の 2 つの照準が付いたアリダードが固定されている。 装置は玉継手 (ball and socket joint) を経由してスタッフ (staff) の上に 搭載されている。 実際には、装置は円周儀の半分である。 利便性のために、時々半円周の縁の別の線に 180° から 360° の目盛りが付けられていることもある。
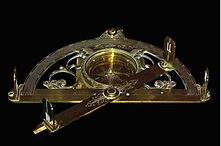
|

|
| バターフィールドのコンパス・グラフォメーター |
ドイツのグラフォメーター、ゲッチンゲン、
都市博物館 (Stadtmuseum)、 装置は横向き 後方にヤコブ・スタッフを付けるソケット |
この形態はフィリップ・ダンフリー ( Philippe Danfrie) の 「グラフォメーターの使用の宣言 (パリ, 1597 年)」 (Déclaration de l’usage du graphomètre, Paris, 1597) で導入され、 グラフォメーターの用語はフランス人の測地学者で人気があった。 望ましい英語の用語は 「半円」(semicircle) あるいは 「半円周儀」 (semicircumferentor) であった。 19 世紀のグラフォメーターには開放照準 (open sights) ではなく、望遠鏡照準が付いていた。
1709 年に出版された ル・ノートルの「庭造りの理論と実践」 (La theorie et la pratique du jardinage) は 幾何学的地形を庭の図面から大スケールの地形の上に移動することで、 グラフォメーターの使用を説明している。
角度、例えば EKG、を測定するために、直径の中点 C を、 機器の点 C でおもり (plummet) を使用して、角の頂点 (angle apex) K に置く。 直径は、直径の両端にある照準を使用して、角の辺 KE と揃える。 別の照準の組を使用して、アリダードを辺 KG と揃え、 アリダードが示す縁から角度を読み取る。 グラフォメーターの更なる使用は、円周儀のものと同じである

|

|
| 19 世紀のグラフォメーター | 図 1: 角 EKG |