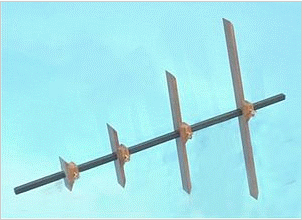
|
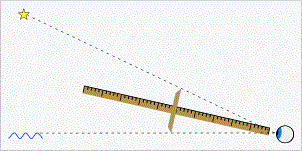
|
|
フィレンツェ、
ガリレオ博物館 (Museo Galile) のヤコブスタッフ |
ヤコブスタッフで星の高度を測定 |
以下は次の翻訳です。
Jacob's staff - Wikipedia (ヤコブの棒)
ウェブスター (英々辞書) から判断すると、 スタッフ (staff) の本来の意味は「棒」、これが時には「杖」の意味 になる。そこで、Jacob's staff を「ヤコブの棒」とすると、原文とかけ離れた印象に なりそうなので、ここでは「ヤコブスタッフ」とカナ表記することにしました。
ヤコブスタッフ (Jacob's staff, ヤコブの棒) は測定の道具で、幾つかの変動がある。 他の呼び方に : クロススタッフ (cross staff, 十字棒)、 バラステラ (ballastella)、 フォアスタッフ (fore-staff, 前方棒)、 バレステラ (ballestella)、あるいは バレスティラ (balestilla) がある。 最も基本的な形では、ヤコブスタッフは棒 (stick) あるいは長い棒 (pole) で 長さの印が付き、より短い棒が垂直に付属している ヤコブスタッフの最も単純な使用は、スタッフの使用者に相対的にオブジェクトの高さと角度の定量的判断を 与えることである。
大半のスタッフ (staff) は、 これよりも、もっとずっと複雑で、通常、幾つかの測定と安定化の造作を含んでいる。 2 つの最も頻繁に使用されることは:
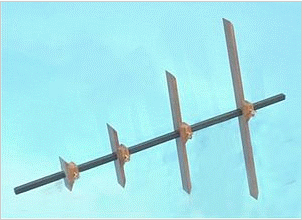
|
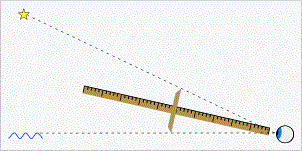
|
|
フィレンツェ、
ガリレオ博物館 (Museo Galile) のヤコブスタッフ |
ヤコブスタッフで星の高度を測定 |
装置の名称の起源は確かでない。 ある人は聖書の長老のヤコブ (Jacob) を言及する ―― 特に創世記 (Book of Genesis) (Gen 32:11)。 これはオリオン座 (Orion) ―― 中世の星図でヤコブ (Jacob) の名前で呼ばれている ―― の類似から名称をつけたかもしれない。 別の可能性のある起源は「巡礼のスタッフ」 (Pilgrim's staff) ―― セント・ジェームス (St. James、ラテン語で Jacobus) ―― である。 クロススタッフ (cross staff) の名称は単に、十字型の形から来ている。
ナビゲーションでは、装置はクロススタッフ (cross-staff) とも呼ばれ、 角度を決定するのに使用された。 例えば、 船の緯度を決定するための水平線と北極星あるいは太陽との角度; オブジェクトの高さがわかっている時に、そこまでの距離を決定するために、オブジェクトの頂上と基底部の間の角度; あるいは、地図上での位置決定のために、2 つの視認できる場所の間の水平の角度; の決定である。
ヤコブスタッフが、天体観測に使用される時には、 天文半径 (ラディウス・アストロノミコス, radius astronomicus) とも言及される。 近世におけるクロススタッフの凋落と共に、ヤコブスタッフの名称は主に 測量技術者の装置の支えを提供する道具に適用される。
元々のヤコブスタッフは 14 世紀に単一の棒の装置として開発され、 天文学の測量に使用された。 これは プロヴァンスのフランス系ユダヤ人数学者の レヴィ・ベン・ゲルション (Levi ben Gerson) により、彼の 「神の戦争の本」 ("Book of Wars of the Lord"、 ラテン語、更にはヘブライ語に翻訳) に始めて記述された。 彼が、この棒に使用したヘブライ語の名称は 「深淵を明らかにするもの」 ("Revealer of Profundities") と翻訳され、 一方「ヤコブスタッフ」の名称は同時代のキリスト教徒により使用された。 その発明は仲間のフランス系ユダヤ人天文学者の ヤコブ・ベン・マキル (Jacob ben Makir) によっている可能性があり、 彼も同じ時期にプロヴァンスに住んでいた。 15 世紀のオーストリアの天文学者の ゲオルク・プールバッハ (Georg Purbach) に (この発明が) 帰属することはあり得そうもない、 というのはプールバッハは 1423 年まで生まれていないからである。(このような帰属は同じ名前を持つ 異なる装置を言及している可能性がある。) その起源は紀元前 400 年頃の カルデア人にたどれるかもしれない。
ベン・ゲルション (ben Gerson) が始めてヤコブスタッフを記述していることはすっかり認められているが、英国の 中国研究家である ジョゼフ・ニーダム (Joseph Needham) は 宋王朝中国の科学者である 沈括 (Shen Kuo, 1031 年 - 1095 年) は 1088 年の 彼の 夢渓筆談 (Dream Pool Essays) でヤコブスタッフを記述していると理論を立てている。 沈括は古物収集家で、古代の物に興味を持っていた; 彼は 江蘇省の家の庭から古代のクロスボーのような装置を発掘したあとで、 これに目盛り付きのスケールを持つ照準があり、これで遠方の山の高さを測定すること に使用できることに気が付き、 数学者が直角三角形を使用して、高さを測定する方法にたとえた。 彼が書いていることは、これで山全体を眺めると、 装置の距離が長くなり、山の一部分を眺めると距離が短かくなる。 これは、横木を目から遠ざけなければならないからで、 一方で距離は反対の端から始まっているからである。 ニーダムはこの観察の実際の応用を何も言及していない。
中世ヨーロッパのルネッサンスの最中にオランダの数学者で、測量技師の アドリアーン・メチウスは 彼自身のヤコブスタッフを開発した。 ゲンマ・フリシウスはこの装置に改良を加えた。 15 世紀のドイツの数学者のヨハネス・ミューラー (Johannes Müller) ( レギオモンタヌスと呼ばれる) は測地学と天文学の測量で この装置の人気をあげた。
クロススタッフ (cross-staff) の元々の形ではポール (pole、棒) あるいは主要スタッフ (main staff) には 全長に目盛りが付いていた。 横木 (cross-piece、下の絵の BC) は、 トランソム (transom)、あるいはトランスバーサル (transversal) とも呼ばれ、 主要スタッフ (main staff) を上下にスライドする。 古い装置では、横木の端は切り落とされていた。 新しい装置では末端に真鍮の備品があり、観測用に真鍮に穴が開いていた。 (海洋考古学では、このような備品が、しばしば残存するクロススタッフの唯一の部分である。)
幾つかの横木を提供するのが普通で、各々が異なる範囲の角度を観測し、 横木 3 本が普通であった。 後の装置では、別々の横木よりは 終端を示すクギ (peg) が付いた唯一の横木に切り替えられた。 これらのクギ (peg) は横木の両側に対称的に配置された幾つかの対の穴の 1 対に搭載された。 これは少ない部品で同じ機能を提供した。 フリシウス (Frisius) の横木のバージョンでは、終端に横木の上でスライドする視準板 (vane) があった。
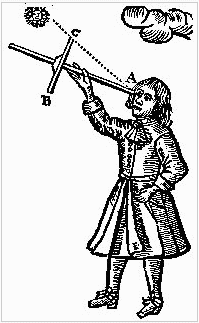
|
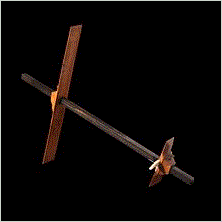
|
|
ヤコブスタッフ、ジョン・セラー
(John Seller) の「実用的航海術」(1672) から |
1776 年の海洋クロススタッフ、パリの国立海洋
博物館 (Musée national de la Marine) に展示 |
使用者は主要スタッフ (main staff) の一方の端を目のすぐ下の頬にあてる。 横木の下の部分の端を (あるいは真鍮の備品の穴を通して) 水平線に照準を合わせる [B]。 主要スタッフの横木を調節して、 横木の他の端に太陽をあわせて [C]、 主要スタッフにおける横木の位置の目盛りから高度を決定できる。 この値は、表を調べて角度に変換した。
元々のバージョンは 大航海時代までは海で使用されたとは報告されていない。 この使用が報告されたのはジョアン・ド・リズボン ( João de Lisboa) による彼の 1514 年の「海の針の論説」 (Treatise on the Nautical Needle) である。 ヨハネス・ヴェルナーは 1514 年にクロススタッフを海で使用することを提案し、 改良された装置がナビゲーションの使用に導入された。 ジョン・ディーは 1550 年代に、これをイングランドに導入した。 改良されたバージョンでは、棒は直接角度で目盛りを付けられた。 この装置の変種は正確にはヤコブスタッフ (Jacob's staff) と呼ばずに、単にクロススタッフ (cross-staff) と呼ばれる。
クロススタッフは使用が困難であった。 一貫した結果を得るために、観測者は棒の端を正確に頬にあてないといけなかった。 観測者は 2 つの方向にある水平線と星を観測する必要があり、 装置を動かさずに一方から他方に視線を動かす。 付け加えると、太陽の観測では、観測者は直接太陽を見る必要があった。 これは不愉快なことであり、太陽の正確な高度を求めることが困難であった。 船乗りは、横木の末端にスモークガラス (smoked-glass) を搭載して、太陽のぎらつきを軽減した。
ナビゲーション用の道具として、 この装置はまもなく代替され、 最初はバックスタッフや四分儀になり、 いずれも太陽を直接見つめる必要がなく、 次に八分儀と六分儀になった。 恐らく バックスタッフに影響されて、ナビゲーターによってはクロススタッフを変更して、 バックスタッフのように操作した。 視準板 (vane) が最長の横木 (cross-piece) の両端に追加され、もう一つが主要スタッフの端に追加された。 装置が逆向きにされ、横木の上方の視準板の影が、主要スタッフの端の視準板に落ちるようにした。 ナビゲーターは装置を持って、水平線が下方の視準板と主要スタッフ末端の視準板に揃うように観測した。 水平線を、棒の端の視準板上の太陽の影と揃えて、太陽の高度が決定できた。 これにより実際は、装置の精度を増大した。というのは、ナビゲーターは棒の端を正確に頬にあてなくてよいからであった。
クロススタッフの別の変種はスピーゲルブーグ (spiegelboog, 英語で Mirror staff, ミラースタッフ) で、 1660 年にオランダ人のジュースト・ヴァン・ブリーン (Joost van Breen) により発明された。
究極的に、クロススタッフは多くの国で バックスタッフと競争できなかった。 操作の点で、 バックスタッフの使用が容易であることが判明した。 しかしながら、 何人かの著者により、精度の点でクロススタッフが バックスタッフよりも優れていることが、示された。 バックスタッフは 1731 年より、 オランダ東インド会社 (Dutch East India Company) の船舶ではもはや許可されず、 八分儀は 1748 年まで許可されなかった。
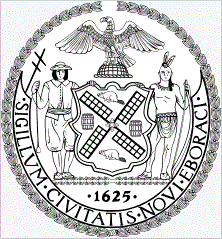
|
|
クロススタッフは現在の
ニューヨーク市章で船乗りの上に登場する。
この市章は 1915 年からのものであるが、 クロススタッフは 17 世紀のものを描写。 |
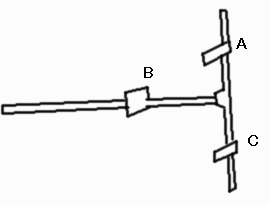
|
測量では、ヤコブスタッフ (Jacob staff) の用語は 一脚 (monopod) ―― 単一の真っすぐな棒で非鉄素材で作られ、 地面に突き刺すために先が尖り金属をかぶせてある。 これはネジの基礎 (screw base) がある、そして時には取り付け具にボール・ジョイント (ball joint) があり、 コンパス, トランシット, あるいは他の機器を支えるのに使用される。
クロススタッフの用語は測量の歴史では異なる意味もある。 天文クロススタッフは角度を測定するために使用されるが、 クロススタッフと呼ばれる他の 2 つの機器も使用される。
過去には、多くの測量技師の機器がヤコブスタッフの上で使用された。 これに含まれるものは :
(訳注:簡単にわかるものだけリンクを付けています。)
機器によっては、 レーザーを基礎とする測量のための現代の光学ターゲット (optcal target) のように、 ヤコブスタッフ ―― 現在では測量ポール ( surveying pole) と呼ばれる ―― の上で なお普通に使用されている。
地質学ではヤコブスタッフはフィールドで、層位学的厚さ (stratigraphic thickness) を測定するために主に使用され、 とりわけ 層理 (bedding) が目で見えない、あるいは不明な時 (例えば覆われた露頭の時)、そして露頭の 配置により、層理 (bedding) の見かけと実際の厚さが発散し、従ってテープ測定の使用を困難にしている時である。 この方法を使用する時、層位学的厚さを測定するための、正確な参照手段がないことにより、 ある程度のエラーレベルが予期される。 高精度デザインにはスタッフ (staff) に沿って垂直にスライドして、しかも 層理 (bedding) に平行な平面で回転することができるレーザーが含まれる。