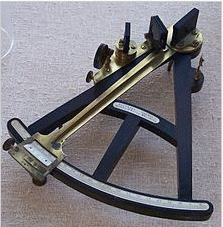
|
|
八分儀、この装置には、中央部に次のラベル。
『クライントン - ロンドン、アバディーンの J.Berry により売却』 フレームは 黒檀製、 象牙の目盛と 副尺。 インデックス・アーム とミラーの支えは真鍮製、 照準望遠鏡の代わりに、視準板 (pinnula) を使用 |
以下の文書は次の翻訳です。
Octant (instrument) - Wikipedia (八分儀)
八分儀は反射四分儀とも呼ばれ、 ナビゲーションで使用される 反射機器である。
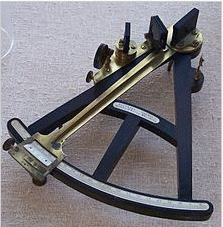
|
|
八分儀、この装置には、中央部に次のラベル。
『クライントン - ロンドン、アバディーンの J.Berry により売却』 フレームは 黒檀製、 象牙の目盛と 副尺。 インデックス・アーム とミラーの支えは真鍮製、 照準望遠鏡の代わりに、視準板 (pinnula) を使用 |
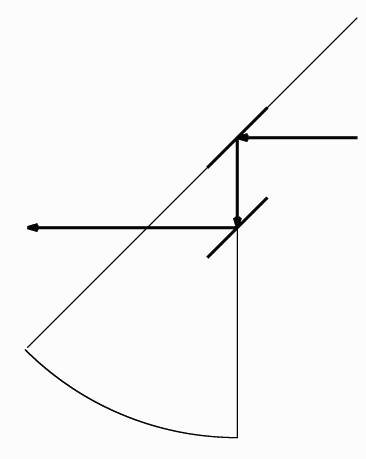
|
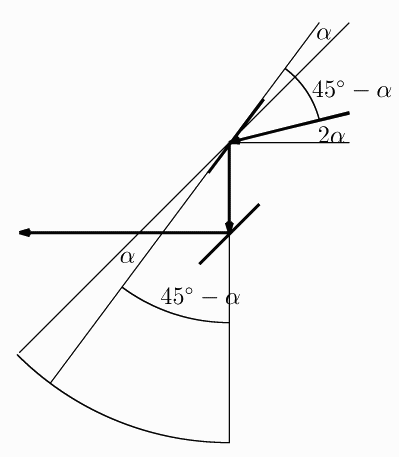
|
octant (八分儀) の名称はラテン語の octans に由来し、円の 1/8 を意味する。 これは機器の円弧が円の 1/8 であるからである。
反射四分儀は 観測者への光の通り道に鏡を使用する機器に由来し、 こうすることで、観測する角度を 2 倍にする。 これにより、この機器は 1 回転 (turn) の 1/8 を使用して、 1/4 回転を測定する。
アイザック・ニュートン の反射四分儀は 1699 年頃に発明された。 機器の詳細な説明が エドモンド・ハレーに与えられたが、 この説明は 1742 年のハレーの死後まで出版されなかった。 ハレーが生きている間にこれを出版しなかった理由は不明である。 しかしながら、これによって八分儀の発明者がニュートンではなく、 一般に ジョン・ハドリー (John Hadley) や トーマス・ゴッドフリー ( Thomas Godfrey) によるものとされることになった。
この機器の 1 つはトーマス・ヒース (Thomas Heath、機器製造家) により建造され、 1742 年の 王立学会の出版前に、 ヒースの店の窓に展示してあったかも知れない。
ニュートンの機器は 2 つの鏡を使用したが、 その配列は現代の八分儀や六分儀で見られる 2 つの鏡とは少々違う配列で使用された。 下の図は機器の構成を示している。
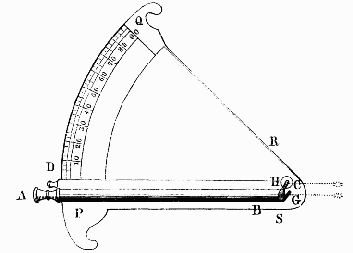
|
||
ニュートンの反射四分儀の描画 (Brewster (1855, p243))
|
装置の 45° の弧 (P-Q) は 0.5° で 90 分割して目盛が付いていた。 各分割は 60 個の部分に再分割され、それは更に 6 分割された。 この結果、弧は 度、分、1/6 分 (10 秒) で目印が付いていた。 従って、この機器は円弧の 5 秒まで読み取ることができた。 目盛の細かさは機器の大きな大きさのみで可能であり、 照準望遠鏡だけでも 3、4 フィートの長さがあった。
照準望遠鏡 (A-B) は 3、4 フィートの長さがあり、 機器の片側に搭載されていた。 水平線ミラー (G) は望遠鏡の対物レンズの前に 45° で固定されていた。 この鏡は十分小さいため、観測者は一方の側でミラーの中の像を見て、 他方の側で、直接前方を見ることができた。 インデックス・アーム (C-D) にインデックス・ミラー (H) が付属し、インデックス・アームの端でやはり 45° で固定されていた。 2 つのミラーの反射面は名目的に互いに向き合っており、 最初のミラーで見える像は第 2 のミラーで反射したものである。
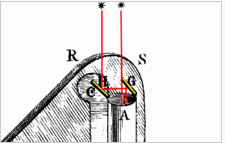
|
|
ニュートンの反射四分儀の鏡の詳細。装置の中の光の 通り道を赤色で表示、この絵は最初の絵を 90° 反時計式に回転 |
2 つのミラーが平行であれば、インデックスは 0° を与える。 望遠鏡を通る視野は一方の側で直接前方が見え、 ミラー G を通る視野はミラー H から反射されるものと同じ像である。 (上の詳細図を参照)。 インデックス・アームを 0 から大きな値に動かすと、 インデクス・ミラーは直接の照準線から向きが違う像を反射する。 インデックス・アームの動きが増えると、 インデックス・ミラーの照準線は S に向けて (詳細図の右に) 移動する 。 これはミラーの配置のわずかな欠陥を見せている。 水平線ミラーは、インデクス・ミラーの角度が 90° に近くなると、視野を妨げる。
照準望遠鏡の長さは、 現代の機器の小さなサイズを前提にすると、注目すべきである。 これは、 色収差を軽減するためのニュートンの選択のようである。 組み合わせレンズ (achromatic lens) が発明される前は、焦点距離が短い望遠鏡では、 問題となるくらいの色収差が生じ、星の位置の決定に悪影響を及ぼした。 これには長い焦点距離は解決方法であり、 ニュートンの望遠鏡は長い焦点距離の対物レンズと、長い焦点距離の接眼レンズの両方を持っていたことであろう。 これにより、過度な拡大なしに色収差を軽減したことであろう。
2 人の人物が 1730 年頃に独立に八分儀を発明した: 一人は英国の数学者である ジョン・ハドリー (1682 年 - 1744 年) で、 もう一人はフィラデルフィアのガラス屋のトーマス・ゴッドフリー (Thomas Godfrey) である。 どちらも正当で対等な発明者であるが、 ハドリーの方がより大きな名声を得ている。 これはロンドンと王立学会が 18 世紀の科学的機器の歴史で演じた中心的な役割を反映しているのである。
この頃に八分儀を作った人物が別に二人おり、 一人が英国の保険仲介人 (insurance broker) で天文学に非常に興味をもっていたカレブ・スミス (Caleb Smith、1734 年)、 もう一人がフランスの数学の教授で天文学者でもあったジャンポール・フーシー (Jean-Paul Fouchy、1732 年) であった。
ハドリーは二種類の反射四分儀を作成した。 二つ目のもののみがよく知られ、馴染みな 8 分儀である。
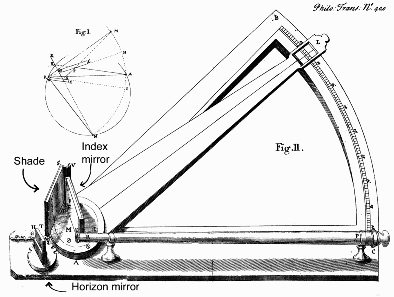
|
|
ハドリーの反射四分儀
この装置は 1699 年のニュートンの反射四分儀の形式に従っている。 |
ハドリーの最初の反射四分儀は単純な装置でフレームは 45° の円弧に及んだ。 上の図は、 王立学会の学会誌 (Philosophical Transaction) に掲載された論文の画像で、 彼のデザインした本質を見ることができる。 小さな照準望遠鏡がフレームの一方の側面に沿って枠に搭載されていた。 大きなインデックス・ミラー (Index mirror) がインデックス・アームの回転の中心に搭載されていた。 二番目の、より小さい水平線ミラー (Horizon mirror) はフレームに搭載され、望遠鏡の照準線にあった。 水平線ミラーにより、観測者は視野の半分でインデックス・ミラーの像を見て、 他の半分で遠方のオブジェクトを見ることを可能にしている。 シェード (影) が機器の頂点に搭載され、これにより明るいオブジェクトを見ることができる。 星の観測には、シェードを軸の周りに回転して、視野の外に移動することが可能である。
望遠鏡を通しての観測で、ナビゲーターはまっすぐ前方のオブジェクトを観測する。 第二のオブジェクトは、水平線ミラーからの反射を見る。 水平線ミラーの光はインデックス・ミラーから反射される。 インデックス・アームを移動することにより、 インデックス・ミラーは、直接の照準線から 90° 以内のどのようなオブジェクトも見せることができる。 二つのオブジェクトが同じ視野にある時に、これを揃えることにより、ナビゲーターは両者の 間の角距離を測定できる。
元々の反射四分儀はほとんど製造されなかった。 バラデル (Baradelle) によって建造されたものは、パリの海洋博物館 ( Musée de la Marine) のコレクションにある。
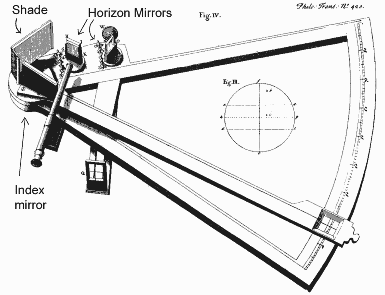
|
|
ハドリーの八分儀
この形は六分儀を見たことがある人には馴染みな形である。 |
ハドリーの二番目のデザインは現代のナビゲータに馴染みな形をしている。 上の画像も、彼の 王立学会 の出版物からのものであり、詳細を示している。
彼はインデックス・ミラーをインデックス・アームに設置し、 二枚の水平線ミラーを提供した。 上部のミラーは、照準望遠鏡の線上にあり、十分に小さく作られていたため、 直接前方を見ることができ、同時に反射してくる光景を見ることができた。 反射してくる光景はインデックス・ミラーから反射してくるものである。 直前の機器と同様に、 ミラーの配置により観測者は直接前方にあるオブジェクトと、 インデックス・ミラーから水平線ミラーで反射して、更に望遠鏡を通ってくる光を 同時に見ることができた。 インデックス・アームを動かすことにより、 ナビゲーターは直接の視野から 90° 以内のどのようなオブジェクトも見ることができた。
このデザインにおける重要な違いは、ミラーにより機器を水平ではなく垂直に保持することを可能にしたことと、 ミラーの設定にゆとりを与え、相互に干渉しなくなった点である。
第二の水平線ミラーは興味をそそられる考案である。 望遠鏡は取り外しができた。 望遠鏡を再装着して、フレームの反対側から第二の水平線ミラーを見ることができた。 二つの水平線ミラーを互いに直角に搭載し、 望遠鏡の移動を可能にすると、ナビゲーターは一方の水平線ミラーで 0° から 90° までの角度を測定し、 もう一方の水平線ミラーで 90° から 180° までの角度を測定できた。 これにより、機器はとても融通がきくことになった。 不明な理由から、この造作は一般使用の八分儀では実装されなかった。
この機器とこの記事のトップにある典型的な八分儀の写真を比較すれば、 より現代的なデザインとの重大な相違点は次のみである。
カレブ・スミス (Caleb Smith) は 英国の保険仲介人 (insurance broker) で天文学に非常に興味をもっており、 1734 年に八分儀を作った。 彼はそれを「天体スコープ」もしくは「海洋四分儀」と呼んだ。 彼は反射面を提供するために、インデックス・ミラーに付け加えて、固定したプリズムを使用した。 研磨した金属鏡面の質が低く、 鏡の銀メッキと 平らで平行な面を持つガラスの製造が どちらも困難な時代においてはプリズムは鏡よりは有利であった。
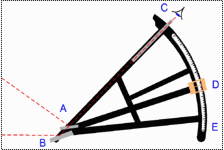
|
| スミスの「天体スコープ」もしくは「海洋四分儀」 |
上の絵において、 水平線成分 (B) はミラーでもよいしプリズムでもよい。 インデックス・アームにおいて、 インデクス・ミラー (A) はアームと共に回転した。 照準望遠鏡はフレームに搭載された (C)。 インデックスはスケール (D) で、副尺 (バーニヤ・スケール)などの機器を使用しなかった。 スミスは装置のインデックス・アームをラベルと呼び、 これは、エルトン (Elton) が彼の「海洋四分儀」で呼んだ方式である。
スミスによる色々なデザイン上の要素はハドリーの八分儀より質が低く、 多く使用されることはなかった。 例えば、天体スコープの 1 つの問題点は観測者の照準線の角度である。 見下ろせば、通常の頭の向きと異なり、観測をすることが困難となった。
八分儀にはそれ以前の機器よりも有利な点が幾つかあった。
照準は揃えることが易しかった。 というのは、水平線と星は、船の縦揺れ・横揺れと共に動くからである。 これにより、観測誤差は観測者にそれほど依存しない状況となった。 というのは、観測者はどちらのオブジェクトも同時に直接見ることができたからである。
18 世紀に利用可能な製造技術で、 機器はとても正確に読むことが可能であった。 精密さを失わずに機器の大きさを小さくできた。 八分儀は誤差を増大せずに「デイビスの四分儀」の大きさを半分にすることができた。
光の通り道にシェード (影) を使用することで太陽を直接観測でき、 シェードを光の通り道から動かせば明るくない星も観測できた。 これで機器は昼夜を問わずに使用できた。
1780 年までに八分儀と六分儀はほとんど完全に、それ以前の全てのナビゲーション機器の代わりになった。
初期の八分儀は主に木製で、 後には象牙や真鍮の部品を組み込んだ。 最も初期のミラーは研磨した金属であった、 というのは平坦で平行な表面を持つ銀メッキされたガラスの鏡を製造する技術が 限られていたからである。 ガラスを研磨する技術が向上するにつれ、 ガラスの鏡が提供されるようになった。 これは水銀を含むスズの アマルガム によるコーティングを使用し、 銀やアルミによるコーティングは 19 世紀まで利用可能ではなかった。 初期の研磨された金属ミラーの貧弱な光学的性質が意味したことは、 望遠鏡照準は現実的ではなかったことである。 この理由から、最も初期の八分儀の大半は単純な裸眼照準の視準板 (pinnula) を 使用した。
初期の八分儀には 後方棒 (backstaff) に共通する幾つかの造作、例えば目盛の 横断線 (transversal) などがあった。 しかしながら、この機器は彫り込むと、明らかに円弧 2 分の精度しかなく、 一方、後方棒 (backstaff) は明らかに 1 分の精度があるように見えた。。 副尺 (バーニヤ・スケール) の使用から 1 分まで目盛を読むことができ、 これにより装置の販売可能性を向上した。 この事実と副尺の方が横断線よりも製作が容易であったため、 18 世紀後半に製造された八分儀は副尺を採用することとなった。
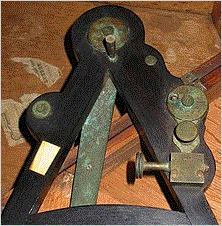
|
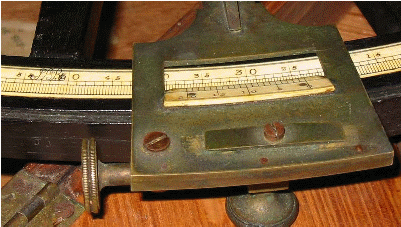
|
|
| 八分儀の裏側。裏側は写真では始終は見ることがない。 右側に水平線ミラーの調節用蝶ネジ。 頂上には八分儀がケースの中で安置される脚の 1 つがインデックス・アームの軸のすぐ下にある。 左側にメモ帳が明確に見える。この小さな要石(keystone)の形の一片の象牙は 親指の爪よりわずかに大きく、ナビゲーターが読み取りの記録用に使用する。 | 八分儀の詳細、 写真は目盛付きスケールと副尺の付いたインデックス・アームの先端を示す。 インデックス・アーム固定用のネジはインテックス・アームの下に見え 微調整用のネジが左に見える。 主目盛の 50 の値の左に SBR のロゴが見える。 スケールには直接、角度とその 3 分の 1 (20') が彫り込まれ、 副尺により分の単位で測定可 |
八分儀は大量に製造された。 これは木や象牙でできており、 全部真鍮でできている六分儀よりは比較的安く、 人気のある機器となった。 デザインは多くの製造業者が同一のフレーム・スタイルと部品を使用して、 標準化された。 異なる店が異なる部品を製造し、 木工職人はフレームの製造に特化し、 それ以外のものは真鍮部品の製造に特化した。 例えば、Spencer, Browning and Rust は 1787 年から 1840 年までイングランドの科学機器製造業者 (1840 年以後は Spencer, Browning and Co. として操業) であったが 「ラムスデンの 目盛り刻印機」(Ramsden dividing engine) を使用して象牙の目盛を製造した。 これらは他の業者により広く使用され SBR の頭文字が 他の多くの製造業者の八分儀に見出されることになった。
これらのとても類似した八分儀の実例は、この記事の写真にある。 トップの画像は基本的に詳細写真のものと同じ機器である。 ―― トップは Crichton - London, Sold by Berry Anderson のラベルが付き、 一方詳細な画像は Spencer, Browning & Co, London の機器である。 唯一の明らかな違いは Crichton 八分儀の水平線シェードの存在で、これは別のものにはない。
これらの八分儀では多くのオプションが利用可能であった。 木のフレームに直接目盛りをつけた基本八分儀は最も安かった。 これらには望遠鏡照準がなく、その代わりに一つ穴あるいは二つ穴の 照準用の視準板 (pennula) を使用した。 象牙の目盛りは価格を上げ、 真鍮のインデックス・アームや副尺 (バーニヤ・スケール)の使用も同様であった。
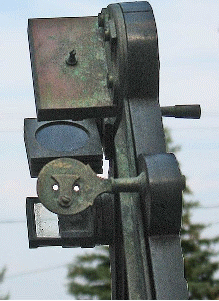
|
| 八分儀の詳細が二つ穴の視準板を示す。 どちらか一方の穴を閉鎖するための小さな覆いも見える。 水平線ミラーは装置の反対側。 左側は透明で、 鏡の側のスズのアマルガムは完全に腐食して、もはや反射しない。 インデックス・ミラーの支えの後部が一番上、 四角いフレーム内の三枚の円形のガラスのシェードは二つのミラーの間。 |
1767 年の最初の 航海年鑑に 月からの距離 の表が掲載されて、 これによりナビゲータは太陽と月の間の角度から (グリニッジの) 現在時を 決定できるようになった。 この角度は時々 90° より大きく、 八分儀では測定できなかった。 この理由からジョン・キャンベル提督 ( Admiral John Campbell) ――「月からの距離方式」の船上実験を実施 ―― は、 より大きな機器を提案し、これにより 六分儀が開発された。
この時以降、六分儀は著しい発展と改良を見ることとなり、 海軍のナビゲーターの選ぶべき機器となった。 八分儀は 19 世紀になってもなお製造され続けた。 もっとも、これは一般にそれほど正確ではなく、それほど高価な機器でなかった。 八分儀は望遠鏡が付いていない型式も含め、 より安かったため、 商業や漁業の船団の船にとっては現実的な機器であった。
19 世紀末に至るまで、ナビゲーターの間で共通に実践されたことは、 六分儀と八分儀を併用することであった。 六分儀はとても注意して使用され、「月からの距離」に使用されたのみであり、 一方で八分儀は毎日のルーティンの太陽の子午線高度の測定に使用された。 これにより非常に正確で値段の高い六分儀を保護し、 もっと手頃な八分儀は八分儀で事が足りる場合に使用した。
1930 年代始めから、1950 年代末にかけて 幾つかの型式の民生用あるいは軍事用の気泡八分儀 (bubble octant) が 航空機の上で使用するために製造された。 すべてが気泡の形で人工水平線が取り付けられ、 地表から何千フィートもの上空で水平線とそろえるために、 気泡を中央になるようにした。 装置の中には記録できるものもあった。
八分儀の使用と調整はナビゲーターの六分儀と本質的に同じである。
ハドレー (Hadley) のものは最初の反射四分儀ではなかった。 ロバート・フックは 1684 年に反射四分儀を発明し、早くも 1666 年にその構想に ついて書いている。 フックのものは単一反射機器であった。 他の八分儀はジャン-ポール・フーシー (Jean-Paul Fouchy) とカレブ・スミス (Caleb Smith) により 1730 年代初めに開発されたが、ナビゲーション機器の歴史で重要にならなかった。