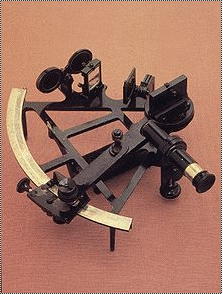
|
| 六分儀 |
以下の文書は次の翻訳です。
Sextant - Wikipedia (六分儀)
英語で単に六分儀 (sextant) と呼ぶ場合に、 天文用六分儀を指していることがあります。 ここで述べている六分儀は、より正確にいえば「航海用六分儀」のことです。 用語は同じでも機能が基本的に違うと考えた方が正解です。 英語では異なるものを同じ言葉で表示することがよくありますが、 日本語ではこのようなことをしないので注意が必要です。 なお、以下の説明では (航海用) 六分儀が元々何を目的とした装置であるかを書いてないので 反射機器の六分儀から 引用します:
六分儀が月距を測定するための装置として発明されたことは、要求される精度が極めて高いことを意味しています。
ジョン・バードが六分儀を製造した時には手作業で目盛りを入れたと思われますが、 彼が製造したグリニッジ天文台の壁面四分儀の精度が 1 秒 (= 1/3600 度) であったこと (ジョン・バードを参照) を考えれば、その製造技術は極めて洗練されたものであったと思われます。
六分儀は二重反射ナビゲーション機器で、2 つの視認できる天体間の 角距離を測定する。 六分儀の基本仕様は天測ナビゲーションの目的のために、 天体と水平線の間の角度を測定することである。
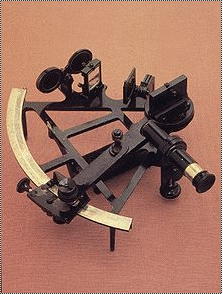
|
| 六分儀 |
この角度 (高度) の評価はオブジェクトの観測、照準合わせなど (sighting the object、shooting the object、taking a sight) と呼ばれる。 角度と測定時の時間は海図あるいは航空図で位置の直線 (position line) を計算するのに使用できる。 例えば 正午の太陽あるいは夜の北極星 (北半球) の照準合わせ (sighting) があり、 これは (天測計算で) 経度の見積もりのためである。 ランドマークの高さの照準合わせにより離れている距離がわかり、 水平に持てば、六分儀はオブジェクトの間の角度を測定して 海図における位置を与える。 六分儀は月と他の天体 (例えば星、惑星) の間の「月からの距離」 (lunar distance, 月距) を測定するのにも使用でき、グリニッジ平均時を決定して、経度を決定できる。
機器の原理は 1731 年頃に ジョン・ハドレー (1682 年 - 1744 年) と トーマス・ゴッドフリー ( Thomas Godfrey, 1643 年 - 1727 年) により始めて実装されたが、 後に アイザック・ニュートン (1643 年 - 1727 年) の未出版の原稿にも発見された。
1922 年に、ポルトガルのナビゲーターで海軍将校の ガーゴ・コーチニョにより航空ナビゲーションに変更された。
デイビスの四分儀のように、六分儀は、機器に相対的ではなく、 水平線に相対的な天体測定を可能にする。 これにより精度が高くなる。 またバックスタッフとは違い、六分儀は星の直接観測も可能にする。 これにより、六分儀の使用は、バックスタッフの使用が困難な夜間でも可能である。 太陽観測に関しては、フィルターにより太陽の直接観測が可能である。
測定は水平線に相対的であるから、測定ポインターは水平線に到達する光のビームである。 従って、測定は機器の角度の精度で制限され、 船乗りのアストロラーベや 類似の古い機器のようにアリダードの長さの正弦エラー (sine error) で制限されるのではない。
六分儀は完全に安定した照準は必要ではない、というのは これは相対的な角度を測定するからである。 例えば、同様する船で六分儀を使用すると、水平線と天体のどちらの像も視野の中を動く。 しかしながら、2 つの像の相対位置は固定されたままで、天体が水平線と接する時を決定できる限り、 測定の精度は動揺の大きさと比較すると高いままである。
六分儀は (現代の多くのナビゲーション装置とは違い) 電気、 あるいは人間が制御する信号 (例えば GPS) に依存しない。 このような理由から、これは船舶にとり極めて現実的なバックアップ・ナビゲーション・ツールであるとみなされる。
六分儀のフレームは、 円のおよそ 1/6 (60°) の扇型であり、 これが名前が由来である (sextāns, sextantis はラテン語の 1/6)。 小さい機器や、大きい機器の両方が使用されている (あるいは、されていた): 八分儀、五分儀、及び (二重反射) 四分儀、 それぞれ円のおよそ 1/8 の扇型 (45°)、円の 1/5 (72°)、円の 1/4 (90°) を張るものである。 これらの機器はすべて六分儀と呼ぶこともある。
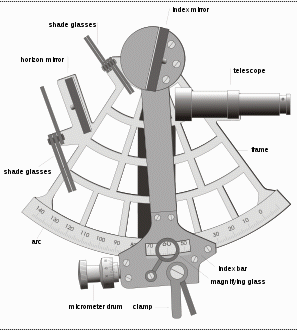
|
| 海洋六分儀 |
枠に付属するのは「水平線ミラー」、インデックス・アーム (これはインデックス・ミラーを動かす)、 照準望遠鏡、サン・シェード (Sun shades)、目盛りが付いたスケール (graduated scale)、 そして正確に測定するためのマイクロメーターの円筒ゲージ (drum gauge) である。 スケールには目盛りが付き、マークされる角度分割は、 インデックス・アームの回転角の 2 倍である。 八分儀、六分儀、五分儀、そして四分儀のスケールの目盛り付けは、 それぞれ 0 から 90°、120°、140°、そして 180° である。 例えば、上の六分儀は -10° から 142° に目盛りが付けられ、 これは基本的に五分儀である; フレームはインデックス・アームの旋回軸に対する扇形で、角度 76°のものである。
2 倍の目盛りを読む必要性は (ミラー間の) 固定光線、 (照準を合わせたオブジェクトからの) 対物光線、 インデックス・ミラーに垂直な法線の向きの考察によっている。 インデックス・アームがある角度、例えば 20° 動くとき、 固定光線と法線も 20° 増える。 しかし、入射角は反射角に等しく、対物光線と法線の間も 20° 増える。 固定光線と対物光線の間の角度は従って、40° 増える。 これが図で示されている場合である。

|
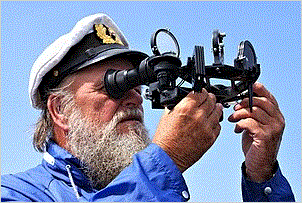
|
|
|
六分儀を使用して 水平線上の太陽の高度を測定 |
六分儀はナビゲーターにより
オブジェクトの間の水平角を 測定するのにも使用できる。 |
今日、市場には 2 つのタイプの水平線ミラーがある。 どちらも良好な結果を与える。
伝統的な六分儀は半水平線ミラー (half-horizon mirror) があり、 これは視野を 2 つに分割する。 一方の側で、水平線の視界があり、 もう一方の側に天体の視界がある。 このタイプの利点は水平線と天体のどちらも明るく、できる限り鮮明である。 これは夜ともやの時に優れており、この時は水平線 [且つ/あるいは] 星は見ることが 困難なことがある。 しかしながら、天体を一掃 (sweep) して、天体の下端が水平線に触れていることを 確認しなければならない。
全水平線六分儀 (whole-horizon sextants) は半透明な水平線ミラーを使用して、 水平線の完全な視界を提供する。 これは天体の下端が水平線に触れていることを見るのは容易である。 大半の観測は太陽あるいは月で、雲がないモヤはまれで、 半水平線ミラーの低照度の場合の利点は実際問題としてはほとんど重要でない。
両方のタイプで、より大きなミラーはより大きな視野を与え、 これにより天体を見つけることが容易である。 現代の六分儀はしばしば 5 cm 以上のミラーがあり、一方 19 世紀の六分儀は 2.5 cm (1 インチ) 以上の大きなミラーはほとんどなかった。 大体の理由は、精密な平坦ミラーは製造・銀メッキと共にそれほど高価でなくなったからである。
人工水平線が便利なのは、水平線が見えない時で、 霧があったり、月がない夜や、なぎの時で、 窓越しに、あるいは木々や建物で囲まれた土地で照準を合わせる時である。 人口水平線には普通 2 つのデザインがある。 人口水平線の一つは風を遮った水たまりから構成され、 使用者が天体とその鏡映の間の距離を測定して、2 で割ることを可能にしている。 別のデザインは、泡を入れた液体を充満したチューブを直接六分儀に搭載したものである。
大半の六分儀には太陽を見る時と モヤの影響を削減する時に 使用するフィルターもある。 フィルターは通常、順番に暗くなる一連のガラスから構成され、 これは単独使用か、組み合わせて使用し、モヤと太陽のギラツキを削減する。 しかしながら、調節可能な偏向フィルターを持つ六分儀も製造され、 暗さの度合いはフィルターのフレームをひねる (twist) ことにより調節する。
大半の六分儀は 1 倍あるいは 3 倍の単眼望遠鏡を搭載する。 多くの使用者は単純な照準チューブを好み、これは広く、明るい視野があり、 夜間に使用が容易である。 ナビゲーターによっては、光増幅の単眼望遠鏡を搭載し、 月が出ていない夜間に水平線を見る助けにしている。 他の人は明かりをつけた人口水平線を好む。
専門的六分儀はクリック・ストップ (click stop) の角度測定器を使用し、 1 度の 1/60 である 1 分を読み取るワームギアがある。 大半の六分儀はワームギアにバーニヤ・スケールを含み、これは 0.1 分を読み取る。 1 分の誤差はおよそ 1 海里で、天測ナビゲーションの最良の可能な精度はおよそ 0.1 海里 (190 m) である。 海上では数海里以内の結果は十分に目で見える範囲なので、許容可能である。 高度な技術と経験があるナビゲーターは、およそ 0.25 海里 (460 m) の精度で位置を 決定できる。
気温の変化は円弧をゆがめ、不正確にする。 多くのナビゲーターは風雨に耐えるケースを購入して、六分儀を船室の外に置き、 外気温と平衡をとるようにする。 標準のフレーム・デザイン (挿絵を参照) は温度変化からの異なる角度エラー を均等にすることを想定している。 ハンドルは円弧から分離され、身体の熱がフレームをゆがめないようになっている。 熱帯仕様の六分儀は、しばしば白く塗装され、日の光を反射することができ、比較的涼しい状態である。 高精度六分儀には インバー (invar, 特殊低膨張率鋼) のフレームと円弧がある。 科学的六分儀の幾つかはもっと低膨張率のクォーツやセラミックスで 建造されている。 多くの商用六分儀は低膨張率の真鍮あるいはアルミを使用する。 真鍮はアルミより低膨張率であるが、アルミ製六分儀はより軽く、使用しても疲れない。 人によっては手が震えないので、より正確であると言っている。 がっしりした真鍮フレームの六分儀は、強風下あるいは荒れた海での作業中に、 揺れにくいが、指摘されるように随分と重い。 アルミ・フレームと真鍮円弧を持つ六分儀も製造された。 本質的に、六分儀は各ナビゲーターにとりひどく個性的で、 彼らは自分達に最適な造作を持つどのようなモデルも選ぶ。
航空機六分儀は今では製造されていないが、特別な造作があった。 大半は人工水平線があり、平坦な頭上窓を通して照準を合わせることを可能にした。 幾つかは人工水平線の液体中のランダムな加速の埋め合わせをするために、 照準毎に何百回もの測定の機械的平均化装置があった。 古い航空機六分儀には 2 つの光の通り道があった、 1 つは標準的なもので、もう 1 つは 開放操縦席の航空機で使用するためにデザインされ、 膝の上の六分儀越しの直接視認を可能にした。 もっと現代的な航空機六分儀は機体からわずかに突き出る潜望鏡であった。 これによりナビゲーターは照準をあらかじめ計算し、機体の観測高度と予測高度の 違いを見て、位置を決定した。
太陽、星、あるいは惑星と水平線の間の角度の測定は、 視認できる水平線を使用して、六分儀に装着される星望遠鏡で実施される。 海上の船舶では、もやのかかった日でも 海上の低い高度から測定を実施でき、もっとはっきりした良好な水平線を与える。 ナビゲーターは右手で六分儀のハンドルを持ち、円弧を指で触れることを避ける。
太陽の測定のために、 ぎらつきを克服するためのフィルターが使用され、 例えば、目の損傷を防ぐためにインデックス・ミラーと水平線ミラーを 覆うシェードが使用された。 始めはインデックス棒を 0、 シェードが両方のミラーを覆うように設定する。 六分儀で太陽に狙いをつけ、望遠鏡越しにどちらのミラーでも太陽を見えるようにする。 次に垂直に下に向けて、直接下の水平線の一部分がどちらのミラーにも見えるようにする。 水平線をもっとはっきりと見ることができるように、 水平線ミラーのシェードを元に戻すことが必要である。 インデックス・バーを開放して (締めネジの解放、 あるいは現代機器の場合にはクイック・リリース・ボタンの使用)、 これを目盛りの高い方に移動すれば、 まもなく太陽の像がインデックス・ミラーに再び現れ、水平線ミラーの水平線レベルのあたりに 揃えることができる。 次にインデックス棒の端の微調整ネジを回転して、 太陽の下端 (下縁) が水平線に接するようにする。 望遠鏡の軸のまわりに六分儀を揺らして、 機器が垂直の状態で読み取りが実施されていることを確かめる。 測定の角度は次に、 提供されるマイクロメーターあるいはバーニヤ・スケールを 使用して、円弧の目盛りから読み取る。 測定の正確な時間も同時に記録を取り、海面上の目の高さも記録する。
代替の手段はナビゲーション表から太陽の現在の高度 (角度) を推定し、次に インデックス棒を円弧上のその角度に設定し、 インデックス・ミラーのみに適切なシェードを適用し、 機器を直接水平線に向け、太陽の光線のひらめきが望遠鏡の中に見えるまで端から端まで一掃する。 微調整は上と同じようにする。この方法は星や惑星の観測にはあまり成功しない。
星と惑星の観測は通常、海の夜明けと夕暮れの海の薄明かりの時に実施され、 天体と海の水平線がどちらも見える時である。 シェードの使用や、天体の下端を区別する必要はない、 というのは天体は望遠鏡の中で単に点として見えるからである。 月は観測できるが、とても速く動くように見え、 異なる時に異なる大きさを持つように見え、時には 月の相により、天体の下端あるいは上端の区別がつくだけである。
観測してから、幾つかの数学的手順を考察して、1 つの位置に帰着する。 最も単純なサイト・リダクション (sight reduction) は地球上の観測天体の等高度円 (equal-altitude circle) を引くことである。この円と推測軌道 (dead-reckoning track) との交点、 あるいは別の観測がもっと正確な位置を与える。
六分儀は他の視認できる角度 ―― 例えば 1 つの天体と別の天体の間、そして陸上のランドマークの間 ―― をとても正確に測定するのに使用できる。 水平に使用すれば、六分儀は 2 つのランドマーク ―― 例えば灯台と教会の尖塔 ―― の間の見かけの角度を測定でき、 これにより離れている距離を決定するのに使用できる。 (但し、2 つのランドマークの間の距離を知っている必要がある。) 垂直に使用すれば、高さが既知の灯台の照明と基底部の 海面レベルの間の観測も、離れている距離を求めるのに使用できる。
機器の鋭敏さから、簡単にミラーが狂い、調節が必要となる。 この理由から、六分儀はエラーがないか、頻繁にチェックする必要があり、 それに応じて調節する必要がある。
ナビゲーターにより調節できる 4 つのエラーがあり、次の順で取り除くべきである。
これはインデックス・ミラーが六分儀のフレームに垂直でない時である。 これをテストするために、インデックス・アームを円弧のおよそ 60° に置き、 六分儀を水平に持ち、円弧を体の反対側に腕の長さで離し、インデックス・ミラーを覗く。 六分儀の円弧はミラーの中に中断せずに連続して見えないといけない。 もしもエラーがあれば、2 つの視野は中断して見えることになる。 ミラーを調節して、反射する円弧と直接見える円弧が連続するように調節する。
これが起きるのは 水平線ガラス / ミラー が機器の平面に垂直でない時 である。これをテストするには、最初にインデックス・アームを 0 にセットし、 次に六分儀を通して星を観測する。 次にタンジェント・ネジ (tangent screw) を前後に回転し、 反射された像が直接の光景の上下を交互に通過するようにする。 もしも、ある位置から別の位置に移動する時に、反射した像が反射していない像の上を直接通過すれば サイド・エラーはない。 もしも、これが一方の側の方向に通過すればサイド・エラーがある。 この代わりに、使用者が六分儀を側面に置き、日中に六分儀をチェックするために水平線を観測する。 もしも 2 本の水平線があれば、サイド・エラーがある。 どちらの場合も、水平線ガラス / ミラー を調節して、それぞれ星あるいは水平線の二重像が 1 つになるまで 続ける。 サイド・エラーは一般に観測には重要でなく、無視ししてもよく、単に利便性の問題に帰着する。
これは望遠鏡 あるいは 単眼鏡 が六分儀の平面に平行でない時である。 これをチェックするために、 90°あるいはそれ以上離れた 2 つの星を観測する必要がある。 2 つの星を視野の左、あるいは右のいずれかに同時に現れるようにする。 六分儀をわずかに動かし、2 つの星を視野の反対側に動かす。 もしもこれらが分離すれば、照準エラーがある。 現代の六分儀は調節可能な望遠鏡を、ほとんど使用しないので、照準エラーを調節する必要はない。
これはインデックス・アームを 0 にセットしたときに、 インデックス・ミラーと水平線ミラーが平行でない時に起きる。 インデックス・エラーをテストするには、インデックス・アームを 0 にセットし、 水平線を観測する。 水平線の反射像と直接像が一直線上にあればインデックス・エラーはない。 もしも一方が他方の上にあれば、2 つの水平線が一致するまで インデックス・ミラーを調節する。 別な方法として、同じ手順は夜間に水平線の代わりに、星や月を 使用して実施できる。
星の高度を測定する際の操作が少しややこしく見えるので考えてみることにします。
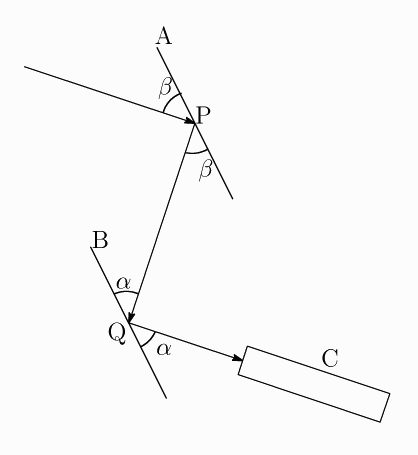
図において, A はインデックス・ミラー、B は水平線ミラー、C は望遠鏡です。 インデックス・アームを角度 0 にして、星に向けた時の図です。 角度 0 ですから、A, B は平行になっています。 従って角度 α と角度 β は一致していなければなりません。 この状態で星の高度を決定するためには、星を捉えながら、下に向けて望遠鏡で水平線を捉えないといけません。
水平線ミラー B と望遠鏡 C はフレームに固定されており、インデックス・ミラー A はインデックス・アームに 固定され、インデックス・ミラーの中央部の軸の周りで回転するようになっています。 そこで、今、インデックス・アームを固定して、フレームだけを反時計方向に δ 回転したとします。 すると角度 β は β-δ に変化します。 考えをやさしくするために、光の道を逆にたどります (望遠鏡の方から光を放出する)。 すると、放出された光は星の方に向かっていたものが、星よりも δ だけ上の方向に向かうことになります。 望遠鏡の中央に星を捉えるためにはインデックス・アームを δ/2 だけ、反時計方向に回転しないといけません。
従って、星を捉えながら、水平線を捉えるためには、フレームを回転させると同時に、 その半分の角度でインデックス・アームを回転しないといけないことになります。 だから、この操作は少し難しい。