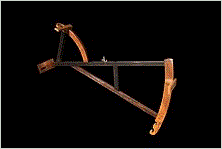
|
|
デイビスの四分儀、ヨハネス・ファン・クーレン (Johannes Van Keulen)
により 1765 年製作、パリの国立海洋博物館 (Musée national de la Marine) に展示。 |
以下の文書は次の翻訳です。
Backstaff - Wikipedia (後方棒、バックスタッフ)
バックスタッフはナビゲーション (航行) 用の機器で、 天体 ―― 特に太陽や月 ―― の高度を測定するのに使用された。 太陽を観測する時に、使用者は太陽を背にして (これが名称の由来)、 水平線視準板 (horizon vane) が上方視準板 (upper vane) が落とす影を観測した。 これはイングランドのナビゲーターである ジョン・デイビスにより発明され、 彼は 1954 年の本 「船乗りの秘密」 (Seaman's Secrets) でこれを説明した。
バックスタッフは影の射影により太陽の高度を測定する任意の機器に与えられる名称である。 後方観測を使用して、太陽の高度を測定するアイデアはトーマス・ハリオット (Thomas Harriot) に 起源があるようである。 この機器の多くの形式はバックスタッフに分類できるクロス・スタッフから進化した。 (しかし) デイビスの四分儀のみが、ナビゲーション機器の歴史で支配的である。 実際は、デイビスの四分儀は本質的にバックスタッフと同じ意味である。 しかしながら、デイビスはそのような機器をデザインした最初の人でもないし最後の人でもなく、 他の人もここで同様に考察する。
ジョン・デイビス船長は 1594 年にバックスタッフの 1 つのバージョンを発明した。 デイビスはナビゲーターで、 船乗りのアストロラーベ, 四分儀, そしてクロス・スタッフのような当時の機器を極めて良く知っていた。 彼は各々の内在する欠陥を知っており、 このような問題を削減し、 太陽の高度を獲得する容易さと精度を増大する新しい機器の創設で努力した。
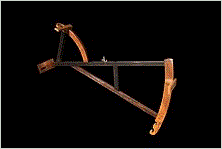
|
|
デイビスの四分儀、ヨハネス・ファン・クーレン (Johannes Van Keulen)
により 1765 年製作、パリの国立海洋博物館 (Musée national de la Marine) に展示。 |
四分儀スタッフ (quadrant staff) の初期の 1 バージョンは図 1 で示されている (下の図)。 これはスタッフ (棒、staff) に固定された円弧で、スタッフに沿ってスライドすることができる (曲がった形が選択されているが、形は重要でない)。 円弧 (A) は水平線視準板 (B) (horizon vane) に影を落とすように設置されている。 ナビゲーターはスタッフに沿って眺め、水平線視準板のスリットを 通して水平線を観測する。 影が水平線と揃うように円弧をスライドすることにより 太陽の高度が目盛りをつけたスタッフで読み取ることができる。 これは単純な四分儀であったが、望ましいほど正確ではなかった。 この機器の精度はスタッフの長さに依存するが、 長いスタッフは機器を扱いにくくする。 この機器で測定できる最大高度は 45° であった。
彼の四分儀の次のバージョンは図 2 で示される。 以前のバージョンの機器上端の円弧は横木 (transom) に設置された影視準板 (shadow vane) で 交代された。 この横木を目盛り付きスケールに沿って動かし、 これがスタッフの上の影の角度を表示した。 スタッフの下に 30° 円弧が追加される。 水平線は、左の水平線視準板 (horizon vane) を通して見え、これを影と揃える。 円弧の上の照準視準板を、水平線の視界と揃うまで移動する。 測定された角度は、横木の位置で表示される角度と、円弧のスケールで測定される角度の和である。
さてデイビスと同一視される機器は図 3 で示される。 この形式は 17 世紀中頃に進化した。 四分儀の円弧は 2 つの部分に分離した。 小さな半径の円弧は 60° のスパンがあり、スタッフの上に搭載された。 大きな半径の円弧は 30° のスパンがあり下に搭載された。 両方の円弧には共通の中心がある。 共通の中心に、スリットがある水平線視準板が設置された (B)。 可動な影視準板 (shadow vane) は、影が水平線視準板に落ちるように上の円弧に設置された。 可動な照準視準板 (sight vane) は下の円弧に設置された (C)。
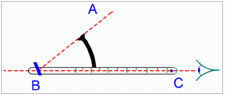
|
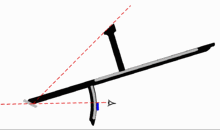
|
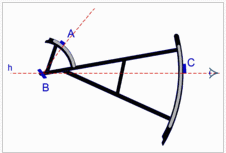
|
| 図 1. デイビス四分儀の単純な先駆、 彼の本「船乗りの秘密」の中の挿絵、 円弧は 45° までの測定に制限 | 図 2. 第二のデイビス四分儀。 彼の本「船乗りの秘密」の挿絵、 上方の円弧は, 下方の円弧と 上方の影を落とす横木と交代、 この機器は今や 90° まで測定可能 | 図 3. 17 世紀中頃までに進化した デイビス四分儀、 上方の横木は 60° の円弧と交代 |
円弧を任意の位置で読み取るよりも、 視準板を特別な位置に設置する方が容易である。 これはバーニヤ鋭敏 (Vernier acuity) ―― 2 本の線分を正確にそろえる人間の能力 ―― によっている。 従って、 比較的少ない目盛りでマークされた 小さな半径の円弧は、影視準板 (shadow vane) を特定の角度で正確に設置できる。 一方で、水平線への直線が影と交差する位置に、照準視準板 (sight vane) を 移動するには大きな円弧が必要である。 この理由は、 位置には 1度の端数がある可能性があり、 大きな円弧では高い精度で小さな目盛りを読むことが可能であるからである。 後に、機器の大きな円弧には、主要目盛りで可能なよりも、高精度で円弧の読み取りを可能にする 横断線でマークされていた。
従って、デイビスは、小さな円弧と大きな円弧の両方を持たせることにより、 四分儀の建造を最適化することができ、 機器全体をそれほど大きくせずに、 大きな半径を持つ単一円弧の事実上の精度を可能にした。 この形式の機器はバックスタッフ (backstaff) と同じ意味の言葉になり、 バックスタッフの最も広く使用された形式の 1 つになった。 ヨーロッパ大陸のナビゲーターはこれをイングリッシュ四分儀 (English Quadrant) と呼んだ。
デイビス四分儀の後の変更は影視準板 (shadow vane) のかわりに、 フラムスティード・ガラス (Flamsteed glass) を使用することである; これは ジョン・フラムスティードにより提案され、 視準板にレンズを設置して、水平線視準板に、太陽の影の代わりに太陽の像を射影した。 これは、少しもやがかかったり、少し曇った条件では有益であった; 太陽のぼんやりした像が水平線視準板に明るく表示されたが、 影では見えなかった。
機器を使用するために、ナビゲーターは影視準板 (shadow vane) を、太陽の高度が 想定される場所に設置する。 太陽を背にして機器を前に持てば、影視準板が落とす影が、 スリットの横で水平線視準板に落ちる。 次に、照準用視準板 (sight vane) を移動して、照準用視準板から、 水平線視準板のスリットを通して一直線に水平線を観測し、 この間、影の位置を同時に維持する。 これにより、水平線と太陽の間の角度を 2 つの円弧から読み取る角度の合計として測定できる。
影の端は太陽の縁を表示するので、値は太陽の視半径で修正しなければならない。
エルトンの四分儀 (Elton's quadrant) はデイビスの四分儀に由来する。 これは アルコール水準器が付属するインデックス・アームを追加して、 人工水平線を提供した。
ドミ・クロス (demi-cross, 半クロス) はデイビスの四分儀と同時代の機器である。 これはイングランド以外で人気があった。
垂直横木 (vertical transome) はクロス・スタッフの半横木 (half-transome) に類似し、 ここからドミ・クロス (Demi-cross, 半十字) の名称が由来する。 これは影視準板 (shadow vane、図 4 の A) を支え、 幾つかの高さの 1 つにセットできる (メイ (May) によれば 3 通り、デ・ヒルスター (de Hilster) によれば 4 通り)。 影視準板 (shadow vane) の高さを設定することにより、測定できる角度の範囲が設定される。 トランソム (横木、transome) はスタッフ (棒、staff) に沿ってスライドでき、 角度はスタッフの上の目盛りの 1 つから読み取れた。
照準用視準板 (C) と水平線視準板 (B) は水平線と視覚的に揃えられた。 影視準板 (shadow vane) の影は水平線視準板 (horizon vane) に落ち、 水平線と揃えられて角度が決定された。 実際には、この機器は正確であったが、デイビスの四分儀よりもっと扱いにくかった。
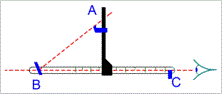
|
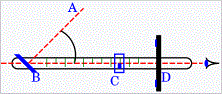
|
|
| 図 4 - ドミ・クロス。この機器はデイビスの四分儀と同時代で、 イングランド以外で人気。デイビスの四分儀の最初のバージョンと類似 (図 1) | 図 5 - プラウ (plough)、クロス・スタッフとバックスタッフの 両方の性質を備えた移行期の機器 |
プラウ (犂、plough) は短期間存在した普通とは違う機器につけられた名称であった。 これは部分的にクロス・スタッフで、部分的にバックスタッフであった。 図 5 で、 A は横木で、これが B の水平線視準板 (horizon vane) に影を落とす。 これは図 1 のスタッフと同じ方法で機能する。 C は照準用視準板 (sighting vane) である。 ナビゲーターは機器を水平に揃えるために、照準用視準板 (sighting vane) と 水平線視準板 (horizon vane) を使用する。 照準用視準板はスタッフに沿って左右に移動できる。 D は横木で、クロス・スタッフで見るものと全く同じである。 この横木には、 2 つの視準板があり、 スタッフに近づけたり、遠ざけたりして、 長さの異なる横木の模倣をした。 横木はスタッフの上で移動でき、角度測定に使用した。
等高度線スタッフは太陽の高度が低い時に特別に高度測定に使用された機器である。
クロス・スタッフは通常、直接観測機器である。 しかしながら、後に、これは後方観測で使用するために変更された。
四分儀の変種 ―― 後方観測四分儀 ―― があった。これは水平線視準板に落ちる影の観測を 太陽の高度測定に使用した。
トーマス・フード (Thomas Hood) は 1590 年にこのクロス・スタッフを発明した。 これは測量、天文学や他の幾何学問題に使用することができた。
これは 2 つの成分 ―― 横木 (transom) とヤード (yard、 帆桁) ―― から構成される。 横木は垂直成分で、頂上の 0° から基底部の 45° まで目盛りが付いている。 横木の頂上で、視準板 (vane) が搭載され、影を落としている。 ヤード (yard) は水平で、45° から 90° まで目盛りが付いている。 横木とヤードは特別な接続金具 (fitting, 図 6 の 2 重ソケット (socket)) で 結合され、横木の垂直調整とヤード (yhard) の水平調整を独立に可能にした。
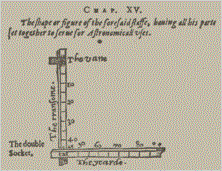
|
| 図 6 - トーマス・フードによるクロス・スタッフ。 クロス・スタッフと呼ばれるが、この機器は太陽の高度測定のために 機器に影を落とすための影視準板を使用する。 |
ヤードを横木の基底部ではなく頂上に設置して、機器を建造することが可能である。
始めは、横木とヤードは、この 2 つがそれぞれ 45° の設定で結合するように設置し、 機器はヤードが水平になるように保持する (この補助のために、ナビゲーターはヤードに沿って水平線を眺めることができる)。 ソケットが緩められ、横木を垂直に移動して、視準板の影が ヤードの 90° 設定に落ちるようにする。 もしも横木だけの動きでこれが達成できれば、 高度は横木の目盛りで与えられる。 もしも、これで太陽が高すぎれば、ソケットのヤードの水平開口部 が緩められ、ヤードを移動して、影が 90° マークに落ちるようにする。 これでヤードが高度を与える。
これは相当に正確な機器である、 というのは目盛りは従来のクロス・スタッフと比較すれば十分に間隔があいているからである。 しかしながら、風があれば、取り扱いが少々やりにくく、困難である。
この機器は、ナビゲーション界におけるバックスタッフ類への末期の追加で、 1748 年にベンジャミン・コール (Benjamin Cole) により発明された。
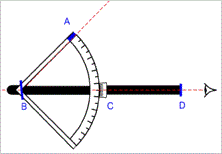
|
| 図 7 - 1748 年のベンジャミン・コールの四分儀 |
この機器は一方の端に旋回する四分儀を持つスタッフから構成されている。 四分儀には目盛り付きスケールの上端 (図 7 の A) に影視準板 (shadow vane) があるが、 これはオプションでデイビスの四分儀のフラムスティード・ガラス (Flamsteed glass) のようなレンズにできる。 これは水平線視準板 (B) に太陽の影を落とすか、太陽の像を射影する。 観測者は照準用視準板 (D) の穴と水平線視準板のスリットを通して水平線を眺め、 機器が水平であることを確かめる。 四分儀成分を回転して、水平線・太陽の影 (太陽の像) が揃うようにする。 次に、高度を四分儀のスケールから読み取ることができる。 読み取りの精度を上げるためには、円形バーニヤをスタッフに搭載する (C)。
このような機器が 18 世紀中頃に導入された事実が示すことは、 八分儀が存在するせよ、四分儀はなお生存可能な機器であったことである。
イングランドの科学者のジョージ・アダムス (George Adams) は同じ時に 非常に類似したバックスタッフを作っている。 アダムスのバージョンが確実にしたことは フラムスティード・ガラスと水平線視準板の間の距離が、視準板と照準用視準板の距離に等しいことである。
エドマンド・ガンター (Edmund Gunter) は 1623 年頃にクロス・ボー四分儀 (船乗りの弓 (mariner's bow) とも呼ぶ) を発明した。 これは弓のクロス・ボー (crossbow) との類似からその名称を得ている。
この機器で興味があるのは、円弧は 120° であるが、90° 円弧として目盛りが振ってあるのみである。 従って、円弧の上の 1° の角度の間隔はわずかに 1° より大きい。 機器の実例には 0° から 90° の目盛り、 あるいは円弧の中央で 0° から 45° の区間が 2 つ折り返されているものがあった。
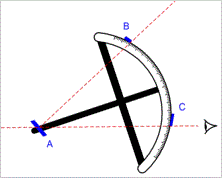
|
| 図 8 - クロス・ボー四分儀の絵、 120° 円弧は 90° 円弧として目盛りが付けられている。 その結果、名目上の円弧サイズよりも少し大きな分割になる。 |
機器には 3 つの視準板がある: 水平線視準板 (図 8 の A, 水平線を観測する開口部)、 影視準板 (B, 水平線視準板に影を落とす)、 照準用視準板 (C, ナビゲーターが水平線視準板で、水平線と影を見るために使用) これは、太陽の高度測定と同時に、 機器の水平性を確保にする役目を果たす。 高度は影視準板と照準用視準板の角度位置の差である。
この機器のバージョンによっては、一年の毎日の太陽の位置が円弧にマークされる。 これにより、ナビゲーターは影視準板を現在の日にセットすることが可能となり、 機器は高度を直接読み取ることになる。