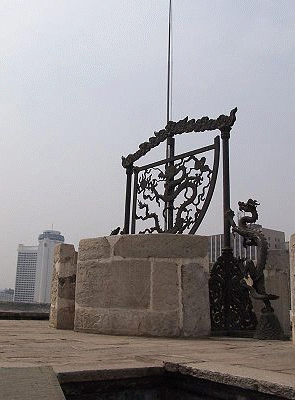
|
| 北京古観象台の 大きな枠組み付き四分儀, 1673 年製造 |
以下の文書は次の翻訳です。
Quadrant (instrument) - Wikipedia
四分儀は 90° までの角度を測定するために使用される機器である。 この機器の異なるバージョンは、 例えば経度、緯度、そして 1 日の時刻などの 色々な測定値を計算するために使用することができる。 これは プトレマイオスにより、 アストロラーベのより好ましい種類として始めて提案された。 この機器の幾つかの異なる変種は後に中世イスラム教天文学者により製造された。 壁面四分儀は 18 世紀のヨーロッパ天文台の重要な天文機器であり、 位置天文学 (positional astronomy) での使用を確立した。
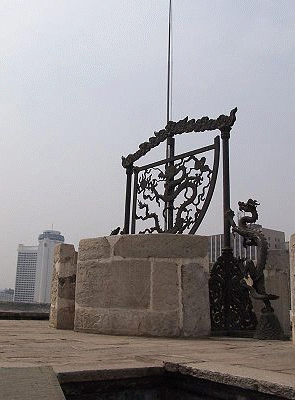
|
| 北京古観象台の 大きな枠組み付き四分儀, 1673 年製造 |
quadrant (クワドラント、四分儀) の用語は 1/4 を意味し、機器の初期のバージョンがアストロラーベに由来する事実を言及した。 四分儀はアストロラーベの作業をアストロラーベの盤面の大きさの 1/4 に 集約した、これは本質的にアストロラーベの 1/4 であった。
古代インドの リグヴェーダの時代の最中に、 'Tureeyam's と呼ばれる四分儀が大きな日食の範囲を測定するのに使用された。 リシ・アトリ (Rishi Atri) による日食観測のための Tureeyam の使用は リグヴェーダの 5 番目のマンダラ (mandala, 巻) に記述され、おおよそ BC 1500 年からBC 1000 年の間が最もあり得る。
四分儀の初期の説明は AD 150 年頃の プトレマイオスの アルマゲスト (Almagest) にもある。 彼は 90° の目盛りをつけた円弧の上のクギ (peg) の 影を射影することにより、正午の太陽の高度を測定する台座 (plinth) を説明した。 この四分儀は、この機器の後のバージョンとは違い、より大きく、 幾つかの可動部分から構成されていた。 プトレマイオスのバージョンはアストロラーベの派生物であり、この原始的な装置の目的は 太陽の子午線の角度を測定するためであった。

|
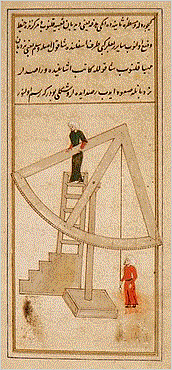
|
| プトレマイオスが四分儀を使う。 | トルコのイラストの四分儀 |
中世イスラム世界の天文学者はこのアイデアの下に改良し、 中東を通して、例えば マラーゲ, レイ そして サマルカンドの天文台に四分儀を建造した。 始めは、この四分儀は普通とても大きく、静止したものであり、 どの方角にも回転でき、任意の天体の高度と方位角の両方を与えた。 イスラム世界の天文学者が天文理論と観測精度で進展するにつれ、 彼らは中世とそれ以後、4 つの異なる形式の四分儀の開発をしたとされている。 その最初のもの ―― 正弦四分儀 (sine quadrant) ―― はバグダッドの 知恵の館 (House of Wisdom) で イブン・ムーサー・アル=フワーリズミー (Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi) に より発明された。 その他のタイプは 普遍四分儀 (universal quadrant)、時の四分儀 (horary quadrant) そしてアストロラーベ四分儀 (astrolabe quadrant) で あった。
中世の間に、これらの機器の知識はヨーロッパに広まった。 13 世紀にユダヤ人天文学者の ヤコブ・ベン・マキル・イブン・ティボン (Jacob ben Machir ibn Tibbon) は 四分儀の更なる発展で極めて重大であった。 彼は熟練した天文学者で、 このトピックに関して何冊かの本を書き、 これには四分儀の改良バージョンの建造・使用の方法を詳細した影響力の ある本が含まれた。 彼が発明した四分儀は novus quadrant あるいは「新四分儀」 (new quadrant) と 呼ばれるようになった。 この装置は革命的であった、というのは、これは幾つかの可動な部分を含まずに建造 された最初の四分儀で、従ってずっと小さく、もっと持ち運べた。
ティボンのヘブライ語の写本はラテン語に翻訳され、デンマーク人学者のピーター・ナイチンゲール ( Peter Nightingale) により 数年後に改良された。 彼の新四分儀が基づいていたアイデアは、 アストロラーベの部品が単一の四分儀に折り畳まれていれば、 平面アストロラーベ (planispheric astrolabe) を定める立体射影はなお動作することである。 その結果、標準的アストロラーベより、はるかに安く、使いやすく、 もっと持ち運びできる機器になった。 ティボンの業績は遠くに届き、 影響したのは コペルニクス, クリストファー・クラヴィウス、そして エラスムス・ラインホルトであり、 そして彼の写本はダンテの 神曲に言及された。
四分儀がより小さく、従って、もっと持ち運びができるようになると、 ナビゲーションでの価値がまもなく明らかとなった。 四分儀の海上ナビゲーションへの最初の記録された使用は 1461 年の ディオゴ・ゴメス ( Diogo Gomes) によっていた。 船乗りは北極星の高度を測定することにより、緯度を確かめ始めた。 四分儀のこの応用は一般にアラビアの船乗りによっており、 彼らはアフリカの東海岸に沿ってトレードをして、 しばしば陸地を見ずに移動した。 まもなく、北極星は赤道の南では見えないという事実によって、 与えられた時刻に太陽の高度を測定することが、すぐにもっと普通になった。
1618 年に、イングランドの数学者の エドマンド・ガンターは 1 つの発明で四分儀を更に順応させ、 これはガンター四分儀 (Gunther quadrant) と呼ばれるようになった。 このポケット・サイズの四分儀は革命的であった、 というのは、これには、回帰線, 赤道, 水平線, 黄道の射影が刻まれていたからである。 正しい表があれば、この四分儀の使用でわかることは、 時刻, 日付, 昼夜の長さ, 日の出・日の入りの時刻、 そして子午線 (meridian) であった。 ガンター四分儀は極めて便利であったが、欠点があった: 緯度が特定の場合のみ目盛りが正しく、従って海での機器使用は限定された。
四分儀には幾つかの形式がある。
次のようにも分類できる。
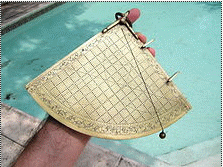
|
| 正弦四分儀 |
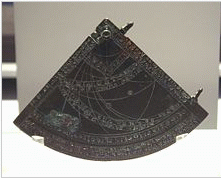
|
| アストロラーベ四分儀 |
幾何学的四分儀は通常、木もしくは真鍮の 1/4 円のパネルである。 表面の印は、紙に印刷して木に張り付けるか、表面に直接印刷した。 真鍮の機器では印は真鍮に直接刻まれていた。
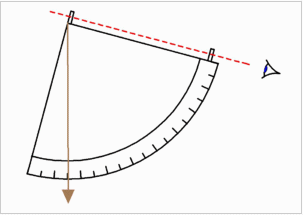
|
| 鉛のおもりが付いた幾何学的四分儀 |
海洋ナビゲーション用の最も初期の実例は 1460 年頃のものが見つかっている。 これらは角度の目盛りが付いておらず、最も普通の目的地の緯度は直接、周囲に刻まれていた。 使用時には、ナビゲーターは、四分儀で目的地の緯度に達するまで北か南に帆走し、 次に目的地の方向に向きを変えて一定の緯度を維持して目的地に帆走した。 1480 年の後では、機器の多くは、角度の目盛りが周囲に付いていた。
一つの端に沿った 2 つの照準は アリダードを形成した。 重りが頂上の円弧の中心から紐で吊るされていた。
星の高度測定には、観測者は照準を通して星を眺め、四分儀を保持して機器の平面が垂直になるようにした。 重りが垂直に垂れ下げられ、紐が円弧の目盛りの読み取りを与えた。 最初の人が観測に専念して、機器を適切な位置に保持している間、 2 番目の人が読み取りをすることは珍しいわけではなかった。
機器の精度はその大きさと、風や観測者の動きが重りに及ぼす効果により制限された。 動揺する船の甲板上のナビゲーターにとり、このような制限は克服することが困難であった。
太陽の高度測定で、太陽を凝視することを避けるために、ナビゲーターは機器を前に保持して、 太陽を側方にすることができる。 太陽方向の照準用視準板 (sighting vane) が後方視準板に影を落とさせることにより、 機器を太陽に揃えることが可能であった。 太陽の中心の高度決定を保証するために注意する必要があり、 影の本影の上部と下部の高度を平均して実施した。
太陽の高度測定のために、後方観測四分儀が開発された。
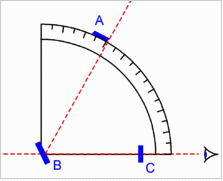
|
| 後方観測四分儀の絵。この機器は バックスタッフ (backstaff) の方法で使用され、 機器における影の位置を観測することにより、 太陽の高度を測定。 |
観測者は影板 (shadow vane, A) を目盛り付スケールの上で移動して、 影が水平線視準板の水平線レベルと一致するようにした。 この角度が太陽の高度である。
大きな枠組み付き四分儀が天体観測 (とりわけ天体の高度決定) に使用された。 これは恒久的な装置 (例えば壁面四分儀) のことも あった。小さな四分儀は動かすことができた。 類似の 天文用六分儀のように、垂直面で使用したり、 任意の平面に調節することもできた。
この建造・使用の詳細は本質的に 天文用六分儀のものと同じである; 詳細はこの記事を参照せよ。
海軍 : 船舶の大砲 (cannon) の仰角を測定するのに使用された。 四分儀は、各大砲の装填後に射程を判断するために、トラニオン (trunnion, 砲耳) に 設置しなければならなかった。 読み取りは船の横揺れの頂点で実施された。横揺れの頂点で大砲が再び補正・チェックされ、 次の大砲が処理され、点火する大砲すべての用意ができるまで継続した。 船の砲撃将校 (Gunner) に伝達され、彼は船長に伝達した : ... 用意ができれば点火命令を下すことができます。.. 次の高い横波で、大砲を点火することになる。
もっと現代的な応用では、四分儀はトラニオン・リング (trunnion ring) に 付属するか、大きな海軍の大砲の場合には、 船の甲板に溶接された測量基準点 (benchmarks) に揃えられている。 これが実施されるのは、大砲が甲板をゆがめないことを確実にするためである。 旋回砲塔の平坦な表面も測量基準点に対してチェックされ、 大砲の射程距離測定のために、 大きな軸受け (bearing) [且つ/あるいは] 軸受けレース (bearing race) に変化がなかったことを 確かめた。
中世には製造業者はしばしばカスタム化を追加して四分儀の所有者を印象付けた。 機器の未使用の広いスペースに、印あるいはバッジを追加して、 重要人物による所有権、あるいは所有者の忠義を示した。