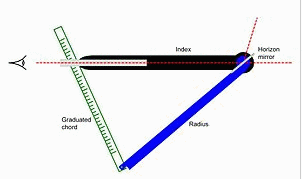
|
| フックの反射機器の典型的描写。 これは計器の細部の正確な描写ではなく、 基本機能の描写。 望遠鏡を搭載したインデックス・アームは黒で表示、 鏡 (灰色) の付いた放射アームは青で表示。 弦は白地に緑、 照準直線は赤の点線で表示 |
以下の文書は次の翻訳です。
Reflecting instrument - Wikipedia (反射機器)
反射機器は測定機能を強化するために鏡を使用する計器のことである。 特に鏡の使用により、2 つのオブジェクト間の角距離 (angular distance) の測定中に、 2 つのオブジェクトの同時観測を 可能にする。 反射機器は多くの職業で使用されるが、 これらは本質的に天測ナビゲーションと結びついている。 というのは、ナビゲーションの問題 ―― とりわけ経度の問題 ―― を解決する必要性が、 この開発の主要な動機であったからである。
反射機器の目的は、観測者が天体の高度、あるいは 2 つの天体間の角距離の測定を可能にすることである。 ここで議論する開発の背後にある原動力は 海上での経度決定問題の解決であった。 この問題の解決には角度測定の正確な方法が必要と理解され、 精度は 2 つの天体を同時に観測することにより、この角度を測定する観測者の能力に依存すると理解された。
それ以前の計器の欠陥はよく知られていた。 2 つの異なる照準線で 2 つの天体を観測することが要求されれば、誤差の可能性が増えた。 この問題を考察した人々は金属鏡 (現代用語では鏡) を使用すれば 同一の視野で 2 つの天体を観測することが可能となることに気が付いた。 引き続いて一連の発明と改良があり、 これにより経度の決定に必要となる精度を越える点まで機器を改良した。 これ以上の改良は、まったく別な技術が必要とされた。
初期の反射機器の幾つかは ロバート・フック や アイザック・ニュートン のような科学者によって提案された。 これらは、ほとんど使用されなかったか、製造されなかったか、徹底的にテストされることもなかった。 ヴァン・ブリーン (van Breen) の機器が例外で、これはオランダ人により使用された点である。 しかしながら、これはオランダの外部にはほとんど影響を与えなかった。
1660 年にオランダ人の ジュースト・ヴァン・ブリーン (Joost van Breen) により 発明された spiegelboog (ミラー・スタッフ) は 反射クロス・スタッフである。 この装置は主に オランダ東インド会社 (Zeeland Chamber of the VOC) でほぼ 100 年間使用された。
フックの機器は一重反射機器であった。 これは一つの鏡を使用して、観測者の目に天体の像を反射させた。 この機器は 1666 年に始めて記述され、その後しばらくしてからフックは 動作モデルを 王立学会の会合で提示した。
装置は 3 つの主要な部品 ―― インデックス・アーム (index arm)、 放射アーム (radial arm)、目盛りを付けた弦 ―― から構成された。 これらの 3 つの部品は下の絵のように三角形に配置された。 望遠鏡照準はインデックス・アームに搭載された。 放射アームの回転ポイントには 1 個の鏡が搭載されていた。 この回転ポイントにより、インデックス・アームと放射アームの成す角度を変化させること ができた。 目盛りのついた弦が放射アームの反対の端に接続し、 弦は端のまわりに回転できた。 弦はインデックス・アームの遠い端に押し付けられて、これに沿ってスライドした。 弦の目盛りは一様で、 これによりインデックス・アームの端と放射アームの端の距離を測定して 2 つのアームの間の角度を測定できた。 弦の表で距離から角度に変換された。 鏡使用のため、測定角はインデックス・アームと放射アームの角度の 2 倍である。。
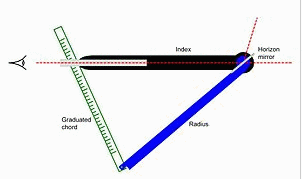
|
| フックの反射機器の典型的描写。 これは計器の細部の正確な描写ではなく、 基本機能の描写。 望遠鏡を搭載したインデックス・アームは黒で表示、 鏡 (灰色) の付いた放射アームは青で表示。 弦は白地に緑、 照準直線は赤の点線で表示 |
放射アームの鏡は十分小さいので、観測者は天体の像を望遠鏡の視野の半分に見ながら、 当時に他の半分でまっすぐ前を見ることができた。 これにより観測者はどちらのオブジェクトも同時に見ることが可能であった。 望遠鏡の視野に 2 つの天体を一緒にそろえることにより、2 つの天体の間の角距離が、 目盛りを付けた弦に表示されることになった。
フックの機器は斬新で当時、少しは注意を引いたが、海上テストをした証拠がない。 この機器はほとんど使用されず、天文学にもナビゲーションにも重要な影響を与えなかった。
1692 年に エドモンド・ハレーは、 王立学会に反射機器のデザインを提示した。
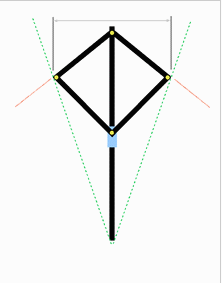
これ (ハレーの反射機器) は興味ある計器でラジオ・ラチーノ (radio latino, 上の訳注参照) の機能に二重望遠鏡を組み合わせている。 望遠鏡 (下の図では AB) は一方の端に接眼レンズがあり、中間に鏡 (D) があって、 反対の端には対物レンズ (B) がある。 鏡は視野の半分 (左もしくは右) をさえぎるのみで、 残りの半分でオブジェクトを見ることができる。 鏡で反射されるのは第二の対物レンズ (C) からの像である。 これにより、観測者が見ることができるのは、まっすぐ通り抜けた像と反射された像であり、同時に互いの横に見えた。 絶対に必要なことは 2 つの対物レンズの焦点距離の長さが同一で、鏡からの距離が 同一であることである。もしもこの条件が満足されなければ、2 つの像は共通の焦点に 合わせることができない。
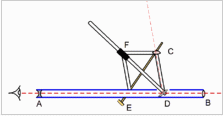
|
| ハレーの反射機器の描画。 望遠鏡は (切り開いて) 青の線、鏡とレンズは灰色。 赤の点線は照準線 |
鏡は装置の一部である radio latino の棒 (DF) に搭載され、 これと共に回転する。 radio latino のひし形の側面と望遠鏡の成す角は、radio latino の 対角線の長さ調節で設定される。 これを容易にし、更に角度の微調整を可能にするために、スクリュー (ねじ) (EC) が搭載され、観測者が 2 つの頂点 (E と C) の間の距離を 変更することができる。
観測者は直接のレンズの視界で水平線を照準に合わせ、鏡で天体を照準に合わせる。 2 つの像を直接隣接させるようにスクリューを回して、計器をセットする。 E と C の間のスクリューの長さをはかり、弦の表で角度に変換して、 角度が決定される。
ハレーは望遠鏡の筒の断面を長方形に指定した。 こうすれば製造が容易であるが、別の断面にすることができるので条件ではない。 radio latino の 4 辺 (CD, DE, EF, FC) の長さは等しくする必要がある。 この理由は望遠鏡と対物レンズ側の角度 (ADC) が 望遠鏡と鏡の角度 (ADF) の正確に 2 倍とする必要があるからである。 (言い換えると、入射角と反射角が等しくなるようにする。) そうでないと計器の照準が狂い、測定結果にエラーが生じる。
天体の高度は (radio latino の) 棒のスライダーの位置の目盛りから決定できる。 しかしながら、これはハレーが計器をデザインした方法ではない。 これが示唆することは、全体的な機器のデザインが radio latino と一致していることはただの偶然で、 ハレーは radio latino に詳しくなかったかもしれないことである。
この計器が海上でテストされたか否かに関しては不明である。
ニュートンの反射四分儀は多くの点で、これに続く ハドレーの最初の反射四分儀に 類似していた。
ニュートンは 1699 年頃にエドモンド・ハレーに そのデザインを知らせている。 しかしながら、ハレーはこの文書に関して何もせず、 彼の死後に発見された書類の中に見つかったのみである。 しかしながら、1731 年にハドレーが彼の反射四分儀を王立学会に 提示した時に、ハレーは王立学会の会員にニュートンのデザインのことを 論じた。 ハレーはハドレーのデザインがより以前のニュートンの機器と全く類似していることを 指摘した。
この不注意による隠匿から、ニュートンの発明は反射機器の 開発に、ほとんど役割を演じなかった。
八分儀の発明で注目に値する点は短い期間に独立にこの装置を発明した人の数にある。 ジョーン・ハドレーとトーマス・ゴッドフリー ( Thomas Godfrey) は共に八分儀を発明したと されている。彼らは独立に 1731 年頃に同じ装置を開発した。 しかしながら彼らだけが発明したのではない。
ハドレーの場合には 2 つの機器がデザインされた。 最初のものはニュートンの反射四分儀にとてもよく似た機器であった。 第二のものは現代の六分儀と基本的に同じ形式であった。 最初のデザインはほとんど製造されなかった。 一方で、第二のデザインは標準的なものとなり、 これから六分儀が派生し、六分儀と共に天測ナビゲーションに使用され、 それ以前のすべてのナビゲーション機器の代わりになった。
カレブ・スミス (Caleb Smith) は イングランドの保険仲介人 (insurance broker) で天文学に非常に興味をもっており、 1734 年に八分儀を建造した。 彼はそれを「天体スコープ」もしくは「海洋四分儀」と呼んだ。 彼は反射面を提供するために、インデックス・ミラーに加えて、固定プリズムを使用した。 研磨した金属鏡面の質が低く、 鏡の銀メッキと 平らで平行な面を持つガラスの製造が共に困難な時代においては プリズムは鏡よりは有利であった。 しかしながら、スミスの機器の他のデザイン要素がハドレーの八分儀よりも質が低く、 著しく使用されなかった。
ジャンポール・フーシー (Jean-Paul Fouchy) はフランスの数学教授で、天文学者であったが、 1732 年に八分儀を発明した。 彼の八分儀はハドレーのものと基本的には同じであった。 フーシーは当時のイングランドにおける発展を知らなかった。 というのは 2 つの国の計器製造者の間のコミュニケーションが限定されていたことと、 王立学会の出版物、とりわけ学会誌 (Philosophical Transactions) はフランスでは配布されていなかったからである。 フーシーの八分儀はハドレーの八分儀により影が薄くなった。
六分儀の起源は直接的で、議論の余地がない。 ジョン・キャンベル提督 ( Admiral John Campbell) が、 月からの距離 (lunar distance, 月距) 方法の海上試験で ハドレーの八分儀では十分でないことに気が付いた。 90° では月からの距離方法で必要となる角距離によっては、測定で不十分であった。 彼は角度を 120° に増やすことを提案し、六分儀ができた。 ジョン・バードは 1757 年にそのような最初の六分儀を製造した。
六分儀の開発と共に、八分儀は二流の機器のようになった。 八分儀は時にはすべて真鍮で製造することもあったが、主に木造フレームの機器のまゝであった。 向上した材料と製造技術の進展の大半が、六分儀のために留保された。
木製の六分儀の実例もあるが、 大半は真鍮で製造されている。 フレームに剛性を持たせるために、計器製造業者は分厚いフレームを使用した。 これにより計器が重くなる欠点があり、 ナビゲーターが重さに逆らって作業をすると、手ぶれにより不正確となった。 この問題を避けるために、フレームが変更された。 エドワード・トラウトン ( Edward Troughton) は 1788 年に二重フレーム六分儀の特許を取った。 これは平行な 2 つの枠を使用し、間に仕切り (spacer) を入れた。 2 つのフレームはおよそ 1 cm 離れていた。 これによりフレームの剛性が随分と向上した。 初期のバージョンでは第二の枠は計器の上部の部分を覆っていたのみで、 これにより鏡と望遠鏡をしっかり固定した。 後のバージョンでは 2 つの完全なフレームが使用された。 仕切り (spacer) は小さなピラー (柱、pillar) のように見えたため、 「ピラー六分儀」とも呼ばれた。
トラウトンは別の材料でも実験をした。 目盛りを銀、金、プラチナでメッキした。 金とプラチナは腐食の問題を最小にした。 プラチナ・メッキの機器は金属が希少なため高価であったが、 金ほど高価ではなかった。 トラウトンは王立学会を通じて ウィリアム・ハイド・ウォラストン (William Hyde Wollaston) と 知り合いで、これにより貴金属を手に入れることができた。 トラウトンの会社で作られた機器でプラチナを使用したものは、 フレームに刻印された Platina (プラチナ) の言葉ですぐに識別できた。 このような計器は、収集家には非常に高く評価され、 製造時と同様に今日でも正確である。
デバイディング・エンジンの開発が進展するにつれ、 六分儀はもっと正確に、そしてもっと小さくすることができた。 バーニヤ・スケールの簡単な読み取りを可能にするために、 小さな拡大鏡が追加された。 これに加えてフレームのぎらつきを軽減するために、 幾つかの六分儀では、光を和らげるために拡大鏡のまわりに 散光器 (diffuser) を取り付けた。 精度が増大すると、円弧のバーニヤ・スケールが ドラム式のバーニヤ・スケールで置き換えられた。
フレームのデザインが時間と共に変更され、温度変化で悪影響を受けないものとなった。 このようなフレームのパターンは標準化され、 多くの異なる製造業者の多くの機器に同じ一般的な概形を見ることができる。
価格を下げるために、現代の六分儀では精密プラスチック製のものが手に入る。 このような六分儀は軽くて、価格が手頃で、しかも高品質である。

|
| 半世紀以上も使用された六分儀。 このフレームは標準デザインの一つである 「3 個の輪」を使用。 適切な剛性を保持しながら、熱膨張を避けるために 使用されたデザインの一つ。 |
「六分儀」の用語を聞けば、大半の人はナビゲーションを考えるが、 この機器は他の職業にも使用されてきた。
これらの型式に加え、色々な六分儀を表す用語がある。
ピラー六分儀は次のいずれかである。
前者の方が、用語の最も普通な用法である。
幾つかの製造業者は円周の 8 分の 1 ないしは 6 分の 1 以外の大きさの機器を提供した。 最も普通なものの 1 つは五分儀 (72° 円弧、144° まで読み取り可) であった。 他のサイズも利用可能であったが、変則的なサイズは決して普通にならなかった。 多くの機器は例えば 135° まで読み取れる目盛りが付いていたが、 単に六分儀と呼ばれた。同様に 100° の八分儀があった。 しかし、これらはユニークな形式の機器として別扱いされていない。
特別な目的のために、もっと大きな機器に対して関心があった。 とりわけ完全円の計器がいくつか製造され、 反射円儀 (reflecting circle) と反復円儀 (repeating circle) として製造・分類された。
反射円儀は 1752 年にドイツの幾何学者で天文学者である トビアス・マイヤー (Tobias Mayer) により発明され、 その詳細が 1767 年に出版された。 彼の開発は六分儀に先行し、 すぐれた測量計器を製造することの必要性に動機づけられた。
反射円儀は完全円の機器で 720° まで目盛りが付いていた。 (天体間の距離測定には 180° 以上の角度は必要性がない。 というのは最少距離は常に 180° 以下だからである。) マイヤーはこの装置の詳細な記述を経度委員会に提出し、 ジョン・バードはこの情報を使用して、 直径 16 インチのものを海軍で評価するために製造した。 この機器はジョン・キャンベル提督 ( Admiral John Campbell) が 「月からの距離方式」の評価期間に使用したものの一つであった。 この計器は 360° まで目盛りが付いていたという点で違っており、 とても重かったためベルトに装着する支えが取り付けてあった。 これはハドレーの八分儀よりも良いわけではなく、 又、使用に際して不便でもあった。 その結果キャンベルは六分儀の製造を勧告した。
ジャン・シャルル・ド・ボルダ は更に反射円儀を開発した。 彼は望遠鏡の照準位置を変更して、 鏡が望遠鏡のどちら側からも像を受け取るようにした。 これにより、0 を読み取る時に、 鏡が正確に平行であることを確認する必要がなくなった。 これにより計器の使用が単純化された。 更なる改良が、エティエンヌ・ルノワール ( Etienne Lenoir) の助けで実施された。 2 人は 1777 年に最終的な形に改良した。 この計器は非常に独特であったため、ボルダ円儀 (Borda circle) あるいは反復円儀 (repeating circle) と呼ばれた。 ボルダ (Borda) とルノワール (Lenoir) はこの機器を 測地測量 (geodesic surveying) のために開発した。 これは天体測定のために使用されたのではないので、二重鏡映 (double reflection) を 使用せずに、2 つの望遠鏡照準で交代した。 そのため、これは反射機器ではなかった。 有名な機器製造家のジェシー・ラムスデン (Jesse Ramsden) によって作られた グレート・セオドライトと 同等なものとして著名であった。
ジョセフ・デ・メンドーザ・イ・リオス ( Josef de Mendoza y Rios) はボルダの反射円儀のデザインをやり直した (ロンドン 1801 年)。 目的は、王立学会で出版された彼の「月の表」(Lunar Tables, ロンドン 1805 年) と 共に使用することであった。 彼のデザインには 2 つの同心円と一つの バーニヤ・スケールがあり、 エラー低減のため、連続する 3 回の読み取りを平均することを勧めた。 ボルダのシステムは、円周が 360° ではなく 400 グラード (grad) であるものに基づいていた。 (ボルダは何年もの間円周を 400° に分割して表の計算をした。) メンドーザの「月の表」はほとんど 19 世紀全体を通して使用された。

|
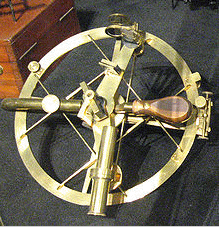
|
|
ボルダの反射円儀
ツーロンの海軍博物館に展示 |
メンドーザ (Mendoza) の反射円儀
国立海洋博物館に展示 (Musée national de la Marine) |
エドワード・トラウトン ( Edward Troughton) も反射円儀を変更した。 彼のデザインでは 3 つのインデックス・アームとバーニヤ・スケールが付いていた。 これにより、同時に 3 通りの読み取りが可能となり、平均を取ってエラーを低減した。
反射円儀はナビゲーション機器として、 英国海軍よりは仏国海軍でより人気があった。
ブリス六分儀 ( Bris sextant) は真の六分儀ではないが、真の反射機器で、 二重反射の原理に基づき、普通の八分儀や六分儀と同じ 規則と誤差にさらされる。 普通の八分儀と六分儀と違い、 ブリス六分儀は幾つかの特別な角度を正確に測定できる固定角度計器である。 この点で、計器の範囲内であれば、 任意の角度を測定できる他の反射計機器とは違っている。 太陽や月の高度の決定に、とりわけ都合がよい。
フランシス・ロナルズ ( Francis Ronalds) は 1829 年に八分儀を変更して角度を記録する機器を発明した。 測量における応用で反射機器の不利な点は、 鏡とインデックス・アームが分離角の半分で回転することを光学が規定することである。 従って角度は、読み取り・書き留めてから、分度器を使用して図面に引く必要がある。 ロナルズのアイデアは、鏡の角度の 2 倍で回転するようにインデックス・アームを設定して、 描画の時に正確な角度で直線を引くのにアームを使用した。 彼は機器の基礎として比例コンパス (sector) を使用し、 一方の先端 (tip) に水平線ガラス (horizon glass) を置き、 2 つのルーラー (ruler) をつなぐ蝶番 (hinge) の近くにインデックス・ミラーを置いた。 2 つの回転要素は機械的に接続され、鏡を支える円筒は要求された角度の比を 与えるために蝶番の直径の 2 倍であった。