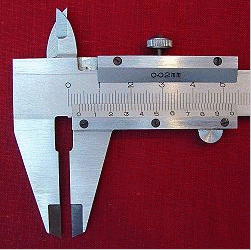
|
| ノギスのスケール、主目盛が上、バーニヤ目盛が下。 測定値は 3.58 ± 0.02、 固定主スケールの 3.00 mm (左の赤マーク) に バーニヤ・スケールの 0.58 mm (右の赤マーク) を追加。 主スケールの読み取りはバーニヤ目盛の左で、 バーニヤ目盛の読み取りは 2 つの目盛の間でもっともそろっている直線の位置です。 0.02 mm の刻みが示すことはノギスの解像度とこの機器の「バーニヤ定数」です。 |
以下の文書は次の翻訳です。
Vernier scale - Wikipedia (バーニヤ・スケール, バーニヤ目盛)
上の項目に対応する日本語 Wikipedia (リンクが張ってある項目) は ノギス ですが バーニヤ もあります。 しかし、これらの項目には直線状の目盛のことしかでてきません。 英語版のバーニヤ・スケール (バーニヤ目盛) では角度を測るための円弧の目盛 (八分儀、六分儀) の場合も含まれ、バーニヤ・スケールの意味が広くなっています。 八分儀のバーニヤ・スケールに関しては 八分儀 に写真が登場します。
バーニヤ以前にはノニウスの装置があり、これがノギスの語源です。 ノニウスの装置のおおよその説明が デバイディング・エンジンに登場しており、これはノギスのようなキャリパー (はさんで長さを測定する装置) ではなく、 角度測定用の特殊な目盛なので、バーニヤ・スケールとノニウスは別物です。
スケールとは定規、目盛の意味があり、バーニヤ・スケールは定規の意味 (副尺) になることも、 その上に付けられた目盛の意味になることもあり、後者の場合にはバーニヤ目盛と訳します。 メイン・スケールも目盛を考えている場合にはメイン目盛 (主目盛) のように訳し方を変える方がわかりやすくなります。
バーニヤ・スケール (/vərˈniːˈər/ ver-NEE-er) は、 ピエール・ベルニエ (Pierre Vernier) に ちなんで名付けられ、 線形スケールにおける 2 つの目盛の間で 機械的補完 (mechanical interpolation) を使用して、 正確な測定をするための視的補助 (visulal aid) である。 これにより、バーニヤ鋭敏 (vernier acuity) を使用して解像度を上げ、測定の不確かさを軽減し、 人間の評価エラーを軽減する。 これは長さ測定や角度測定の多くの形式の機器に 見ることができる、とりわけノギス (vernier caliper) に見られる、 これはヒューマンスケールのオブジェクト (内径と外径を含む) の長さを測定する。
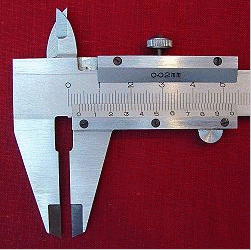
|
| ノギスのスケール、主目盛が上、バーニヤ目盛が下。 測定値は 3.58 ± 0.02、 固定主スケールの 3.00 mm (左の赤マーク) に バーニヤ・スケールの 0.58 mm (右の赤マーク) を追加。 主スケールの読み取りはバーニヤ目盛の左で、 バーニヤ目盛の読み取りは 2 つの目盛の間でもっともそろっている直線の位置です。 0.02 mm の刻みが示すことはノギスの解像度とこの機器の「バーニヤ定数」です。 |
バーニヤは補助スケールで、単一測定値のポインターの代わりとなり、 例えば 10 分割が、長さで主目盛の 9 分割に等しい。 補完された読み取り (interpolated reading) を得るのは、 バーニヤ目盛のどの目盛が主スケールの目盛と一致しているかの観察によっており、 2 点間の視的見積もりよりもわかりやすい。 そのような取り決めはバーニヤ定数 (vernier constant) と呼ばれる、 高い目盛の比率を使用することで高解像度になる。 バーニヤは単純な線形の仕組みが適切な場合に 円形あるいは直線の目盛で使用できる。 実例には、精密な許容誤差で測定するキャリパー (caliper) と マイクロメーターがあり、 これが搭載されているのは、 ナビゲーション用 六分儀、測量用 セオドライト、そして一般に科学用機器である。 補完 (interpolation) のバーニヤ原理 (Vernier principle) は、 電子測定システムの一部分として、 線形あるいは回転運動を測定するためのアブソリュート・エンコーダー (Absolute encoder) のような、 電子変位センサー (electronic displacement sensor) でも使用される。
余剰の精度に貢献した第 2 のスケールのついた最初のノギス (caliper) は、 1631 年にフランスの数学者 ピエール・ベルニエ (1580 年 - 1637 年) により 発明された。 この使用は数学者且つ歴史家のジョン・バロウ ( John Barrow) により、 「ナビガティオ・ブリタニカ」 (Navigatio Britannica (英国のナビゲーション), 1570 年) に英語で詳細に説明された。 ノギス (calipers) は今日、最も典型的なバーニヤ・スケールの使用例であるが、 これらは元々は天文 四分儀のような角度測定機器のために開発された。
言語によってはバーニヤ・スケールはポルトガル人の数学者且つ宇宙構造論者 (cosmographer) の ペドロ・ヌネシュ (Pedro Nunes, ラテン名 ペトロス・ノニウス (Petrus Nonius), 1502 年 - 1578 年) にちなんでノニウス (nonius) と呼ばれている。 この用語は 18 世紀末まで英語で使用された。ノニウスは今では、ヌネシュが開発した初期の機器を言及している。 バーニヤの名称は、フランスの天文学者の ジェローム・ラランド (1732 年 – 1807 年) により、 彼の 「天文学の論説」 (Traité d'astronomie, 2 巻、1764 年) を通して世に広まった。
バーニヤ・スケールの使用例は、 オブジェクトの内径・外径を測定するノギスで 示される。
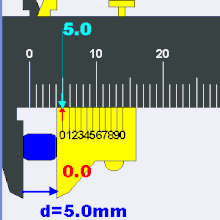
|
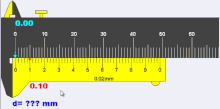
|
|
操作を見やすくするため、 ノギスのバーニヤ定数は 0.1。 通常、ノギスのバーニヤ定数は 0.02。 |
通常の 0.02 バーニヤ定数、 オブジェクトの測定は 19.44 mm (小数点以下 2 桁まで) |
バーニヤ目盛は固定した主目盛の間隔の一定割合で間隔を空ける。 従って、定数 0.1 のバーニヤに対して、バーニヤの各目盛は主目盛の 9/10 の間隔を空ける。 もしも 2 つの目盛をゼロで揃えれば、バーニヤ目盛の 最初の目盛は主目盛の目盛より 1/10 短く、2 番目の目盛は 2/10 短く、 これが 9 番目の目盛まで続き、ここで 9/10 ずれる。 完全に 10 番目の目盛まで数えれば目盛がそろう。 というのは 10/10 (=主目盛の単位) 短いからで、 従って主目盛の 9 番目の目盛に揃う。 (単純には、各 VSD (Vernier Scale Division) = 0.9 MSD (Main Scale Division), 従って、各長さの減少量 0.1 を 10 回加えると、 始めて 1 個の MSD になる。)
もしもバーニヤをわずかに ―― 例えば固定した主目盛の 1/10 ―― 動かせば、 目盛の組で揃うのは、最初の組である。というのは、ここが元々 1/10 ずれている唯一の場所だからである。 わずかに動かす量が 2/10 であれば 2 番目の組が揃う。これが元々 2/10 ずれている唯一の場所だからである。 わずかに動かす量が 5/10 であれば 5 番目の組が揃う、等々。 どのように動かしても、唯一の組が揃い、この組が固定した主目盛の目盛間の値を示している。
1 つの主目盛分割 (main scale division) の長さと 1 つのバーニヤ目盛分割 (bernier scale division) の長さ の違いはバーニヤ最小測定単位 (least count of the vernier) と呼ばれ、 これはバーニヤ定数 (vernier constant) とも呼ばれる。 最小の主目盛の大きさ、すなわち連続する主目盛間の距離 (ピッチ (pitch) とも呼ばれる) を S とし、 連続するバーニヤ目盛間の距離を V とし、 (n - 1) 個の主目盛分割が n 個のバーニヤ目盛分割に等しいとする。 すると
| 主目盛分割 (n-1) 個の長さ | = | バーニヤ目盛分割 n 個の長さ、従って |
| (n-1)S | = | nV、従って |
| nS - S | = | nV, 従って、最小測定単位 S - V = S/n |
バーニヤ・スケールは非常にうまく動作する。 というのは、大半の人はどの直線が揃っているか否かを見出すのに、とりわけ卓越し、 能力は実践で向上し、目の光学機能を越えている。 この揃っていることを検知する能力はバーニヤ鋭敏 (vernier acuity) と呼ばれる。 歴史的には代替技術のどれも、これも他の超鋭敏 (hyperacuity) を 使用しておらず、バーニヤ目盛に競合相手以上に利点を与えた。
ゼロ誤差は、測定機器がゼロ位置で、ゼロでない値を示す状態として定義される。 ノギス場合は、主目盛の 0 がバーニヤ目盛の 0 と一致していない場合である。 ゼロ誤差には 2 つのタイプがある : 目盛が 0 より大きい数に向かっている時、これは正である。そうでなければ負である。 バーニヤ・スケール、あるいはノギスをゼロ誤差 (zero error) で使用する 方法は次の公式を使用することである。
実際の測定値 (actural reading) = 主目盛 + バーニヤ目盛 - (ゼロ誤差)
ゼロ誤差は強打などによる損傷によって生じることがあり、 これにより、ノギスの顎 (jaws) が完全に閉じている時、あるいは互いに接触しかけている時に、0.00mm のマークがずれる。
正のゼロ誤差 (positive zero error) が言及することは、ノギスの顎 (jaws) が単に閉じて、観測値が実際の 0.00 mm より大きい正の 観測値である時である。 もしも観測値が 0.10 mm であれば、ゼロ誤差は +0.10 mm として言及される。
負のゼロ誤差 (negative zero error) が言及することは、ノギスの顎 (jaws) が単に閉じて、観測値が実際の 0.00 mm より小さい負の 観測値である時である。 もしも観測値が 0.08 mm であれば、ゼロ誤差は -0.08 mm として言及される。
もしも正であれば、誤差は機器が読み取る平均観測値から引く。 従って機器が 4.39 cm を読み取り、誤差が +0.05 であれば、実際の長さは 4.39 - 0.05 = 4.34 である。 もしも負であれば、誤差は機器の読み取る平均観測値に加える。 従って機器が 4.39 cm を読み取り、上と同様に誤差が -0.05 cm であれば、実際の長さは 4.39 + 0.05 = 4.44 である。 (このように考えて、この値はゼロ補正と呼ばれる。 これは常に観測値に代数的に追加されて正しい値になる。)
ゼロ誤差 (ZE) = ±n × 最小測定単位 (least count, LC)
順行バーニヤ (Direct verniers) は最も普通である。 指示目盛 (indicating scale) の作成は、 ゼロの点が、データ目盛の開始点と一致する時に 、 目盛付けがデータ目盛のものよりも、わずかに小さく、 最後の目盛を除いて、データ目盛付けと一致しないことである。 指示目盛 N 目盛は、 データ目盛 N-1 目盛に及んでいる。
逆行バーニヤ (retrograde vernier) は幾つかの機器に見い出され、 これに測量機器が含まれる。 逆行バーニヤは順行バーニヤに類似するが、 目盛 (の間隔) が主目盛よりは、わずかに大きい点が違っている。 指示目盛 N 目盛は データ目盛 N+1 目盛に及んでいる。 逆行バーニヤはデータ目盛に沿って後方に延長もする。
順行バーニヤと逆行バーニヤは同じ方法で読み取る。
この節に含まれるのは、 精密解像度測定をするためのバーニヤ原理を使用する技術への言及である。
バーニヤ分光学 (Vernier spectroscopy) はキャビティ増強 (cavity-enhanced) をするレーザー吸収分光学 (laser absorption spectroscopy) のタイプで、微量ガス (trace gases) にとりわけ鋭敏である。 この方法は 周波数コム・レーザー (frequency-comb laser) に高フィネス (high-finesse) 光学共振器 (optical cavity) と組み合わせて、 高度な並列方式で吸収スペクトル (absorption spectrum) を生成する。 この方法は有効な光学経路長 (optical path length) における光学共振器 (optical resonator) の増強効果 (enhancement effect) により とても低濃度の微量ガスの検知も可能である。