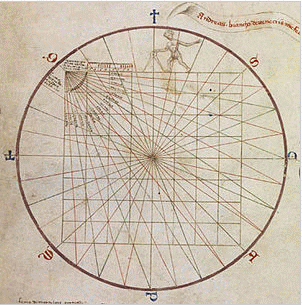
|
|
トンド・エ・クアドロ(tondo e quadro, 円と正方形)
アンドレア・ビアンコ (Andrea Bianco) の 1436 年の地図帳から |
以下の文書は次の翻訳です。
Rule of marteloio - Wikipedia (マルテロイオの方法)
rule とは、規則、法則の意味ですが、少し大仰に響くので、ここでは「方法」と訳し rule of maruteloio を「マルテロイオの方法」と訳することにします。 マルテロイオの方法とは羅針盤によるナビゲーションの方法で、緯度は使用しません。 「リーグの統率」(regiment of league) が登場します。但し、これは大西洋の横断の場合のみのようです (地球が丸いことを組み込んでいないので誤差がでる)。十把一絡げで推測航法と呼ばれ、三角法を航海に組み、 ルネッサンスを契機にしてヨーロッパに登場したものと思われます。
羅針盤もコンパスも英語では compass で、区別がありません。 日本では通常コンパスは携帯コンパスのように針が回転するもので、 羅針盤はコンパス・カードが回転するものを指すことが多いようです。しかし、この型式の羅針盤が発明されるのが 1300 年頃で、 それ以前の船乗りのコンパスは携帯コンパスのように針が回転するものです。「マルテロイオの方法」は 13 世紀にさかのぼる ことが想定され、そのため羅針盤と称すると都合が悪くなり、全面的に「コンパス」の訳語を使用します。
原文に出てくる単語で、英語でないものはそのまま原語で表記しています。 その中に alargar, avanzar, avanzo, ritorno があります。これはアンドレア・ビアンコの本に出てくる言葉で、 以下の頁を読めば意味がわかります。カナ表記があると読みやすくなるので検索エンジンで探した所、 alargar, avanzo はスペイン語、ritorno はイタリア語です。 「マルテロイオの方法」に貢献したのはイタリアとマヨルカ (現在のスペイン領、当時はイスラム世界) と思われるので、多文化圏の産物です。 検索された辞書ではすべて発音が聞け、発音をカナ表記すれば
| alargar | avanzar | avanzo | ritorno |
| アラルガル | アバンツァー | アバンツォ | リトルノ |
アラルガルよりもアラルギャルの方が近いかもしれません。いずれにせよ、単なるカナ表記です。 なお、これ以外によく出てくる言葉で toleta があります。これはイタリア語の辞書にもスペイン語の辞書にも出てきません。 ベニスの方言と思われます。トレタと読めばよいと思います。table (表) の意味です。
マルテロイオの方法とは中世の航海計算の技術であり、 コンパスの方向、距離、そしてトレタ・デ・マルテロイオ (toleta de marteloio) と呼ばれる簡単な三角関数の 表を使用する。 方法は船乗りに、2 つの異なるナビゲーション・コースの間の横断をプロットする方法を 教え、このためにトレタ (Toleta) と基本的な算術の助けで 3 角形を解く。
数の操作に不愉快であれば、目で見てわかる トンド・エ・クアドロ(tondo e quadro, 円と正方形) に頼ることができ、 デバイダーで解答を得る。 マルテロイオの方法は地中海のナビゲーターが、 天測航行が発展する以前の 14 世紀、15 世紀に普通に使用したものである。
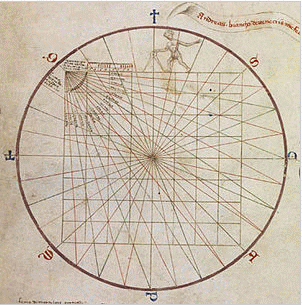
|
|
トンド・エ・クアドロ(tondo e quadro, 円と正方形)
アンドレア・ビアンコ (Andrea Bianco) の 1436 年の地図帳から |
語源はベニスの言葉に由来する。 ベニスの船長で、地図製作者であったアンドレア・ビアンコ (Andrea Bianco) は、 彼の 1436 年の地図帳で数表を導入した。 この数表を、彼はトレタ・デ・マルテロイオ (toleta de marteloio, マルテロイオの表) と 呼び、その数表を使用する方法をラゾン・デ・マルテロイオ (raxon de marteloio, マルテロイオの道理) と呼んだ。
マルテロイオ (marteloio) の意味自身は不明である。 最も広く受け入れられている仮説は、 アドルフ・エリク・ノルデンショルド (A.E. Nordenskiöld) によって始めて提示されたもので、 "marteloio" は "ハンマー" (ベニスの言葉で maltelo) に関連しており、 時の経過を告げる船上の鐘を打つために使用される。 提案されたことは接尾語の -oio が意味することは、 マルテロイオ (marteloio) は、 ハンマーそれ自身のことでも、ハンマーを打つ人のことでもない。 むしろ、 4 時間ごとの見張りの交替の時の 「ハンマー打ち、騒音、大騒ぎ」を示唆する意図がある。 見張りの交替時には甲板上に多くの人手があるため、 パイロットが船の速度を測定し、(必要であれば) 方向を変えるのに都合のよい時である。
(広く受け入れられてはいないが) 別の仮説では "marteloio" は 次の言葉がなまったものである:mari logio (海の方法)、mare tela (海のネットワーク)。 あるいは次のギリシャ語に由来するものである: homartologium (όμαρτόλογίον, "手引書" (companion piece) の意)、 imeralogium (ήμερόλογίον, "日々の計算" (daily calculation) の意)。 あるいは北フランスの matelot に由来し、これは更に ブルトン語の martolod (船乗りの意) に由来する。
「マルテロイオの方法」は中世ヨーロッパのナビゲーションで使用され、 最も顕著には 14 世紀から 16 世紀にかけての地中海であった。 もっとも、もっと古い起源があるかもしれない。 これは「コンパスと海図」によるナビゲーションの不可欠な部分であり、 ヨーロッパに地理座標と天測ナビゲーションが到来する以前のことであった。

|
|
15 世紀の船乗りが船上でコンパスを見ている
1403 年のジョン・マンデヴィルの旅行記から |
中世のナビゲーションは 2 つのパラメーター ―― 方向と距離 ―― に依存した。 船上では、方向は船乗りのコンパス (これは 1300 年頃に登場) によって決定された。 距離は推測航法 (すなわち、距離 = 速度×時間) で測定され、 時間は半時間用の砂時計で測定され、 速度の読み取りは、小さな丸太 (chip log, 測距儀) の何らかの形式で実施された。 (これは 14 世紀から 15 世紀に使用された古い方法であり、 船上の木片や、くずを使用し、木片が船のへさきから、船尾まで流れ去る時間を計るために リズムのある歌を歌った。)
コースを設定するには、 点 A と点 B の間のコンパスの方向と距離を知る必要がある。 港の相対位置の知識は海での長い経験により船乗りに修得されていた。 この情報は時々収集されて、ナビゲーターの手引書に書き下された。 この手引書はポルトラノ (portolano) と呼ばれた。 (portolano はイタリア語の"港の本" (port book) で、ギリシャ語では periplus ( ペリプルス)、 ポルトガル語では roteiro、英語では rutter (水路誌) である。) これらの手引書はポルトラノ海図 (portolan chart) と呼ばれる種類の海図を作るのに使用された。 ポルトラノ海図は 13 世紀末の ジェノヴァ (Genoa) で製造がはじまり、 ヴェネツィア (Venice) や マヨルカ (Majorca) に伝播した。 ポルトラノ海図には緯線・経線の格子がなく、 その代わりに蜘蛛の巣状のコンパスの方位線があり、 船乗りに地点間の距離と方向の概念のみを与えた。
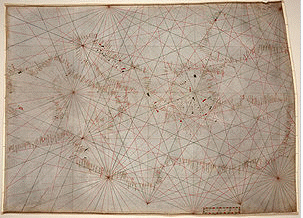
|
|
作者不明のジェノヴァのポルトラノ海図 (1235 年頃から
1350 年頃)、 ワシントン DC の アメリカ議会図書館 |
手引書ないしはポルトラノ海図によりナビゲーターが直ぐわかることは、 例えば ピサがジェノヴァの 85 マイル南東 (南東 = 伝統的なコンパス・ローズの命名では「シロッコ」 ("Scirocco")) にあることである。 従って、船をジェノヴァからピサに向けて出発する船は、この方位をこの距離、維持することである。 しかしながら、大半の航路はそんなに整然としていない。 マヨルカから ナポリ (Naples) に航行したい船乗りが言えることは、 後者が真東 (コンパス・ローズの "Levant") 600 マイルほど にあることである。 しかし、途中に サルデーニャ島があり、ルート上で船の方向を変えないといけない。 これは言うは易し行うは難しである。 地理座標 (緯度、経度) はこの時代には存在していなかったからである。 海上で船の正確な位置を決定する唯一つの方法は過去の方位と前進距離を計算することであった。
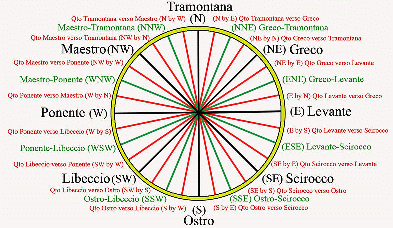
|
|
コンパス・ローズの 32 方位と
伝統的な名前 (それと伝統的な色) |
島は予期される障害である。 サルデーニャ島を迂回するには、単に一定距離を南東に航行し、 その後に方位を北東 ("Greco") に変更することである。 もっと問題があるのは、船が意図したルートから突風で吹き流された時、 あるいは タッキング (tacking) をして、繰り返し方位を変更したときである。 如何にして意図したコースに復帰するのか ? ここにマルテオイオの方法が登場する。
マルテロイオの方法は海上で方位を変更する問題に対処した。 もっと具体的には、 これによりナビゲーターが 1 つのナビゲーション・ルートから別のナビゲーション・ルートに横断する構想の助けをする。 例えば、一隻の船がが コルシカからジェノヴァに帆走するとする。 このコースは真北 ("Tramontana") に 130 マイル程である。 しかし風が協調的でなく、船は北西 (Maestro) に 70 マイル程帆走することを余儀なくされた。 どうすれば元のルートに戻れるか ? 方位を北東 (コンパス・ローズの "Greco") に再設定することは十分に意味があることのように思われる。 しかし、この方位でどれほど長時間帆走するか ? ナビゲーターは船が元のルートに到達し、そして再び北に方向転換する時を どのようにして知るか ? どのようにして、元のルートを行きすぎたり、手前すぎたりすることを避けることができるか ?
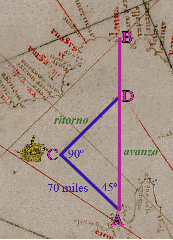
|
|
横断問題:意図したコース AB (方位 N), 実際のコース AC (方位 NW)
ritorno (復帰コース (北東) の距離) と avanzo (意図したコースで有効な距離) の計算は三角形 ACD を解く問題である |
これは三角形を解くための数学の問題である。 どれほどの時間、ナビゲーターが船が正しくないコースを航行したのかを知っていれば、 意図したコースからどれほど外れているのかを計算でき、 (方位を変更してから) どれほどの時間で元のコースに戻ることができるかを評価できる。 コルシカからジェノヴァの実例では暗に含まれた三角形 ACD があり、 一辺が与えられ (実際の北西コースで AC = 70 マイル)、 A における 45° の角度 (これは実際の北西コースと意図した北コースの成す角度)、 そして C における別の角度 90° (実際の北西コースと復帰北東コースの成す角度)。 ナビゲーターへの挑戦は北東の復帰コースを航行するのに必要な距離 (辺 CD の長さ、これは ritorno (リトルノ) と呼ばれる) と直進する時までに意図したコースを進んだ場合の前進距離 (斜辺 AD の長さ、これは "全 avanzo" (アバンツォ) と呼ばれる) を求めることである。
これは初等的な三角法で、 1 辺 (70 マイル) と二角 (45° と 90°) が与えられた時に二辺を解くことで、 正弦定理を適用して直ちに実施され、
| = | = |
となり、これより ritorno = 70 マイル、全 avanzo = 98.99 マイル の解が得られる。 これが意味することは、船が現在位置 (C) から北東に針路をとり、70 マイル帆走すれば、 元々の意図したコースに到達する。 合流点 D に到達するまでに、元の意図したコースでは 98.99 マイル前進している。 ここで方位を真っすぐ北に取り、残りの 30 マイル程度をジェノヴァに向けて帆走する。
残念なことに中世の船乗りは 14 世紀、15 世紀の初歩的な教育しか受けてはおらず、 問題を処理するための正弦定理を知っていなかったであろうし、あるいは 簡単に処理できなかったと思われる。 その結果、中世の船乗りは、より単純で、より扱いやすい計算法が必要であった。
学者で牧師であったマヨルカの ラモン・リュイ (Ramon Llull) はナビゲーションにおける横断問題を解く方法に 言及した最初の著作家である。 彼の Arbor Scientiae (科学のあずまや) (1295 年) の幾何学の問題の節でリュイは 次のように書いている。
リュイが説明しようとしていることは、 船は実際には東に帆走しているが、南東に帆走している時に、 すでに移動した距離から、意図した南東への距離を計算できることである。 後者の距離は、イタリア人が "avanzar" (アバンツァー) と呼び、リュイが "miliaria in mari" (ミリアリア・イン・マリ) と呼んでいるもののようである。 リュイは正確には述べていないが、 "装置" (instrument) を言及しており、 恐らくはこれはある種の三角関数の表である。 リュイの意味することは、 船乗りは意図したコースの miliaria の計算に、正しくないコースで実際に帆走した距離に、2 つのルートの間の角度の 余弦 (cos) をかけることである:
但し θ は 2 つのルートの間の角度である。
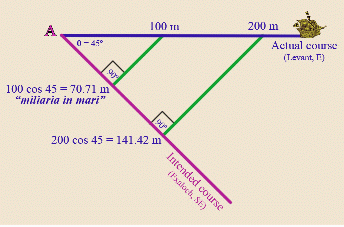
|
| ラモン・リュイの miliaria in mari、彼の 1295 年の実例 |
リュイの実例を使用すると、南東 ("Scirocco"、カタロニア語 "Exaloch") に 帆走することを意図した船が東 ("Levant") に帆走することを余儀なくされ、 角度の違いは θ=45° である。 正しくないルートで 100 マイル帆走すると、意図したルートの miliaria は 100 × cos 45° =70.71 である。 正しくないルートでの帆走を 2 倍して 200 マイルにすると、 意図したルートでの miliaria は 2 倍されて 141.42 マイル (= 200 cos 45°) になる。
(図式的には、リュイ の miliaria in mari は実際のコースで帆走した距離から、 意図したコースに垂線を下して直角三角形を作って測定される。)
リュイは彼の Ars magna generalis et ultima (偉大な一般・究極的技芸) (1305 年頃記述) でもう少しはっきり書いている。 今度は実例を逆にして、東に帆走するつもりが、実際には南東に帆走するとしている。 リュイは南東の方位で 4 マイル毎に意図した東向きのコースでは 3 マイル (実際には 2.83 マイル) 進むとしている。 従って、リュイが注意するように : 船が現在のコースを 100 マイル帆走する毎に 意図したコースでは「25 マイル (実際には 29 マイル) 遅れをとる」ことになる。
注意すべき点は、この節でリュイは方法を勧めているのではなく、それを報告しているのであり、 この方法がすでに知られ、当時の船乗りに実際に使用されていることを暗示している。 これは恐らく驚くべきことではない ―― 三角法はキリスト教のヨーロッパではまだ未発達であったが、 正弦、余弦の数表はアラビア数学ではすでに知られていたからである。 1230 年代に至るまで マヨルカ王国はイスラム世界の支配下にあり、リュイの時代には多文化圏の中心地であり続け、 繁栄したユダヤ人の共同体があり、 彼らの多くが数学や天文学に手を出し、その船乗りは地中海を通して多大な接点を持っていた。 マヨルカの船乗りが何らかの三角法の数表を手にしていたことはあり得ないことではない。 これにもかかわらず、1295 年にラモン・リュイによって示唆されている数表の正確な内容と レイアウトははっきりしない。
リュイよりも一世紀以上後に船乗りの三角法の数表が始めて垣間見られることになる。 ベニスの船長であるアンドレア・ビアンコ (Andrea Bianco) の 1436 年のポルトラノ海図の最初の二つ折りで、 彼はラゾン・デ・マルテロイオ (raxon de martelio) を述べ、どのようにしてコースを横断し、復帰するのかを説明している。 彼はトレタ・デ・マルテロイオ (toleta de marteloio) と呼ぶ単純な三角法の数表を提示し、船乗りがこの表を記憶することを薦めている。
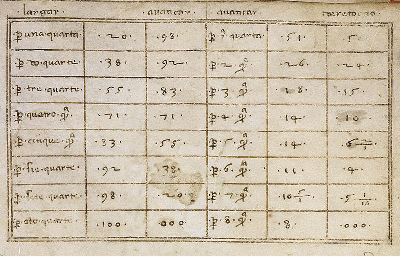
|
| アンドレア・ビアンコの 1436 年の地図のトレタ・デ・マルテロイオ (toleta de marteloio) |
トレタ・デ・マルテロイオ (toleta de marteloio) は次のように設定されている。
| Quater (逸脱の角度) |
Alargar (コース からの距離) |
Avanzar (真のコース の前進) |
Quater (復帰の角度) |
Ritorno (コースへ の復帰) |
Avanzo di ritorno (復帰中 の前進) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 98 | 1 | 51 | 50 |
| 2 | 38 | 92 | 2 | 26 | 24 |
| 3 | 55 | 83 | 3 | 18 | 15 |
| 4 | 71 | 71 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | 83 | 55 | 5 | 12 | 6 1⁄2 |
| 6 | 92 | 38 | 6 | 11 | 4 |
| 7 | 98 | 20 | 7 | 101⁄5 | 2 1⁄5 |
| 8 | 100 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 100 マイル毎 | alargar 10 マイル毎 | ||||
Toleta の数値は現代的な公式で近似できる。
| Alargar | = | 100 × sin(q × 11.25) |
| Avanzar | = | 100 × cos(q × 11.25) |
| Ritono | = | 10 / sin(q × 11.25) |
| Avanzo di ritorno | = | 10 / tan(q × 11.25) |
但し、数値はクォーター・ウィンドを 11.25° (11°15'、クォーター・ウィンドの通常の定義) にしてうまく行く。 (訳注 : Quarter wind (クォーター・ウィンド) とは、四分の 1 円 (quater) を 8 個に等分した角度。 q クォーター・ウィンドとは q × 90/8 = q × 11.25度。 現在の 羅針方位で採用。)
toleta は単純な表で、幾つかの数の列がある。 最初の列には実際のコースと意図したコースの差の角度が、クォーター・ウィンドの数で表示される。 差が一旦決定されると、2 番目の列には Alargar (Widening (拡張)、 船の意図したコースからの現在距離) が与えられ、 一方 3 番目の列には Avanzer (Advance (前進)、現在の方向の帆走による、 意図したコースでの前進距離 ―― これはラモン・リュイの miliaria di mari に同値) が与えられる。 Alargar と Avanzer の数値はビアンコの表では、現在のコースの 100 マイルの帆走に対して示される。
実例 : 一隻の船が点 A から点 B に向けて、東の方位 ("Levante") に帆走しようとする。 しかし風向きにより、南東微東 (southeast-by-east, "Quarto di Scirocco verso Levante") の方位に 帆走することを余儀なくされる。 (南東微東 (southeast-by-east) は 32 ポイント・コンパスで東からクォーター・ウィンドの順番で 3 クォーター・ウィンド (33.75°) である。 東からクォーター・ウィンドの順番で、 1 クォーターは 東微南 (east-by-south)、 2 クォーターは 東南東 (East-southeast)、 3 クォーターは 南東微東 (southeast-by-east) である。) これにより、ナビゲーターはトレタの 3 番目の列の q=3 を参照すべきである。
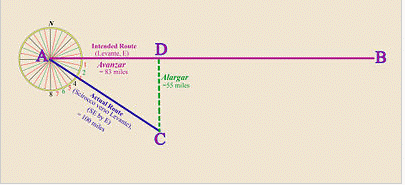
|
| ビアンコの Toleta から alargar と avanzar を計算 |
船が南東微東 (SE-by-E) の方位で 100 マイルを帆走したとする。 意図した東向きのコースからの距離をチェックするために、 船乗りは alargar の列の対応する項目を見て、直ちに意図したコースから 55 マイル 離れていることがわかる。 avanzar の列が教えることは、現在の南東微東のコースで 100 マイル 帆走すれば、意図した東 (E) 向きのコースで 83 マイル前進したことである。
次のステップは意図したコースに復帰する方法を決定することである。 実例を継続すると、意図した東向きのコースに戻るために、 船乗りは、船の向きを北東よりの方向に変えなければならない。 しかし、色々な北東よりの角度がある ―― NbE, NNE, NE, ENE など ([訳注:羅針方位を参照])。 船乗りは方位の選択がある ―― もしも鋭い角度 (例えば東寄りの北) で復帰すれば、 もっと穏やかな傾き (例えば北寄りの東) よりも、意図したコースには速く復帰する。 どの角度を選ぶにせよ、古いコースに到達するためには、 この方位で、正確にどれほどの時間を帆走するか推測しなければならない。 帆走が長すぎれば、行き過ぎる可能性がある。
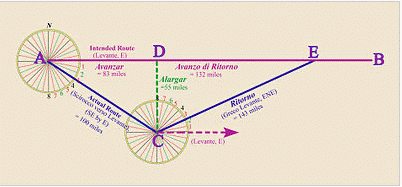
|
| ritorno と avanzo de ritorno の計算 |
復帰コースの計算が toleta の最後の 3 列の目的である。 4 番目の列は、復帰角度が意図したコース方位のクォーター・ウィンドで表示される (現在のコース方位でない)。 我々の実例では船乗りは東に行くことを意図したが、南東微東 (southeast-by-east) で 100 マイルを 帆走した。 風から判断して、船を東北東 (ENE, east-northeast, "Greco-Levante") で元々の コースに復帰することが最善であると船乗りが判断した。 ENE はクォーター・ウィンドで意図した方位 ―― 東 ―― の 2 つ上である。 そこで彼は、表の 4 列目の第 2 行 (クォーター・ウィンド = 2) を眺める。
第 5 列は ritorno であり、 これは、元々のコースに復帰するために、選択した復帰角で移動しなければならない距離である。 ENE の方位 (q = 2) で復帰しようとする。次に ritorno の列の 2 番目の行を読まなければならない。 ここには 26 がある。 これは、逸脱した 10 マイルごとに、 ENE の方位で移動しなければならない必要なマイル数を表す。 alargar (意図したコースからの距離) は 55 マイルであったことを思い出そう。 従って、意図したコースに戻るためには ENE で 5.5 × 26 = 143 マイルを移動しなければならない。 別の言葉では、143 マイルの間、ENE の方位を維持しなければならない。 この距離を移動してから、船を真っすぐ東に向けるべきで、こうすれば意図したコースに正確に戻る。
6 番目の最後の列 (avanzo di ritorno) は復帰への移動で実施した、意図したコースの長さを与える。 これも 10 マイルの alargar 毎で表示される。 alargar 55 で、復帰の角度は ENE (従って q = 2) であり、 従って avanzo di ritorno は 5.5 × 24 = 132 である。 別の言葉では、すべてがうまく行き、船乗りが 143 マイル (ritorno) の間、ENE の方位を 維持すれば、その復帰中に意図した東向きのコースで、追加の 132 マイルを進む (avanzo di ritorno)。
最後に冒険の全体で東への方位で有効となった距離 (total avanzo) を計算するために、 逸脱の最中の avanzar (83 マイル) に avanzo di ritoruno (132 マイル) を 追加しなければならない。 従って、彼は意図したコースでは全部で 83 + 132 = 215 マイルを進んだ。 地図で出発点 (A) からの距離を測定すれば、船乗りは彼の正確な現在位置を 図で表すことができる。
これはトレタ・デ・マルテロイオ (toleta de marteloio) の最も単純な使用であり、 根本的には三角法の表である。 しかしながら正弦法則のように、一度に横断問題に取り組まずに、 むしろ、 2 つの直角 3 角形の問題に分離し、順番に解法を進めている。 現代の三角法は alargar を計算するステップをなしですませ、ritorno を 直接計算する。しかしこのためには完全な正弦表で武装する必要がある。 toleta は少々単純な表で、これを調べて計算することが簡単で、随分コンパクトで、(ビアンコが勧めるように) ナビゲーターが記憶できる。
トレタ・デ・マルテロイオ (toleta de marteloio) は、丸めた心地よい数 ―― 100 と 10 ―― で表示されている。 しかし、実際には、船は通常復帰前に 100 マイルを帆走することがなく、 これは幾分違う距離、例えば 65 マイルである。 これを計算することは比例を解く単純な問題である。 例えば、船が南東微東 (southeast-by-east) で 65 マイル帆走すれば、意図した東向きのコースからの alargar を 計算することは、単純に x を求める次の問題である。
| = |
但し 55 は 100 マイルに対する alargar である (表の第二列の q = 3 で与えられる)。 これは単純な「三数法」 ("Rule of Three") ―― たすきの掛け算 (cross-multiplication) の方法 ―― で実施され、3 つの数を使用し、掛け算と割り算を次々に実行して、4 番目の数を解く。
従って 南東微東 (SE by E) で 65 マイル帆走すれば、alargar = x = 35.75 マイルである。avanzar などは同様に 考えられる。
「三数法」 ("rule of three") は 14 世紀にすでに知られていたが、掛け算と割り算を実行する技術は、 大体は文盲社会の出身である中世の船乗りにはわかりにくかったことであろう。 にもかかわらず、できないわけではなかった。 アンドレア・ビアンコが促すように「船乗りは掛け算と割り算をうまく実行する方法を学ぶべき」である ("saver ben moltiplichar e ben partir")。 商業とナビゲーションの重要な接点を見出すのはここである。 商業の数学 ―― アラビア数字、掛け算、割り算、分数、 物資の勾配と売却の計算とそれ以外の商取引で必要となる道具 ―― は 基本的にナビゲーションの数学と同じであった。 そしてこの種類の数学は そろばん学校 (abacus schools) で教えられ、 これは 13 世紀に北イタリアの商業中心地に設置され、 商人の子息を訓練した。この全く同じクラスがイタリアのナビゲーターを輩出した。 歴史家の E.G.R. テイラー (Taylor) が注意するように 「船乗りは毎日の仕事で、数学を使用した 最初の職業集団である」。
数を操作する高度な技術に悩むものには代替手段があった。 これは「円と正方形」 (circle and square, tondo e quadro) と呼ばれる目視装置で、 これもアンドレア・ビアンコにより 1436 年の地図帳で提供された。
円は 32 方位のコンパス・ローズ (あるいは羅針方位線の集まり) であった。 円は 8 × 8 平方格子と共に刻み込まれた。
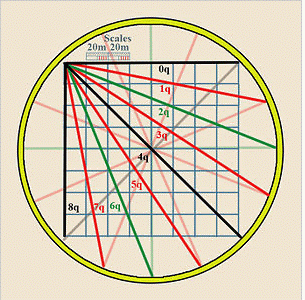
|
| トンド・エ・クアドロ(tondo e quadro) の基本機能の複写 |
中心のコンパス・ローズ (compass rose, コンパスの薔薇) は見過ごすことができる ―― 実際、円自身は無視できる、というのは、これは格子を横断して走る発散する線 (ray) の作図以外に 何の目的もないように思われる。 興味あるローズ (rose, 薔薇) は平方格子の左上角にあり、一連のコンパス方位線が発散している。 元々の 1436 年のトンド・エ・クアドロ (tondo e quadro) で、ビアンコは 16 本の発散する線を描いた ―― すなわち ビアンコは 8 方位 (half-quater winds or eighth - winds (otava)) を含め、 発散する線は 5.625 度の間隔であった。 「円と正方形」 (circle-and-square) の他の作図 ―― 例えばコロナロ・アトラス ( Cornaro Atlas) ―― は、クォーター・ウィンドの距離 (11.25°) で 放射する 8 本の線しか使用しない。 視覚的に、これらの線は 32 方位のコンパス・ローズ (32-wind compass rose) の右下の 1/4 を複製している : 東 (East, 0q), 東微南 (E by S, 1q), 東南東 (ESE, 2q), 南東微東 (SE by E, 3q),南東 (SE, 4q), 南東微南 (SE by S, 5q), 南南東 (SSE, 6q), 南微東 (S by E, 7q) そして南 (South, 8q)。
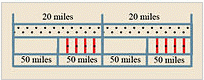
|
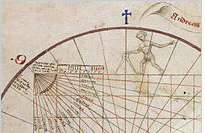
|
|
ビアンコのトンド・エ・クアドロ
(tondo e quadro) の棒目盛りの複製 |
ビアンコのトンド・エ・クアドロ
(tondo e quadro) の詳細 |
格子の上部に、距離の棒目盛り (bar scale) があり、部分単位 (sub-unit) に 切れ目が付いている。 目盛りには 2 組みの数があり、 1 つは各平方格子を 20 マイルで測定し、 もう 1 つは各平方格子を 100 マイル (図式を参照) で測定するためのものである。 最上部の棒は四角形毎に 20 m の棒目盛りで、黒丸毎に 1 マイルを表す。 一番下の棒は四角形毎に 100 m の棒目盛りで、単位四角形の長さは 2 つの等しい 50 m の 部分四角形 (sub-square) に分割され、一連の点と赤い線はこれを更に 10 マイルの長さに分割している。 従って、どちらの目盛りを使用するかに依存して、 全格子 (8 個の四角形) の辺の長さは (四角形毎に 20 マイルの目盛りを使用して) 160 マイルまで測定できるか、 (四角形毎に 100 マイルの目盛りを使用して) 800 マイルまで測定できる。
デバイダーを持つ 智天使 (cherub) が示唆することは、 ナビゲーターが alargar と avanzar を計算するために、視覚的な測定で如何にして格子を使用し、 数を操作したわけでないことである。
実例: 船が意図したコースの下方 2 クォーター・ウィンドで 120 マイル移動したとする (意図したコースが東であれば東南東 (ESE) で移動)。 デバイダ―と 20 m の目盛りを使用して、ナビゲーターはディバイダーで 120 マイルを計測できる。 左上角 (A) で、彼はディバイダ―の一方の端を置いて、 東南東向き (ESE) の半直線 (= 東向き (East) の半直線の下の 2 クォーター・ウィンド) に沿って、点 (図式の点 B) をマークする。 直定規 (straightedge ruler) を使用して、東向き (East) の半直線まで直線を引き、対応する点 C をマークする。
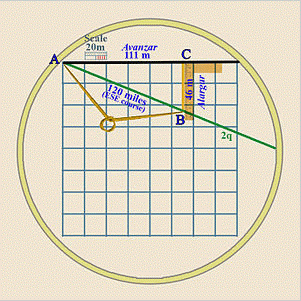
|
| トンド・エ・クアドロ(tondo e quadro) で三角形を解く |
直角 3 角形 ABC が作られたことは簡単にすぐわかる。 BC の長さは alargar (意図したコースからの距離) で、 46 マイルと 計測できる (これは視覚的には 2 つの格子正方形と少々、すなわち 20 cm + 20 cm と少々であるが、 この少々はデバイダ―と 20 cm の棒目盛りで 6 cm と評価できる。) AC の長さは avanzar (有効距離)、111 マイルである ―― 視覚的には 5 個の格子正方形と少々、あるいは (20×5) + 11 で、 再びデバイダ―と目盛りで測定される。
これが「円と正方形」で、 掛け算、割り算あるいは三数法による数の操作なしですませる方法である。 ナビゲーターは avanzar と alargar の測定のみで、視覚的に査定できる。
この方法は、どのような方位と逸脱にも使用できる。というのは 唯一の目的は三角形をデバイダーと目盛りにより解くことであるからである。例えば 最初のコルシカからジェノヴァ (Genoa) への実例を使用すれば、意図した方位は北であるが、 船は実際は北西に帆走し、ナビゲーターはデバイダーを長さ 70 マイルにセットし、 4 番目のクォーター・ウィンド (= (tondo e quadro の南東向きの半直線)、というのは北西向き (NW) は北向きから 4 番目のクォーター・ウィンド) に沿って置く。 全く同様にして alargar と avanzar を計算する ―― 格子の水平のトップに線を引き、四角形を測定するなど ....。
トンド・エ・クアドロ (tondo e quadro) はアラビアの正弦四分儀 (Rubul mujayyab) ととてもよく似ており、 角で発散する半直線が調節できる重りの線 (plumb line) の役目を真似ている。
トレタ・デ・マルテロイオ (toleta de marteloio) (そして視覚的対応物であるトンド・エ・クアドロ (tondo e quadro)) は 意図したコースに復帰する明示的な仕事にデザインされているが、 これはもっと多くの方法で多様なナビゲーション問題に使用できる ―― 例えば 複数の方向変換を持つコースのプロットなどがある。
マルテロイオの方法 (rule of marteloio) の興味ある応用の一つは三角測量で、 例えば岸辺のランドマークから船までの距離の決定である。 (これは、ベニスのナビゲーターである Michael of Rhodes のノートで試みられている最後の演習で、 ここで再現する。
実例 : [訳注: 以下方位は 32 羅針方位] ある夕方に北西 (NW, "maestro") に帆走している船が真西 ("Ponento") のランドマークに気が付くが、 距離がわからないとする。 船は一晩中北西 (NW) に帆走し続け、翌朝 40 マイル後にランドマークが、今や現在位置の 西南西 (west-southwest, "Ponento-Libeccio") にある。 船からランドマークの距離を求めることはマルテロイオの方法の応用である。
問題を解くために、夕方の位置 (地図の A) から開始して、 船とランドマークの間の距離を、意図したコースとして扱い、 船の実際のコース (NW) を逸脱と扱う。 朝における船の位置 (C) からランドマークまでの距離を見つけ出すことは、 距離 BC を計算される ritoruno として扱う問題である。 ritorno の計算に、alargar を知る必要があり、 これは 2 段階の手順である。
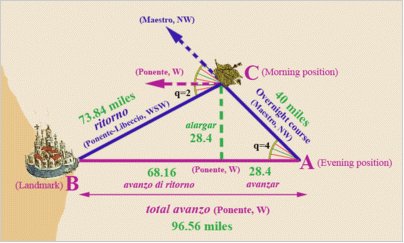
|
| マルテロイオの方法を適用して船と陸上の目印の距離を測定 |
最初に北西 (NW) は西 (W) の上に 4-クォーター・ウィンドであることに注意する。 そこでトレタ (toleta) で q = 4 の列を調べて、 alargar は北西 (NW) コースで 100 マイル毎に 71 マイルである。 しかし船は一晩で 40 マイルしか帆走していないので、我々は比例 71/100 = x/40 を解かなければならない。 これは三数法により x = alargar = 28.4 マイルである。 言い換えると、A から C へ 40 マイルを北西 (NW) に一晩帆走することにより、今や意図した西向きのコースから 28.4 マイルである。
さて ritorno を求めよう。注意したように、ランドマークは船の朝の位置 (C) の西南西 (WSW) である。 従って、ランドマークに復帰するには船は方位を現在の北西 (NW) の方位から西南西 (WSW) の方位 ―― すなわち北西 (NW) から 6 クォーター・ウィンド下 ―― に変更しなければならない。 しかしながら、トレタ (toleta) はクォーター・ウィンドを「意図した」方向 (この場合は西) の言葉で明記し、 西南西 (WSW) は西 (W) の 2 クォーター・ウィンド下である。従って、q = 2 の列を見る必要がある。 これにより ritorno は 26 × 2.84 = 73.84。これでわかり、 ランドマークは船の朝の位置から 73.84 マイル離れている。
話を完結するために、前日夕方のランドマークまでの距離 (点 A からランドマーク B までの距離) を見つけよう。 これは単に avanzar と avanzo in ritorno を加える問題である。 計算により直ちに avanzar (40 マイルに対して、q = 4) は 28.4 マイル (= 71 × 40 / 100)、 そして avanzo di ritorno (alargar 28.4 マイルに対して q = 2) は 2.84× 24 = 68.16 である。 従って、avanzo 全体 = 28.4 + 68.16 = 96.56 マイル である。 これが前日夕方のランドマークと船の距離である。
マルテロイオの方法はターゲットとして avanzar も使用できる。 例えば船が トルデシリャス線 (Tordesillas Line) ―― 1494 年の条約で法的に、 カーボベルデ (Cape Verde) の西 370 リーグに設置された子午線 ―― を 見つける意図で出発したとする。 船はこれを見つけるために、 カーボベルデから出発して、常に西の方位に帆走する必要はない。 むしろ、もっと都合のよい方位 (例えば南西 (SW)) で出発することができ、 西を意図したコースとして扱うことができる。 従ってマルテロイオの方法を使用すれば、意図した西へのコースの avanzar が 370 リーグに達するまで帆走する。
実際、 カーボベルデから出発する必要性さえなく、別の場所 ―― 例えば セビリア (Seville) ―― から 出発して、 カーボベルデの既知の距離と方位、及び マルテロイオの方法を使用して、終にトルデシリャス子午線に達した時を計算する。 これには 2 段階必要である。カーボベルデ (地図の B) はセビリア (地図の A) の 400 リーグ南西 であるが、船はセビリアからまっすぐ西に向かって、外海でトルデシリャス子午線に到達したい。 どれほど長期間帆走する必要があるか ?
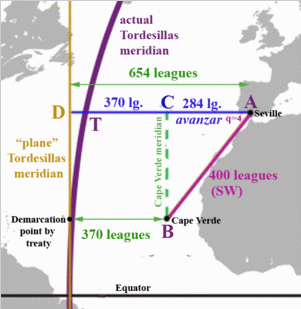
|
| マルテロイオの方法でトルデシリャス線を見つけること |
これをマルテロイオの方法で解く方法は問題を逆に提示する : 西を意図した方向、南西 (SW) を実際のコースとして扱う。 南西 (SW) は西 (W) の下 4 クォーター・ウィンドであり、 トレタ (toleta) を q = 4 で調べると、 avanzar が 100 マイル帆走ごとに 71 マイルである。 そこで、もし船がカーボベルデへの「実際の」 SW コースで 400 リーグを帆走すれば、 意図した西向きのコースで 284 リーグ (= 71 × 4) の avanzar を達成する。 無論、船は実際にカーボベルデの南西 (SW) に向けて帆走するわけでなく、外海に向けて西 (W) に帆走する。 別の言葉では、船がセビリアから西に帆走する時、 (内在的な) カーボベルデの子午線 (地図の点 C) に帆走するまでに、284 リーグを帆走することが わかっており、そしてその後、トルデシリャス線までの 370 リーグを開始すべきである。 別の言葉では、トルデシリャス線 (地図の点 D) に到達するために、 セビリアから西向きに全部で 284 + 370 = 654 リーグを帆走する必要がある。
この特別な実例はマルテロイオの方法の柔軟性を示すが、これは主な欠点の 1 つも示している。 結果は地球の曲率を無視している。即ち、経線は北極で集中すること、高緯度では狭くなることを無視している。 マルテロイオの示唆することとは反対に、 カーボベルデの西 370 リーグはセビリアの西 654 リーグと同じ経線上にない。 セビリアはカーボベルデの随分北にあるため、子午線はカーボベルデの緯度より、 セビリアの緯度で互いに密集する。 セビリアから西に帆走する船は、実際、 654 リーグを帆走する点 (点 D) より、はるかに手前で本当のトルデシリャス子午線に到達する (地図の点 T)。
マルテオイオの方法では、 世界の表面が平坦であるかのように、 船乗りが海図の上に平面 3 角形を描くことにより、ルートを作図する。 これは地中海のコンパクトな緯度に制限された帆走では十分に実用的であるが、 もっと壮大な規模では誤解を招くものである。
15 世紀末と 16 世紀に、航海天文学の改良と緯線 の導入により、ナビゲーターは帆走距離の評価によるのではなく、 天測により、海上での位置決定が可能となった。 マルテロイオの方法の後継は 「リーグの統率」("Regiment of the Leagues", regimento das léguas) で、 ポルトガルのナビゲーターが大西洋の航海で使用した。 あるいは、ウィリアム・ボーン (William Bourne) が導入した言葉を使用すれば、 "Rule to Raise or Lay a Degree" (緯度 1° を上下する方法)、 "Table of Leagues" (リーグの表) あるいは "Rule for Raising the Pole" (極に向かって緯度を上げる方法) とも呼ばれ、 ポルトガルのナビゲーション・マニュアルである Regimento do astrolabio e do quadrante (アストロラーベと 4 分儀の方法) (1509 年頃リスボンで出版、1480 年頃に記述) に始めて書き下された。 これはマルティン・コルテス・アルバカール ( Martín Cortés de Albacar) が 1551 年の Breve compendio la esfera y del arte de navegar (球とナビゲーション技法の短い概要) で 世に広めた。
「リーグの統率」はマルテロイオの方法とそれほど違っていない。 「リーグの統率」は西に向かう方位を「意図したコース」、測定はそこからの逸脱に設定する。 もっと明確には、リーグの表 (league table) は alargar の固定した値を考え、この値は緯度 1° (あるいは、当時の測量では (ポルトガルの) 17.5 リーグ、 あるいは (イタリアの) 70 マイルに同値) である。 帆走方位から異なるクォーター・ウィンドごとに relevar と afastar を与え、 帆走方位は、意図されたコースからではなく、常に南北の軸からのクォーター・ウィンドで指定される。 relevar は、あらかじめ定められた 1° の緯線を越えるために船が進まなければならない実際の コースのリーグ数である (開始緯線からの alargar は 17.5 リーグ)。afastar は東西の方位で単に対応する avanzar である。
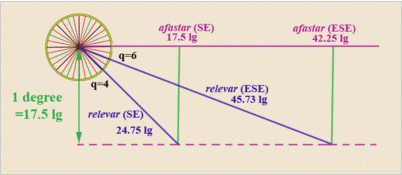
|
| 「リーグの統率」の挿絵 |
実例 : 一隻の船が東南東 (ESE, East-southeast) の方位で出発するとする。 これは南 (South) から 6 クォーター・ウィンド上である。 (思い出してください : マルテロイオとは違い、リーグの統率は常に北から南への子午線から、上に向かうクォーター・ウィンドで測定する。) どのリーグの統率の表 (例えば 1551 年のマルティン・コルテス・アルバカールの表) を 見ても、q = 6 に対して、表は relevar を 45 11/15 リーグ、 afastar を 42 1/4 リーグとして与えている。 これが意味することは、東南東 (ESE) に帆走する船は緯度を 1° 進むために は 45.73 リーグ帆走しなければならない (マルテロイオの 言葉を使用すれば、東向きからの 17.5 リーグの alargar)、 そして対応する afastar (マルテロイオの言葉では avanzar) は 42.25 リーグである。
その代わりに、もしも船が南東 (SE) 方位 ―― すなわち南 (South) の上の 4 クォーター・ウィンド ―― で出発すれば、 q = 4 におけるリーグの統率の表の対応する値は relevar = 243/4 と afastar = 17 1/2 である。
東南の方位を取れば、東南東の方位を取るよりは、 1° の alargar に、より速く (即ち より小さい relevar で) 到達し、 東南東の方位よりも afastar はより小さくなる (子午線により近い)。
数学的には
| relevar | = | 17.5 / cos θ |
| afastar | = | 17.5 × tan θ |
但し θ = 11.25 × 北南の軸からのクォーター・ウィンド数である。
用語の違い ―― とりわけ緯度の使用 ―― があるが、 「マルテロイオの方法」と「リーグの統率」はとてもよく似ている ―― これらは共に平面地図における三角形の解法に関するものである。 「リーグの統率」が「マルテオイオの方法」よりも有利な点は表に緯度を導入したことで、 これにより位置を (四分儀、アストロラーベ等による) 天文観測でチェックでき、 距離や方位を船乗りの評価に完全に依存する必要がなくなった。
「リーグの統率」により地理座標をナビゲーションの誘導に使用できるようになった。 例えば、 トルデシリャス線 (カーボベルデの西 370 リーグの子午線) を探すことが、 正確な緯度参照によりずっと単純となった。 例えば、2 隻の船がカーボベルデ (北緯 17°) から出発して、 一隻が西微北の方位 (WbN、 すなわち西の上 1 クォーターあるいは北の軸から q = 7) で、 もう一隻は西北西の方位 (WNW, 西の上 2 クォーターあるいは北の軸から q = 6) とする。 リーグの統率を使用すれば、トルデシリャス子午線を横断する時の正確な緯度を計算できる ―― 異なる方位に伴う afastar で西の 370 リーグを単に割ればよい。 西微北の船は北緯 21° 21' で子午線に到達し、 西北西の船は北緯 29°で到達する。 従って、砂時計と速度からリーグを数えるのではなく、方位を維持して、定期的な天文観測により、 経度を評価できる。
トレタ・デ・マルテロイオ (toleta de marteloio) はより現代的ナビゲーションに使用される横断表 (traverse table) の先祖である。 現代的な用語体系では、横断 (traverse) は 「船が連続する幾つかの方向に帆走する時の船が通過する曲がった通り道」で、 「横断を解消すること」 (resolving traverse) は 「2 つ以上のコースと距離と同じように船を運ぶ単一のコースと距離を見つけること」である。 マルテロイオの言葉では、横断の解消時に、与えられた既知の情報は 「実際のコース」と 「ritorno」であり、 不明な情報は 「意図したコース」と「total avanzo」 である。
横断表は曲がったコースの部分ごとに 3 つの値を使用する ―― 距離 (Dist.)、緯度の差 (D.Lat. 北南軸に沿った移動) そして 東西距 (Departure) (Dep.、東西軸に沿った移動)、 後の 2 つは次の公式で計算される。
| 緯度の差 | = | 距離 × cos θ |
| 東西距 | = | 距離 × sin θ |
但し θ は、θ の値が 45° より小さい時には 北南軸からのコースの角度の違い; しかしながら、もしも θ が 45° を越えれば、θ は東西軸からの角度の違いとして 表示され、公式は入れ替える、すなわち緯度の違いの公式は東西距 (Departure) となり、 東西距 (Departure) の公式は緯度の違いとなる。 あるいは、もっと簡単に θ を最も近い主要ウィンド (principal wind) (N, S, E, W) からの角度の違いとして計算。 そして公式を適用し、より大きな数の適切な列 (D.Lat あるいは Dep) に配置する。
コース部分ごとに、ナビゲーターは関連のある 3 つ組 (Dist., D.Lat., Dep.) を 挿入し、最初から終点までの潜在的な方位、及びこの方位で有効となった距離を計算する。 次に加法と減法により、すべての緯度の差と東西距 (departure) を組み合わせて、 全体の緯度の差と東西距 (departure) を手に入れて、これを全体の方位と有効な距離に変換する。
ラモン・リュイの 1295 年の示唆的な意見を別にして、 マルテロイオの最も初期の言及は 1390 年のもので、 ジェノヴァの Oberto Foglieto とか称する人の母親の地所の目録があり、ここに unum martelogium....item carta una pro navegando と書かれている。 最初の明白な登場と説明はベニスの船長であるアンドレア・ビアンコの 1436 年の地図帳である。 他の初期の写本が、それ以来マルテロイオの方法に関係して見つかり、これに含まれるものに
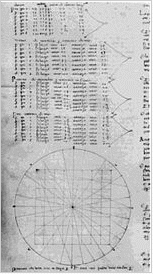
|
|
トレタ・デ・マルテロイオ (toleta de marteloio) と 8 方位のトンド・エ・クアドロ (tondo e quadro)
コルナーロ地図帳 (1489 年頃) から |