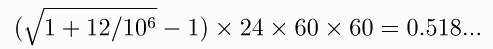
このページは英語版の Wikipedia の翻訳ページではありません。 英語版の Wikipedia のページを翻訳するときに、ティコ・ブラーエの横断線等を 調べるはめになり、どういうわけだか江戸時代の象限儀に関してのページを読むことになりました。 ところが逆に矛盾点だらけの話となったので、当初は ティコ・ブラーエの観測装置 の訳注で説明を加えていました。 しかしティコ・ブラーエの観測装置 に色々と追加していくうちに全体が大きくなりすぎたため、現在のページにまとめ直すことにしました。
ヨーロッパではティコ・ブラーエ以後は天体観測に望遠鏡を使用したものになり、 その精度も飛躍的に向上していきます。江戸時代に望遠鏡を使用した大象限儀もありますが、 その精度は角度の 1 分でしかなく、ティコ・ブラーエの装置の精度 (1/6 分) よりも低いものでした。 従って、江戸時代の天体観測は、古代の天体観測に属するもので、近代的なものとは到底言えません。 円周儀の 訳注のメイソン・ディクソン線の測量を読めば 1763 年頃の英国の王立天文台の装置の精度が 1 秒 (角度) であることがわかります。 ヨーロッパでは測量装置よりは、天体観測の装置の方が早くから高精度化し、 江戸時代の天体観測はこの点からも古代の天体観測です。 江戸時代には三角法が随分使用されるようになったと言われていますが、 恐らく江戸時代の人にはティコ・ブラーエが縦横無尽に使用した三角法 (三角法の歴史の訳注 2, 3, 4, 5 を参照) を理解できなかったと思われます。 このように結論してよいと思われるのは、『和蘭天説』の紀限儀の挿絵が本質的な所で、 でたらめだと判断できるためで、 その背景となる三角法を理解していないことが明白なためです。 (和蘭天説に関して を参照のこと。) だから江戸時代の三角法は恐ろしく貧弱なのです。(現在の高校で学ぶ三角法のレベルに達していない。)
測量 江戸時代 測量機器 間縄 小方儀 象限儀 水木 見盤 岩橋善兵衛
の象限儀の写真に垂揺球儀 (すいようきゅうぎ) という 振り子時計が写っています。 少し疑問となって色々調べてみました。 次のようなページもあり、どうやら木星の衛星から経度を決定するガリレオの方法 (経度の歴史を参照) を実施する目的もあるようですが,...
伊能忠敬測量隊が観測した木星の小星凌犯現象
木星の衛星から経度を決定するガリレオの方法の適用の是非に関しては あとで議論することにして、ここでは 時計の精度と使用法を問題とします。
垂揺球儀 (すいようきゅうぎ) に関しては
というような具合に書いてあります。1 点重要なことで誤解を招く書き方をしている、
垂揺球儀 (すいようきゅうぎ) は振り子時計です。 振り子時計は温度が一定であれば、物理法則 (振り子の等時性) により正確無比なのですが、 温度が変化すると振り子の長さが変化して、必然的に進んだり、遅れたりします。 温度補正をしていない振り子時計では、夏になれば遅れ、冬になれば進むのです。 どの程度、狂うのか計算してみることにしましょう。 振り子時計の振り子が鉄でできているとします。 20°C では 熱膨張率はおよそ 12/106で、 振り子の周期は振り子の長さの平方根に比例するので ( 振り子 を参照)、 温度が 1° 上昇すれば振り子時計の 1 日の遅れは次のようになり、
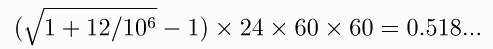
ほぼ 0.5 秒だけ狂う勘定になります。 振り子時計 を読めば、 振り子をガラスにすれば精度が上がることがわかりますが、垂揺球儀には使用していないと思う。 (そもそも江戸時代の人は振り子時計が狂う理由を知らなかったと思う。高校で学ぶ程度の力学だが....) また ジョン・ハリソンが 1726 年にしたように すのこ型振り子によって熱補正することも考えられますが、 江戸時代の人が熱膨張率のことを理解していることはありそうもないし、 またよしんば熱膨張率のことを理解していても、 これを利用して「すのこ型振り子」を作成するには 純度の高い金属を使用する必要があると思われ、 この点からも敷居の高い方法と思われます。
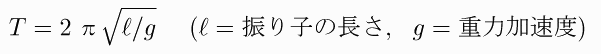
垂揺球儀は温度補正をしていない普通の振り子時計なのです。 南中時から南中時まで動かすことがアイデアなのです。 昼間と夜間の温度差が仮に 10 度程度だとします。昼間は温度が高いので、時計は遅れます。 しかし夜間は温度が低いので、時計は進みます。仮に昼夜間の平均温度が最高温度と最低温度の中間であるとすると、 平均温度からの逸脱は 昼間が +5° 、夜間が -5° となり、5° 程度の変化では、時計の狂いは一日動いても ±2.5 秒の 違いしかありません。従って、昼間夜間の平均温度からの逸脱による時計の狂いは大きくても半日分の ±1.25 秒になります。 そのため、24 時間ならしてしまうと、変化が余り出てこない可能性があります。 昼間と夜間の温度差が 10 度より多少多くても、あまり問題がなさそうです。 (無論、寒暖の差が激しければこのようなこの程度で済むはずもありませんが.....) つまり誤差が 3 秒であるとは、絶対的なものでなく、相対的なもので、しかも経験的なものと思われます。 いずれにせよ、垂揺球儀で達成できる精度は、ごく当たり前の振り子時計で実現できる精度と思われます。 これを十分に承知したうえでオランダ人が日本人に使用させた。
さて、垂揺球儀はいつ頃から使用されたのでしょうか ? 当然、江戸に現代的な天文台ができた時からです。 中国の天文学 の 中国におけるイエズス会の活動 によれば
だから、日本で最初の現代的な天文台が建設された時から垂揺球儀が使用されているのです。 望遠鏡と時計を使用する天文台が当時の「現代的な天文台」だからです。 天文台に時計を使用するアイデアはオランダ人のアイデアなのです。
ヨーロッパで天体観測に時計を本格的に使用したのはティコ・ブラーエが 最初であると思われます。(ティコ・ブラーエ以前にも時計は使用されたようですが、ティコ・ブラーエほど正確ではなかった) ティコ・ブラーエが使用した時計はどのようなものか不明ですが、 彼が時計を使用した頃と ほぼ同じ頃にヨスト・ビュルギがクロス・ビート・エスケープメントを使用した 時計を発明ないしは改良しています (1584 年)。この時計は 1 日の誤差が 1 分以内 (あるいは 30 秒) で、 天体観測用に使用され、秒針が付いていた (ティコ・ブラーエの観測装置 のティコ・ブラーエの使用した時計はどのようなものか ?を参照)。 このような天体観測用の時計は、時々座標が既知の星を観測して、秒単位で時刻合わせをしたと思われます。 (時刻の合わせ方は 三角法の歴史の 訳注の方位角もしくは高度から時刻を決める方法 を参照。) その後に振り子時計が天体観測に使用されるようになりますが、 当初は振幅の大きなバージ・エスケープメントを使用した振り子時計ですから 1 日に誤差は 15 秒もあり、 これも天体観測により時々秒単位の時刻合わせをしたはずで、アンカー・エスケープメントを 使用した正確な振り子時計となっても、同様であったと思われます。 (振り子時計の訳注:振り子時計の忘れ去られた開拓者 を参照。) しかし、これでも振り子時計が狂い、その原因が温度変化による振り子の長さの変化であることが知られるようになったのでしょう。 これにより温度補正をした振り子の登場となります。 日本に「現代的な天文台」が建設されるのは、ヨーロッパで温度補正をした振り子 (水銀振り子、すのこ型振り子) が登場しかけている頃です。 (しかもヨーロッパでは 18 世紀中頃に温度補正をした振り子により、1 週間で数秒の精度を達成していますから、 日本の垂揺球儀は到底比較になりません。振り子時計を参照。)
日本における最初の現代的な天文台の建設の指導にあたったのはオランダ人の 宣教師です。 彼はいわゆる教養人のはずで、時計の製造法を伝授できたとは思われません。 そのため、日本の時計の製造技術に合わせた装置しかオプションになかったのです。 恐らく当時の日本では、秒針の付いた恒星時計は製造ができなかった。 また、このような時計があっても、時計の時刻合わせをするためには、 天球の赤道上で赤経の知られた星を知っている必要があります。 ところが当時の日本には天文学の知識は皆無なので、 天体による時刻合わせをするための基礎的な星表がまだ無いのです。 しかもオランダ人は当然、温度変化により時計が狂うことを知っていた。 そこで、オランダ人は垂揺球儀を考え、比例を使った観測をさせたのだと思われます。
垂揺球儀のアイデアがオランダ人のものであることに関しては、もう少し別な根拠もあります。 北京古観象台には、 1673 年に天文台の責任をまかされたフェルディナント・フェルビーストが 製造させた観測装置 (北京古観象台の 訳注:フェルビーストの製造した観測装置を参照。) が残されており、これはほぼティコ・ブラーエの 装置 (ティコ・ブラーエの観測装置 を参照) を真似したものです。 しかしティコ・ブラーエの装置の中で「壁面四分儀 + 時計」は真似できませんでした。 多分、時計の理由からです。 ほぼ 50 年後にオランダ人が、江戸の天文台の建設の援助をすることになった時、 何を考えたと思いますか ? 当然フェルディナント・フェルビーストが中国でしたことを 乗り越えてみようと考えたのです。だから意図して「大象限儀 + 時計」を持ち込んだのです。 大象限儀とティコ・ブラーエの壁面四分儀はほぼ同じ大きさで、 しかも大象限儀には対角線目盛ないしはティコ・ブラーエの 横断線が書き込まれていたはずですから、 なおさらオランダ人がフェルディナント・フェルビーストないしは ティコ・ブラーエを意識していたことがはっきりします。 だから、大象限儀はティコ・ブラーエの壁面四分儀の生まれ変わった姿なのです。
垂揺球儀の製造は江戸時代の日本人にとって非常に困難だったかもしれません。 これは製造法の違いによっていると思われます。 ヨーロッパの機械式時計の製造が活発となるのは 14 世紀です。 (塔時計 を参照。) 当初は歯車の製造は手作業でした。 しかしデバイディング・エンジン (目盛り刻印機) に記載されていることによれば、 18 世紀にはヨーロッパには「歯車を切り抜く機械」がありました。 (産業革命の一歩手前の状態です。) つまり手作業によって歯車を作っていたのではない。 これは何百年もの間機械式時計を作っていたことによる結果です。精密機械を製造するために、最初に精密加工機械を 製造する現代的な方式が既に定着していたのです。 一方江戸時代の日本では昔のヨーロッパのように手作業で歯車を切り抜いて製造していたと思われます。 しかも、その技術は門外不出であったはずですから、技術力が発展したはずもありません。 (日本には特許の法律がなかった。) ヨーロッパでは「歯車を切り抜く機械」をもとにして「デバイディング・エンジン」が 製造され、ここから更に精密 セオドライトができるようになります。 明治時代には日本は精密セオドライトを輸入するしか方法がありませんでした。 だから、この原因を考えれば、当然のことながら、江戸時代の歯車は手作業によって製造されていたことになります。 完成品は同じに見えても製造方法が基本的に違っていた。 すべて手作業で製造された江戸時代の時計はヨーロッパのものと比べ 随分製品むらがあり、精度もかなり落ちたはずです。 従って垂揺球儀は仮にうまく作れていたとしても、温度補正のない普通の振り子時計程度の 精度しかないことは自明なことです。
垂揺球儀が正確ではなかったことは、その使用法からも明らかです。 太陽の南中時から南中時まで計測するという点から言っても、江戸時代の人は何も理解していないのです。 時計を正確な地方時に合わせるためには平均太陽時に合わせる必要があり、 平均太陽時と太陽時の違いは年間で ±15 分も違いが生じます。 この違いが均時差と呼ばれます。 だから時刻の起点を南中時においてはいけないのです。これでは正確になりません。
天体観測に使用する時計は恒星時を表示するようにできており、 恒星時を表示する時計は星の観測のみで時刻合わせができます。 赤経が既知の天体が子午線を通過する時点で時刻合わせができたのです。 だから太陽の南中で時刻合わせをするよりはずっと易しく、 夜間であれば、ほぼリアルタイムで時計が狂っているかどうかの判断ができます。 恒星時を平均太陽時に変換することもできますが通常はこれをしません。 だから時計は 2 種類必要です。恒星時を表示する時計 (天体観測用) と 平均太陽時を表示する時計 (日常用の時計) の 2 種類です。
平均太陽時に基づく時計 (日常用の時計) の時刻合わせをするには、 そもそも太陽の南中時が季節により変動するため、 時刻合わせをするためには「均時差の表」が必要です。 この均時差の表を作成するには正確な天体観測と、 ケプラーの法則やニュートンの運動方程式の知識が必要です。 (均時差を参照のこと。) 従って、江戸時代には均時差の表はヨーロッパの天文学者しか作成できなかったことは自明のことです。
当時のヨーロッパでは振り子時計を持っている人は、 日時計も所有し、しかも「均時差の表」が必要でした。 日時計で正午になった時に、「均時差の表」で平均太陽時との違いを調べ、 そのあとで振り子時計の時刻合わせをしたのです。 これが振り子時計の時刻合わせの方法でした。 江戸時代には均時差の表の話が登場しません。 従って「均時差の表」は輸入されることがなく、 正確な時計は日本に 1 台も存在していなかった。
更に、この「均時差の表」は経年変化があるため 10 年に 1 度ぐらいの割合で作成し直す必要があります。 たから振り子時計の所有者が時計を正確にしたければ、「均時差の表」を購入し直す必要がありました。 ヨーロッパでも産業革命以前には庶民は時計を個人的に所有できず、 頼りにしていたのは公共の時計 (大聖堂や市役所などの時計) です。 このような公共の時計の時計守は常に最新の「均時差の表」で時刻合わせをしたことでしょう。以上の点から考えても、垂揺球儀が正確であった可能性は皆無といってよいとおもわれます。
江戸時代の日本には精密な天体観測に基づく時刻の概念がなかったというべきです。
比較のために、ヨーロッパの歴史を付け加えます。 ヨーロッパでは 14 世紀に機械式の塔時計が普及し始め、 15 世紀にはヨーロッパ中の都市に広まります (小さな町にも普及します)。 機械式の時計は高価で一般の人は購入できませんでしたが、 各都市には公共の塔時計 (大聖堂や市役所) があり、これで時刻概念が定着したのです。 町に住んでいれば、それが小さな町であるにせよ、普通の人が時刻を知ることができるようになったのです。 (塔時計を参照。) 1656 年には振り子時計が作られ、まもなく均時差の表も出版されます。 これで機械式時計はすべて振り子時計となり、塔時計は日時計と均時差の表で時刻合わせをするようになります。 これにより、町に住んでさえいれば、普通の人でも正確な時刻がわかるようになりました。 しかし、まだ標準時には至っていません。 産業革命により、鉄道が普及すると、鉄道時間 (標準時) が使用されるようになり、 (有線の) 電信による全自動の時刻配信サービスが始まります。これは 19 世紀の前半のことで、 この時点では主だった公共の時計がこの時刻配信サービスに組み込まれ、 普通の人も正確な時刻を知ることができるようになったのです。これが 19 世紀前半のことです。 (鉄道時間を参照のこと。)
このヨーロッパ (とりわけ英国) における状況と日本が同じ状況になったのは恐らく 日本で時報がラジオ放送により送信されるようになった 1912 年のことです。 日本には塔時計のような公共の時計の歴史がほとんど皆無なので、 恐らく安価な時計があっても時刻合わせをすることができなかったはずです。 ヨーロッパでも安価な時計が流通するようになるのは 19 世紀で、 この時点では各家庭の時計は公共の時計で時刻合わせをするだけでよかったのです。 (アメリカの田舎では公共の時計がありませんでしたから、 時計の時刻合わせのためにアナレンマの付いた日時計が必要でした。 日時計の正午合わせを参照のこと。 アナレンマは均時差の表ほど正確ではないので、大体の時刻にしかあわせることができません。) 日本人がこれと同等なことができるようになるのは 20 世紀になってからだと断言できます。 (日本では日時計が普及しておらず、均時差の概念をまるで知らなかったでしょうから、 アナレンマが付いた日時計など到底あるはずがない。) つまり、20 世紀に入ってから日本で時計がようやく普及した。それ以前には日本にはそもそも時刻の概念がなかった。 日本でかってラジオから送信された時報も天体観測に基づくものであったことは自明なことで、 この時には日本においても天文台は普通の人にとって意味があるものとなった。
精密な時刻を維持する時計は単独では意味がなく、 必ず天体観測で時刻合わせをする必要があります。 しかも、天文台には恒星時を表示する恒星時計と、 平均太陽時を表示する通常の時計の 2 種類が必要です。 天体観測から恒星時計の時刻合わせをし、これを平均太陽時に変換して、 通常の時計の時刻合わせをするのです。(厳密を期すために均時差の表は使用しないとする。) さて、恒星時計を秒単位で時刻合わせをするためには、天体観測の精度をどの程度にすればよいでしょうか ? 時計を合わせるだけであれば、赤経の精度だけでよさそうですが、 全体的な観測精度を上げておかないと何らかの不具合がある可能性があり、 赤経と赤緯の観測精度を同程度にする必要があります。ところが
となり、時間の 4 秒が角度の 1 分に対応していることがわかります。 つまり、時間の 1 秒を測定するためには象限儀の精度は 1/4 分でないといけません。 江戸時代の大象限儀は精度 1 分なので、これでは観測精度が不足します。 一方、ティコ・ブラーエの壁面四分儀の精度は 1/6 分なので十分に対応できました。 ヨーロッパではティコ・ブラーエ以後の天体観測には望遠鏡が使用されており、 角度で 1/4 分の精度は十分に達成できる精度で、これにより秒を表示する恒星時計が使用されたのです。 時計は単独では意味がなく、時刻合わせをするためにも天体観測が必要なのです。 しかもその精度は角度で 1/4 分が必要となります。この精度は江戸時代には達成できませんでした。 すべてうまくいったとしても、江戸時代の天体観測で可能な時計の精度は 4 秒なのです。 この点からも江戸時代に精度が 1 秒の時計があるはずがない。
ヨーロッパで精密時計を最も必要としていたのは天文学者です。 天文学者こそが精密時計を必要としていた。 我々の生活でも秒の単位は必要な場合があります。 電車に間に合うかどうか、のような場合には秒針がないと判断できません。 改札を抜けた時に、時計の秒針からあと 30 秒程度で電車が発車することが わかれば誰もが走ります。つまり、時間の秒は現代の日常生活に必要で、 そのために秒針があるのです。 それに引き換え、江戸時代にはこのような必要性はありませんでした。 だから秒を表示する時計の必要性はなかったのです。
この上にヨーロッパでは経度の決定のために、更に精度が要求されることになりました。 月距による方法にせよ、海洋クロノメーターによる方法にせよ、 高精度の観測は是非とも必要で、必要性から時計が高精度化していったのです。 これと比較すると江戸時代には秒を表示する時計の必要性はほとんどなかったのです。 やむにやまれぬ必要性がない限り、機器の進展はありえないのです。 普通の性能の時計に関しても、ヨーロッパでは必要となっていきます。 19 世紀に入り、英国の産業革命が更に進展をすると、 工場や企業で働く人が増えます。工場や企業では一定の時間に仕事を開始し、 一定の時間に仕事を終了しなければならなくなります。 (賃金は労働時間に見合うように支払われるようになったからです。) だから秒単位の時計の必要性はないかも知れませんが、分単位の時計の必要性は 出てくることになります。(振り子時計の大量生産、廉価な振り子時計の登場!) 日本の江戸時代には、労働時間に見合うように賃金が支払われていたわけではありません。 だから、この点からも正確な時計の必要性はなかったのです。
話が全体的におかしいのですが、伊能忠敬の経度の決定のことに関しては
伊能忠敬測量隊が観測した木星の小星凌犯現象
に解説があります。 他にも幾つか記述を見た気がしますが、この文書自身がおかしいし、 インターネットで見ることができる記述全体がおかしいです。 それは常に「同時に 2 点で観測」だからです。 これはあり得ないのです。 長期間観測をすれば、これは可能性があるかもしれませんが、 1 回きりの観測で 2 地点で同時に観測可能であるという偶然は ほとんど期待できません。
もしも木星の衛星の凌犯現象から経度を決定したければ、 木星の衛星の凌犯現象が基準点 (例えばグリニッジ天文台) でいつ起きるのかを記した天体暦があればよいのです。 (軌道計算をすることができるのであれば、基準点を江戸の天文台とした天体暦を 作成することが可能なはずです。) このような天体暦は 1767 年度版の航海年鑑が 刊行されるまでは使用された可能性があります。 しかし、これ以後は、誰も木星の衛星の凌犯現象から経度を決定しようなどとはしなかったはずで、 「月距 (月からの距離 を参照) の観測」ないしは 海洋クロノメーターによって 経度を決定しようとしたはずです。
ある地点の経度の決定には何らかの正確な天体暦が用意されていればよく、 各地点における天体観測によって、その地点の経度が基準点と相対的に決定されるのです。 すべて話が妙なのですが、次のように考えると説明がつきます。 仮に
伊能忠敬測量隊が観測した木星の小星凌犯現象
に書かれていることが正確であるとします。 そうすると原典となっているオランダ語の本は 「木星の衛星の凌犯現象を記した天体暦」のはずで、 この天体暦は 1767 年度版の航海年鑑が出版されたより以前の本で、 特定の年における「凌犯現象を記した天体暦」と思われます。 しかし、本の著者はこれ以後、 何年間か有効となる近似式を与えていた可能性があります。 均時差の中の 数学的詳細 を読めば、これと類似のことが想定されます。 ここでは基本的には、あまり変化しない定数を変化しないと仮定して近似式を得ているのです。 ところが、経年変化から、余り変化しない定数が変化するのです。 この場合は定数を最初から修正し、近似式の評価をやり直す必要があります。 これが可能となるには原理となる式の導き方を理解できていないといけない。 恐らく、これが不可能だったのでしょう。 そのため、オランダ語の本の賞味期限を過ぎた公式を使用し、 かなりの誤差が出る部分は同時観測で補おうとした。
以上のように考えれば 伊能忠敬の経度の決定をめぐる妙な記述の説明になるし、 江戸時代は、かなりレベルが低かったことの証明になります。
経度を決定する方法で、一番古くから提唱されている方法は月食の観測です。 これは古代ギリシャで提唱された方法です。 月食のことを触れずにいきなり木星の衛星の凌犯現象のことを持ち出すことは とても違和感があり、天体観測の歴史がないことが自明なことになります。
伊能忠敬が地図作成を 開始するのが 1800 年で、 ほぼ同時期の 1804 年から実施される ルイス・クラーク探検隊 では 円周儀 (わんか羅針 (わんからしん) あるいは杖先羅針 と基本的に同じもの) を使用した地図が作成されますが、 経度の決定に関しては 海洋クロノメーターも 航海年鑑も使用されている。 (円周儀の訳注のルイス・クラーク探検隊を参照。) 伊能忠敬の時代には情報の伝達が遅く、外国の本がすぐに手に入らなかったのだと思われます。 それと、航海年鑑は英語で書かれていますから、これも情報の伝達が遅かった理由かもしれません。 英語では最新のことが分かっても、オランダ語ではこうではなかった。 オランダ語の本では最新のことがわからないという点は明治維新前後に知られていたと思います。 どこかに書いてあった。
時間が前後しますが、 最初はティコ・ブラーエの著した 「天文学の観測装置」(Astronomiae instauratae mechanica) をネットで読めるとは思っていませんでしたから、 暗中模索でした。知りたかったことはティコ・ブラーエがどのようにして、 壁面四分儀に横断線を使用したのかと言う点でした。 結論から言えば、ティコ・ブラーエの壁面四分儀の図を拡大表示すればわかったことですが、 どういうわけだか、これに思い至らず、どういうわけだか
測量 江戸時代 測量機器 間縄 小方儀 象限儀 水木 見盤 岩橋善兵衛
に遭遇することになりました。 このページに登場する大阪市立科学館に展示してある伊能忠敬が使用した中象限儀が見え、 ここに斜めの線が見えます。直ちにこれがティコ・ブラーエの横断線に相違ないと 気がつきました。 これを見ているうちに『ティコ・ブラーエの壁面四分儀』の画像を拡大するとどうなるのかな ? と思い至り、画像を 2 度クリックして最大にしてみると、.. 確かに同じようなものですが、横断線が見えます。 ところが、ティコ・ブラーエの横断線は交互に向きを変えています。 しかし基本的には同じです。
最初は色々混乱したのですが、伊能忠敬の象限儀はヨーロッパ由来であることが確実となり、 江戸時代の象限儀の製造法はオランダ人が教えたことの別な証拠が見つかったことになりました。
大阪市立科学館に展示してある伊能忠敬が使用した中象限儀の大きさは、 115 cm, 1 分が測定できるとのことです。だから、この点から考えると ティコ・ブラーエの壁面四分儀よりは小さく、精度が低い。 大象限儀のことに関しては大きさが 182 cm であること以外の事実が わかりません。そのうち、ようやく次を見つけました。
伊能忠敬記念館 - HITNET(ヒットネット)産業技術史資料共通データベース
によると、大象限儀の精度は 1 分とのこと。中象限儀と同じ。これは少し意外でした。 この理由はしばらく不明でしたが、そのうち明らかとなりました。 時計の精度を上げられないので、赤緯のみ精度を上げても、 全体の精度を上げられないためです。
ティコ・ブラーエの使用した壁面四分儀は角度の 1/6 分を測定でき、 この精度に合わせるために使用した時計の精度は 1 秒です。 これはあいまいな言い方で、厳密には天体観測から時計が狂っていることが 判明すれば秒単位で時刻合わせをした。 ところが日本では秒単位で恒星時を表示して、秒単位で時刻合わせをする時計を 製造することが可能ではなく、垂揺球儀 (すいようきゅうぎ) となった。
しかし原因はもっと別にあるのかもしれません。 時計が狂っているかどうかを判断するには精密な天体観測が必要です。 つまり精密な天体観測をするためには精密な時計が必要で、 逆に時計が精密であることを判断するには精密な天体観測が 必要なのです。精密時計=精密天体観測 なのです。 従って、江戸時代に精密な時計を製造できなかったことは 精密な天体観測ができなかったことと密接に結びついていると 考えるべきかもしれません。
高性能な機械は使用する人に技術を要求します。 例えば、ティコ・ブラーエの精度で完璧な観測をするためには、 月の視差や大気差 (= 大気による光の屈折) のことも知っている必要があるからです。 以上の点に関してはティコ・ブラーエのチームも随分エラーをしたようですが、 江戸時代の日本人には以上の知識は皆無であったはずなので対処法があるはずもない。
大気差の問題は 1753 年から 3 年間のグリニッジ天文台の観測で決着がついたそうです。 ((ジョン・バードの訳注:大気差と光行差を参照。) なお、この時に使用した観測装置はジョン・バードが製造した壁面四分儀で、精度が 1 秒とのことです。 精度に 60 倍もの開きがあり、技術力に違いがありすぎる。 つまり、ヨーロッパでは瞬く間に観測装置が高精度化していったのです。 それに反し、江戸時代には象限儀、測量装置、時計などはほとんど変化が見られない。 つまり、このような装置は日本人が自力で開発したのではなく、単にヨーロッパの 真似をしただけで、しかも瞬く間にヨーロッパに置き去りにされたのです。
伊能忠敬の象限儀には確かに横断線も使用しており、 緯度の決定では非常に効果が期待できそうですが、 問題がかなりありそうです。
問題点の一つに象限儀は基本的には固定式であることがあります。 象限儀は水平面を確保して、垂直に設置し、正確に子午線の方向を向くようにしないといけません。 移動すれば、再度正確に調整しなおす必要があり、これはかなり難しくなります。 人手によって輸送するためには装置を軽くする必要があり、 そうすると (装置の剛性の確保が難しくなり) 精度が犠牲になる可能性がある。
ティコ・ブラーエの装置にも分解できる装置があります (ティコ・ブラーエの観測装置の高度を測定するための天文用六分儀)。 これは重りだけによって、装置が垂直であることを確保するだけのようです。 金属でできており分解、組み立てが容易と思われます。 但し、かなり重いと思われるので輸送には馬車などが必要となりそうです。 ティコ・ブラーエのように 10 秒単位ではなく、分単位にすれば装置はある程度、 軽くできるはずですが、ネジ (ボルトのようなもの) が必要となります。 このネジは装置を組み合わせるのにも、また装置が正確に上を向くためにも 使用されます。(何箇所もある)
これに反し、 八分儀や六分儀で天体の高度を測定するのに、 装置の水平、垂直をあまり意識する必要はありません。 単に視野の中に水平線を中央に水平に捉え、同時に天体を捕捉すればよいだけです。 八分儀や六分儀は角度を測定するために特化された装置で象限儀の機能とは 目的が違うと考えた方がよいと思います。 目盛りの精度に関しても、 八分儀と象限儀が同等で (角度の 1 分)、六分儀がそれより精度が高いので (角度の 1/6 分、月からの距離 を参照)、 象限儀の使用はかなり不利となります。 (これはティコ・ブラーエが天体観測をしたとき以後の、ヨーロッパにおける多大な進展なのです。) 八分儀や六分儀の使用には、水平線がないといけませんが、 人工水平線を使用すれば問題が解消されます。 但し、操作は少し複雑となる。 伊能忠敬の地図作りと同時代のルイス・クラーク探検隊は地図作りに 八分儀や六分儀を使用した。 (円周儀の訳注の ルイス・クラーク探検隊を参照のこと。) 緯度測定に関しても伊能忠敬よりはルイス・クラーク探検隊の方が分が良い。
この時点では日本は欧米にすぐにも追い付けるようにも見えたのですが、 円周儀に続く英国の産業革命の駆動力の一つともなった精密化が 日本でも可能となるのは第二次大戦後なのです。 産業革命ではすべての産業において効率化が必要となり、精密化はその要因の一つとなります。 1960 年代のある頃、 ようやく日本でも精密セオドライトや海洋クロノメーターの製造が可能となった。 しかし、これ以後はすべての産業で精密化が可能となった。
「メイソン・ディクソン線の測量」のことを書き忘れていることに気が付いたので 追加することにします。 (円周儀の メイソン・ディクソン線の測量を参照) メイソン・ディクソン線の測量は 1750 年 - 1753 年 に実施され、 このときは天頂セクターと呼ばれる望遠鏡を使用して、緯度を秒の単位で測定しています。 伊能忠敬の地図作りはこれより 50 年後ぐらいになりますが、 象限儀の精度は分ですから、正確さではおよそ比較にならない。地球の半径を 6400 km とすれば、 伊能忠敬の象限儀では
の区別がつき、メイソン・ディクソンの方法ではこの 1/60、つまり 30m 程度の区別がつきます。
『和蘭天説』は紀限儀のことを検索しようとして気が付いた本です。 最初は、この本の紀限儀の挿絵が妙であることに気が付き、 その次に象限儀の挿絵も妙であることに気が付きました。 どちらもフェルディナント・フェルビーストが 北京古観象台で製造した装置を描いたつもりなのだという ことに気が付き、同時に本の著者が何も理解していないことに気づくことになりました。 なお、フェルディナント・フェルビーストが製造した装置は元をたどればティコ・ブラーエが製造した装置で、 ティコ・ブラーエ自身が発明したものです。 『和蘭天説』はティコ・ブラーエなどが実施した天体観測がどのようなものであるかを、 作者が想像によって記述した作り話の本と思われ、 事実に基づくものではないと思われます。
紀限儀は三角法の使用に依存するので、古来から中国にある装置ではありません。
和蘭天説とは 司馬江漢が著した本で、1795 年に 作成した「天球全図」の説明書とのことです。 和蘭天説で見ることができますが、 この本には紀限儀の挿絵が載っています。 もう少し鮮明な画像を 天文学史ギャラリー ★ その2 で見ることができます。次がその画像への直接のリンクです。 まず最初に絵を見てください。(別窓で開いてみてください。右クリック + 新しいウィンドウで開く)
『和蘭天説』所載の紀限儀
紀限儀とは北京古観象台にある 天文用六分儀のことで、この装置はフェルディナント・フェルビースト がティコ・ブラーエの装置を真似して製造したものです。 但し、フェルディナント・フェルビーストは単純にティコ・ブラーエの 装置を真似したのではなく、ティコ・ブラーエの 2 つの装置
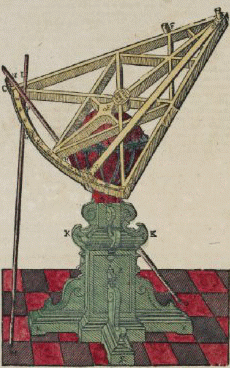
天文用六分儀 |
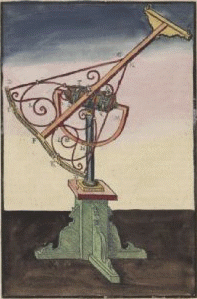
二部円弧 |
を折衷して、コピーした点が事情をややこしくしています。 (挿絵はティコ・ブラーエの観測装置のものです。) 紀限儀は、装置自身は天文用六分儀の真似をしていますが、 装置の支えの部分は二部円弧を真似しています。 この点に関しては 北京古観象台 の訳注:フェルビーストの製造した観測装置 をご覧ください。
天文用六分儀も二部円弧も 2 天体の角度 (角距離) を決定するための装置で、 天文用六分儀は 60° 以内の大きな角度を決定するのに使用され、 二部円弧の場合は小さな角度 (30° 以内) を決定するのに使用されます。 天文用六分儀には対物照準は 1 個しかなく、2 つの接眼照準が対物照準を共有します。 それに反して二部円弧の場合は [対物照準 + 接眼照準] が 2 組あります。 対物照準はいずれの場合もシリンダーで、接眼照準には左右 (あるいは上下) にスリットがあり、 このスリットの間隔はシリンダーの直径に等しくなるように作られています。
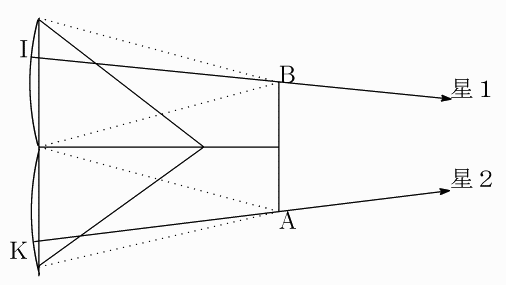 |
二部円弧は点 A, B を中心にした
中心角 15° の円弧を並べたもの、 15° までの星の角度を測定する。 A, B : 対物照準 (シリンダー) I, K :円弧をスライドする接眼照準 (照準板) |
| 天文用六分儀の使用法 | |
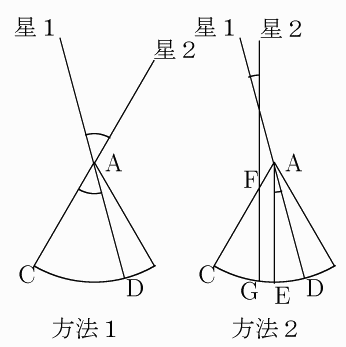 |
A : 対物照準 (シリンダー)
C, D: 接眼照準 F : 対物照準 (シリンダー) G : 着脱可能な接眼照準 E は円弧の中点、AE と FG は平行。 円弧の目盛りは C から振ってある。 方法 2 を適用する時は 角度の目盛りから 30° を引く |
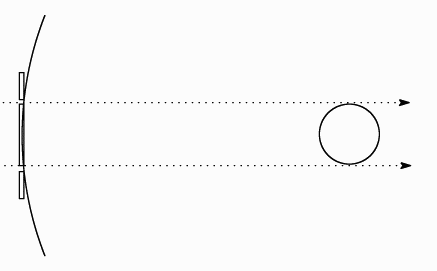
|
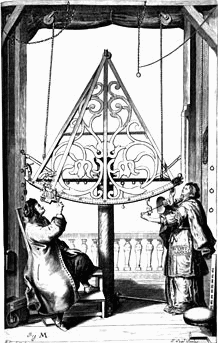
なおティコ・ブラーエの照準板の搭載方法は 2 種類あり、1 種類がアリダードに搭載するもので、 もう一種類が円弧の上をスライドする方式です。天文用六分儀の場合はアリダードに搭載しており、 二部円弧の方は円弧の上をスライドする方式です。
2 天体の赤緯が既知であれば、2 天体の角度を測定することにより、その赤経の差を決定することが できます。 (三角法の歴史の 訳注 5 を参照。) これが天文用六分儀あるいは紀限儀の本来の使用目的です。 赤経の差を求めることができれば視認できる星の赤経をすべて相対的に決定できるからです。
フェルディナント・フェルビーストの製造した紀限儀は次のようなものです。 どちらの挿絵も英語版 Wikipedia の 北京古観象台の挿絵です。 2 番目の挿絵の紀限儀はこのままでは形を判別できませんが、クリックして拡大表示を見ると極めて 鮮明に見ることができます。

フェルディナント・フェルビースト 北京古観象台、紀限儀 |
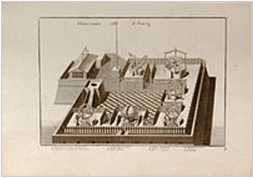
ヨーロッパ人による 初期の天文台の絵 |
ここで和蘭天説の紀限儀に戻ります。和蘭天説の紀限儀では、 アリダードが一組しかないので 2 つの星の角距離を測定できません。 天文用六分儀には先にも述べたように接眼照準が 2 つあり、 扇形の上の端に固定されたものと、可動式のアリダードに搭載するものがあります。 和蘭天説で見当たらないのは扇形の上の端に固定された接眼照準です。 また紀限儀の対物照準は六分儀の円弧の中心にシリンダーの形で存在していないといけないのですが、 これがぜんぜん別物です。
和蘭天説の挿絵の装置の支えが半円となっており、これは紀限儀と同じです。また半円を動かすハンドルの 形が違っていますが、ほぼ原理は同じです。このハンドルは司馬江漢の絵ではクランクになっていますが、 実際の紀限儀では両手で回す丸いハンドルになっています (以下の絵をクリックして拡大表示すれば見ることができます)。 ここから判断すると司馬江漢はかなり詳細な絵を見ていることになります。 しかし、 司馬江漢は紀限儀が 2 つの星の角距離を求めるための装置であることを 理解していない。従って、司馬江漢の絵はダビンチが描いたような科学絵ではない。
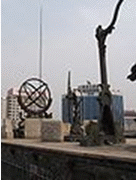
和蘭天説の挿絵には滑車が描いてあり、最初はこれは司馬江漢が間違えたのではないかと 考えたのですが 天文用六分儀 に「天文用六分儀に滑車を使用することもある」という記述があることに気がつき、 ひょっとすると滑車に関しては司馬江漢が正しいかもしれないという気がしてきました。 それどころか紀限儀では角度の 30° が観測しにくいことにも気がつきました。 真ん中の支えの棒が邪魔になり、 このあたりでは可動式のアリダードを使用できない。 そうすると紀限儀が全体的にうまく作られていない可能性があることになり、 滑車も使用したのかもしれない可能性がでてきました。(つまり重心の位置で装置が回転していない。)
ともかく司馬江漢は紀限儀の絵を見て、それを元にして絵を描いた。 このような絵があったことは北京古観象台 の訳注:フェルビーストの製造した観測装置 を読めば類推でき、その一つに
北京天文台の装置の『形式と構造』を詳細に描いた希少な一連のイラストの原作
(以下では「北京天文台の装置のイラスト」と呼ぶ)
があり、現在でも「オクスフォード科学史博物館」に残されています。 上に掲載した「ヨーロッパ人による初期の天文台の絵」もそのような絵の 1 つと思われます。 この絵を 2 度クリックして大きな画像にすると、確かに飾りが司馬江漢の紀限儀の絵と ほぼ同じであることがわかります。従って、絵を真似したことは確実です。
司馬江漢は装置の目的と、照準の合わせ方を理解することができなかった。 ひょっとすると司馬江漢が模写した元々の絵を描いていた人がこれらのことを理解していなかったのかもしれません。 理解していないことの一つに対物照準がシリンダー になっていることがあります。これは 2 つのアリダードに共通な対物照準なのです。 対物照準がシリンダーとなっていることはすぐにもわかるはずで、特殊なことを していることは想像できたはずですが、実際にどうするのかまでは理解できなかった。 ましてや接眼照準には左右にスリットがあり、スリットの間隔が対物照準のシリンダー の直径に等しいということが想像だにできなかったと思われます。恐らく「視差」を理解できていない。 装置に関しての詳しい説明が書いてある本は ティコ・ブラーエの「天文学の観測装置」で、これはラテン語で書かれ 司馬江漢は (そして当時の日本人の誰もが) これを読めなかったのです。 (ティコ・ブラーエの観測装置を参照)
もう一点付け加えます。天文用六分儀 (起限儀) はティコ・ブラーエが発明した装置ですが、 これと類似した装置をタキ・アルジンも製造しています。(タキ・アルジンのイスタンブール天文台を参照。) ここから判断をすると、三角法にたけていると天文用六分儀を発明することが可能となることがわかります。 従ってティコ・ブラーエの発明は必然的なもので、 三角法に慣れ親しんでいるのであれば、装置を発明できなくても、 装置の正確な絵を見れば用途がすぐにわかった可能性もあるのです。(以下の図を参照。) つまり、この点からも江戸時代の三角法はそれほど優れたものでなかったことが判断されるのです。
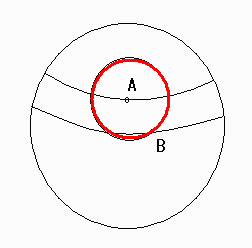
天文学史ギャラリー ★ その2 にはもう一つ妙な絵があります。
『和蘭天説』所載の象限儀
この絵は象限儀 (四分儀) としていますが、1/4 円の反対側に小さな 1/4 円があり、 これはおかしい。 四分儀には円の中心に対物照準があり、対物照準と接眼照準の 距離のみが精度に貢献するはずで、反対側に小さな 1/4 円があっても、まるで無意味です。 司馬江漢が観測装置に無知だということはわかりますが、 何かの絵を真似したはずです。 とても疑問になっていましたが、 ふとしたはずみに 「オクスフォード科学史博物館」(The Museum of the History of Science in Oxford) のページ
Tycho in Beijing (北京のティコ)
を見ている最中に、原因がわかりました。 (「北京のティコ」の翻訳は 北京古観象台の 訳注:フェルビーストの製造した観測装置に掲載しています。) 司馬江漢は「北京のティコ」のページに掲載されている 2 つ目の装置の 絵を描いたつもりなのです。 この絵は「北京天文台の装置のイラスト」の一つで、 四分儀の絵ではありません。 この装置は最初に説明をしたティコ・ブラーエの二部円弧 (bipartite arc) で、 フェルディナント・フェルビーストが紀限儀を製造した際に支えの構造を真似した装置です。 更にこの装置の絵は「北京天文台の装置のイラスト」を描いた作者の一人が 紀限儀が二部円弧にもとづいていると誤解して描いた絵なのです。 (北京古観象台 の 訳注:フェルビーストの製造した観測装置を参照。)
次の点は明らかです。 司馬江漢は二部円弧を四分儀と誤解し、自分の考えに合わせて絵を描いた。(誤解が何重にも積み重なっている。) 司馬江漢は 2 つの星の角距離を測定することの意味がわからなかったし、 これによって 2 つの星の赤経の差が求められるとは思いもしなかった。 つまり三角法を知らなかったのです。司馬江漢は「天球全図」の説明のために『和蘭天説』を著したとのことですが、 基本的な方法を理解していなかった。 江戸時代の人たちはティコ・ブラーエのように三角法を縦横無尽に使用することができなかったし、 そのような使用法があるとは想像すらできなかったと思われます。 この方法は現代的には簡単なこと (つまり高校数学) で 三角法の歴史の 訳注 5 に書いてあります。 しかし、ひょっとするともっと基本的に座標の考え、あるいは座標変換を理解できなかったのかもしれません。
しかし司馬江漢をあまりに責めるのはよくないかもしれません。 北京古観象台の装置の絵だけでは、どのように観測したのかを理解しにくいからです。 方位角四分儀があればもう少し理解できた可能性があります。 星の座標決定には「恒星時 + 高度 + 方位角」が必要で、ここから星の赤緯・赤経が求められます。 北京古観象台では高度と方位角を別々の装置 (地平経儀 + 地平緯儀) で決定しており、 これを司馬江漢が理解していたとは到底思われません。 司馬江漢は高度決定のみが重要であるという考えに取りつかれていたのかもしれません。 司馬江漢は恐らく 三角法の歴史の 訳注 4 の方法を理解していなかった。
以上、『和蘭天説』の挿絵で否定的なことを書きましたが非常に明白になった点があります。 それは司馬江漢が北京の天文台の装置の絵を見ていたことです。 そして、この絵は現在「オクスフォード科学史博物館」に残されている 「北京天文台の装置のイラスト」もしくはこの類似物 であることがほぼ確実です。 (北京古観象台 の訳注:フェルビーストの製造した観測装置を参照。) そしてこのような絵が日本にも輸入されたことも疑いの余地がない。 イラストの中には渾天儀もありますから、 当時の日本人は北京の天文台で渾天儀が使用されていることを知ったはずなのです。 渾天儀の 訳注:観測用の渾天儀 の中で、江戸時代の日本人は北京の天文台で渾天儀が 使用されていることを知り、その真似をしたと推論をしましたが、 それが裏付けられたことを意味します。 イラストだけから装置の存在を知り、その真似をしたのです。 よもや、イラストに描かれている渾天儀が洋式渾天儀で ティコ・ブラーエによってデザインされたものであり、 そこには大象限儀と同様に 横断線 (あるいは対角線目盛) が刻み込まれ、 そして特殊な照準装置が使用されているとは 思いもよらなかったことでしょう。 つまり、江戸時代の人は 挿絵と見かけ上同じような渾天儀を製造できれば、これで同等な観測ができると考えたのです。
これと似たような話はゴロゴロあります。 八分儀や 六分儀の真似をした装置を日本人も製造しますが 精度ではヨーロッパのものに太刀打ちできるわけがない。当時の日本の製品は 当時のヨーロッパのものと比較すれば (その初期のものは別として) まるでおもちゃでしかないのに、 見かけ上おなじであれば、さもそれが同等の製品であるかのように 書かれている。バカみたいな話です。 18 世紀末には (つまり英国産業革命の時には) 八分儀の精度は 1 分で江戸の大象限儀と同じとなり、 六分儀の精度は 1/6 分で江戸の大象限儀を超える精密機械となったのです。 この目盛りは極めて均一・精密なもので、機械 (デバイディング・エンジン、目盛刻印機) でないと刻印できないのです。 またそうでないと信頼できる装置にはならない。
江戸時代の日本人で渾天儀を使用した人たちはティコ・ブラーエによって翻弄された人たちです。 ティコ・ブラーエは中国のみならず、日本にも絶大な影響を及ぼした。
「和蘭天説に関して」を書いている最中は「和蘭天説」のことのみ議論していたのですが、 どうも全体的に妙なのでもう少し付け加えたいと思います。 次を見てください。別窓で開く方が良い (右クリック + 新しいウィンドウで開く)。
貴重資料-NAOJ Library - 国立天文台 - 三鷹図書室
ここに「測量集成(そくりょうしゅうせい)」という古書のページの画像がありますが、 「紀限儀図解」という文字が見え、(海洋ナビゲーション用の) 六分儀の説明があります。
紀限儀は天文用六分儀で、海洋ナビゲーション用の六分儀は全く別物です。 話がややこしくなるので海洋ナビゲーション用の六分儀を「海洋六分儀」と呼ぶことにします。
先にも述べたように、紀限儀 (天文用六分儀) は 2 つの星の赤経の差を求めるためにティコ・ブラーエが発明した装置です。 一方、海洋六分儀の主な用途には、(1) 月と星 (あるいは太陽) の角度 (月距) の測定、(2) 天体の高度の測定、 の 2 つがあります。
六分儀を使った測量の数学的解説
を見れば、海洋六分儀の使用方法はある程度わかっているようです。 しかし紀限儀 (天文用六分儀) と海洋六分儀は全く目的が違うので、 2 つの装置を混同することは、紀限儀 (天文用六分儀) の使用方法をわかっていないということを意味しています。 恐らく「紀限儀 (天文用六分儀)」の詳しい説明はほとんどどこにもなく、 ティコ・ブラーエ自身の説明以外にはないような気がします。 英語圏でさえこのような状況なので、日本語圏では装置の目的に関しては説明があるはずがない。 つまり、これが意味していることは、 紀限儀という装置が日本に紹介されて以来、誰も使用方法を知らなかった。 「和蘭天説」の挿絵が無批判で受け入れられているようですから、ほぼ間違いないと思われます。
これで「和蘭天説」と「測量集成(そくりょうしゅうせい)」のページには決着がついたのですが、 六分儀を使った測量の数学的解説 の挿絵には更に問題があることがあります。 この挿絵は『六分圓器量地手引草』からの引用で、誤解を招く部分があります。
誤解を招く点は六分儀を内陸で使用するのに「人工水平線」が必須なのにそれが読みとれないことがあります。 六分儀で高度 (角度) を測定する時に、装置が垂直になるようにしないといけません。 このための必須の操作があります。 「人工水平線」には複数の形式があり、おおまかにはチューブに水を入れた水準器のようなもののようです。 しかし個々の「人工水平線」では操作が違うと思われるので、 水平線が見える時に星の高度を決める時の操作で説明をします。 まず水平線と星を照準に捉え、装置を望遠鏡の軸の周りで左右に小さく回転します。 このとき、星と水平線が両方見えますが、水平線は固定された状態で見え、星は小さな円弧 (半径が大きいのでほぼ直線) を描きます。 この円弧が水平線に接するようにします。これで垂直が確立すると同時に高度が確定するのです。
この時の操作で決まるのは水平面と星との成す角度であって、地上の物体と星の成す角度ではないのです。 ところが『六分圓器量地手引草』では 山裾の点と山の頂上の角度を求めているように見えます。 だからここから判断をすると、海洋六分儀の使用法を理解していない。
更に『六分圓器量地手引草』に描かれている方法は実際には恐らく適用できない。 山頂の点 M と 2 点 A, B が与えられたとします。 A, B として選べる点は恐らく街道沿いの点になり、 A, B の標高が同じとなる点を選ぶことはできても、M, A, B の 3 点が同一の垂直面に あることは期待できそうもありません。 このような場合でも A, B を含む水平面からの山の高さは容易にわかり、 こちらの方が現実的だと思われます:∠MAB と ∠MBA 及び AB の距離が分かれば、正弦定理を適用することにより MA の距離がわかり、MA が水平面と成す角度から M の高さがわかるはずです。 つまり『六分圓器量地手引草』は三角法の授業で使用することはできても、 実際の測量法を述べているわけでないので、恐らくこれは三角法の教科書と言うべきものでしょう。 読者が抽象的な書き方に耐えることができないため、 それにあわせて仮想的な測量によって三角法の説明をしていると思われる。 『和蘭天説』と同様に『六分圓器量地手引草』も作り話の本と言うべきではないかと思う。
誠之館所蔵品 「六分儀(セキスタント)」に六分儀と称するものの写真があります。 この装置は 180° まで測定できるようになっており、 写真の説明では「月距」(月からの距離を参照) を測定するための装置であろうとしていますが、 これは間違いです。
180° までの角度が測定できることは、これが水平の角度を測定するためのもので、 測量に使用したものに相違ないのです。 反射計器の 六分儀の型式を読めば、 ヨーロッパには地上の測量に使用された「測量技師の六分儀」があったことがわかります。 「誠之館所蔵品」の六分儀は「海洋六分儀」ではありません。 海洋六分儀は海水による腐食に耐えるように高価な材料を使用して製造するはずで、 そうであれば現在でも目盛りの部分は健在なはずです。 「誠之館所蔵品」の六分儀の目盛部分はかなり腐食しており、 この点からも海洋六分儀でなく、 「測量技師の六分儀」の一形式であろうと思われます。
そこでもう一度『六分圓器量地手引草』のことを考えます。 挿絵には「海洋六分儀」のような絵が描かれています。この本は測量の本です。 従って、本来ここには角度の180° を測定できる「測量技師の六分儀」を描くべきなのです。 だから、この挿絵は写実的なものではなく、 「和蘭天説」の挿絵と類似なもので、本の作者が想像して描いた絵なのです。 ひょっとすると、この本の作者はヨーロッパに「測量技師の六分儀」なるものが あることをオランダ語の本から知り、その真似をしようとしたのかもしれません。 反射計器を 読めば、120° 以上の角度を測定できる装置も六分儀と呼んでいることがわかり、 誤解が積み重なっている可能性があります。以上の点からも「和蘭天説」と 同様に実物を扱った本ではないと思われます。
六分儀は本来「月距」(月からの距離) を 測定するために考案された装置です。江戸時代の六分儀はこの目的のために使用されたわけではないので、 必要とされる性能を持っていたわけではありません。 本当の八分儀や六分儀を製造するには デバイディング・エンジンが必須です。 デバイディング・エンジンは英国の 経度懸賞という国家的事業の結果生まれたものの一つなのです。 従って、江戸時代の六分儀は粗悪なイミテーションに他なりません。この点では当時の日本製の六分儀は第二次大戦後まで続く 日本の製品が持つ「安かろう、悪かろう」の典型例なのです。 以下これに関する説明です。
八分儀の 八分儀の終焉 を読めば、太陽の高度を測定するには通常は六分儀ではなく、 八分儀を使用したと思われます。 これは六分儀がとても高価であったためです。 六分儀の値段がどの程度のものであったのか推察してみましょう。 まず海洋クロノメーターの価格が問題となります。 ジョン・ハリソン に書かれていることを引用すると
初期には海洋クロノメーターの価格は極めて高価であった (およそ船の価格の 30%)。
とあるので、現在の価格で 1 億円程度でしょうか ? しかし 19 世紀初頭には海洋クロノメーターの価格は
およそ技能労働者 (skilled worker) の半年から 2 年程度の給与に等しい
とあるので、1 千万円程度でしょうか ? この段階でも六分儀の値段は海洋クロノメーターよりは安いと思われます。 しかし 経度の歴史 の月がよいか、クロノメーターがよいか ? によれば、19 世紀中頃には
月からの距離方式に十分な品質を持つ一台の (そして高価な) 六分儀を購入するよりも、 2 台もしくはそれ以上の値段の安いクロノメータを購入して相互チェックすることが可能となったのである。
とあり、海洋クロノメーターの 2, 3 台分の価格よりは六分儀の方が高いことになります。 更に ジョン・ハリソンには 海洋クロノメーターの半値の甲板時計 (deck chronometer) のことが指摘されています。 すべて手作業で作っていますから、甲板時計も 1 台の価格は少なくとも 10 万円を切ることはないと思われ、 海洋クロノメーターは最低でも 20 万円にはなるでしょう。 そうすれば六分儀は最低でも百万円にはなると思われます。(熱膨張対策のために高価な材料を使用すれば、恐らくこれよりはるかに高い。) こんなに値段が高くなるのは手作業による精密加工 (無論デバイディング・エンジンは使用します) 、海水による腐食対策、熱膨張に対する最低限の対策等々で費用がかかるためと思われます。 江戸時代には、ヨーロッパの六分儀にこのような配慮がされているとは考えなかったでしょうから、 見かけ上同じような形をしていれば、同等の性能があったと考えたのでしょう。
江戸時代には精密加工や熱膨張対策をしているはずがない。 垂揺球儀のことを思い出してください。江戸時代の日本人は温度によって 金属が伸縮することを知らなかったし、それが観測精度に影響することとは考えもしなかった。
そもそも江戸時代の日本人は月距を測定していなかったので、 六分儀にはどの程度の精度が必要であるかを知らなかったのだと思われます。 江戸時代に日本人が製造した六分儀では月距の測定は無理であったはずです。 (高性能な機械では観測の度に機械の調整をする必要があります。 正確な観測結果を出すためにはこの作業は必須で、とても面倒な作業です。江戸時代の日本人にはこれができなかったと思われます。 機械には調整が必要であることは産業革命に至って始めてエンジニアに芽生えた考えなのです。)
間宮林蔵が用いた測量器具
には ゴローニンの「幕末日本見聞録」の一節が引用されており、、 ここで間宮林蔵が 1812 年に国後島で捕らえられたロシアの海軍士官ゴローニンに 「月距の方法」(月からの距離を参照。) を尋問しようとする話が登場します。 (「月距の方法」とは断っていませんが、これは自明です。) ここから判断をすると英国の 航海年鑑はオランダ語に翻訳されなかったようです。 (オランダ語に翻訳されていれば間宮林蔵は読むことができた。) 英語圏以外では英国の「航海年鑑」を翻訳したかどうかを探してみると、
History of the Nautical Almanac
を検索でき、フランスは一時期、英国の「航海年鑑」を仏語にコピーしたものを 出版していたようです。しかし次年度の「航海年鑑」しか出版しなかったので長期間の航海では 役に立たなかった。 ドイツもスペインも母国語で「航海年鑑」 を出版していたようですが、英国と独立に計算したか否かは不明です。 多くの国は英国の「航海年鑑」に依存していた可能性があります。
Lunar Distance Navigation
にはドイツ語の月距の表の画像が英国の月距の表と上下に並べて掲載されています。 表は全く同じ形式を採用している (1 時間ごとの天体の月距を掲載している) ので、独自に計算したものであるにせよ、 計算が正しければ全く同一な表となります。基本的にヨーロッパ中が英国の真似をした。 オランダは恐らく英国の「航海年鑑」をそのまま利用した。 オランダは小さな国ですから、ナビゲーターの数も多くはなく、 独自に計算することも母国語に翻訳することもどちらも極めて非効率的であったと想定されます。
間宮林蔵がゴローニンに「月距の方法」を聞こうとしましたが、拒否されました。 説明できなかったからです。 恐らく、これは始めてのことではなく、 間宮林蔵はオランダ人にも「月距の方法」を聞こうとしたのに決まっています。 「月距の方法」を理解するには英国の「航海年鑑」を参照する必要があり、英語が読めないといけません。 実際の操作も何らかの訓練を受ける必要があり、そのような諸々の理由を説明するのが 困難なため、常に説明を拒否されたのではないかと思います。 それに仮に多額の授業料を払って「月距の方法」を理解できたにせよ、 「航海年鑑」は年ごとに違っているのです。 伊能忠敬の経度決定方法の是非に関しての記述から、 江戸時代に日本で流通していたのはオランダの古い本である可能性が高いです。 日本に流入したオランダの本は恐らくオランダ本国で売れ残った本で、 安く手に入れた本を日本で高値で売りさばいた。 こうなると、最新版の英国の「航海年鑑」を年ごとに手に入れることは恐らく無理であったと思われます。 この理由からも「月距の方法」の説明を常に拒否されたものと思われます。
しかし、よしんば「月距の方法」がわかり、「航海年鑑」を手に入れることができても、 日本製の六分儀では役に立たなかったはずです。恐らくここまでしてみれば、 日本がどれほどヨーロッパに立ち遅れているかを実感したことでしょう。
「江戸時代の六分儀は本当の六分儀ではない、その 1」 では江戸時代の六分儀が熱対策をしていない以上、本当の六分儀ではないと議論しました。 ここでは六分儀の本来の目的であった「月距」の測定が江戸時代の六分儀では、どだい無理であることを議論します。
月は (星に相対的に) 1 時間に 0.5° 動きます。 「月距」による経度の決定は、月の移動距離から、グリニッジ時間を測定する方法です。 しかし、時間の測定を 1 分の精度で実施しないと地球上での現在の位置を確定できないと 思われます。(1 分の精度で実施できても 30 km 程度の誤差が生じる。現代の GPS のように高精度ではない。) そのため、時間の 1 分を測定するには、月の 1 時間の移動距離である 0.5° の 1/60 の角度、 すなわち 0.5 分を測定できないといけません。
こうなると製造が困難な部品があることがわかります。 江戸時代には望遠鏡も日本で作られたかのように言われていますが、 性能のよい望遠鏡には色消しレンズ (組み合わせレンズとも言う) が必要です。レンズの色収差を克服するには 波長により屈折率の異なる 2 種類のレンズを使用しないといけません。 このようなレンズを製造するには「屈折率」とか「波長」という光学の概念を知っていないといけません。 従って江戸時代の職人には色消しレンズを製造できるわけがない。実際、日本で色消しレンズを自由に製造できるようになるのは第二次大戦後の 1960 年代 のことです。このような色消しレンズは焦点距離の短いレンズを製造する時に必要となり、 六分儀に搭載する望遠鏡もこのようなレンズが必要だと思われます。 八分儀の ニュートンの反射四分儀を読めば事情が分かる。 ニュートンの時代には色消しレンズがないので、小さい望遠鏡を作れません。 そのためニュートンの装置はとても大きいのです。 従って、江戸時代には科学の知識がない職人が (望遠鏡を搭載した) 本物の六分儀を製造できたわけがない。 日本では伝統的に「技術」は「科学」と別物のように扱われていますが、 これは「迷信」です。(報道がこのように洗脳しているだけです。) 「科学」がなければ「技術」が成立しない。
以上の事実から、江戸時代の国産の六分儀には望遠鏡が付いているはずがないことが結論できました。 しかし、この事実から江戸時代の六分儀は精度の 1 分が達成できないことが論理的に結論できます。 その理由は、ティコ・ブラーエのような特殊な照準装置 (ティコ・ブラーエの観測装置を参照) を使用しなければ、精度はまず先に人間の 目の角解像度 (分解能) で制限を受けます。人間の角解像度は 1 分と書かれていたり、2 分と書かれていたりします。 個人差があるかもしれませんが、 2 分ぐらいと考える方が妥当なようです。つまり、六分儀に 1 分の目盛りが付けられて いたにせよ (手作業でこれを実現することは少しあり得ないのだが)、1 分の精度で観測することは不可能です。 だから、江戸時代の国産の六分儀は唯の「おもちゃ」であることが論理的に結論できるのです。 少し大きな装置であれば 1 分の精度で目盛りを入れることができますが、 裸眼では 1 分の精度で観測することは少し無理であることは 古代から知られていた事実だと思われます。
また 1/6 分の精度を実現しようとしても 1 度を 360 等分する必要があり、 バーニヤスケールでも少し無理そうで、 ワームギアが必要となりそうです。 しかし精密なワームギアを製造するには精密な旋盤がないと、どだい無理です。 また六分儀には目盛りの部分を拡大表示するレンズが付いているものがありますが、 これは焦点距離の短いレンズなので色消しレンズが必要で、江戸時代には到底製造することが無理なのです。 (江戸時代の大象限儀は 1 分の精度があり、これには望遠鏡が付いています。 この望遠鏡は長いので焦点距離の長いレンズを使用したはずです。 従って、レンズは無論色消しレンズではない。)
目盛りを付けるにも問題がある点があります。18 世紀にジョン・バードがグリニッジ天文台に製造した壁面四分儀の精度は 1 秒ですが、 彼は 1 秒の目盛を振ったわけではなく、 90° を極めて精密に 96 等分しただけです (96 = 3×25)。 実際に角度を測定する時は、四分儀の目盛の値にマイクロメータ (つまりワームギア) の目盛の値を加えたのです。 従って、細かい目盛りがあるかどうかが装置の性能を示しているのではなく、 目盛りがどれほど高精度に刻まれているかが問題なのです。 但し、これには精密なワームギアの製造が前提になります。 不正確な目盛りをいくら細かくしても意味がない。 しかし、こんなに単純なことを理解していない人の方が多いようです。
マイクロメータによると、マイクロメータの精度は 1/100 mm 程度のようです。 この精度は高いように見えますが、 現代の機械では多分精度が不足する。1 ミクロン (= 1/1000 mm) 程度の精度でないと、 いろんなことで困ることになる。(特に高速回転をするベアリングではこの程度の精度がないと役に立たないのではないかと思う。 もっとも半導体ではナノ (= 1/106 mm) の単位ですから、ミクロンでは意味がない。) 英国は産業革命の時に色々な機械を製造していますが、その精度は恐らく 1/100 mm 程度だと思います。
半径 2m の壁面四分儀の角度 1 秒に対する円弧の長さは
となります。この数値はマイクロメータの精度に匹敵し、ジョン・バードが製造した壁面四分儀の精度が 1 秒であることに対応しています。 マイクロメータは一番最初に天文学者が使用し、これがそのうち一般に使用されるようになったと思われます。 だから天文学の長さの計測方法とその精度が産業に影響を与えていると考えられる。
また 1/100 mm が古典的な方法で長さを計測できる限度ではないかと思われるので、 恐らくこれが英国の産業革命の時の精度であると思われます。